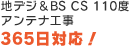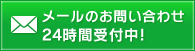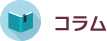テレビ画面の乱れでアンテナを修理する前に自分でできる対処の方法を解説。業者に工事を依頼する費用の相場も紹介【最新版】
戸建てのお住まいなどで、地上デジタル放送(地デジ放送)やBS放送、CS放送、さらに新4K8K衛星放送などの衛星放送をご覧になる方法として、もっとも便利でリーズナブルなものは、現在でもやはり、お住まいにテレビアンテナを設置することになります。
ケーブルテレビ(CATV)や光テレビに比べて、地デジ・BS/CSテレビアンテナの設置は、NHK受信料や衛星放送の有料チャンネルを除けば、いったん設置すれば、その後の長年にわたって、無料でさまざまなチャンネルを視聴できるため、特に持ち家の戸建て住宅にお住まいの方にはうってつけの方法です。
ただ現在、お住まいにて長年、テレビアンテナでテレビ放送をご覧になっておられる方の中には、時にテレビ放送の画面に不具合が生じた経験はないでしょうか?
例えばテレビ画面に、いわゆるブロックノイズと言われる、デジタル映像信号の乱れで生じるモザイク状のノイズが入る。同じ画面のまま停止(フリーズ)する。またブラックアウトしたテレビ画面に「E101」などのエラーコードとメッセージが表示されるといった症状です。
これらの不具合は、一時的な電波状態の変化や、テレビの不具合である場合は、時間の経過やテレビ電源のオンオフ、設定の調整など、簡単な操作で回復できる場合もございます。
ただ、このようなテレビ画面の不具合が頻繁に起こる、さらにはその状態が続いたまま回復しないでいると、当然、いつまでも正常にテレビ放送が視聴できなくなってしまい、お住まいの方はさぞお困りになると存じます。
そして、このようなテレビ画面トラブルの原因には、さまざまな要因が考えられます。
そもそもテレビアンテナは、主に家の屋根の上や壁などの屋外に設置され、長年、台風などの自然災害、雨や風、雪などの影響を受け続け、経年劣化が進んでいく機器になります。
そのため、電波の方向に調節した角度のズレや、部分的な故障などのトラブルにより、
アンテナの修理
が必要となり、受信性能の低下や喪失が起こることもございます。
またアンテナから各お部屋までのテレビを接続しているケーブル配線の間にも、電波レベルを増幅するブースター、電波を各部屋へと等分に送る分配器。また地デジ、衛星放送の電波を一本のケーブルにまとめ、テレビなど受信機器の直前で分離することにより、ケーブルや機器の無駄をなくす混合器、分配器などの機器が設置されております。
これらの機器やケーブルそのものも、長年の使用で経年劣化が進み、電波の漏洩、ノイズの混入などのトラブルが発生するケースがございます。
他にも、テレビなど受信機器そのものの不具合や経年劣化。現場に届いているテレビ電波が、気候や天候の影響を受けて、レベル(強度)や品質が変動する、電波を遮る周辺の建物の建設、取り壊しなど、周辺環境の変化で、受信できる電波の状態が大きく変動することも考えられます。
テレビ画面トラブルの原因が、お住まいでも屋根の上に設置されているアンテナや、アンテナの付近にある機材のトラブルなどの場合は、作業に大変な危険が伴い、専門の知識や技術、工具や機材なども必要となるため、テレビアンテナ修理を含めた対応については、アンテナ工事の専門業者にご依頼になることがオススメとなります。
ただ、お住まいによってはテレビアンテナや機材が、ご自宅でも手の届きやすいベランダや屋根裏、マルチメディアボックスなどに設置されていること。また室内配線やテレビなど受信機器本体のトラブルの場合は、お住まいにおける簡単な調整などで復旧できるケースもございます。
今回の本コラムでは、お住まいの各お部屋、または一部のお部屋でテレビの映像が乱れる、映らなくなった場合に考えられる要因について、室内のテレビや配線。お住まいのテレビアンテナ本体や、アン手から各お部屋までを結ぶ配線部やその間の機器。さらに周辺の電波環境や受信条件の変動と、主な要因別に解説し、お住まいで可能な限りの対処法をご案内いたします。
もしお住まいのテレビで、上記のような画面トラブルが発生した場合は、下記の各項目から、お住まいで一番近いと思われる症状をご確認ください。
そして記事内でご説明している、要因ごとの対処方法をお試しいただくことで、画面のトラブルが解消される可能性がございます。
ご自宅で急にテレビ画面の乱れ、エラーコードの表示などの問題が生じた場合は、業者に依頼するなどのお手間や費用をかけず、当コラムの内容をご参照の上で、お住まいにて手早く復旧していただければ幸いです。
ただ、トラブルの原因によってはご自宅での対処が難しいことや、複合的な要因などにより、原因の特定が難しいケースもございますので、その場合は、当あさひアンテナのフリーダイヤル、または当サイトのメールフォーム、LINEアカウントまで、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
地デジ・衛星放送のテレビ画面が正常に映らなくなる主な要因とその症状とは?
ブロックノイズやエラーコードの表示など、お住まいにあるテレビの画面が乱れる原因は、テレビ本体の不具合などを除けば、基本的に、テレビなどに届く地デジ、衛星放送の電波レベル(電波の強さ)が低下している、またはノイズ(無関係の電波による雑音)の混入により、正常なデジタル信号の受信ができない状態であることが考えられます。
そしてその主な要因としては、
・電波障害などでお住まいに届くテレビ電波レベルや品質が低下している。
・お住まいのアンテナの故障、老朽化などで十分なテレビ電波が受信できない。
・アンテナから各お部屋までをつなぐケーブル配線や機器の不調で必要な電波が届かない。
・室内にあるテレビそのものや室内ケーブル配線の不具合。
の4つの可能性が考えられます。
そして、お住まいでテレビ画面の乱れが出ている症状によって、おおよその原因の目安を判断することもできます。
もしご自宅にあるすべてのテレビなど受信機器で、テレビ映像に同様の問題が出る場合は、周辺の電波環境やアンテナ本体、または各部屋のアンテナコンセントに至るまでの配線部に問題があり、各部屋へ届く電波レベルや品質に問題が出ていると考えられます。
ただ、気候や天候によるわずかな電波レベルの低下や、アンテナの軽度の不具合で受信性能がやや低下している場合は、住宅内でもアンテナ配線から遠い一部のお部屋でのみ、テレビ映像の乱れが生じるケースもございます。
また、特定のお部屋にある一台のテレビのみで画面の乱れが出ている場合には、そのテレビ本体や室内の配線部に問題が出ている可能性が高くなります。
以下のコラム本文では、上記した4点の主な要因別に、テレビ映像が乱れる原因と、原因別で考えられる主な症状。そして原因、症状別に、お住まいにてご自分でも可能な対処法を解説してまいります。
テレビ画面が乱れる要因1:テレビ本体や室内ケーブルなどの不具合
もしご自宅の各お部屋に設置しているテレビで、地デジ放送、衛星放送のテレビ画面にブロックノイズなどが入って乱れる。または「E101」などのエラーコードとメッセージが表示されて、テレビ放送が映らない場合は、周辺の電波状況の悪化から、お住まいのアンテナ本体や配線部にあるブースターなど機器の不具合。ひいてはテレビそのものの不具合まで、さまざまな要因が考えられます。
ただ、もしお住まいに複数のテレビ、レコーダーなどがあるお住まいで、特定の一台のテレビのみに問題が出て、他の部屋にあるテレビは正常に映る状態であれば、原因はそのテレビ本体や室内の配線など、可能性は限られてまいります。
またエラーコードが表示された場合は、そのエラーコードの種類や、同時に表示されるメッセージ内容によって、トラブルの原因を絞り込むこともできます。
以下の項目では、お住まいの特定のテレビ本体や、そのテレビに接続されている室内の配線などが原因で、テレビのご試聴に支障が出ているケースについて、考えられる原因のパターンと具体的な症状、業者に依頼せずともご自宅で可能な修理、対処法についてご説明してまいります。
チェックポイント1:テレビ本体の不具合
お住まいの各お部屋にあるテレビ本体やレコーダーなどの録画機器は、多くの場合、ほぼ毎日のようにテレビ放送を映し続けている、いわば非常に酷使されている家電製品のひとつです。
テレビに限らず電子機器は、長年、使い続けると、通電により内部の基盤が徐々に劣化してゆき、いずれは不具合が生じてまいります。
テレビ放送を視聴する頻度にもよりますが、テレビのように使用する頻度が高く、待機電源などで常に通電している家電製品の寿命は、10年程度と考えられています。
そしてテレビ本体もこの年数を過ぎると、徐々に経年劣化が進んで、不具合が出てまいります。
テレビ本体の不具合のパターンには、テレビ映像の乱れなどのほか、リモコンが反応しない、正常に操作できないなど、さまざまな状態が考えられます。
また確認の方法としては、問題が出たテレビを、お部屋のアンテナコンセントとは別のアンテナケーブルに接続する。もしくは正常に映るテレビなどの機器を、問題が出たお部屋のアンテナコンセントに接続する方法が考えられます。
後述するアンテナケーブルやB-CASカードの問題ではなく、テレビ本体の不具合の場合、別のアンテナコンセントに接続しても同じ不具合が起こる。もしくは問題の出た部屋のアンテナコンセントに別のテレビを接続すれば問題なく映る場合は、テレビ本体に問題があると考えていいでしょう。
そしてテレビ本体の不具合が軽度のものである場合には、主電源のオンオフや、テレビのリセットなどで回復するケースもございます。
リセットとは、一般的には、テレビ本体の主電源をオフにし、テレビの電源プラグも外した状態で、数分ほど待ち、再度、電源プラグを入れて主電源もオンにするという作業です。
この手順により、いったんテレビ内の電気の流れをなくすことで、一時的な回路の不具合などが解消される可能性もございます。
ただテレビのモデルやメーカーによっては、テレビの設定画面から操作するなど、その他のリセットの方法もございますので、付属するマニュアルやメーカーの公式サイトでご確認の上、ご自宅のテレビに適したリセット方法を実行してください。
ただ、このリセットを実施しても不具合が解消されていない場合は、テレビの内部に回復の難しいトラブルが出ていると考えられ、テレビ本体の買い替え、もしくはメーカーや購入店に修理のご相談をされることがオススメになります。
なお、テレビ本体の不具合で、テレビ放送が正常に映らない場合の対処法については、下記のコラム記事でも詳しく解説しております。
・テレビ本体の不具合・故障とその原因、症状別の対処法と修理費用
チェックポイント2::室内ケーブル配線の問題
室内の特定のお部屋のみで、地デジや衛星放送の画面が乱れる要因として、実際に多いケースとしては、室内のアンテナコンセントから設置されているテレビ、レコーダーなどを接続するアンテナケーブル(テレビケーブル)の問題が考えられます。
屋外に設置されたアンテナから各お部屋のアンテナコンセントまで。また室内のアンテナコンセントとテレビなど受信機器を接続するケーブルは、基本的には電波を通す芯線である銅線(内部導体)の周りを、絶縁体、外部導体、被膜で覆った、断面が各層の同心円状になる「同軸ケーブル」と呼ばれるケーブルです。
室内用のアンテナケーブルは、両端に室内での設置に適したⅠ字型、L字型などの接続プラグ(端子)が設置され、その部屋に適した長さと、地デジ、衛星放送(右旋放送)、新4K8K衛星放送(左旋放送)など、ご覧になる放送の電波に対応する製品を使用します。
このとき、お部屋の模様替えや、ケーブルを引っかける事故などに備えて、アンテナコンセントからテレビまで、壁の端を添わせた長さより、多少の余裕がある長さのケーブル製品をお選びになることがオススメです。
しかしその一方、テレビの電波は、アンテナケーブルを送信される間にも徐々に減衰(電波レベルの弱まり)が生じますので、必要な余裕よりも極端に長いケーブルを使用すると、ケーブルの途中で電波レベルが低下する、ノイズが混入するなどして、画面の乱れなどの原因になることがございます。
したがって室内用アンテナケーブルは、長すぎず短すぎず、お部屋に合わせた適正な長さの商品を使うことがオススメと言えます。
また室内用アンテナケーブルにも太さや素材などによる品質の種類があり、細いものは曲げやすく取り扱いやすい半面、強く曲げる、ケーブルにものを乗せるなどすると、内部の断線やケーブルの歪みによる映像信号の狂いなどが生じやすくなります。そのため機器間の接続など、短い配線での使用に適します。
逆に太いものはやや取り回しにくくなる半面、丈夫で減衰が少なく、ある程度の長さでも使用でき、さまざまな周波数帯の放送にも対応できます。
そのため、ご自宅でも使用する場所(長さ)や視聴する放送に適した太さ、品質のケーブルをお選びになることも重要です。
テレビ放送による電波の周波数帯の違いでは、まずもっとも一般的なテレビ放送である、地上デジタル放送(地デジ放送)では、UHF(極超短波)でも、470MHz(メガヘルツ)から710MHzまでの周波数帯の電波にデジタル信号を乗せて、テレビなどのチューナーに送信しています。
対して衛星放送の電波は、静止衛星から送信された12GHz(ギガヘルツ)帯の電波を、BS/CSアンテナのコンバーターで変換し、従来の2K衛星放送で使われる「右旋円偏波」は1032MHzから2071MHz。
2018年(平成30年)に導入された「新4K8K衛星放送」でも、BS放送のNHK、広域民放の4Kチャンネル以外で使われる「左旋円偏波」は、2224MHzから3224MHzの周波数帯に変換され、ケーブル配線に送られます。
電波は周波数帯が高いほど、ケーブル内での減衰や漏洩が生じやすいため、それまで地デジ放送や2K衛星放送のみをご覧になっていたご自宅で、衛星放送、特に新4K8K衛星放送を導入された場合、室内のアンテナケーブルが従来のままでは、周波数帯の高い電波で減衰などが生じ、右旋や左旋の衛星放送のみで、映像が乱れることもあるため、ご注意くださいませ。
特に新4K8K衛星放送(左旋)の電波は、周波数帯の高さから、ケーブル本体だけでなく、接続プラグの部分もシールド性能の高い4K8K(3442MHz)対応の製品が必要となります。
なお、アンテナケーブル(同軸ケーブル)の品質、対応できる放送については、製品のパッケージや、ケーブルの側面に印字されている「S-5C-FB」などの記号で判別できます。
ケーブルの太さや素材などの種類や、太さに応じた適正な長さと用途。上記の記号の読み方など、同軸ケーブルの概要については、下記のコラム記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照くださいませ。
・テレビ放送(地デジ、衛星放送BS/CS、4K8K)に合わせたテレビアンテナケーブルの種類と選び方、徹底解説!
・テレビ放送や受信機器、設置工事に合わせたアンテナケーブル(同軸ケーブル)の種類と違い、選び方を徹底解説!
・テレビアンテナとテレビを結ぶアンテナケーブル(同軸ケーブル)とは? ご家庭向けケーブルの種類と性能の違いを徹底解説!
・地デジアンテナとテレビを接続するケーブル(同軸ケーブル)とは? 衛星放送でも使えるケーブルの種類や市場や通販の価格も解説
・地デジや衛星放送のアンテナとテレビを接続するケーブルとは? 同軸ケーブルによるアンテナ配線とその工事について徹底解説!
そして、接続しているケーブルの品質や長さに問題がない場合は、接続部の接触不良や、ケーブルそのものの劣化などが考えられます。
アンテナケーブルの両端にあるプラグを、アンテナコンセントやテレビのチューナー端子にしっかりと差し込むことで電波(映像信号)が伝わり、地デジ、衛星放送のテレビ放送をご試聴になれます。
ただ、この接続端子の間も、長く放置していると静電気などの要因で、徐々にチリなどの汚れが溜まり、接触不良が生じる。またケーブルにものを引っかけるなどで徐々に接続が緩むなどで、電波の漏洩、ノイズの混入が起こって、テレビ側で電波の受信が不安定になるケースもございます。
ちなみに、テレビなど受信機器のチューナー側に届く電波レベルがやや不十分、またノイズが多いなどの問題が生じると、地デジや衛星放送の画面にブロックノイズが混ざる、フリーズが生じるなどの不具合が出てまいります。
そして電波の弱さやノイズが一定レベルを越えると、テレビ放送が映らなくなり、テレビ画面に「E201(チューナーに届くテレビ電波レベルが低い)」、「E202(チューナーに電波がまったく届いていないか、あるいは電波レベルが極端に低い)」、「E203(そのチャンネルを放送しているテレビ局が放送休止中である)」、「E204(使用されていない空きチャンネル番号である)」などのエラーコードが表示されます。
なお上記のエラーコードは、テレビ、レコーダーなどのメーカーやモデルは異なっても、同一のものが表示されますが、あくまで機器本体の自己診断であるため、場合によっては、例えば電波レベルの低下でも「E203」「E204」が表示されるなど、正確な表示ではないケースもございますので、ご注意くださいませ。
いずれにせよ、特定のお部屋にあるテレビなどの受信機器で、画面の乱れや、主に上記のエラーコードの表示が発生した場合には、上記のテレビ本体のリセットなどの対処の他、ケーブル配線をいったん取り外して、芯線の歪みや折れ、汚れなどがないか状態を確認してください。
そしてケーブルやテレビ、アンテナコンセントの端子の汚れを、乾いた布で清掃した上で、あらためて緩みがないようにしっかりと接続してください。
このような対処を行っても、状態が回復しない場合は、使用しているケーブル本体の歪みや断線、劣化などの問題が考えられます。
上記の通り、ケーブルを強く曲げる、引っ張るなどすると、ケーブルの歪みや断線などで正常に電波が送信できなくなります。
特に部屋の角などでケーブルを曲げる際には「曲げ半径」に注意することが重要です。この曲げ半径とは、アンテナケーブルなどの各種ケーブルに設定されているもので、ケーブルを壁などに沿わせて曲げる場合に、曲げ部分のカーブとちょうど一致する円形の半径を示すものです。
ケーブルの曲げ半径は、主にケーブルの太さや品質(素材)によって異なり、基本的に太いケーブルほど大きくなります。この曲げ半径より急な角度でケーブルを曲げる、特にコーナーで90度に曲げるなどすると、ケーブルの歪みによる送信不良や断線の原因となります。ケーブルごとの曲げ半径については、ケーブル付属の説明書やメーカーの公式サイトなどをご参照の上、極端に折り曲げるなどのことは決して行わないでください。
また前述のように、ケーブルに物を乗せるなども断線や歪みの原因となるほか、アンテナケーブルも設置から10年程度で経年劣化が進み、特に破損などの点はなくとも、不具合が生じるケースもあるため、破損、劣化により不具合の原因となるアンテナケーブルは、交換する必要がございます。
なお、ケーブルの状態を確認する方法として、映像などに問題のないテレビがある部屋のケーブルと交換した上で、問題のケーブルは別の部屋でも映像の不具合が発生する、または別のケーブルと交換すれば不具合が解消されるようであれば、ケーブルに破損が生じていると考えられます。
他にも、室内にテレビ、レコーダーなど複数の受信機器を設置する場合の、ケーブル配線の問題も考えられます。
室内のアンテナコンセントからテレビ、レコーダーなど複数の受信機器にケーブルを接続する場合、例えばアンテナコンセントからのケーブルをテレビの入力端子に接続した後、短いケーブルでテレビの出力端子からレコーダーの入力端子に、先送りにするようにして接続する(もしくはその逆)。
あるいはアンテナコンセントからのケーブルを分配器に接続し、分配器からの複数のケーブルを各機器の入力端子に接続するという形になります。
ただ、受信機器を経由して次の機器の入力端子にケーブルを接続する形式では、次の機器に行くほど到達する電波レベルが低下します。また分配器を接続すると、2分配では2分の1ずつなど、電波レベルを等分に分配して各ケーブルに送信することになります。
そのため、これらの配線の形式では、特に先送りではケーブルの最先端にある受信機器などに、必要なレベルの電波が届かなくなり、テレビ映像が乱れることも考えられます。
特に、お住まいの中でもアンテナから遠く、アンテナコンセントまでの配線が長くなるお部屋では、その分、アンテナコンセントに届く電波も減衰するため注意が必要です。
この場合の対処法は、すべての機器に必要な電波が届くよう、ケーブルを接続する機器の順番や、接続の方法(先送りか分配器か)を変更する。または室内の配線に、室内用ブースターやラインブースターなど補助的なブースター(電波の増幅器)を設置して、不足する電波レベルを高めるという対処がございます。
または住宅に設置されている屋外用ブースターの増幅レベルを高めるのもひとつの方法ですが、屋外用ブースターは、住宅内に送られるテレビ電波を全般的に増幅する機器のため、他の部屋との電波レベルの兼ね合いも重要となります。
さらにまれなケースですが、テレビのチューナーに届く電波レベルが90㏈(デシベル)以上と強すぎる場合も、テレビの映像などが乱れる要因となるため、この場合は、設定画面からテレビなど受信機器のアッテネーター機能(チューナーに入力される電波が強すぎる場合、ある程度、弱める機能)をオンにするか、アッテネーター機能がない場合は、別売りのアッテネーター(減衰器)をケーブルの途中やあチューナー端子に接続して、電波レベルを適切なレベルだけ弱めることが対処になります。
他にも、室内ケーブル配線の近くに、電子レンジやWi-Fiルーターがある場合には、機器が発する電波や電磁波の干渉により、テレビ映像の乱れが起こることがございます。特に電子レンジの場合は、使用している時にのみテレビ画像やWi-Fiの接続が不調になってまいります。
この場合には、配線や機器の位置が離れるように配置し直す。またシールド性能の高いケーブルに交換するといった対処が考えられます。
室内ケーブルの配線で考えられるテレビ映像の乱れの原因と、その対処法はおおむね以上の通りですが、総じて、配線部の問題により、テレビなど受信機器のチューナーに十分な電波が届いてない、というケースが多くなります。
このような場合には、テレビのリモコンで設定画面を表示して、ボタンの操作によりUHF(地デジ)やBS(衛星放送)の「アンテナレベル画面」を表示すると、ケーブルからチューナーに届いている電波レベルが、数値や帯状のインジケーターなどで表示されます。
このアンテナレベルが、画面上で示される基準値以上であれば、地デジ、衛星放送が問題なく視聴できる状態ですが、基準値を下回っていると、何らかの要因により十分な電場が届いていないと判断でき、テレビ画面が乱れる要因となります。
したがって室内のテレビ、レコーダーなどの各機器で、アンテナレベルを確認することも、テレビ映像の乱れの原因を特定し、また対処によって復旧できたかを確認する上で、たいへん参考になる方法と申せます。
このアンテナレベル画面の表示方法や名称、画面の見方などは、テレビのメーカー、モデルなどによっても異なるため、詳しくはやはりテレビに付属するマニュアルや、メーカーの公式サイトなどをご確認ください。
なお、この項でご説明した、アンテナ配線によるトラブルとその解消法や、エラーコードの種類と、その種類別の対処法、アンテナレベルの確認などについては、以下の各コラム記事でも詳しく解説しております。
・アンテナ受信トラブルでテレビ画面に「E201」などエラーコードが表示されて映らない問題の原因と解決する対処の方法とは?
・テレビアンテナで地上デジタル放送が受信できない際の修理とは?E201などが表示されて映らない原因と工事費用の相場を解説
・突然テレビ画面が映らなくなったら解決の方法は? 音は出る、E201などエラーコード、アンテナ受信など原因別の対処法を解説
・テレビ放送のアンテナ受信レベルが下がる原因とは? アンテナレベルチェッカーで電波強度を確認する方法とその他の対処法を紹介
・地デジ用UHFテレビアンテナのレベルが下がる原因と対処法とは? VHFアンテナとの違い、受信感度が高まる工事の方法を解説
・地デジや衛星放送のアンテナレベルとは? テレビでの受信レベル確認や低下する原因、工事で改善する方法を解説!
チェックポイント3:B-CASカードの不具合
テレビなど受信機器本体の問題に近い要因として、受信機器に挿入されている「B-CASカード」と呼ばれるICカードのトラブルも考えられます。
B-CASカードとは、現在のデジタル放送である地デジ放送、衛星放送のテレビ、レコーダーなど受信機器に同梱されている、著作権保護のためのICカードです。
現在の日本の地デジ放送、衛星放送で、電波に乗せて送られる映像信号は、コピー制御信号(CCI)を加えた暗号化が行われており、無料放送のチャンネルでも、暗号化された信号をそのまま受信して、放送を視聴することはできません。
この映像信号の暗号化を解くためには、現在の大半のデジタル放送対応テレビ、レコーダーなどの受信機器に同梱されている「B-CASカード」を、テレビなど本体のスロットに挿入することが必要です。
このB-CASカードに内蔵されている暗号キーを、暗号化されたデジタル信号と照合することで、信号の暗号化が解かれて、通常の映像信号となり、はじめてテレビ放送が視聴、録画できることになります。
ただ、このB-CASカードそのものの破損や不具合、汚れによる接触不良などが生じると、テレビ側など機器側でB-CASカードが認識できなくなり、映像信号の暗号化を解除ができず、地デジ、衛星放送のデジタル放送を視聴できないことになります。
なお、このB-CASカードは、基本的には一般的なカードサイズですが、小型テレビやチューナー内蔵のパソコン、ポータブルプレイヤーなどには、通常より小さい「miniB-CASカード」が本体に内蔵されていることもございます。
他にも、近年の4K、8Kテレビなどの4K8K対応受信機器には、従来のB-CAS方式に代わって、機器本体に、B-CASの機能をバージョンアップさせた「ACASチップ」が内蔵されているため、B-CASカードなどの設置は不要となっております。
このB-CASカードのトラブルが生じた場合には、主にテレビ画面に「E100(機器にB-CASカードが挿入されていない)」「E101(挿入されたB-CASカードが読み取れない)」、「E102(挿入されているB-CASカードが正しく認識されない。カードが破損しているケースが多い)」、「E103(契約していない有料チャンネルを選択している)」などのエラーメッセージが表示されます。
「E103」の場合は、ご契約している有料チャンネルや、無料チャンネルに切り替えて映るかどうかご確認ください。もしご契約中の有料チャンネルで「E103」が表示される場合は、気づかないうちに解約されているケースもございますので、お支払いに使用しているクレジットカードの期限などをご確認ください。
そして、上記のどのエラーコードが表示された場合も、まずテレビなど機器にB-CASカードが挿入されているかもご確認ください。
きちんと挿入されている場合は、アンテナケーブルの場合と同様、B-CASカードの接触不良や汚れ、破損などで、B-CASカードが機能せず、暗号化が解かれない状態になっていると考えられます。
その場合は、まずテレビ本体の主電源を切った上で、B-CASカードを外し、カードの特にIC部分(金色の接触部)を、乾いた柔らかい布などで丁寧にぬぐって汚れを落としてください。ティッシュペーパーなど目の粗い紙では、IC部分が傷つく要因になるためご注意くださいませ。また機器側のスロットが汚れている場合には、市販のカードクリーナーを使用する方法もございます。
B-CASカード本体やスロットの汚れを落とした後は、カードを前後や裏表、正しい方向にしっかりと挿入して、主電源を入れ直してください。
それでもテレビ放送が正常に映らない場合は、B-CASカードそのものの劣化や破損が考えられます。
この場合も、お住まいで他に受信に問題のないテレビなど受信機器がある場合は、問題のないテレビのB-CASカードと差し替えてみてください。そして挿入したB-CASカードに合わせて、テレビの画面トラブルが生じるようであれば、B-CASカードそのものの破損と考えられます。
このB-CASカードは、B-CASカードによる著作権管理システムを管理する株式会社「ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)」からの貸与という形で、テレビなどの受信機器に添付されるものになります。
テレビなど機器に添付されたB-CASカードが自然に故障した場合は、B-CAS社に連絡することで、無償でB-CASカードを交換してもらえます。
ただ機器の購入後、三年が経過している。またはお客様のミスによりB-CASカードを破損された場合には、有償での交換となり、2024年現在では、再発行費用2,100円に消費税を加えた、計2,310円が必要となります。
なお前述の通り、B-CASカードは、B-CAS社から個人に貸与されているものであるため、B-CAS社へ申請する以外の方法、例えば知人から有償、無償とわず譲り受ける。ネットオークションなどで購入するなどの方法で入手すると、法に触れることになりますのでご注意くださいませ。
B-CASカードの詳細や交換、再発行の手順については、下記のB-CAS社公式サイトか、弊社のコラム記事をご確認くださいませ。
・徹底解説「B-CASカード(ビーキャスカード)」の基礎知識とテレビ画面に「E101」などのエラーコードが出る原因とは?
・B-CAS社公式サイト:https://www.b-cas.co.jp/
チェックポイント4:アンテナコンセントのユニット不具合
ここまではテレビなど機器やアンテナケーブルについてご説明してまいりましたが、それらに電波を送信する、お部屋のアンテナコンセントにもトラブルが発生するケースがございます。
詳しくは後の項でご説明いたしますが、お住まいに設置されたテレビアンテナから送られるテレビ電波は、アンテナからの同軸ケーブルによって、配線部の途中で電波を増幅する「ブースター」や、アンテナ側からの一本の同軸ケーブル(送信される電波)を、各部屋に通じる複数のケーブルへと、電波レベルを等分に分配する「分配器」などを経由しています。
そして一般的には、この分売期からのケーブルが、各部屋のアンテナコンセントへと接続されます。
アンテナコンセントの構造は、部屋側のカバーに、コンセント部分のユニットが固定され、背面で分配器からのアンテナケーブルに接続されています。
このユニット部には、後述する、一本のケーブルに混合された地デジ、衛星放送(右旋・左旋)の電波を、ふたたび2つのコンセントに分ける分波器の機能を持つものもございますが、どのようなユニットでも、長年の使用でケーブルと同様、コンセント部分の汚れや、ユニットそのものの劣化により、電波の漏洩やノイズの混入などが生じることもございます。
また新4K8K衛星放送(左旋)をご試聴になる場合には、ユニット部分も従来の放送(周波数帯)に比べて、シールド性能の高い4K8K(3442MHz)対応のアンテナコンセントを使用する必要がございます。
お部屋にあるアンテナコンセントが、テレビ用のコンセントのみのシンプルなものであれば、対応する新品のユニットをご購入の上、ご自宅で交換することも可能です。交換の詳細な手順は長くなるため、下記のコラム記事の内容をご確認くださいませ。
ただ、アンテナコンセントと電源コンセントが一体化したコンセントの場合は、作業に危険が伴い、交換などの工事には電気工事の免許が必要となります。
お部屋に用意されているものが電源一体型のアンテナコンセントである場合や、ご自宅でのユニット交換作業が難しいと思われる場合には、当あさひアンテナのフリーダイヤル、または公式サイトのメールフォーム、LINEアカウントまで、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
アンテナコンセントの概要や交換の手順などについては、以下の各コラム記事をご参照ください。
・アンテナコンセントとは?その種類や耐用年数、交換法などを徹底解説!
・テレビ端子(アンテナコンセント)がない部屋でのテレビ番組ご視聴方法
テレビ画面が乱れる要因2:お住まいのテレビ電波環境の問題
上記でも少し触れましたが、現在の地デジ放送では、お住まいの周辺にある地デジ電波塔から周辺のエリアに、地デジ電波として、UHF(極超短波)のうち、470MHzから710MHzまでの周波数帯の電波を送信しています。
地デジ電波の波長の幅は40センチから60センチ程度で、電波塔の先端である高い位置から、周辺の住宅にある地デジアンテナまで、音が広がるように送信されています。
この地デジ電波は空間を遠くまで伝わるほど、電波レベルが減衰する性質もあるため、関東地方、首都圏における東京スカイツリーのように、その地域の主となる電波塔(送信所、基幹局、親局)の周辺に、基幹局からの電波を受信して増幅し、あらためて周辺のエリアに送信する「中継局(サテライト局)」が数多く設置されており、日本国内の大半のエリアを放送エリアとしてカバーしています。
ただ、電波塔から送信された地デジ電波は、電波塔から距離が離れるほど、減衰によって電波レベルが低下していきます。また地デジ電波は一定の波長の幅を持つため、ビルなどの障害物にぶつかっても、障害物を乗り越えて広がる性質もございますが、それでもビルの影に当たる直近のエリアや、住宅密集地の家と家の間の狭い空間などには届きにくくなることもございます。
また地デジアンテナ(UHFアンテナ)により地デジ電波を受信できるエリアでも、主に電波塔からの距離と、山地など電波を遮る地形の影響から、実際に受信できる電波レベルは異なってきます。
一般的な基準として、電波塔が視認できる周辺エリアで山地などの障害物もなく、地デジ電波が80㏈(デシベル)以上で受信できるエリアは「強電界地域」と呼ばれます。
そして強電界地域の周辺で、やはり山地など障害物になる地形が少なく、80㏈から60㏈の強さで地デジ電波が届くエリアは「中電界地域」。中電界地域より遠いエリアや、山地などの付近で電波が遮られやすく、到達する地デジ電波が60㏈以下になるエリアを「弱電界地域」と呼びます。
お住まいの地デジアンテナは、基本的にこの電界地域に合わせて、機種や受信性能、設置位置などを選ぶ必要がございます。
基本的に強電界地域では、地デジアンテナの受信性能で8素子(相当)から14素子。中電界地域では14素子から20素子。弱電会地域では20素子からそれ以上の高性能モデルが使用されます。
現場の電波レベル(電界地域)に対してアンテナの受信性能が低いと十分な電波レベルが確保できないことはもちろん、受信性能が高すぎる場合も、余計なノイズなども受信してしまい、かえって地デジ映像の乱れにつながることもございます。
またこの地デジ電波レベルも、気候や天候の影響を受け、空間を伝わる間の減衰量、つまり各現場で実際に受信できるレベルに違いが生じます。電波は水分に吸収されやすいため、一年を通した気候の変化により、同じ現場でも6㏈程度の変動が生じるほか、雨や雪の際には大きく電波レベルが低下します。
そのため、お住まいの地デジアンテナで受信できる電波レベルがやや弱い場合、特定の季節や気候、雨、雪の日などに、地デジ画面が乱れるケースが出てまいります。
当あさひアンテナをはじめ、アンテナ工事の専門業者であれば、各現場の電界地域や周囲の受信条件、気候や天候による電波レベルの変動も計算し、最適なアンテナ機種や設置位置、またブースターなどの設置も含めて、余裕のある受信レベルを確保する工事を行います。そのため気候、天候などの影響で地デジ画像が乱れることはまずございません。
ただ、実際の工事を下請け業者が担当する家電量販店やホームセンター、ハウスメーカーなどのアンテナ工事では、設置時の電波レベル調査が、当日の電波レベルを確認するだけで不十分なケースもあり、特に受信レベルが弱くなりやすい壁面へのデザインアンテナの設置などでは、特定の季節や悪天候の際に、地デジ電波レベルが乱れるといったケースもございます。
この場合、お住まいの中でも、アンテナからもっとも遠く、ケーブル配線の長さから減衰量が大きくなるお部屋でのみ、地デジ画像の乱れが生じるケースもございます。
他にも、お住まいの近隣、電波塔の方向に、高層マンションなどのビルが建築され、地デジ電波が遮られる電波障害が生じるケースもございます。またそれまで電波を遮っていた建物が取り壊されることで、お住まいの電波状態が変動し、電波レベルの向上やノイズの混入などにより、お住まいのアンテナ設備とのバランスが狂うことも考えられます。
これら気候や天候、障害物など、周辺の電波状態、環境の変動や、アンテナ設置時の電波レベル確保不足などにより、地デジ電波の受信レベルが低下した場合、軽度のレベル不足で地デジ放送の画面が乱れる際には、前述したご説明と同様、アンテナが受信した電波レベルを増幅するブースターを設置する、設置されている場合は増幅レベルを上げる。また一部のお部屋でのみ電波レベルが低下する場合は、室内用ブースターやラインブースターなど補助的なブースターを設置して、不足する電波レベルを補填するという対処がございます。
ただ、住宅の近隣に高層建築が建てられるなど大きな障害物の発生で受信レベルが低下した場合には、地デジアンテナの機種(受信性能)の交換、設置場所の変更など、ご自宅では難しい大掛かりな工事による対処が必要となります。
衛星放送の場合は、日本の地上からみて、東経110度の方向(南西方向)に静止して見える人工衛星(静止衛星)から、上記した12GHzの電波を送信しています。
12GHzの電波は、波長の幅が約25ミリと非常に短く、光に近い性質を持ち、静止衛星から日本全域に照射されるような形で送信されています。
そのため衛星放送の電波は、地デジ電波のように地域による大きな電波レベルの差はなく、日本全域にてほぼ安定したレベルで受信できます。ただ、日本でも北部や南端、離島など、中央に比べて静止衛星からの距離が出るエリアでは、距離による減衰で受信できる電波レベルがやや弱まります。
また12GHzの電波は、性質が光に近い分、日光が遮られると影ができるように、障害物に遮られやすいく、障害物を乗り越える力が弱いという面もございます。
衛星放送用のBS/CSアンテナは、アンテナのディッシュを東経110度の方向へと正確に向けること。そしてアンテナを向けた方向に、12GHzの電波を遮るわずかな障害物もないことが設置の必須条件になります。
そのため、お住まいにBS/CSアンテナを設置した時点では受信には特に問題はなくとも、その後、アンテナを向けた方向に、ビルや民家などの建物ができる。樹木やその枝葉が伸びる。またクレーン車が停車する、洗濯物が干されるなどの一時的な障害物の発生でも、12GHzの電波の受信レベルが下がり、衛星放送の画面が乱れる原因となります。
また12GHzの電波は、多少の悪天候には大きな影響は受けませんが、雨や雪の粒が波長の幅(25ミリ)に近くなると、12GHzの電波が雨や雪の粒に吸収され、乱反射も生じることで、BS/CSアンテナの側で十分に受信できず、映像の乱れやまったく映らなくなる「降雨減衰」「降雪減衰」が生じます。
降雨、降雪減衰への対策は、基本的に天候の回復を待つことになりますが、一般的な戸建て住宅向けの45型(ディッシュの有効直径が45センチ)の製品ではなく、50型、60型、75型などやや大型で受信性能が高いモデルを使用することも対策となります。なお日本国内でも上記した北部など、12GHzの電波が弱くなるエリアでも、やや大型のBS/CSアンテナが使用されます。
またBS/CSアンテナのディッシュを向けた東経110度の方向に障害物ができた場合は、ご自宅の庭木などであれば、刈り取るなど撤去することで対応できます。ただ隣家の庭木や家屋の一部、設備やビルなどで12GHzの電波が遮られる場合は、隣家の方とご相談になるか、またお住まいでBS/CSアンテナの設置位置を変更する必要がございます。
BS/CSアンテナがお住まいのベランダなどに設置されている場合であれば、お住まいでアンテナの位置をずらすなど、ある程度の対応も可能ですが、障害物を避けて受信感度を確保しやすい屋根の上に設置し直すなどの場合は、作業に危険が伴うため、当あさひアンテナをはじめとする、アンテナ工事の専門業者にお任せください。
なお、建物その他、後になって建造された建築物や道路、線路などの設備によって、電波が遮られ、お住まいで地デジ、衛星放送の受信ができなくなる電波障害が発生した場合は、民法709条「原因者負担の原則」に基づき、その建築物のオーナーや建築主が費用を負担して、電波障害の出たお住まいでテレビ放送の視聴ができるよう、対応を取る必要が生じます。
お住まいで大規模な建造物により電波障害が出た場合のご相談先は、お住まいの自治体の担当部署になりますが、現在では建築主が、テレビ電波の受信や日照権などに関してもあらかじめ可能な限り対策を取り、問題が出る可能性のお住まいには説明が行くケースが多くなります。
地デジ放送や衛星放送の電波の概要や、電波環境によって生じる受信トラブルなどについては、以下の各コラム記事でも詳しく解説しております。
・現在の地上波テレビ放送で地上デジタル放送が開始されたのはいつ? デジタル放送とか何か、その仕組みや特徴も全解説!
・教えて!BS、CSやスカパーとは? 視聴料金からアンテナの選び方、業者による設置工事の費用相場、サポートの方法まで全解説
・地デジアンテナ設置に重要となる「強電界地域」「中電界地域」「弱電界地域」とは
・電波障害? テレビが映らない原因はアンテナトラブル? 確認と対処法
・地デジ用テレビアンテナの受信レベルが低くなる原因とは? ブースターによる対処法など受信レベルを改善する工事の方法を解説!
・テレビ放送電波の感度が低くなる原因は? 地デジアンテナの受信レベルを上げるための地デジ電波の基礎知識と工事の対処法を解説
・地デジやBS/CSアンテナで受信感度が落ち突然テレビが映らなくなる原因、受信レベルを上げ映るよう解決する対処法の工事は?
・テレビアンテナの受信レベル低下で地デジやBS放送が突然、映らなくなる原因と、受信感度を上げて解決する工事など対処法とは?
・雨や雪が降るとBS、CSの衛星放送が映らなくなる原因と衛星放送用テレビアンテナを調整して映るようにする対処方法とは?
テレビ画面が乱れる要因3:テレビアンテナ本体のトラブル
戸建て住宅の場合、一般的に、地デジアンテナ、BS/CSアンテナとも、屋根の上に立てたマストが設置位置に選ばれることが多くなります。
これは、地デジアンテナ、BS/CSアンテナとも、高所であれば、周辺の障害物に影響されにくいため受信環境が良く、全方向への角度調整も行いやすいため、安定した受信も確保しやすいことからです。
一方、屋根の上へのアンテナ設置では、アンテナ本体が風雨や雪、海沿いの潮風、野鳥が留まり酸性のフンをするなど自然環境の影響を受けやすくなり、老朽化やそれに伴うトラブルも生じやすくなるデメリットも生じます。
したがって、お住まいの見た目や、風雨などの影響を避けたアンテナの耐久性などを重視される場合には、住宅の外壁やベランダの内外。お住まいの条件で可能であれば屋内空間などにテレビアンテナを設置することもございます。
そのため現在では、地デジアンテナ機種として、屋根の上に設置される魚の骨のような形で、受信性能が高い半面、外観性がやや悪く自然環境にも影響を受けやすい古典的機種、八木式アンテナの他、主に壁面などに設置するパネル状のアンテナで、見た目が良く自然環境などにも強い一方、受信性能がやや低下しやすいデザインアンテナ。
そして屋根の上のマストに固定されるポール状の形で、自然環境への強さや外観性の良さを実現しながら、安定した受信も確保しやすい最新モデル、ユニコーンアンテナなども登場しています。
そしてこれら地デジアンテナには、アンテナの真正面にあたる方向でのみ受信性能が高まる「指向性」という性質があるため、近隣の地デジ電波塔の方向(もしくは地デジ電波がビルなどに反射、回折して方向が変わった反射波、回折波の方向)など、地デジ電波が現場に届く方向に合わせて、アンテナの正面側を正確に向ける必要がございます。
BS/CSアンテナに関しても、上記の通り、アンテナのディッシュを東経110度の方角に向けて、仰角、方位角(上下、左右の角度)とも、ミリ単位で正確に調整することが必須です。BS/CSアンテナに関しては、この角度調整がミリ単位で狂っても、受信感度が大きく低下するため、注意が必要です。
またBS/CSアンテナに関しては、前述の通り、衛星から送られる12GHzの電波を、アンテナのコンバーターで、ケーブルでの送信に適したMHz帯の電波に変換していますが、このコンバーターの作動には電源が必要となります。
BS/CSアンテナ(コンバーター)の電源は、アンテナ配線部に設置されたブースターの電源部。またはテレビなど受信機器で「BS電源設定」を行い、BS/CSチューナーの端子から、アンテナケーブルを通じて、ブースター側に電源を供給する形になります。
このコンバーターへの電源供給が正常に行われていないと、12GHzの電波がMHz帯に変換されないため、衛星放送が視聴できなくなります。
またテレビなどのチューナーからコンバーターに給電する場合、特定のテレビなど機器から常時給電する形式と、住宅内のすべてのテレビで衛星放送を視聴する際のみ随時給電する形式があり、給電方式に応じたテレビ側の設定や、配線部の機器の設置などが必要となります。
特に特定のテレビから常時給電する場合は、給電するテレビの電源が切れていると、他のテレビでも衛星放送を視聴できなくなります。
他にも、BS/CSアンテナに接続されるケーブルや接続部の劣化や、電源設定のミスなどでケーブルがショートを起こすと「E209」のエラーコードが表示され、保護機能が作動してコンバーターに電源が供給されなくなるため、やはり衛星放送が視聴できなくなります。
この場合は、劣化したケーブル、端子部などの交換、適切な電源設定を行うなどの方法で、ショートを解消することで、衛星放送を視聴できるようになります。
実際にお住まいのテレビアンテナ本体で起こりやすいトラブルとしては、やはり設置から10年程度すぎたアンテナで、経年劣化により耐久性が低下したときに生じやすくなる、アンテナ本体の部分的な破損や角度の狂いになります。特に屋根の上のマストに設置されたテレビアンテナは、自然環境に影響を受けやすく、老朽化やそれに伴うトラブルが生じやすくなります。
上記のように、地デジアンテナやBS/CSアンテナは、電波塔や静止衛星の方向から角度がズレると、受信感度が大きく低下しますが、本体の固定部やマストの経年劣化が進むと、この角度の狂いが生じやすくなります。
またアンテナ本体の経年劣化により、地デジアンテナの素子やBS/CSアンテナのコンバーター、またケーブルの接続部などが破損し、受信性能の低下や喪失、また電波の漏洩、ノイズの混入などが生じて、テレビ放送が正常に視聴できなくなることもございます。
このようなトラブルが生じた場合、角度の狂いでは、テレビアンテナの角度をあらためて正しく調整し、場合によっては劣化した設置部の部品を交換して、しっかりと固定し直す対処が必要です。
またアンテナの部分的な破損では、部品の交換などの補修を行うか、アンテナ本体の老朽化や損傷が激しい場合は、アンテナそのものの交換を行うことになります。なおご家庭用の45型BS/CSアンテナでコンバーターが故障した場合は、価格的にコンバーターのみの交換とアンテナそのものの交換が大差ないため、BS/CSアンテナ本体ごと交換します。
このアンテナの角度調整や、老朽化したテレビアンテナの交換に関しては、お住まいのアンテナがベランダの手すりなど、安全に作業が行える位置に設置されている場合は、お住まいでアンテナの固定部を調整して、近隣の電波塔や東経110度に向けて角度調整を行う。または同タイプのアンテナに付け替えを行うことも可能です。
ただ、屋根の上のマストなど、高所に固定されているアンテナの場合、アンテナの修理や調整、交換の作業には、大変な危険が伴うため、専門の安全講習を受け、専門技術と法令に適応した装備によって作業を行う、当あさひアンテナをはじめとする、アンテナ工事の専門業者へご依頼になることが必要です。
また、屋根の上でマストに設置された八木式アンテナやBS/CSアンテナなどの老朽化が進み、交換が必要になった場合では、地デジアンテナでは壁面へのデザインアンテナ設置やユニコーンアンテナ、八木式アンテナ高耐候モデルの採用。BS/CSアンテナも高耐風モデルの採用や設置位置の変更で、自然環境に強く、経年劣化やトラブルのリスクを抑えることができるアンテナ設置をお選びになるのも、ひとつの方法といえます。
なお、当あさひアンテナでは。老朽化したアンテナ本体を新しいアンテナに交換する工事に伴う、屋根の上などに設置された既設アンテナの撤去工事を、撤去したアンテナの処分も含めて、5,000円(税込み5,500円)からでお引き受けいたしております。
当あさひアンテナでは、各種地デジアンテナ、BS/CSアンテナのモデルについても、国内大手メーカーの最新機種、高品質モデルをご用意し、アンテナ本体および基本的な設置具、ケーブルなどの価格も含めた、業界最安に挑むアンテナ工事の基本設置工事費でご案内しております。
したがって老朽化したアンテナの交換に必要となる費用は、基本的にアンテナ撤去費用プラス、新しいアンテナの基本設置費用になります。
他にも、屋根の上にある既設アンテナの軽微な故障については、修理の工事を同じく5,000円(税込み5,500円)から。角度のずれたアンテナの角度調整に関しては、8,000円(税込み8,800円)からでお引き受けしております。
なお、地デジ、BS/CSアンテナ本体の種類や設置費用、取り付け工事のや修理の手順と、おすすめ業者、角度調整の手順や交換の目安などについては、以下の各コラム記事で詳しくご説明しております。
・戸建て住宅でのテレビアンテナ基本設置工事の費用相場は? 料金を抑えることができる業者の選び方も紹介【2024年度最新版】
・テレビアンテナの修理を業者に頼む方法と費用の相場は? アンテナ修理の種類と火災保険に対応もできる最適な業者の選び方も解説
・新築住宅でテレビアンテナ工事の流れは? 即日工事、相見積もりで安くて高品質の工事を依頼できる業者の種類、費用相場も紹介!
・工事業者がおすすめする戸建て住宅テレビアンテナ取り付け位置の比較と選び方・適したアンテナ機種や事業者による費用も紹介!
・戸建て住宅のテレビアンテナ工事で人気のアンテナ機種は? 料金や工事費用の相場、失敗しない業者の選び方も解説!
・衛星放送用バラボラアンテナ・BS/CSアンテナの種類と選び方とは? 地デジテレビアンテナとの違い、家屋への設置工事を解説
・地デジテレビアンテナをさまざまな場所に設置する工事と、アンテナの向きや方向を自分で調整する方法とは? 費用の相場も解説!
・地デジ放送のテレビアンテナを地図で正しい電波の向きに調整する方法とは? 自分でアンテナの方向を調整できる設置の位置も解説
・BS/110度CSアンテナで安定して衛星放送を受信できる設置の場所とアンテナの向きや角度を正確に調整する方法
・地デジ用テレビアンテナ設置の工事で向きや角度を調整すべき方向と「指向性」の関係とは? 自分で方角を調整する方法も解説!
・BS/CSアンテナの角度調整に重要な「指向性」とは? 人工衛星の方向を確認できるスマホアプリ「BSコンパス」も徹底解説!
・衛星放送用BS/CSテレビアンテナの寿命は何年? 取り付けから約10年後の交換工事の時期や映らなくなった時の対処法を解説
・地デジ、衛星放送でテレビアンテナの向きに適した方向とは? アンテナ機種別の設置位置や自分で角度調整を行う方法も解説!
・地デジ、衛星放送用テレビアンテナを正しい向きに自分で調整する方法とは? アンテナ角度の調整に必要となる工事の手順も解説
・テレビアンテナの寿命と交換時期は? 地デジ・衛星放送別に必要な工事を徹底解説!
・BS/CS衛星放送や地デジ用アンテナの寿命と交換時期は何年? 取り付けから約10年でテレビが映らない時の対処法を解説!
・ご自宅に設置されているテレビアンテナを交換する時とは? 工事にかかる費用の相場はいくらか、また工事を進める方法を解説!
・衛星放送用のBS/110度CSアンテナには電源が必要? BS/CSアンテナにテレビなどの設定で電源を供給する方法とは
テレビ画面が乱れる要因4:アンテナからアンテナコンセントを結ぶ配線部の機器の問題
ここまでの項目でも少しご説明いたしましたが、お住まいに設置された地デジ、衛星放送のテレビアンテナから、各お部屋を接続するまでのアンテナケーブル配線の間にも、さまざまな機器が設置されております。
まず、お住まいに地デジアンテナの他、BS/CSアンテナや地方局用地デジアンテナ等、複数のテレビアンテナを設置されている場合は、各アンテナからのケーブル(電波)をまとめて配線部をシンプル化し、コストを抑える「混合器」という機器に接続し、その先のケーブルを一本化します。
ただ地デジアンテナとBS/CSアンテナの場合は、後述する混合器の機能を兼ね備えた「UHF・BSCS混合ブースター」を使用することが多くなります。
そしてアンテナ配線部では混合器を除いてアンテナのもっとも近くに設置される、配線部でも重要な機器が、アンテナの受信した電波レベルを増幅する「ブースター」です。
ブースターは基本的に、前述した中。弱電界地域などで、不足する地デジ電波レベルを増幅するための機器ですが、電波状態を問わず、戸建て住宅で三台以上のテレビを設置する場合には必要となるため、実質的には設置が必須の機器となります。
一般的に設置される屋外用ブースターは、アンテナが設置されるマストの下部など、アンテナの近くに設置され、電波を増幅する本体である「増幅部」。屋根裏などのアンテナ配線部に設置され、電源コンセントに接続されて、配線部のケーブルを通じて増幅部に電源を供給する「電源部」に分かれます。
機器の種類では、地デジ放送のみに対応する「UHFブースター」と、地デジ放送、衛星放送に対応し、双方の混合器の役割も持つ、前述の「UHF・BSCS混合ブースター」も存在します。
このブースターは、配線部の心臓部ともいえる重要な機器ですが、それだけにトラブルによりテレビ画像が乱れる原因にもなりやすい部分です。
ブースターの増幅部には、電波の増幅レベルを調整できるスイッチやダイヤルなどがついており、お住まいの条件(テレビを設置するお部屋の数など)に応じて、増幅レベルを調整します。またブースターには、電波だけでなく電波に混入するノイズも増幅してしまう性質があるため、適切なレベル調整のほか、ノイズが混入しないようできるだけアンテナの近く。ただしブースターの発する電磁波がアンテナに悪影響を与えない距離に設置する必要がございます。
またブースターは電源を必要とする電子機器であるため、長年の使用により通電による回路の経年劣化が進んでゆき、10年程度で寿命を迎えます。寿命を迎えると電波の増幅機能の停止、低下などが生じやすくなり、その場合は住宅内の各お部屋に届く電波レベルが低下し、映像の乱れやエラーコード表示などの原因になります。
そのため、ブースターの調整不足などで到達する電波レベルが低下し、お住まいのテレビ画面が乱れる場合は、増幅レベルの再調整。またブースターの故障や劣化で十分な増幅レベルが得られなくなった場合は、ブースターの交換が必要となります。
この作業も、ブースターの増幅部がベランダや屋根裏、天井裏など手が届きやすい場所にある場合は、ご自宅での調整、交換も不可能ではございません。
ただ屋根の上など作業に危険が伴う位置の場合はもちろん、現場に適したブースターの交換や調整には専門知識が重要となるため、やはりアンテナ工事の専門業者にご依頼になることがオススメです。
そしてブースターからのケーブルの先に設置されるのが、上記した「分配器」です。
分配器はアンテナやブースターから送られる電波を、複数のケーブルへと等分の電波レベルで分配する役割を持ち、分配器からのケーブルが、各お部屋のアンテナコンセントのユニットへと接続されます。
分配器には2分配から8分配(7分配を除く)の6種類があり、通常はお住まいの分配数に、予備の一端子を足した分配数の機器が使用されます。
他にも、一本のケーブルに地デジ電波、衛星放送の電波を混合している場合には、上記したようにアンテナコンセントのユニット部、またはアンテナコンセントの先に、それぞれの周波数帯をあらためて2本のケーブルに分ける「分波器」を設置し、各ケーブルをテレビなど受信機器のチューナー端子に接続することになります。
以上が、一般的な戸建てのお住まいにおける、テレビアンテナからテレビなど機器までの配線の構造です。そして室内アンテナケーブルの配線でご説明したのと同様、この配線部のケーブルや機器の劣化でも、電波の漏洩やノイズの混入などが生じ、テレビ画面が乱れる要因になり得ます。
また新4K8K衛星放送など周波数帯の高い電波になるほど、電波の漏洩が生じやすくなるため、周波数帯に対応できる高品質のケーブルやシールド性能の高い4K8K(3442MHz)対応型などの機器が必要となります。また分配器でも使用しない予備の端子には、電波の漏洩、混入を防ぐフタの役割となる、ダミー抵抗器を設置することも必要です。
他にも、上記の項目でもご説明した通り、同じ住宅内のケーブル配線でも、アンテナからの距離が遠く、配線が長くなるお部屋ほど、電波の減衰量が高くなり、到達する電波レベルの低下で、テレビ画面が乱れる要因にもなり得ます。
これらケーブル配線部や機器の交換も、天井裏やマルチメディアボックスに設置されている分配器などであれば、お住まいで交換が可能なケースもございますが、ケーブル配線部全体の交換など、大掛かりな作業になる場合には、やはりアンテナ工事の専門業者にお任せくださいませ。
またアンテナ配線部の問題により、一部のお部屋で電波レベルが低下している場合には、前述のように室内用ブースター、ラインブースターの設置で、電波レベルを補完することも有効な対策となります。
アンテナ配線部や各機器の機能、設置や交換、修理の内容や費用については、詳しくは下記のコラム記事で詳しくご説明しておりますので、こちらをご参照くださいませ。
・テレビアンテナでブースター、分配器など周辺機器の設置や修理、交換の費用相場は?工事の方法やどこの業者に頼むか選び方も解説
またブースター、分配器など、各機器や、新4K8K衛星放送などに対応できる機器についての詳細は、以下のコラム記事をご確認くださいませ。
・テレビアンテナに「ブースター」は必須の機器なのか? その種類と性能、必要なケースを解説【地デジ設置・あさひアンテナ】
・テレビの映りが悪い時に使うアンテナブースターとは? 屋外用・屋内用ブースターの違いと症状別の選び方を徹底解説!
・地デジ用テレビアンテナの受信レベルが低くなる原因とは? ブースターによる対処法など受信レベルを改善する工事の方法を解説!
・テレビ放送の映りが悪い際にアンテナブースターの交換は必要?
・1基のアンテナから家にあるすべてのテレビに電波を送る「分配器」とは? その種類と選び方、分波器などとの違いを徹底解説!
・テレビアンテナへの分配器の設置で、現場の電波レベルや条件に適した選び方と注意点を徹底解説。分波器や分岐器との違いとは?
・テレビアンテナの電波を各部屋に分岐する方法は? 分配器と分波器の違い・接続方法や選び方
・地デジ用と衛星放送用、両方のテレビアンテナ設置で工事コスト軽減のため必要な機器、混合器、分波器とは何なのか?
・戸建て住宅のテレビアンテナ工事に必要な配線と分波器の役割とは? 地デジ、BS/CS放送に適した機器の選び方も解説!
・「新4K8K放送」を視聴するためのアンテナ工事、配線について徹底解説!
・「新4K8K衛星放送」ご視聴に必要な機器・完全チェック解説! テレビで全4K8Kチャンネルを見るための機材とは?!
テレビ画面のトラブルに対してご自宅でも可能な対処法・まとめ
一般的な戸建て住宅にて、テレビ画面の乱れが生じた場合に考えられる要因と、お住まいで可能な対処方法の一覧は、以上の通りでございます。
また本文の内容の他にも、お住まいでのテレビ画面の乱れに対する対処法としては、以下の各コラム記事の情報が参考になるかと存じます。
・テレビアンテナの修理を自分で行う方法・原因と対処を解説。おすすめ工事業者の比較と選び方、費用の相場も紹介!
・地デジ放送は映るのにBS/CS衛星放送が映らない場合の対処法
・BS/CS衛星放送は映るのに地デジ放送が映らない場合の対処法
ただ、実際のお住まいごとのテレビ電波の受信条件、テレビアンテナや配線の構造や設定などはセナ万別のため、上記の内容をご理解の上でも、原因の特定や対処が難しい場合もあるかと存じます。
そのような場合は、取り急ぎ、当あさひアンテナのフリーダイヤルへのお電話、または当サイトのメールフォーム、LINEアカウントまでお問い合わせくださいませ。
フリーダイヤルへのお問い合わせでは、アンテナ工事の作業車に同乗する研修を重ね、現場にてプロの専門知識を習得したオペレーターがご対応の上、お住まいで発生しているテレビ画面トラブルの具体的な症状。またお住まいのアンテナや配線の構造などから原因を推察し、お住まいで可能な限りの対処を詳しくご説明いたします。
そしてお電話でのご案内で問題が解決した場合には、料金は1円たりともいただきません。
またお電話では原因がはっきりしないか、お客様ご自身で対処が難しいケースでは、そのままお電話でご依頼くだされば、弊社のアンテナ職人が最短即日で現場へと駆け付け、正確な原因の特定と、復旧に必要な工事内容と、お見積もり費用をご提示いたします。
当あさひアンテナでは、現地への出張調査やお見積もりなどは、出張料、キャンセル料などの各種費用をすべて含めて「完全無料」で行っておりますので、お客様は弊社のご説明とお見積り費用にご納得いただき、工事をご契約いただくまで、一切の費用はかかりません。
また修理内容に関しても、アンテナや機材の修理や交換など、現場の状況に応じて、アンテナの状態から修理後のトラブル再発などの可能性も考慮して、もっとも低価格でコストパフォーマンスが高いと思われる方法をご提案いたします。
実際の施工は、弊社スタッフである、優秀なアンテナ職人による完全自社施工で、豊富な経験と高い技術力による丁寧な施工をお約束いたします。
工事料金についても、緊急の修理でお客様のお手間を省くべく、現金だけでなく、各種クレジットカードや電子マネーでのご精算にも対応しております。
さらにアンテナ交換を行った後のアフターサービスでは、業界最長クラスの、施工日から「10年保証」サービスをご用意しております。もし弊社の施工後、万が一にもトラブルが再発した場合には、保障範囲内の問題であれば、完全無料で復旧までご対応いたします。
突然、お住まいのテレビが正常に映らなくなり、ご自身での対処が難しい際には、可能な限りの低料金にて、早急な復旧をお約束する当あさひアンテナまで、まずはお気軽にご一報くださいませ。