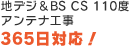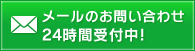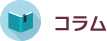地デジ、衛星放送のテレビアンテナ故障例、テレビ放送が映らなくなった場合に考えられる原因とその対処法は? 必要な工事を解説
テレビが映らない、画面にエラーコードが表示される、電波が十分に届いていないなど、地上波デジタル放送(地デジ)、衛星放送(BS/CS)のアンテナ故障例について、その主な原因と、修理のための工事の方法をご説明してゆきます。
2023年(令和5年)現在でも、地上デジタル放送(地デジ)や、衛星放送(BS/CS)のテレビ放送をご視聴になる方法は、テレビアンテナ設置が主流になっております。
地デジや衛星放送のアンテナ設置であれば、NHK受信料、衛星放送の有料チャンネルなどを除いて、アンテナが作動している限り、永続的に無料でご視聴いただけるのが最大のメリットです。近年ではテレビアンテナもさまざまなモデルが登場し、住宅の外観にも影響を与えないことが多くなっております。
ただこのように便利なテレビアンテナも、主に屋外に設置されることから、風雨などによる老朽化も進み、ある日突然、トラブルが発生してテレビ放送が視聴できなくなることもございます。
そこで当コラムでは、地デジ、衛星放送のテレビアンテナについて、発生しやすい故障例とその原因。またそれぞれの対処法や、トラブルを避けられるアンテナ機種、アンテナ設置方法について、2023年(平成5年)の最新情報を元に解説してまいります。
【地デジ放送の基礎知識】
ここでは地デジ放送の基本的な仕組みと、2023年現在、使用される地デジアンテナの種類について解説してまいります。
地デジ放送の仕組み
地デジ放送(地上デジタルテレビ放送)は、2011年(平成23年)に完全停波した、かつての「地上アナログ放送」に代わる形でスタートした地上波放送(地上派テレビ放送)です。2003年(平成15年)に放送スタートし、それ以降、地上アナログ放送が停波するまで、移行期間として、双方が並行して放送されていました。
地デジ放送は、テレビ番組を放送するテレビ放送局から、日本全国に多数、設置されている中継局(電波塔)を経由して、各戸建て住宅や集合住宅などの建築物に設置された地デジアンテナまで、地デジ電波を送信する形式のテレビ放送です。
地デジアンテナによって住宅などで受信された地デジ電波は、住宅内の配線を通じて屋内のテレビなど受信機器に送信され、機器内の地デジチューナーが、電波をテレビ映像用の信号に変換することで、地デジ放送を視聴できるようになります。
地デジ放送の電波
現在の地デジ放送の電波は、中継局から送信される「UHF(極超短波)」帯の電波です。
UHF帯の電波は、かつてのアナログ放送で主な電波として使われていた「VHF(超短波)」帯の電波と比べると、直進性(まっすぐ進む性質)が高くなります。そのため中継局からの距離が遠くなるほど、電波強度(電波レベル)が弱くなることに加えて、中継局とアンテナとの間に、高層建築物や山地などの障害物があると、電波が遮られてしまいます。一般住宅などの地デジアンテナで受信できる地デジ電波レベルが弱い状態であると、テレビ放送が映らない、映像が乱れるなど視聴トラブルの原因となります。
ちなみにアナログ時代のテレビ電波であったVHF波は、UHFより周波数が低いため、UHF波に比べると高層建築の向こう側や、山間部でも受信しやすいという性質がありました。
反面、周波数が高い電波は波長が短くなるため、受信に必要なアンテナも小型化できます。そのため現在の地デジアンテナは、アナログ放送時代に比べると小型化が進み、さまざまな機種も登場しております。
地デジ電波については、以下のコラム記事もご参照ください。
地上デジタル放送の「地デジ電波」基礎知識
地デジ放送の電波が強い地域、弱い地域
現在の日本国内では、ほとんどの地域で地デジ放送が受信できます。ただ各中継局からの距離や地形などによって、エリアごとに受信できる地デジ電波のレベル(強弱)には違いがございます。
基本的に、そのエリアで受信できる地デジ電波レベルの強さの順に「強電界地域」「中電界地域」「弱電界地域」。そして「難視聴地域」の区分が存在します。
この電界地域に公式な定義は存在しませんが、電波強度の単位「㏈(デシベル)」において、そのエリアで受信できる地デジの電波レベルが「80㏈」であれば強電界地域。「80㏈」から「60㏈」になるエリアは中電界地域。「60㏈」以下となるエリアが弱電界地域とされています。ただこの電波レベルは、悪天候時にはやや下がる他、一年を通した季節の変化などにより「6㏈」前後の変動も生じます。
また地デジ中継局からの距離が極端に遠い、山間部などで地デジ電波が遮断されるなどの要因で、地デジ電波がほとんど受信できないエリアは「難視聴地域」にあたります。
お住まいの地域の地デジでの地デジ電波の強さを調べるためには、一般社団法人「放送サービス高度化推進協会」の公式サイト内「放送エリアの目安」が参考になります。ただ個々の現場では、周辺の建築物や地形などにより、例えば強電界地域でも局地的に地デジ電波の受信レベルが低くなる、といった事態も考えられます。
ご自宅などでの正確な地デジ電波の強さは、アンテナ工事の専門業者などに依頼して、専用のアンテナチェッカーを使用して計測することで、確認できます。
各電界地域などについては、以下のコラム記事にも詳細がございます。
地デジアンテナ設置に重要となる「強電界地域」「中電界地域」「弱電界地域」とは
徹底解説!強・中・弱の地デジ電界地域に適したテレビアンテナ工事の選び方、調べ方とは?
地デジ放送用の地デジアンテナ
2023年現在、地デジ放送を受信するための地デジアンテナには、主に「八木式アンテナ」「デザインアンテナ」「ユニコーンアンテナ」の3機種がございます。なお地デジアンテナでは衛星放送を受信できませんのでご注意ください。
以下、3機種についての概要をご説明してまいります。
八木式アンテナ
八木式アンテナは、戸建て住宅の屋根の上などによく見られる、魚の骨のような形状をした金属製のアンテナです。
名称は開発者に由来し、八木アンテナ、八木・宇田アンテナとも呼ばれます。大正時代の1920年代に開発された古典的アンテナで、アナログ放送時代はテレビアンテナと言えば基本的に八木式アンテナのみでした。
八木式アンテナの特性は、現在の地デジアンテナとしても、三機種の中でもっとも受信性能が高い点になります。
これは基本的に、屋根の上などの高い位置に設置するため、周辺の障害物に影響されにくく電波を受信しやすいことに由来します。
さらに八木式アンテナには、矢印状の骨組みに設置された短い横棒「素子(エレメント)」数が多いほど受診性能が高くなる特性があり、設置できる素子数の幅が広いメリットもございます。
現在の八木式アンテナは、地デジの高電界地域向け「4素子から14素子」。中電界地域向け「14素子から20素子」。弱電界地域向け「20素子から28素子」の機種がある他、Ⅹ字型の金具に複数の素子パーツをつけた高性能素子を用いて受信性能を高めた「パラスダックアンテナ」では、27素子、30素子モデルも存在します。
このように受信性能が高くモデルごとの幅も広いため、現在でもさまざまな地域で八木式アンテナが使用され、弱電界地域では屋根の上に高性能の八木式アンテナを設置する以外の選択肢がないこともございます。
また古典的機種であることから、本体価格も現在の地デジアンテナではもっとも低価格となります。
八木式アンテナの設置位置としては、屋根の上が基本ながら、現場の電波状態によっては、ベランダの内外、また専用の設置具で壁面に固定する。軒下に吊り下げるなどの設置方法も可能です。
半面、八木式アンテナは、アナログ放送時代に比べると小型化していますが、現在の地デジアンテナではサイズが大きく外見も特徴的であるため、住宅の外観や景観とマッチしないこと。また景観地域や高さ制限などの条例で屋根の上に設置できないこともございます。
さらに主に屋根の上に設置されるため、長期間、使用し続けるうちに、風雨や雪、海沿いの潮風、また鳥が留まり、フンをする鳥害などの影響を受けて、腐食や錆の発生などの老朽化が進みやすく、老朽化が進んだアンテナは傾きによる角度のズレや、大きな災害の際に倒壊するなどのトラブルも考えられます。
デザインアンテナ
デザインアンテナとは、2009年(平成21年)ころに普及しはじめた、主に長方形の薄型の箱のような形状の地デジアンテナです。
基本的に壁面やベランダの内外などに設置され、ボックスアンテナ、ケースアンテナ、フラットアンテナ、平面アンテナ、壁面アンテナなどとも呼ばれます。デザイン性が高くカラーバリエーションも豊富なため、住宅の壁面に設置しても外観性や景観を乱さない上、風雨や雨など気候にも影響されにくく、経年劣化が進みにくいため、耐用年数も長くなるなどメリットが豊富です。
さらに現場の電波状態が強く、住宅の建材、断熱材などが電波を通しやすいといった条件が揃った場合は、屋根裏、天井裏への設置で、自然環境からの影響や、住宅の外見への影響をほぼゼロにする設置も可能です。
デザインアンテナのデメリットは、受信性能が、八木式アンテナの素子数に比較して、主要機種で「20素子相当」「26素子相当」とやや低くなること。また同素子数の八木式アンテナと比べてもやや受信感度が低い他、設置位置の低さもあって、八木式アンテナに比べると受信性能が低くなること。本体価格も八木式アンテナに比べてやや高い点が挙げられます。
基本的にデザインアンテナは、強電界地域から中電界地域での使用が推奨される他、地デジ電波が遮断されやすい高層建築物の付近や住宅密集地などでは使用できないこともございます。
ユニコーンアンテナ
ユニコーンアンテナは、2017年(平成29年)に日本の大手アンテナメーカー「マスプロ電工」さんが開発した、第三世代といえる最新鋭の地デジアンテナです。形状はポールの先にほぼ円筒形のアンテナ本体が設置された、八木式アンテナより小型で非常にスタイリッシュなデザインとなっております。
設置位置は屋根の上、また専用設置具で屋根の張り出し部(羽目板)や壁面の高所などに設置でき、アンテナの高度を確保できます。
ユニコーンアンテナの受信性能は「20素子相当」ですが、高さを確保できるため周辺の障害物からの影響を避けることができ、受信感度が高まるため、デザインアンテナの設置が難しい現場でも使用できることが多くなります。
またスッキリとした外観のため、住宅のデザインや景観を損なわない上、その形状から風雨を受け流せるため、経年劣化が進みにくく、アンテナトラブルを避けられて耐用年数が長くなるなどのメリットがあり、八木式アンテナとデザインアンテナの長所を兼ね備えた地デジアンテナとも呼ばれます。
ただデメリットとしては、最新機種であるため地デジアンテナでは価格がもっとも高くなること。また同じ20素子から高性能の八木式アンテナに比べると受信感度は低くなるため、弱電界地域では使用できないケースが多いといった点がございます。
各地デジアンテナの詳細については、以下のコラムもご参照ください。
地デジテレビアンテナの長老「八木式アンテナ(八木アンテナ)」とは?
地デジ用テレビアンテナ一番人気のデザインアンテナとは? 価格から工事費用、料金相場、失敗しない業者の選び方まで徹底解説!
地デジアンテナの最先端、ユニコーンアンテナとは? 特徴、メリット、工事費用の相場まで徹底解説!
台風対策に最適!地デジ「デザインアンテナ」と「ユニコーンアンテナ」とは?
この最小デザインアンテナがすごい!スカイウォーリーミニ(マスプロ電工)
【衛星放送(BS放送、CS放送)の基礎知識】
続いて、いわゆるBS放送、CS放送などの衛星放送の基礎知識や、衛星放送用のBS/CSアンテナについて解説してゆきます。
衛星放送(BS/CS放送)の仕組み
衛星放送とは、地球上から約36,000キロ上空、宇宙空間の周回軌道上で、地球の自転に合わせて周回し、地上からは常に上空の一点に位置する「静止衛星」から、テレビ電波を送信する方式のテレビ放送です。
日本の衛星放送には「BS放送」「CS放送」の2種類があり、2018年(平成30年)には、それぞれに4K、8Kのチャンネルを追加する形で「新4K8K衛星放送」もスタートしております。
これらの衛星放送は、やはり戸建て住宅などの各建築物に、パラボラアンテナであるBS/CSアンテナを設置することで、衛星からの電波を受信し、テレビなど受信機器に内蔵された、または外付け型の衛星放送(4K8K)チューナーにより、テレビ用の映像信号に変換することで、衛星テレビ放送を視聴できます。
衛星放送の電波
BS放送、CS放送の人工衛星は、CS放送の一部サービスを除いて、基本的にどちらも東経110度に位置しております。そのため一台のBS/110度CSアンテナの設置で、BS放送、CS放送の双方を受信できます。
基本的に衛星放送は人工衛星から日本の全域に電波が送信されているため、日本全国でBS/CSアンテナの設置により受信できます。
衛星放送は広範囲へ効率的に放送電波を送信することができ、地上の地形や建物などの障害物、また災害などに影響されないという特徴がございます。ただ人工衛星から放送電波を送信しているため、衛星からの距離が遠くなる離島部や、国内の北部、南端などの地域では、やや電波レベルが弱くなります。
また衛星放送の電波は、高周波数で非常に波長が短くなるため、波長の大きさに近い大粒の雨や雪などの際には、雨や雪の粒に電波が吸収され、乱反射するなどの状態になり、BS/CSアンテナで受信できるレベルが低くなり、受信不良が起こることもございます。
これらを「降雨減退」「降雪減退」と呼び、衛星放送の特性となっております。これらの減衰は天候の回復により解消します。
衛星放送についての詳細は、以下のコラム記事もご確認ください。
衛星放送(BS放送・CS放送)の「テレビ電波」基礎知識
衛星放送の種類
・BS放送
BS放送は、東経110度に位置する「放送衛星」から電波を送信する衛星放送です。
BS放送では主にBSの広域民放、NHKを中心とした無料放送チャンネルの他、月額契約で視聴できる有料チャンネルが存在します。
・CS放送
CS放送は、やはり東経110度に位置する「通信衛星」から電波を送る衛星放送になります。
主なCS放送は東経110度の人工衛星から送信されますが、他に東経124度、128度の軌道上にある人工衛星も利用されます。このためBSを含むそれぞれの放送は「110度BS/CS」「124度CS」「128度CS」とも表示されます。
CS放送には現在、110度CSデジタル放送「スカパー!」と、124度128度CSデジタル放送「スカパー!プレミアム」が存在します。
それぞれ大半は有料チャンネルですが、さまざまなジャンルに細分化されており、お好みに合わせたチャンネルを選択して視聴できる点が特徴です。ただ124度128度CSデジタル放送「スカパー!プレミアム」のご視聴には、110度BS/CS用とは別に専用のアンテナ、または110度BS/CSを含めすべての衛星放送を受信できるマルチアンテナが必要です。
新4K8K衛星放送
「新4K8K衛星放送」は前述のように、従来のBS放送、CS放送であるフルハイビジョン(2K、FHD)放送に、4K、8Kに対応するチャンネルを追加したものです。
具体的な違いとして、4Kは2Kの4倍、8Kは2Kの16倍の画素数に加え、色彩や色調の表現、動画のなめらかさや音質も格段に向上し、よりリアルで精細、細かな動きの映像を一般のご家庭でご視聴いただけます。
ただ新4K8K衛星放送では、従来の衛星放送の「右旋円偏波」では周波数帯が不足したため、大半のチャンネルで「左旋円偏波」という電波を新しく導入しております。そのため旧来の2K対応BS/CSアンテナではBSの一部4Kチャンネルしか受信できず、すべての4K8K放送を受信するためには、4K8K対応のBS/CSアンテナが必要となります。
他にも受信装置として4K、8Kテレビの他、ブースター、分配器などのアンテナ機器も「3442MHz(4K8K)対応型」が必要となります。
新4K8K衛星放送については、以下のコラム記事もご参照ください。
「新4K8K放送」を視聴するためのアンテナ工事、配線について徹底解説!
「新4K8K衛星放送」ご視聴に必要な機器・完全チェック解説! テレビで全4K8Kチャンネルを見るための機材とは?
【衛星放送(BS/CS放送)を受信するためのBS/CSアンテナ機種】
基本的に、現在の一般的な110度BS/CS放送を受信するためのBS/CSアンテナは、浅いお椀のようなディッシュ部と、その中央で電波を集めるコンバーター、それを固定するアームによって成り立つパラボラアンテナです。
基本的に前述した、124度128度CS放送の専用アンテナ、また2K対応型と4K8K対応型の違いを除けば、メーカー、モデルを問わずアンテナの形状や受信性能はほぼ同じになります。なお2023年現在の110度BS/CSアンテナは、大半が4K8K対応型です。
ただBS/CSアンテナの中にも、アンテナサイズの他、外観性や耐風性に工夫を凝らしたモデルも存在します。
BS/CSアンテナのサイズ
BS/CSアンテナは、ディッシュの直径が大きいほど受診能力が向上します。一般家庭用のBS/CSアンテナは、ディッシュ直径が45センチの「45型」が主流ですが、より受信性能が高い「50型」「60型」「75型」なども存在します。
これらディッシュ部が大型のBS/CSアンテナは、前述した国内の北部や離島部など、衛星放送の電波レベルが弱いエリアで使用される他、降雨減衰や降雪減衰の対策としても有効です。なお90型以上の超大型BS/CSアンテナは、マンションなどの集合住宅に設置される共同受信用になり、一般のご家庭で使用されることはまずございません。
半面、大型のBS/CSアンテナは、強風や積雪などによる影響を受けやすくなり、アンテナトラブルのリスクも高まります。またアンテナ本体の重量も増すため、戸建て住宅などに設置する場合は、設置場所がアンテナ重量に耐えうるか確認することが必要となります。
カラーバリエーション
BS/CSアンテナは、障害物のない上空に向けて設置されるため、夏場などは太陽光を受け、熱や紫外線による影響を受けやすくなります。
そのため基本的な本体色は、太陽光に影響されにくい白色になりますが、近年では住宅の外観性にも配慮して、アンテナの熱吸収を抑える塗料を用いた、建物の外観と調和する黒色などのBS/CSアンテナも販売されております。
高耐風モデル
BS/CSアンテナは、ディッシュ部を持つ構造から、風雨の影響を受けやすい性質がございます。
一般的なBS/CSアンテナの耐風水準は「風速20m/s(秒速20メートル)」程度ですが、台風などの際には、この風速を越える強風が吹くことも珍しくございません。このような強風にも対応できるBS/CSアンテナが「高耐風モデル」です。
BS/CSアンテナの高耐風モデルでも代表的なモデルが、国内の代表的なアンテナメーカーである「DXアンテナ」さんの「BC453SG」です。
BC453SGは45型、4K8K放送対応のBS/110度CSアンテナですが、強風対策として、ディッシュ部に細かいパンチングホールがいくつも開いており、風を通す構造になっております。さらに取り付け金具も強風に抵抗できるよう強化されております。
BC453SGの受信可能な風速は台風時並みの「50m/s(秒速50メートル)」です。さらにアンテナ本体が壊れない目安である耐風速は「70m/s」の性能を誇ります。そのため台風などによりアンテナ設置部が根こそぎ破損するなどの事態がない限り、かなりの強風でも大きなダメージを受ける可能性の低いBS/CSアンテナモデルだといえます。
BS/CSアンテナや各モデルについては、以下のコラムもご参照ください。
BS/CSアンテナ(衛星放送用アンテナ)の基礎知識
台風対策に最適! 究極の高耐風BS110度CSアンテナ「BC453SG」(DXアンテナ)
【アンテナトラブル例:アンテナ角度のズレ】
ここからは、各アンテナ機種で起こり得るアンテナトラブルの実例と、その対処についてご説明してゆきます。
まずはもっとも発生しやすい、アンテナ角度のズレから解説いたします。
地デジアンテナにおける角度のズレ
前述のように地デジアンテナ機種の中でも、屋根の上に設置される八木式アンテナは、強風や大雪などによって傾く、倒れるなどの問題が発生しやすくなります。
地デジアンテナが中継局や電波の方角へ向いていないと、受信できる地デジ電波が弱くなり、地デジのテレビ画面が乱れる。映らなくなり各種のエラーコードが表示されるなどのトラブルが起こりえます。
このような場合は、アンテナ角度の再調整が必要です。ただアンテナの設置位置がベランダや屋上フロアのある住宅などの場合を除いて、屋根の上や外壁の高位置、屋根の破風などに設置されたアンテナの角度調整には、大変な危険が伴います。
そのため高所でのアンテナ角度調整は、アンテナ工事の専門業者などに依頼されることが基本と言えます。
地デジアンテナの角度調整については、詳しくは以下のコラム記事で解説しております。
・地デジのテレビアンテナで受信できる方向は指向性で決まる? アプリでアンテナの方向調整に最適な角度を調べる方法も徹底解説!
BS/CSアンテナにおける角度のズレ
BS/CSアンテナは、衛星から直進的に送信される電波を受信するため、非常に指向性が高くなります。そのためBS/CSアンテナの向きが、衛星の方向からわずかにずれただけでも、衛星放送を受信できなくなるケースがございます。
またBS/CSアンテナは特に風雨の影響を受けやすい形状でもあるため、激しい台風などでアンテナ角度のずれが生じることもございます。
ご自宅のBS/CSアンテナが、ベランダの手すりなど、安全に手が届く位置に設置されている場合は、ご自宅での微調整で受信状態を回復できることもございます。この場合の調整方法は、まずは衛星放送を受信できるテレビで、設定画面などからBS/CS放送の「アンテナレベル」画面を表示してください。これはテレビ側に届いているBS/CSの電波レベルを数値などで表示する画面です。詳しいアンテナレベルの表示方法、また数値の読み取り方などは、テレビなど機器に付属のマニュアルや、メーカーの公式サイトなどをご確認ください。
この画面でアンテナレベルを確認しつつ、BS/CSアンテナの向きをミリ単位で調整してゆきます。この際、アンテナ角度を動かしてからテレビ側のアンテナレベルに反映されるまで、数秒のタイムラグが出るため、アンテナレベルを確認しながら、1度動かすごとに5秒間ほど待ち、アンテナレベルを確認しながら、緻密に調整してゆくことがポイントです。
なおBS/CSアンテナが屋根の上や外壁の高い位置など、作業が危険になる位置に設置されている場合は、やはりアンテナ工事の専門業者などに依頼することをおすすめいたします。
BS/CSアンテナの角度調整については、詳しくは以下のコラム記事で解説しております。
BS/CSアンテナの角度調整に重要な「指向性」とは? 人工衛星の方向を確認できるスマホアプリ「BSコンパス」も徹底解説!
【アンテナトラブル例:アンテナ老朽化】
各種テレビアンテナにも、機種ごとに寿命(耐用年数)が存在します。
八木式アンテナの寿命は、10年から15年程度です。ただ風雨や雪の多い地域、また潮風の吹く海の近くなど環境が厳しい現場では、その寿命は10年を切ることもございます。
ご自宅の八木式アンテナの外見を確認して、全体的に錆が目立つ、マストや屋根馬の全体が錆付いている、素子の外装や支線が破損しているなどの症状が見て取れたら、交換がおすすめです。
デザインアンテナについては、普及から十数年程度でまだデータが少ないのですが、およそ15年から20年程度が寿命とされております。ただアンテナの設置環境、特に屋根裏空間などに設置されている場合は、より寿命が長くなると考えられます。
ユニコーンアンテナも最新機種であるため、具体的な寿命は不明ですが、おおよそ15年から20年程度と考えられます。
BS/CSアンテナの寿命も環境などによって変動しますが、およそ10年程度とされております。
テレビアンテナは寿命が過ぎても使用できることもございますが、各部の老朽化により固定部が弱まるなどして、アンテナ角度のズレや倒壊などのトラブルが発生するリスクが高まります。
いざアンテナトラブルが発生してのアンテナ修理や交換は、工事の手配に日数がかかる。その間、テレビ放送が視聴できない。またアンテナの倒壊、落下などで住宅の破損や大変な事故が発生する恐れもございます、
各モデルとも寿命を過ぎたテレビアンテナは、定期的にメンテナンスや点検を行い、老朽化が見られる場合は、お早めに交換されることをおすすめいたします。
特に注意が必要なアンテナは、アナログ放送時代の八木式アンテナです。
アナログ放送時代は、NHK、広域民放用のVHFアンテナだけでなく、地域によっては独立放送局(地方チャンネル)を受信するUHFアンテナが設置されることもございました。そして当時の地方チャンネルと、現在の地デジ放送は同じUHF帯の電波を使用しているため、現在でも当時のUHFアンテナをそのまま地デジアンテナとして流用しているケースもございます。
このような場合は、UHFアンテナより大型のVHFアンテナもそのまま残っていることが多く、さらに2023年現在では相当の老朽化も予想されます。現在、特に地デジ放送のご視聴には問題がなくとも、できるだけ早急に旧UHFアンテナの撤去および、新たな地デジアンテナの設置をおすすめいたします。
各種テレビアンテナのの寿命、またVHFアンテナについては、以下の各コラム記事でも詳しくご説明しております。
テレビアンテナの寿命と交換時期は? 地デジ・衛星放送別に必要な工事を徹底解説!
VHFアンテナとは? UHFアンテナとは? 基礎知識とアナログテレビアンテナの問題点
【アンテナトラブル例:アンテナ倒壊】
前述のようにアンテナ本体の老朽化と、台風や地震などの災害が重なると、アンテナの傾きや倒壊などの事故が起こる可能性も生じます。
特にアンテナが倒壊した場合の影響には、以下の例が挙げられます。
・アンテナ本体の破損やアンテナケーブルの切断。
・テレビ放送の視聴不能。
・倒壊したアンテナによる屋根の破損。
・アンテナの落下とそれに伴う重大な人身、物損事故。
アンテナの倒壊は、前項で記した通り、老朽化した八木式アンテナ、BS/CSアンテナで発生しやすくなります。
特にこれらのアンテナで、寿命に近い年数が過ぎた場合は、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。寿命が過ぎたアンテナで老朽化が確認できる場合は、早急な交換が必要です。
なお、各種の天災でアンテナが倒れるなどの被害が生じた場合には、火災保険の「風災保証」などによって修理費用が保証されることもございます。
各種アンテナが倒れたときの対処や、火災保険の適用については、以下の各コラム記事でも詳しく解説しております。
屋根の上でテレビアンテナが倒れたときのアンテナ修理工事(前編・原因と対処)
屋根の上でテレビアンテナが倒れたときのアンテナ修理工事(後編・修理と対策)
地デジや衛星放送のテレビアンテナが折れた、倒れたといったトラブルが起こる原因と早急な修理を行うための工事方法を徹底解説!
【アンテナトラブル例:アンテナ機器のトラブル】
住宅などに設置されたテレビアンテナから、室内のテレビなど受信機器まではケーブルで接続されていますが、これらの機器トラブルによってテレビ電波が正しく届かなくなることもございます。以下、各機器の紹介と、機器別のトラブル例や寿命を解説してゆきます。
なお、地デジアンテナのみや、2K対応型のBS/CSアンテナを設置している住宅で、新4K8K衛星放送をご視聴になる場合は、4K8K対応BS/CSアンテナだけでなく、各機器も4K8K対応型に交換する必要がございます。
アンテナケーブル
テレビアンテナから各部屋のアンテナコンセントまで。またアンテナコンセントからテレビ機器までを接続するケーブルです。現在は主に「同軸ケーブル」と呼ばれるものが使用されておりまます。
アンテナケーブルは、太陽光の紫外線や長期間の使用により劣化します。また特に細いケーブルは過度な折り曲げや、上に物を乗せるなどで断線するケースもございます。このように劣化したアンテナケーブルは、映像にノイズが入るなどのトラブルの原因にもなります。
アンテナケーブルの寿命は、一般的には10年程度と言われております。
アンテナケーブルに関する詳細は、以下の各コラム記事でもご説明しております。
室内のテレビアンテナケーブルを延長する方法とは? アンテナ線なしのワイヤレスで地デジ、衛星放送を見る方法も解説!
テレビ放送(地デジ、衛星放送BS/CS、4K8K)に合わせたテレビアンテナケーブルの種類と選び方、徹底解説!
テレビ放送や機器に合わせたアンテナケーブル(同軸ケーブル)の種類と選び方、徹底解説!
アンテナとテレビを結ぶアンテナケーブル、その種類と性能を徹底解説!
混合器
地デジとBS/CSの二基のアンテナを設置する場合、双方のケーブルからの電波を一本のケーブルに混合する装置です。
混合器を使うことでアンテナ配線をシンプルにして、トラブルの可能性や工事のコストを軽減できます。この混合器も長期間の使用により劣化します。劣化した混合器は効率的に電波をまとめることができなくなり、映像が乱れるなどのトラブルの原因となります。
混合器はアンテナのそばに設置するため屋外用の製品も多く、アンテナ本体と同じかそれ以上の寿命になります。アンテナ本体やケーブルなどの交換時には、混合器も一緒に交換することがおすすめといえます。
なお後述するブースターと混合器の機能を一体化した「UHF/BSCS混合ブースター」という機器もあり、この機器を使用する場合は混合器の設置は必要なくなります。
分波器
分波器は、アンテナコンセントやテレビなど機器の前で、混合器で一本のケーブルにまとめた地デジと衛星放送の電波を、二本のケーブルに分け、テレビ側のそれぞれのチューナー端子に接続するための装置です。屋内で使用されることが多いため、寿命は比較的、長くなります。この分波器が劣化すると、電波を分離する性能が低下します。そのため、地デジ放送は映っても衛星放送は視聴できない、またはその逆のトラブルなどが発生してきます。
テレビ放送が視聴できないトラブルで、アンテナ本体やケーブルに問題がない場合は、分波器の問題であるケースが多くなります。
混合器、分波器に関する詳細は、以下の各コラム記事でもご説明しております。
地デジ用と衛星放送用、両方のテレビアンテナ設置で工事コスト軽減のため必要な機器、混合器、分波器とは何なのか?
ブースター
テレビアンテナが受信した電波を、必要なレベルまで増幅させる装置がブースターです。主に地デジや衛星放送の電波が弱いエリアで設置されますが、現在では戸建て住宅に複数台のテレビを設置することが多く、テレビ電波に高いレベルが必要となるため、実質的にはほとんどの住宅に設置されています。
通常、設置されるブースターは屋外型のもので、電波レベルと同時に、電波に混じるノイズも増幅させる性質があるため、基本的にアンテナの真下や、距離の近い屋根裏などに設置されます。また混合器とブースターが一体化した機器などもございます。
このブースターが故障すると、電波を増幅することができなくなり、テレビ側に届く電波レベルが低下するため、画面の乱れや映らないなどのトラブルの原因となります。ブースターには電源が必要な場合もあり、多くの場合は屋外に設置されるため、その寿命は10年程度と言われております。ただブースターを屋内に設置している場合は、寿命がやや長くなります。
ブースターに関する詳細は、以下の各コラム記事でもご説明しております。
テレビアンテナの「ブースター」徹底解説・後編(機種選び・設置編)
テレビアンテナの「ブースター」は必ず必要なのか? 【地デジ設置・あさひアンテナ】
分配器
ブースターによって増幅された電波のケーブルを入力端子に接続し、複数の出力端子に接続したケーブルへと分配し、各部屋のアンテナコンセントへと送信する装置です。分配された個々の先の電波は、元の電波レベルから分配数で割られる形になって減少するため、ブースターの時点で必要十分なレベルに電波を増幅する必要がございます。分配器の寿命も、おおよそ10年程度になります。
分配器に関する詳細は、以下の各コラム記事でもご説明しております。
ご自宅のすべてのテレビに電波を送る「分配器」とは? その種類と選び方を徹底解説!
アンテナ工事の「分配器」とは何?「分波器」「分岐器」との違い
テレビアンテナへの分配器の設置で、現場の電波レベルや条件に適した選び方と注意点を徹底解説。分波器や分岐器との違いとは?
テレビアンテナの電波を各部屋に分岐する方法は? 分配器と分波器の違い・接続方法や選び方
【その他の受信トラブル例】
テレビアンテナ本体には特に問題がないにもかかわらず、テレビ放送が映らない場合の原因には、さまざまなものが考えられます。
主な原因には以下の者が挙げられますが、原因の特定はテレビに表示されたエラーコードの内容なども参考にすすめてゆきます。
電波障害
前述のように、豪雨、豪雪などの際にはテレビ電波の減衰が起こり、元より電波レベルの低いエリアでは受信不良にいたることがございます。特に衛星放送は雨や雪に影響されやすくなります。
この場合の対処には、アンテナに設置されているブースターの電波増幅レベルを高めて、テレビなど受信機器側に、常に安定した電波レベルが供給されるようにするといった方法がございます。
周辺環境の変化を含む電波障害の原因と、その対処については、以下の各コラム記事でも詳しくご説明しております、
電波障害? テレビが映らない原因はアンテナトラブル? 確認と対処法
周辺環境の変化
自宅の近くに、高層マンションなどの建築物が建築されるなどで、テレビ電波が遮断され、電波状態が悪化することもございます。特にBS/CSの電波は、アンテナの前にある樹木の葉が茂る、洗濯物が干されるなどの要因でも受信不良にいたることがございます。
この場合が、アンテナ設置位置の変更などで対応できます。
接続不良
アンテナコンセントからテレビ、レコーダーなどへの接続、また機器同士の接続不良で十分なテレビ電波が届かなくなることもございます。
原因としては接続部の汚れ、機器を動かした際に接続部がはずれかけるなどのケースが考えられます。またアンテナ配線部のブースター、分配器などの接続で同様の問題が生じることもございます。
この場合は接続部を確認して、いったん外して汚れを落とすなどした後、あらためてしっかりと接続し直します。
テレビ、チューナーの故障
テレビやチューナーそのものが基盤の劣化などにより故障するケースもございます。
テレビ放送が正しく映らない状態で、アンテナ機器や接続部などを確認しても問題がない場合は、テレビ本体のトラブルと考えられます。モデルなどによっても変化しますが、一般的なテレビの寿命は8年から10年程度といわれます。
この場合は、テレビそのものを買い替えることになります。
【アンテナ修理を専門業者に頼む場合は?】
アンテナのトラブルでテレビ放送を視聴できなくなった場合は、テレビアンテナ工事の専門業者へ点検や修理を依頼することが、もっとも確実で安心できるといえます。特にアンテナトラブルの際には現場の電波状況の測定が必要となります。専門業者であれば電波状態の確認も確実と言えます。
なおアンテナ工事業者へ修理を依頼するときの費用は、業者からご自宅の現場、ご自宅の構造、アンテナの位置などによりさまざまです。
アンテナ工事の専門業者は、基本的にインターネット上の公式サイトで、各工事の価格を表示しております。このような価格表を確認したうえで、業者に見積もりを依頼して、その内容を確認してください。
なおその場合は、当あさひアンテナをはじめ、見積もり料、出張料、キャンセル料が無料の業者を選んで、相見積もりをとり、価格だけでなく工事内容なども比較する。また見積もり時のスタッフの対応から優良業者を判定されることがおすすめといえます。
アンテナ工事業者に修理を依頼する場合の、症状ごとの対応や修理費用の目安は以下の通りです。
(テレビアンテナがズレて、受信できる電波レベルが低下した場合)
・アンテナの角度調整工事:5,000円から20,000円程度。
(テレビアンテナが倒壊したなどの故障時)
・地デジ、BS/CSアンテナの修理工事:15,000円から20,000円程度。
(老朽化、故障した古いテレビアンテナの処分)
・既設テレビアンテナの引き取りと処分:5,000円から15,000円程度。
(新規テレビアンテナ設置(アンテナ本体価格込み、アンテナ設置のみ))
・八木式アンテナ:17,000円程度から。
・デザインアンテナ:25,000円程度から。
・ユニコーンアンテナ:33,000円程度から。
・BS/CSアンテナ:17,000円から27,000円程度。
(周辺の障害物などで電波状況が悪くなってテレビ放送が映りにくい)
・ブースターの設置、交換工事:25,000円から35,000円程度。
(テレビの台数を増やしたことでテレビ画面が乱れるようになった)
・分配器の設置、交換などの配線工事:7,000円程度から25,000円程度。(分配数による)
上記の修理費用は、多くの業者の価格を平均した、あくまでも目安です。実際には、各種の工事を複合することや、業者によってはアンテナの設置場所などによって高所作業費が必要となる場合もあり、工事費用の総額はさまざまに変わってまいります。
【まとめ】
一般的に発生しやすいアンテナトラブルと、その対処法は以上の通りになります。
なお、2024年末時点での、アンテナ基本設置工事や修理の工事費用に関する最新情報。また相見積もりの手順などについては、以下の各コラム記事でご紹介しております。
・戸建て住宅でのテレビアンテナ基本設置工事の費用相場は? 料金を抑えることができる業者の選び方も紹介【2024年度最新版】
・テレビアンテナの修理を業者に頼む方法と費用の相場は? アンテナ修理の種類と火災保険に対応もできる最適な業者の選び方も解説
・新築住宅でテレビアンテナ工事の流れは? 即日工事、相見積もりで安くて高品質の工事を依頼できる業者の種類、費用相場も紹介!
当あさひアンテナではどのようなアンテナトラブルであっても、弊社フリーダイヤル(0120-540-527)。またはメールフォーム、LINEアカウントにご一報いただければ、最短即日で現場へ出張して、早急な復旧を果たせるようご対応いたします。
突然のアンテナトラブルでお困りの際は、当あさひアンテナまで、どうぞお気軽にご相談ください。