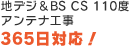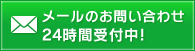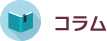部屋にあるテレビアンテナ用コンセントの交換、増設方法は? 工事の方法から耐用年数、端子の種類まで徹底解説!
ひとくちに「コンセント」といって、多くの人が思い浮かべるものは、一般の戸建ての家、またビルなどの建物の内部、壁面の足元に見られることが多い、電源を供給するための差込口のことではないでしょうか。
一般的に日本で電源の差込口などの意味で使われる「コンセント」とは、英単語では「concent」になり、意味は、動詞で「同意する」や、名詞で「承諾、一致」になります。ただこの電線の差込口としての「コンセント」は、実は和製英語であり、英語圏では使われません。
英語圏にて「電源の差込口」の意味で使われる言葉は、イギリスでは、受け口や軸受け、また昔の燭台でろうそくを立てる部分を意味する「Socket」。アメリカでは出口などを意味して、電気の出口という意味の「outlet」になります。
また、電源を差し込む際には、その部分を「プラグ(plug)」と呼ぶこともあります。日本では「コンセントプラグ」と呼ばれることもございますが、正確には「コンセント」は壁などに設置された「差込口」であり、「プラグ」は電化製品などのコードの先についた、電源の差込部分のことを言います。
プラグ(piug)は英語圏でもコンセントに差し込む側の意味で使われる他、動詞として「(栓などで)ふさぐ」「(穴などにものを)詰める」や「接続する」「宣伝する」。名詞では各種の「栓」や、自動車のエンジンなどに使われる「スパークプラグ」や「噛みタバコ」。また「広告、宣伝」の意味で使われます。
さて、電源のコンセントといえば、いまや日常生活には欠かせないものです。テレビやパソコン、無線LANなど、どれだけ便利で重要な電化製品であっても、電源を供給するコンセントがなければ、たちまち無用の長物になってしまいます。
ただ、テレビやブルーレイレコーダーなどの機器にとっては、電源の他にもうひとつ、重要な「コンセント」がございます。それが「アンテナコンセント」です。
アンテナコンセントは、やはり住宅の壁面などに設置されている「差込口」のひとつで、電源ではなく、住宅などに設置されたテレビアンテナから、アンテナケーブル(同軸ケーブル)を使った配線で、住宅内の各部屋にテレビ電波を送信する部分です。
このアンテナコンセントにテレビアンテナケーブルを接続し、室内にあるテレビなどの機器と接続することで、地上デジタル放送(地デジ)や衛星放送(BS放送、CS放送、新4K8K衛星放送)などテレビ放送をご視聴できるようになるのです。
もっとも現在では、ご家庭でテレビを見るための方法としては、地デジ、BS/CS等のテレビアンテナを取り付ける以外にも、ケーブルテレビ(CATV)や光テレビなどがある他、テレビ本体にもゲーム機やパソコンのモニターとしての役割もございます。またテレビ本体がインターネットへの接続機能を持つことで、ネット上の「Amazon prime video」「NetFlix」「U-NEXT」「YouTube」など、さまざまな動画配信、動画投稿サイトを直接、ご視聴にもなれます。
そのため、現在ではご自宅へのテレビアンテナの設置が不要となるケースも多く、テレビ機器でも、あえて地デジ放送や衛星放送のチューナーを搭載していない「チューナーレステレビ」も注目を集めております。
ただテレビアンテナには、いったんご家庭などに設置すれば、衛星放送の有料チャンネルを除いて、10年以上、時には20年、30年など長期にわたって、適切なメンテナンスのみで大きな費用をかけず、無料でテレビ番組をご視聴になれるというメリットがございます。
そのため現在でも、戸建住宅のマイホームなど、長きにわたってお住まいになる家であれば、テレビアンテナの取り付けとご利用が、テレビの視聴方法としては最適となります。したがって住宅内の適切な部屋に、適切な数のアンテナコンセントがなければ、多くの場合、テレビの魅力も半減してしまうといえるでしょう。
今回の当コラムでは、地上波や衛星放送のテレビ電波を各部屋に送る、この「アンテナコンセント」について、多くのご自宅に設置されているコンセントの種類や耐用年数。また既存のコンセントの寿命が近づいた際の交換方法などの情報など、重要なポイントを、2023年(令和5年)度の最新情報に基づいてご紹介いたします。
他にも、アンテナコンセントの増設、追加設置をDIYで行う方法や、依頼できる業者、会社。工事にかかる費用、価格の相場といった情報もございます。ご自宅に古いアンテナコンセントがある場合は、老朽化により不具合が発生すると、テレビ放送が映らない、また映りが悪くなるなどの原因にもなり、大変なご不便も生じてまいります。
当コラムの内容をご確認の上、アンテナコンセントの基礎知識をご理解されることで、適切な対処法によってそのような不便を避け、あるいはトラブルを解決していただければ幸いです。
アンテナコンセントの種類
まず最初に「アンテナコンセント」は、一般の方には「アンテナ端子」と呼ばれることもあり、この2種類の言葉は、ほぼ同じ意味のものとして混同されがちです。
ただ正確には「アンテナコンセント」とは、アンテナケーブルと接続する、おもに壁などの設置場所に取り付けられたテレビアンテナのコンセント部、その全体のことを指します。現在ではアンテナコンセントだけではなく、電源や電話回線、LAN端子なども一体化した「マルチメディアコンセント」も登場し、人気を集めております。
そして「アンテナ端子」とは、アンテナコンセントなどに設置された、アンテナケーブルと接続する部分のことを指します。この端子部分には、主に設置された年代により、さまざまな別の形状がございます。
特にアンテナ端子については、その形状によって、対応するケーブルや接続部などが別となる場合もあるため注意が必要です。
以下、各種のアンテナコンセント(アンテナ端子)について、その形状や特徴、対応するケーブルなどについて一覧でご説明してゆきます。
なお、アンテナコンセントで送信される地デジ電波であるUHF波、衛星放送の電波である12GHz帯。およびそれぞれの放送の特徴については、以下の各コラム記事でも解説しております。
地デジアンテナ設置に重要となる「強電界地域」「中電界地域」「弱電界地域」とは
アンテナ端子の種類
ここではまず、ご自宅の各種アンテナコンセントに設置されている、アンテナケーブル(同軸ケーブル)の接続部「アンテナ端子」の種類。各アンテナ端子の種類ごとに対応できる、アンテナケーブルの先にあるプラグの種類について、一覧でご説明してまいります。
・F型端子。
「F型端子」とは2020年代、令和の現在ではもっとも主流のアンテナ端子になります。
アンテナコンセント側のアンテナ端子では、接続部が壁から飛び出して邪魔にならないよう、差し込み口が丸くくぼんだ中に、円筒形の部分があり、円筒形の中心に丸く小さな穴がついています。円筒形の横部分にはネジ切りが入っています。
F型端子に使用するコードの先には「スクリュープラグ」「F型コネクタ(F型接線)」がついています。双方とも中央の穴に差しこむ細い金具の線と、円筒形の部分に合わせる筒状の部分があり、やはり筒状の内側にネジ切りがついています。
スクリュープラグおよびF型コネクタは、中央の穴に線の部分を差し込む形で、双方の円筒形と筒の部分を合わせ、ネジ切り部分をねじ込むことでしっかりと合わさり、そう簡単には抜けないという特徴がございます。
特にF型コネクタは、プラグ部分にネジ式の回転部が装着されているものであり、F型端子側にしっかりねじ込むことで、固定されて抜けなくなる他、端子部から電波の漏洩や混入を防ぐこともできます。
なおF型端子には、後述するプッシュ端子用のコネクタも接続可能ですが、ネジ切りがないため抜けやすくなるという難点もございます。
また、アンテナコンセント側のF型端子には、主に以下のようなパターンがございます。
・1:アンテナコンセント側にF型端子が2か所あり、それぞれ地デジ放送とBS/CS放送に対応している。
・2:壁にF型端子が1か所あり、1か所で地デジ放送とBS/CS放送の双方に対応している。
・3:壁にF型端子が1か所あり、地デジ放送のみに対応している。
「1」および「2」は、ご自宅に地デジとBS/CS双方のテレビアンテナが設置されている場合になります。
住宅に地デジアンテナとBS/CSアンテナの双方を設置する場合は、それぞれのアンテナをできるだけ近い場所に設置し、双方のケーブルを「混合器」という機器で一本のケーブルにまとめることで、以降のケーブル配線や機器をシンプルにします。
混合器でまとめたケーブルは、テレビ側で地デジとBS/CSそれぞれのチューナーに接続する前に、「分波器」というケーブルを二股にする機器により、ふたたび地デジとBS/CSの電波を分離します。
そして「1」の場合は、アンテナコンセント内に分波器が設置されていて、コンセントの時点で地デジとBS/CSのアンテナ端子を分けている形になります。この形では、地デジとBS/CSの端子それぞれにアンテナケーブルを接続し、そのままテレビやレコーダー側の地デジ、BS/CSチューナーに接続するだけなので、接続が簡単になります。一方で、同じアンテナケーブルが2本必要となるため、配線がかさばるといった難点が出てまいります。
「2」の場合は、アンテナコンセントから1本のアンテナケーブルをテレビ側に伸ばし、その先、テレビの近くに分波器を設置してケーブルを2本に分け、地デジとBS/CSチューナーそれぞれの端子に接続することになります。設置はやや複雑になりますが、配線をシンプルにまとめることができるのがメリットです。
ただ「1」「2」とも、地デジとBS/CSのチューナー側への接続を間違えないよう、注意が必要となります。
「3」の場合は、1本のアンテナケーブルで、テレビなどの地デジチューナーのみと接続することになります。BS/CS放送もご覧になりたい場合は、BS/CSアンテナの設置と、各部屋のアンテナコンセントへのBS/CSアンテナケーブルの配線が必要となります。かなり大掛かりな工事となるため、アンテナ工事の専門業者にご依頼される必要がございます。
ただ屋内でも一台のテレビのみでBS/CS放送をご視聴になれればいい場合は、業者に依頼せず、ご自宅のベランダや室内などにご自身でBS/CSアンテナを設置し、テレビと接続することも不可能ではございません。その手順については以下のコラムをご参照ください。
BS/CSアンテナの設置方法と工事費用の目安
BS/CSアンテナ(衛星放送用)を室内に設置する方法
また混合器、分波器については、以下のコラム記事でも関連の情報をご説明しております。
地デジ用と衛星放送用、両方のテレビアンテナ設置で工事コスト軽減のため必要な機器、混合器、分波器とは何なのか?
・プッシュ端子。
「プッシュ端子」とは前述したF型端子より、少し古い形のアンテナ端子になります。
形状はF型端子とほぼ同様のものですが、唯一の違いは、端子やコネクタ側にネジきりがなく、すべすべした形になっていることです。
そのため接続に力がいらず、スムーズに差し込むことができます。半面、ネジを締め込むことができないため、ケーブルにものなどをひっかけてしまうだけで、抜けやすいという難点もございます。
それ以外の点は、F型端子とほぼ同様になります。ただブッシュ端子にネジ切りの入ったF型コネクタのケーブルを接続しようとしても、ネジ切りが邪魔になって接続できない。無理に接続すると端子部分が傷つくなどの問題が生じることもございますので、プッシュ端子には必ず、接続部がプッシュコネクタになったアンテナケーブルをご使用ください。
なおプッシュ端子、F型端子とも、ケーブル側のプラグには、形状と材質の違いがございます。
形状の違いでは、ケーブルと同じ方向に、まっすぐプラグがついた「S型(ストレート)」と、プラグ部分の形状がL字型に曲がり、ケーブルと端子を直角に接続できることで、ケーブルの収まりを整理できる「L型」になります。
材質では、表面が銀色で廉価ながら、長期の使用で酸化や腐食が進みやすい「ニッケルメッキ」と、金色で腐食や酸化が起こらず、映像の劣化が生じにくい他、表面の柔らかさで端子側に密着して接続できる「金メッキ」がございます。
・同軸直付端子。
同軸直付端子は、地デジ放送が普及する前に主流であったアンテナ端子の形状です。
アンテナケーブルには、基本的に「同軸ケーブル」というケーブルが使用されています。この同軸ケーブルの中心部にはまず電波などを伝える銅製の針金である内部導体(中心軸)が通り、内部導体をポリエチレンなどの絶縁体が厚めに覆っています。さらにその表面を網状になった細い銅線の束である外部導体が覆っており、表面側はポリ塩化ビニルなどによる保護皮膜で覆われています。
市販のアンテナケーブルは、この同軸ケーブルの両端に、スクリュープラグやF型コネクタが装着されているのですが、直付端子ではこの同軸ケーブルの先端を加工して接続することになります。
加工の方法は、先ず同軸ケーブル先端部の保護被膜を取り除き、外部導体を折り返す形にして、絶縁体も切り落として、内部導体の針金部分を、数センチほどむき出しの形にします。
この内部導体を、アンテナ端子側の穴に差し込む、またはねじ部分に挟み込んで締めるなどで、端子を接続します。また、アンテナ端子の真下などには、表面をはがしていないケーブルの先端部を通して、ネジで固定するリングが設置されているため、ケーブルが抜けにくくなっております。
この直付端子は、内部導体をむき出しにするため、特に周波数帯の高い電波で、電波の漏洩や外部電波(ノイズ)の混入が多くなることから、現在の地デジ放送、衛星放送ではほとんど使われることがなくなっています。
同軸ケーブルやアンテナ配線部に関しては、以下の各コラム記事でも詳しく解説しております。
室内のテレビアンテナケーブルを延長する方法とは? アンテナ線なしのワイヤレスで地デジ、衛星放送を見る方法も解説!
テレビ放送(地デジ、衛星放送BS/CS、4K8K)に合わせたテレビアンテナケーブルの種類と選び方、徹底解説!
テレビ放送や機器に合わせたアンテナケーブル(同軸ケーブル)の種類と選び方、徹底解説!
アンテナとテレビを結ぶアンテナケーブル、その種類と性能を徹底解説!
・フィーダー端子。
フィーダー端子は、直付端子よりさらに以前、日本のテレビ放送黎明期から、昭和にかけてアナログ放送の時代に使われたアンテナ端子です。この端子では、同軸ケーブルではなく、フィーダー線という細いケーブルを横に2本並べてくっつけたような形のケーブルを使用します。フィーダー線は、断面が、円がふたつ並んだメガネのような形に見えることから、メガネ線とも呼ばれます。
フィーダー端子の接続では、このフィーダー線の先を二股に割く形にして、直付端子と同じく、それぞれのケーブルの芯線をむき出しにする。またはそれぞれの先に小さなU字型の金具がついたケーブルを使用します。
フィーダー端子側には、同軸端子と同じ形式の2つのネジがあり、2つに分けたケーブルの先をそれぞれ接続して、ネジを締める形で固定します。ただフィーダー端子はアンテナ端子、ケーブルともかなり古い形になるため、現在のF型コネクタなどがついた同軸ケーブルをそのまま使うことはできません。同軸ケーブルや各種コネクタの先端に接続する、フィーダー端子用の金具がついた整合器を設置して使用する必要がございます。
フィーダー端子は前述の直付け端子と同じく、電波の漏洩や混入が起こりやすい他、わずかなトラブルでも受信不良が生じやすく、テレビ画面が乱れやすい端子になります。そのため、ご自宅のアンテナ端子がフィーダー端子である場合は、お早めにF型端子のアンテナコンセントへと交換されることをおすすめいたします。
アンテナコンセントの形状
アンテナコンセント部分の形状には、前述した、地デジとBS/CS端子が2個に分かれたもの。ひとつになったもの。また地デジ端子のみのものがございます。また近年の住宅では「マルチメディアコンセント」も多くなっております。
マルチメディアコンセントとは、アンテナコンセントと、インターネットなどに使用する有線LANのコンセント。また固定電話回線のコンセントや電源コンセントなどが一か所にまとまったものです。住宅の各部屋で、一か所からそれぞれのケーブルを接続することができるため、部屋の配線などが非常にすっきりとします。
他にも、これらすべてではなくとも、アンテナコンセントと電源コンセント、また電話回線などが一体型になったものもございます。
アンテナコンセントの耐用年数と交換方法
アンテナコンセントにも上記のようにさまざまな種類がございますが、その耐用年数は、どれも約10年といわれています。
このアンテナコンセントの老朽化により、不具合が生じた場合には、業者に依頼して交換してもらうことになりますが、簡単な工事であれば、ご自宅でも可能になります。
なお、基本的にご自宅にて個人でアンテナコンセントを交換する場合の作業は、基本的に現在の最新式であるF型端子か、ひとつ前の端子で形状はほとんど変わらないプッシュ端子から、F型端子への交換が基本になります。
特にご自宅に前述した旧式の直付端子、フィーダー端子が設置されている場合では、アンテナコンセント部だけでなく、テレビアンテナ本体や、配線部に設置された、受信したテレビ電波を必要なレベルまで増幅する装置であるブースターをはじめ、前述した分配器などの機器。またアンテナケーブル(同軸ケーブル)そのものも、非常に古いタイプのままである可能性が高くなります。
このようなアンテナ機材、ケーブルのままでは、老朽化による劣化はもちろん、現在の地デジ電波、衛星放送の電波には対応できず、配線の各部からテレビ電波の漏洩や、ノイズの混入などにが起こるリスクが高くなります。
その場合には、テレビの画面が乱れる、映らないといった受信不良をはじめ、ご自宅にある無線LAN機器でも電波の混信によりトラブルが発生するなど、さまざまな不具合が想定されます。
そのため特に上記のように古いタイプのアンテナコンセントがあるご自宅では、現状で不具合の有無を問わず、お早めに交換を検討されることをおすすめいたします。
ただ、マンションや借家などの賃貸住宅にお住いの方は、アンテナコンセントの交換作業を行う前に、住宅のオーナー様や物件を管理する会社などに工事の許可を得る必要がございます。アンテナコンセントに限らず、賃貸物件において無断で住宅設備の交換、設置などの工事を行うと、契約違反になる可能性もございます。特に工事で壁や配線を傷つけてしまうと、民事訴訟などのトラブルになることも考えられますので、ご注意ください。
以下、アンテナコンセントの交換に問題がない場合の、作業の手順をご説明いたします。
アンテナコンセントの交換手順
まずは工具として、各種のドライバーやペンチ、カッターなどの工具が必要です。また作業用の手袋もあったほうがいいでしょう。
工具が揃っている場合は、以下の順に作業を進めてゆきます。
・1:住宅の受信システムの確認と適合するアンテナコンセントの購入。
まずは交換用に新しいアンテナコンセントを購入されることが必要ですが、ご自宅に適合する種類を選ぶ必要がございます。
現在、設置されているアンテナコンセントと同じ形状を選ぶことはもちろんですが、各住宅のアンテナの受信システムには大きく2種類があり、その形式に合ったアンテナコンセントを選択しなければなりません。
この受信システムとは、ご自宅のテレビアンテナから、屋内に複数あるアンテナコンセントへの、アンテナ配線の配分方法になります。
この配分方法は、以下の二種類になります。
・分配方式。
これは現在の主流である配分方法です。アンテナから延びて屋内に入ったアンテナケーブルを「分配器」に接続して配分します。
分配器とは、一つの入力端子と、屋内のアンテナコンセント数に合わせた、複数の出力端子を持つ機器で、それぞれのケーブルに接続することで、出力数に合わせて、アンテナからの電波を等分に分配し、各部屋のアンテナコンセントに送る装置のことです。
メリットは、アンテナからの電波を等分に分配するため、すべてのアンテナコンセントに同様の高いレベルで電波を送信できる点です。
デメリットは分配器の機器代金が必要なため、工事費用が高額になる点です。
分配器に関しての詳細は、以下のコラムをご確認ください。
ご自宅のすべてのテレビに電波を送る「分配器」とは? その種類と選び方を徹底解説!
テレビアンテナへの分配器の設置で、現場の電波レベルや条件に適した選び方と注意点を徹底解説。分波器や分岐器との違いとは?
アンテナ工事の「分配器」とは何?「分波器」「分岐器」との違い
・送り配線方式。
これも現在、多くの住宅で採用されている分配方式です。この方式では分配器を使用せず、アンテナが受信したテレビ電波を、一本になった長いケーブルを使って、各部屋のアンテナコンセントへと順番に通し、各アンテナコンセントに電波を送る方式です。
メリットは工事費用が安くなることです。半面、各アンテナコンセントに接続するたび、電波の量が少なくなるため、配線の先に行くほど電波レベルが落ちていくという点です。
ご家庭の受信システムがどちらの形式であるかは、アンテナコンセントを外すことで確認できます。
アンテナコンセントを外して、そこにアンテナケーブルが1本だけ配線されている場合は「分配方式」。2本ある場合は「送り配線方式」の可能性が高くなります。ただし一か所のアンテナコンセントを確認するだけでは、判断が不正確になります。
複数のアンテナコンセントを外してみて、それぞれのケーブルの状態を確認してご判断される必要がございます。
新しいアンテナコンセントは、この配線方式に合わせたものが必要となります。商品のパッケージや、店舗で確認されるなどして、的確な形式の者をご購入ください。以下、実際の作業に入ります。
・2:ご自宅のブレーカーを落とす。
アンテナコンセントの近くには電源コンセントが設置されていることも多くなります。感電防止のため、まずはブレーカーを落としてから作業に入ってください。
・3:アンテナコンセントのカバーを外す。
ネジで固定されたアンテナコンセントの場合はネジをドライバーで外す。ネジがないタイプの場合は、カバーの上か下にある設置部分にマイナスドライバーを差し込んで、カバーを外してください。
・4:アンテナコンセントの取付枠を外し、本体部を引き出す。
カバーの次は、アンテナコンセント本体を設置している取り付け枠を外します。壁紙がアンテナコンセントにかぶさっている場合は、余分な箇所をカッターなどで切ると作業が進めやすくなります。取り付け枠を外した後、アンテナコンセント本体を引き出してください。
なお、この際や以降は、工具や部品を壁の中に落とさないようご注意ください。
・5:アンテナコンセントからケーブルを外す。
アンテナコンセント本体にはアンテナケーブルがつながっているので、このケーブルを外してください。
この際、贈り配線方式ではアンテナのケーブルが「入力(IN)」と「出力(OUT)」の2本ございますので、どちらがケーブルなのか確実に確認できるようにしてください。
・6:新しいアンテナコンセントに取り付け枠を設置する。
古いアンテナコンセントから取り付け枠を外し、新しいアンテナコンセントをにはめ込んでください。
取り付け枠は多くの場合、元のものを流用できますが、取り付け枠まで交換なさりたい場合は、元のものと同じものを用意しておく必要がございます。違うタイプでは枠に合わないことがございますので、ご注意ください。
・7:新しいアンテナコンセントとケーブルを接続する。
次に、新しいアンテナコンセントにアンテナケーブルを接続してください。ケーブルをアンテナコンセントに差し込み、ねじを締めて固定します。なお送り配線方式で「入力(IN)」「出力(OUT)」に分かれている場合は、正しい方に接続する必要がございます。
・8:取り付け枠を元の場所に取り付ける。
アンテナコンセントとケーブルを接続した後は、ケーブルを壁の中に入れ、取り付け枠を元の場所に設置します。この取り付け枠の設置がずれているとカバーもはまらなくなるので、ご注意ください。
・9:カバーを設置する。
本体の設置が完了した後は、カバーを元通りに設置すると、これで交換作業は完了です。
・10:テレビが正常に映るかを確認する。
作業が完了したら、最後に新しいアンテナコンセントとテレビなどの機器をケーブルで接続して、正常に映るかをご確認ください。
正常に映るようであれば、作業には問題がなかったことになります。
アンテナコンセントの交換は以上の通りです。基本的には簡単な作業ですが、アンテナの送信形式がわからないなど不明な点がある。うまく作業できるか不安という場合は、プロであるアンテナ工事の専門業者にご依頼をおすすめします。
特にマルチメディアコンセントへの交換は、有線LANや電話、電源など複数の配線を一か所に集め、正しく設置しなければならず、コンセント自体の構造も複雑となるため、大がかりな工事になってしまいます。
特にコンセント電源部の工事に関しては電気工事に当たるため、専門の資格を持った電気工事士が担当する必要がございます。電気工事の素人である一般の方が電気配線の工事を行うことは、感電などが考えられてたいへん危険であることはもちろん、法令に抵触する危険性もございます。
そのためご自宅でアンテナコンセントをマルチメディアコンセントに交換なさりたい場合には、やはり専門の業者、会社などにご依頼されることがもっとも安心でき、良いと申せます。
アンテナコンセントについて・まとめ
アンテナコンセントや端子の基礎知識、そして具体的な交換方法について、ご理解いただけたでしょうか。ご自分でのアンテナコンセントの交換方法や可能な例については、こちらでも詳細をご説明しておりますので、よろしければご確認ください。
住宅の部屋にテレビコンセント(アンテナコンセント)を増設する工事の方法は? 設置されるアンテナ用端子の種類も解説
もしご自宅で古いアンテナコンセントを新しいものへと交換したいが、ご自身での作業が難しい。また通常のアンテナコンセントからマルチメディアコンセントへと交換したい。その他、アンテナコンセントの新規設置、交換についてのご相談、お問い合わせは、当あさひアンテナのフリーダイヤル(0120-540-527)。メールフォーム、LINEアカウントまで、どうぞお気軽にお寄せください。
もちろん当社では、地デジアンテナでは、屋根の上など屋外の高所に設置できて受信性能が高い八木式アンテナ。ボックス状で家の外の壁面やベランダ等の他、条件が許せば屋根裏空間などにも設置できるデザインアンテナ。新たに開発されたポール状のスタイリッシュな地デジアンテナであるユニコーンアンテナ。
BS/CSアンテナでは、一般ご家庭向けの45型モデルをはじめ、50型、60型、75型から90型、120型など、集合住宅向け共同受信用の大型モデル。さらにはカラーバリエーションや高耐風モデルなどのさまざまなモデルもご用意しております。
他にも各現場やお客様のご希望に対応できる室内アンテナ、屋外屋内アンテナなどのアンテナ機種。さらにはブースター、分配器、混合器などアンテナ周辺機器に関しても、国産大手アンテナメーカーによる高品質なモデルをご用意しております。
そしてこれら各種アンテナの基本設置工事においては、アンテナ本体および、基本設置部材や同軸ケーブル、防水加工などをセットにした基本設置工事の価格を、業界最安に挑む料金でご提供しております。各工事費については、ブースターなど各種機材の設置などオプション工事も含め、弊社の公式サイトにて、明確な価格体系でわかりやすくご提示しております。
実際のアンテナ工事にあたっては、まず現場の電波調査、お見積もりを、出張料、キャンセル料など別途にかかる費用、金額も含め、完全な無料で実施しております。
現場ではエリアの特性に合わせ、住宅のさまざまな場所、位置で、綿密な電波レベルの調査を実施。現場の条件で可能な限り、お客様のご要望に沿ったアンテナ機種、設置位置の施工をご提案いたします。
施工に際しては、豊富な経験と高い技術を誇る弊社のアンテナ職人が、可能な限りシンプルかつ丁寧で見栄えが良く、また風雨などにも強く、高寿命となるアンテナ設置をお約束いたします。
さらにアンテナ工事の完了後には、工事を担当したアンテナ職人が自筆のサインを入れた保証書をお渡ししており、業界でも最長クラスとなる「10年間」の長期保証、アフターフォロー制度を御用意しておりますので、アンテナの設置後も長きにわたってご安心いただけます。
その他、急なアンテナトラブルでお困りの際には、テレビアンテナの修理、角度の調整など。また既設アンテナが老朽化した際には、旧アンテナの撤去、処分と新規アンテナへの交換など、さまざまなサービスにも対応しております。
アンテナコンセントに関する工事だけでなく、一般的な各種テレビアンテナ工事のご相談についても、どうか同業他社との価格、サービス内容をご比較になった上で、確実に高品質てお得な工事をご提案する、当あさひアンテナをお選びいただき、すべてお任せいただければ幸いに存じます。