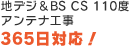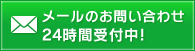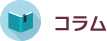地デジ・八木式アンテナで後悔しないポイントは? 性能・工事費用・設置方法・機種の選び方まで、専門家が解説
新築住宅を建てたばかりの方や、お住まいで使用しているテレビアンテナが古くなって、故障や不具合が出ている方には、新しく設置するテレビアンテナにはどのような種類があるか、どれを選べばいいのかというお悩み、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
テレビアンテナの選択は、快適なテレビの視聴環境を実現する上で非常に重要ですが、現在ではさまざまな種類のアンテナがあり、一般の方にはわかりにくい面もあるでしょう。
特に、昭和の昔から知られていて、現在でも一般住宅の屋根の上に多く見られる
八木アンテナ(八木式アンテナ)は、
現在では、その魚の骨のような古くさい見た目から、敬遠される方もいらっしゃるでしょう。
しかしこの八木式アンテナは、実は開発から約100年経った今でも、その高い性能とコストパフォーマンスから多くのご家庭で選ばれ続けている、非常に優れたアンテナなのです。
この記事では、アンテナ工事の専門家が、八木式アンテナの基本的な概要、主な種類と設置方法、メリット・デメリット、設置の注意点から、工事を依頼すべき会社の選び方といった最新情報、関連の知識まで、専門外の方にもわかりやすく徹底解説いたします。
この記事を最後までお読みいただければ、八木式アンテナの本当の価値や、他の機種と比較した特長がわかり、ご自宅に最適なアンテナ機種、設置の方法を、自信を持って選べるようになるでしょう。
八木式アンテナとは?今も現役の定番アンテナを再入門
八木式アンテナとは、地上波テレビ放送がアナログ放送だった昭和の時代から、完全に地上デジタル放送となって10年以上が経つ2025年(令和7年)に至るまで、現役で使われ続けているテレビアンテナです。
現在でもよく住宅の屋根、その頂点部に、地面と垂直になるように立てたマスト(支柱、ポール)の先に固定されている、魚の骨に似たアンテナ、といえばおわかりになるでしょう。そして現在では、このようなアンテナは、少し古臭いというイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、八木式アンテナの歴史と性能を知れば、今なお多くの家庭で採用されている理由がわかります。
まずは、この定番ともいえるアンテナ機種の基本からご説明していきます。
100年の歴史を持つ「元祖」テレビアンテナ
八木式アンテナは、今から約100年前、大正時代に当たる1920年代に、当時の東北帝国大学(現・東北大学)工学部の、八木秀次博士と宇田新太郎博士によって開発されたアンテナです。
一般には特許を取得した八木博士の名を冠した「八木式アンテナ」「八木アンテナ」の名称で知られますが、現在では研究を主導した宇田博士の名前も含め、正式名称は「八木・宇田アンテナ」と呼ばれます。他にもその受信の特性から「指向性短波アンテナ」と呼ばれることもあります。
この八木式アンテナは、アナログテレビ放送の時代から、日本の一般家庭におけるテレビ視聴を支え続けてきた機種です。
そしてテレビの進歩に歩調を合わせて、八木式アンテナも技術の改良を重ね、現在の地上デジタル放送(地デジ放送)においても、その高い受信性能から、古典的ながら主流のアンテナ機種のひとつとして活躍しています。
「魚の骨」の構造と仕組み:なぜこの形に意味があるのか?
八木式アンテナの最大の特徴は、なんといってもその「魚の骨」のような独特の形状です。
現在の地デジアンテナ(UHFアンテナ)としての八木式アンテナは、矢印のような形の骨組みに、いくつもの短い横棒がついた形状で、それこそ魚の頭と骨を思わせる形状になっています。
そしてこの形状は、実はテレビなどの電波を効率よく受信するために計算され尽くした、非常に合理的な設計なのです。
八木式アンテナの各部分には、それぞれ重要な役割があります。それは以下の通りです。
| 名称 | 役割 |
|---|---|
| 放射器(ラジエーター) | アンテナの横棒の奥にある素子と黒い箱が一体化した部分で、電波を集めてケーブルに送る役割。 ケーブルに接続された箱状の部分は給電部とも呼ばれます。 |
| 導波器(ディレクター) | 本体のうち横の支柱部分で、支柱と直角に短い横棒(素子)がいくつも並ぶ部分。 先端を電波塔の方向に向けて電波を放射器へと導き、感度を高めます。 |
| 反射器(リフレクター) | 放射器の後ろにある矢印や魚の頭のような部分。アンテナ後方からの不要な電波(ノイズ)を反射し、また導波器から流れてくる地デジ電波も放射器側に反射します。 |
※上記は各部の基本的な解説です。
八木式アンテナの前方(受信性能を発揮する側)は、反射器の反対側の先端(魚の頭の反対側)になります。この前方側を、近隣の電波塔がある方向へと向けて設置します。
電波を集める「放射器(ラジエーター)」と「導波器(ディレクター)」
アンテナの多くを占める中心の支柱が「導波器(ディレクター)」と呼ばれる部分です。この部分には「素子(エレメント)」と呼ばれる電波を集める短い横棒のパーツが並んでおり、これが魚の骨に見える大きな要因です。
魚の頭とは反対側に当たるアンテナ正面の受信方向を、地デジ電波が送られてくる電波塔の方向に向けることで、地デジ電波は導波器に導かれるようにして、後方まで流れます。いわば導波器は、やってきた電波を放射器に集中させるレンズのような役割を果たしています。
そして導波器の後部に位置するのが、電波を受け取る「放射器(ラジエーター)」です。放射器は輻射器(ふくしゃき)とも呼ばれ、電波を集める放射素子と給電部(電波を電気的な信号に変換し、ケーブルに送る黒い箱のような部分)が一体化した形で、放射素子が集まった電波を放射するように集め、給電部へと送ります。
この導波器に並ぶ素子の数が多いほど、より多くの電波を集めることができるため、アンテナの受信感度が高くなるのです。
特定方向の電波を強める「反射器(リフレクター)」
放射器の後ろにある、魚の頭、もしくは矢印の先端に、やはり長い素子(反射素子)を並べた部分が「反射器(リフレクター)」です。8素子など素子数の少ない小型の八木式アンテナでは、この反射器が一本の長い反射素子になっている場合もあります。
この反射器は、受信したい電波塔とは逆の方向から来る余計な電波(ノイズ)をブロックする役割を果たします。これにより、放射器に集まる電波にノイズが混ざりにくくなるのです。
さらに放射器を通り過ぎた地デジ電波も、あらためて放射器に向かって反射させることで、受信できる電波をより強力にします。
八木式アンテナはこのような構造により、特定の方向(アンテナの前方)からの電波だけを強く受信する「指向性」が生まれ、受信感度が高まって安定したテレビ視聴につながるのです。
八木式アンテナの主なモデルとは?
八木式アンテナには、お住まいの地域の電波環境や設置場所の状況に合わせて、いくつかのモデルが存在します。
ここでは代表的なモデルの種類と、その特徴をご紹介します。
ご自宅に最適なモデルを選ぶための参考にしてください。
幅広いエリアに対応:素子数別モデル
八木式アンテナの性能をもっとも分かりやすく表すのが、各製品にも明記される「素子数」です。
素子(エレメント)とは、八木式アンテナが魚の骨に見える大きな要因である、本体の支柱部に並ぶ短い横棒のことで、これが電波をキャッチして伝えるパーツになります。本体でも導波器部分に並べられたこの素子の数が、八木式アンテナの受信性能に直結します。
一般的な八木式アンテナの素子数は、モデル別で主に8素子、14素子、20素子ですが、実際の本体の横棒を数えると、この数値より多くなります。これは、実際に電波を集めて送る導波器の部分の素子数に加えて、集まった電波をケーブルに送る給電器と一体になった放射器、魚の頭の部分で電波を反射する反射器は、複数の素子が並んでいてもそれぞれ1素子と数えるためです。
以下、八木式アンテナの各素子数別モデルの主な特徴になります。
| 素子数 | 特徴・推奨エリア |
|---|---|
| 8素子 | 小型で扱いやすい。電波レベルが非常に強い「強電界地域」向け。 |
| 14素子 | 標準的なモデル。多くの「中電界地域」で利用可能。 |
| 20素子 | 一般的な高性能モデル。電波が弱い「弱電界地域」や、安定した受信を求める場合に最適。 |
一般的に、多くのご家庭では14素子または20素子のモデルが選ばれます。
実際に多くのエリアで使用されることが多いのは20素子モデルになりますが、現場が電波塔のすぐ近くなど、電波レベルが強いエリアで、あまり受信性能の高いモデルを使用すると、地デジ電波だけでなくノイズも受信してしまい、かえって地デジ受信の品質が下がる場合もあるためご注意ください。
なお、素子数が多いほどそれを並べる導波部も長くなるため、素子数はアンテナ本体のサイズにも直結します。14素子と20素子では、導波器の長さが違うだけで反射器の幅に大きな違いはありませんが、8素子モデルは反射器もやや長い素子のみになるため、全体的にコンパクトです。
そのため8素子モデルは、受信感度を確保できる現場であれば、ベランダへの吊り下げ設置など、限られたスペースにも設置しやすいというメリットもあります。
特定エリアで受信感度が向上:ローチャンネル用モデル
実際に市販されている八木式アンテナの商品には、見た目や素子数、価格帯などはほとんど同じでも、製品名に「オールチャンネル用」と「ローチャンネル用」と明記されているものがあります。これは、そのアンテナ製品で対応できる周波数帯の違いです。
地デジ放送で、デジタル化した映像信号を乗せるために使われる電波の周波数帯は、UHF(極超短波)のうち470MHzから710MHzです。この周波数帯を6MHzずつ「チャンネル(映像信号を送る経路)」にわけて、地デジ放送の各放送局に割り当てています。これがテレビの「チャンネル」の由来です。
地デジの電波塔で、各テレビ局に割り当てられ、送信されるチャンネル(周波数帯)は、他の電波との混信などが起こらないよう、電波塔によって使い分けられています。ただ電波は周波数帯が高くなるほど、送信時の減衰が大きくなるため、実際に使用されるチャンネルは、できるだけ低い周波数帯のものが選ばれます。
そのため日本の地デジ電波塔から送信されるチャンネルは、その多くが、おおむね600MHz以下のやや低めの周波数帯になります。この周波数帯を「ローチャンネル帯(低い周波数帯のチャンネル)」と呼ぶのです。
そして八木式アンテナの内、オールチャンネル用は470MHzから710MHzのすべての周波数帯を平均的に受信できる機器です。対してローチャンネル用とは、おおむね470MHzから600MHz以下に特化して、その周波数帯の受信性能を高めた機種です。
したがって、受信できる地デジ放送チャンネルがローチャンネル帯しか使われていないエリアで、八木式アンテナを使用する場合には、ローチャンネル用のアンテナを使うことで、より受信感度を高めることができるのです。
ちなみに受信できる周波数帯を細かく調節できるのは、八木式アンテナの構造からくる特徴になります。デザインアンテナ、ユニコーンアンテナでは設計上、この調節が難しいため、基本的にオールチャンネル用のみになります。
この点も、八木式アンテナが受信性能で他の地デジアンテナ機種より優れる理由のひとつになります。
なお、お住まいの受信環境でオールチャンネル用とローチャンネル用のどちらのアンテナが適しているか(そのエリアで受信できるチャンネルの周波数帯)は、総務省の公式サイトなどをはじめ、インターネット上の検索で調べることもできますが、アンテナ工事の専門業者にご相談になれば、適切なアンテナ機種を勧めてくれます。
高性能化と小型化:高性能型モデル
八木式アンテナの受信性能は、素子数に応じて向上しますが、通常の20素子モデルより高い受信性能をが必要になる場合に向けて、より高性能型の八木式アンテナも開発されています。
このようなより高性能の八木式アンテナは「超高性能アンテナ」「パラスタックアンテナ」「スタック型」などと呼ばれています。
高性能型パラスタックアンテナとは、通常モデルでは1本ずつ並んでいる素子を、Ⅹ字型の部分の上下左右に並べた高性能素子を採用したモデルで、通常の八木式アンテナよりも、格段に高い受信感度を実現できます。
パラスタックアンテナには14素子や20素子の他、27素子、30素子などの多素子モデルもあり、通常モデルに換算すれば、数十素子から百数十素子に相当する高い受信感度を発揮します。
したがって、弱電界地域よりさらに電波塔から遠く、到達する電波レベルが非常に微弱な地域や、ビルなどの障害物が多い都市部でも、安定した受信感度を実現できます。
また高性能素子を使用するモデルであれは、5素子程度の素子数でも、通常モデルに遜色ない受信性能を発揮できるため、アンテナ本体を小型化できるメリットもあります。
環境が厳しいエリアに:高耐候モデル
八木式アンテナの弱点のひとつは、金属の機器部がむき出しの構造や、高い位置への設置から、風雨、積雪、潮風などに影響されて、老朽化やそれに伴うトラブルが生じやすい点です。
しかしその点を考慮して、天候など自然環境への耐性を強化したモデルも存在します。
このようなモデルは、受信性能は上記で解説したモデルと同等のため、沿岸地域や積雪地帯など、特定の条件で環境が厳しい場所に設置する場合に選ばれます。
以下が、自然環境別に対応できる、主な八木式アンテナ高耐候モデルの種類になります。
- 塩害用モデル:海沿いで潮風によるサビを防ぐため、ステンレス製の部品や特殊な防錆塗装が施されたモデルです。
- 雪害用モデル:積雪の多い地域で雪の重みに耐えられるよう、構造が強化されている。また雪が付着しにくい構造や、付着しにくい加工などの設計になっているモデルです。
他にもメーカーによって、素材や表面加工でサビ、腐食への耐性を高めたステンレスモデル、高耐食モデルなどもあります。また近年の八木式アンテナは、素材などの改良で全体的に軽量化が進んでおり、耐風性能が高まっています。
これらの高耐候モデルは、さまざまな自然環境の現場で、八木式アンテナを長期間、安心して使うための重要な選択肢となります。
八木式アンテナのメリット・デメリットを正直に解説
どのよう製品にも優れた点と、注意すべき点があります。
八木式アンテナは現在でも受信性能に優れるテレビアンテナですが、古典的なアンテナモデルであるため、今日の感覚からは欠点と呼べる部分も見られます。八木式アンテナが本当にご自宅に合っているか判断するためには、メリットとデメリットの両方をしっかりと把握しておく必要があります。
この項目では、アンテナ工事の専門家の視点から、八木式アンテナの長所、弱点とも包み隠さず正直に解説します。以下、八木式アンテナのメリット・デメリットを一覧でまとめました。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 性能 | 受信感度が高い。弱電界地域にも強い。 | – |
| 費用 | 本体価格、工事費ともに比較的安い。 | – |
| 設置場所 | 屋根上、屋根裏、壁面など自由度が高い。 | – |
| 外観 | – | 特徴的な形状が建物の外観を損ねる可能性がある。 |
| 耐候性 | – | 屋外設置のため、台風や積雪の影響を受けやすい。 |
| その他 | – | 鳥がとまりやすく、フン害などのリスクがある。 |
※上記はメリット・デメリットの要点です。
メリット1:高い受信性能で安定したテレビ視聴を実現
八木式アンテナが昭和から現在まで、長年にわたり愛用されている最大の理由は、その卓越した受信性能にあります。
テレビ電波を効率よく集める構造により、電波塔から遠い、障害物が多いなどにより、他の地デジアンテナ機種では、十分な受信が難しいような電波の弱い「弱電界地域」でも、安定した地デジのテレビ視聴を可能にします。
八木式アンテナは基本的な設置位置が、住宅の屋根の上などの高所に当たる点も、電波を遮る周辺の障害物の影響を避けて、受信感度が向上する大きな要因のひとつです。
また、八木式アンテナは構造上、アンテナ前方からの電波を強く受信する「指向性」が高く、アンテナ正面で受信性能を発揮する「半値幅」が狭くなります。そのため、同じ素子数(相当)の他機種と比べると、半値幅の範囲内での受信感度が高くなります。
さらに八木式アンテナは、指向性を発揮する先端を近くの電波塔の方向に向けることで、電波塔の方向から届く電波のみをキャッチし、他方向からの不要な電波の干渉を受けにくいのも特長です。
そのため高層ビルが密集する都市部や山間部など、電波環境が複雑な場所でも十分な受信レベルを確保でき、その真価を発揮します。
総じて八木式アンテナは後発の他機種に比べて、21世紀の現代でも受信性能においてはもっとも優れた地デジアンテナ機種になります。
メリット2:他のアンテナに比べて設置費用が安い
コストパフォーマンスの高さも、八木式アンテナの大きな魅力のひとつです。
八木式アンテナは古典的でシンプルな構造であり、古くからテレビアンテナとして使われているため、建物への施工法も確立しています。そのため後述するデザインアンテナやユニコーンアンテナと比較して、八木式アンテナ本体の価格も、設置工事にかかる費用も安価な傾向にあります。
初期費用をできるだけ抑えたい方や、アンテナの見た目よりも実質的な性能とコストを重視する方にとって、八木式アンテナは非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。
メリット3:設置場所の自由度が高く、屋根裏にも対応可能
八木式アンテナは、一般的には受信感度を確保できる屋根の上に設置されるイメージが強いモデルですが、実は設置場所の自由度が高いアンテナでもあります。
専用の金具を使えば、家の壁面やベランダの手すりにも設置できます。また現場の条件によっては、ベランダの内部空間に設置できることもあります。
さらに受信できる電波レベルが強い、住宅の建材が電波を通しやすいなど、一定の条件を満たせば、家の外観を一切損なわない「屋根裏空間への設置」も可能です。
屋根裏に設置することで、アンテナ本体の見た目の問題を解決し、雨風や鳥害からアンテナを守ることもできるため、近年では人気の設置方法となっています。
デメリット1:特徴的な見た目が家の外観を損ねる可能性
八木式アンテナの設置を考慮される際に、お客様がもっとも懸念されるポイントのひとつが、アンテナの見た目の問題ではないでしょうか。
昔ながらの魚の骨のような特徴的な形状は、現在の住宅で屋根の上に設置すると、どうしても目立ってしまいます。
特に、デザインにこだわった新築住宅や、景観を重視する地域では、外観や景観を損ねる大きな要因となり得ます。日本国内の景観地域では、景観条例によって一定の高さや形状のテレビアンテナを設置することが規制されている場合もあり、実質的に八木式アンテナの設置が制限されるケースもあります。
法的な制限がないエリアでも、外観的なデメリットを許容できるかどうかが、八木式アンテナを選ぶ上での大きな分かれ道となるでしょう。なお現在では、設置位置の工夫により、八木式アンテナの外観的デメリットをある程度、抑えることができるケースもあります。
デメリット2:台風や積雪など天候の影響を受けやすい
もうひとつ、八木式アンテナの形状や構造、特に屋根の上という高い場所に設置されることで生じる問題が、自然環境の影響を直接、受けやすいというデメリットなります。
例えば強い台風などの際には、指向性の高さもあって、風圧でアンテナの向きがずれてしまい、テレビが映らなくなることがあります。
また、積雪の多い地域では、雪の重みでアンテナが傾いたり、破損したりするリスクも考えられます。他にも沿岸部では潮風を受け、アンテナ本体な固定するマストのサビが進行しやすいという弱点も出てきます。
これら自然環境の影響は、一度でアンテナを故障させることはなくとも、長年の間に、徐々に八木式アンテナを老朽化させ、受信性能や耐久力を低下させる要因になります。
屋外に設置された八木式アンテナの寿命は、一般的に10年程度と言われています。ただ素材などを改良した近年のモデルでは15年程度ともいわれます。寿命をすぎた八木式アンテナが即座に壊れるわけではありませんが、全体的な老朽化により不具合が生じやすくなるほか、強い自然災害などが最後の一押しとなって、アンテナを破損させるケースも見られます。
これら自然環境の影響も、前述した高耐候モデルの採用や、設置位置の工夫で、ある程度の対策とすることも可能です。八木式アンテナ設置の際には、しっかりとした固定と、お住まいの地域の気候を考慮することが重要です。
デメリット3:鳥がとまりやすくフン害などのリスクがある(鳥害)
これも実質的には自然環境の影響と言えますが、八木式アンテナの独特な形状は、野鳥たちにとって格好の休憩場所になりがちです。
近年では「しあわせ鳥見んぐ」などといわれるバードウォッチングが人気を集めていますが、八木式アンテナに鳥がとまることで、受信不良やアンテナ角度のズレ、部分的な破損。さらには酸性のフンを受けることでの、アンテナの腐食、屋根や外壁の汚損、洗濯物への被害なども考えられます。
これら、鳥の影響による被害を「鳥害」と呼びます。
また、まれに鳥がアンテナに巣を作ってしまうことで、受信感度に影響が出たり、アンテナ自体が破損したりするケースもあります。
このような鳥の被害に対しては、近年ではロックバンドの名称でも知られる「結束バンド」をアンテナ本体にいくつも巻き付ける。その他、鳥よけグッズを使用して、アンテナに鳥が留まりにくくする、鳥か来ない環境を作るなどの対策が有効です。
【完全版】八木式アンテナの設置費用|総額いくらかかる?
お住まいにテレビアンテナを設置する上で、もっとも気になるポイントは、やはり取り付けにかかる費用ではないでしょうか。施工の品質さえ確保できれば、より安いテレビアンテナ工事をお求めになるのは、お客様にとっては当然のご要望と言えます。
この項目では、お客様の「結局、アンテナ取り付け工事には全部でいくらかかるの?」という疑問にしっかりお答えしていきます。
実際のアンテナ工事の費用は、アンテナ本体の価格や取付工費だけでなく、様々な工事費や部材費が組み合わさって決まります。
まずは、費用の内訳から総額の相場まで、詳しく見ていきます。
【一覧表】アンテナ設置にかかる費用の内訳
まず、テレビアンテナ設置工事にはどのような費用が含まれるのか、全体像を把握しましょう。
ここでは八木式アンテナの取り付けを例に説明しますが、基本的な項目は、他のアンテナ機種の場合も大きな違いはありません。
また担当する業者によっても料金体系は異なりますが、一般的に以下のような項目が挙げられます。
| 項目 | 費用相場の目安(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| アンテナ本体 | 3,000円~10,000円 | 八木式アンテナ本体の価格。素子数や性能による。 |
| 基本工事費 | 15,000円~30,000円 | アンテナの組立、設置、方向調整、配線接続などの基本的な作業費。 |
| ブースター設置 | 15,000円~25,000円 | 電波を増幅する機器の本体価格と設置費。 |
| 分配器設置・交換 | 5,000円~15,000円 | 電波を各部屋に分ける機器の本体価格と設置・交換費。 |
| 高所作業費 | 5,000円~10,000円 | 3階建ての屋根など、特殊な足場が必要な場合の追加料金。 |
| 既存アンテナ撤去・処分 | 5,000円~10,000円 | 古いアンテナを取り外し、処分するための費用。 |
| 出張費 | 0円~5,000円 | 業者の拠点から現場までの移動にかかる費用。無料の業者も多い。 |
※上記は主な項目の一覧です。
八木式アンテナの工事費込みの料金相場:25,000円~
それでは、八木式アンテナを新しく設置する場合の、工事費用の総額はいくらになるのでしょうか。
アンテナ本体と基本的な工事費を合わせた一般的な料金相場は、25,000円から40,000円程度です。
例えば、当「あさひアンテナ」では、DXアンテナ社製の高品質20素子八木式アンテナ「UA20」とマスト、屋根馬など基本設置具、同軸ケーブル、防水加工をセットにした基本設置工事費を22,000円(税込み24,200円)からでご提供しております。
他にも、各素子数モデルやローチャンネル用、高性能パラスタックアンテナ。また塩害用、雪害用、ステンレスモデルなどもご用意しており、設置位置も含めて、お客様のお住まいの受信レベルや周辺環境、ご要望に適した八木式アンテナ工事をご提案いたします。
ただし、上記の基本設置工事費用は、あくまでもアンテナ本体をお住まいに取り付け、ケーブルのみで配線を行う、シンプルでごく基本的な工事の場合です。
アンテナ取り付け工事に当たっては、以下にご説明する各種の機材、工事などの追加費用が発生するケースも多いため、必ず事前に詳細な見積もりを取ってください。
【要注意】追加費用が発生する5つのケース
「業者の公式サイトなどでは工事費用が低価格に思えたのに、最終的な工事費用は高くなった」というトラブルは避けたいものです。
そうならないためには、どのような場合に、アンテナ工事の追加費用が発生するのかを事前に知っておくことが大切です。
アンテナ取り付けの基本工事費に加算される費用としては、主に以下の5つのケースが考えられます。
ケース1:電波を増幅する「ブースター」が必要な場合
お住まいの地域が電波の弱い「弱電界地域」である、お住まいにて複数台のテレビで同時に視聴したりする場合、テレビアンテナで受信できる電波だけでは、映像信号のレベルが足りなくなることもあります。
そのような場合に必要となるのが、アンテナの近くで受信した電波を増幅する「ブースター(増幅器)」という機器です。
ブースターが必要かどうかは、専門業者が電波調査を行って判断しますが、一般的にはどのようなエリアでも、お住まいに三台以上のテレビを設置する場合にはブースターが必要になるため、現在の戸建て住宅では実質的に設置が必須と言える機器です。
ブースターを設置する場合、機器本体と設置費用を合わせて22,000円程度の追加費用がかかるのが一般的です。またブースターにもUHF(地デジ)対応型やUHF/BSCS(地デジと衛星放送)混合ブースターなどの種類もあり、それによって設置費用が変わってきます。
ケース2:複数テレビで見るための「分配器」工事が必要な場合
アンテナで受信し、ブースターで増幅されて一本のアンテナケーブルで送られる電波を、リビングや寝室など複数の部屋のテレビに送るためには、「分配器」という機器が必要です。
新築の戸建て住宅には通常、屋根裏、天井裏やマルチメディアボックスなどに、この分配器があらかじめ設置されていますので、取り付け工事の必要はないことが多くなります。
しかし、古い住宅で分配器がない場合や、衛星放送もご覧になる住宅で、分配器がBSCS、4K8K放送に対応していない場合は、分配器の新規設置や交換が必要になります。
その際の追加工事費用は、使用する分配器の分配数にもよりますが、5,500円程度が相場です。
ケース3:3階建てなどの「高所作業費」が発生する場合
八木式アンテナの設置工事は、主に屋根の上など高所での作業となり、危険が伴います。
特に、3階建て相当の屋根や壁面への設置など、標準的なハシゴでは届かない場所での作業には、より安全確保のための準備が必要となるため「高所作業費」が発生します。
この費用は、業者の安全対策にかかるコストであり、5,000円~10,000円程度が目安です。
業者によっては通常の2階建ての屋根でも発生する場合があります。この費用は、安全に工事を行うために必要な費用であるとご理解ください。
ケース4:ベランダや屋根裏などの特殊な設置方法
一般的な屋根の上への八木式アンテナ設置ではなく、ベランダの手すりや壁面、屋根裏など特殊な場所に設置する場合、基本設置工事に追加の費用がかかることがあります。
これは、設置場所に合わせて特殊な固定金具が必要になったり、作業がより複雑になったりするためです。
例えば、壁面に設置するためのサイドベース金具や、屋根裏での配線作業などが追加料金の対象となる場合があります。
ご希望の設置場所がある場合は、見積もりの段階でしっかり業者に伝えて、必要な費用を確認してください。
ケース5:古いアンテナの「撤去・処分費」が必要な場合
お住まいにすでに古いテレビアンテナが設置されていて、それを新しいものに交換する場合には、既存アンテナの撤去工事(持ち帰り処分を含む)が必要です。
この作業にも費用が発生し、相場は8,800円程度です。
テレビアンテナは自治体のルールに従って正しく処分する必要があり、処分費用も発生するため、アンテナ工事の際に、同時に専門業者へと任せることが、手間も省けて安心です。
既設アンテナの交換をご検討の方は、見積もり価格にこの撤去・処分費が含まれているかもしっかり確認してください。
八木式?デザイン?ユニコーン?あなたに最適なアンテナはコレ!
ここまでのご説明で、八木式アンテナのことは一通り分かったけど、他のアンテナ機種の特長はどうなのかと思われる方も多いでしょう。
現在、家庭用の地デジアンテナの種類(機種)は、八木式アンテナに加えて、デザインアンテナ、ユニコーンアンテナの、主に3種類になります。
本項目では、この3機種のそれぞれの特徴を比較してご紹介します。あなたのライフスタイルや価値観にもっとも合うアンテナ機種を見つけてください。
【一目でわかる比較表】3大アンテナを7項目で徹底比較
まずは、3種類の地デジアンテナ「八木式アンテナ」「デザインアンテナ」「ユニコーンアンテナ」を7つのポイントで比較してみます。
それぞれの長所と短所が一目でわかります。
| 項目 | 八木式アンテナ | デザインアンテナ | ユニコーンアンテナ |
|---|---|---|---|
| 受信性能 | ◎(非常に高い) | △(現場により低い場合も) | 〇(比較的高い) |
| 本体・工事費用 | ◎(安い) | 〇(標準) | △(高い) |
| デザイン性 | △(目立つ) | ◎(非常に良い) | ◎(良い) |
| 耐候性 | △(天候に弱い) | ◎(非常に強い) | ◎(非常に強い) |
| 設置場所 | 屋根上、壁面、屋根裏 | 壁面、屋根裏、ベランダ | 屋根上、破風板 |
| 寿命の目安 | 10年~15年 | 15年~20年 | 15年~20年 |
| 鳥害リスク | △(あり) | ◎(ほぼなし) | ◎(ほぼなし) |
※以上は主な比較ポイントです。
【ケース別】こんな人には「八木式アンテナ」がおすすめ
以下の項目に当てはまる方は、八木式アンテナが最適な選択肢となる可能性が高いです。
- とにかく安定した受信感度を最優先したい方。
- アンテナの設置費用をできるだけ安く抑えたい方。
- 電波塔から遠い、山間部など電波が弱い地域にお住まいの方。
- 周囲に高層ビルなど電波を遮る障害物が多い方。
- アンテナの見た目は特に気にならない方。
性能とコストパフォーマンスを重視するなら、八木式アンテナがもっとも合理的な選択と言えます。
【ケース別】こんな人には「デザインアンテナ」がおすすめ
一方で、以下のようなご要望をお持ちの方には、デザインアンテナがおすすめです。
お選びになる際の主なポイントは、以下の通りです。
- 新築で、家の外観を絶対に損ねたくない方。
- 台風や積雪が多い地域で、アンテナの倒壊リスクを減らしたい方。
- 鳥のフン害などを避けたい方。
- 電波が比較的強い地域(強電界~中電界地域)にお住まいの方。
- 壁面や屋根裏など、目立たない場所に設置したい方。
デザイン性と自然災害への強さを求めるなら、デザインアンテナが有力な候補になります。
デザインアンテナとは、壁面やベランダの手すりに設置できる薄型パネル状の地デジアンテナです。本体のカラーバリエーションも豊富で、住宅に設置しても家の見た目や景観を乱しにくい。さらに本体の構造や設置位置から風雨などに強く、耐用年数が長くなるというメリットがあります。
一方でデザインアンテナはその構造から、同じ素子数相当でも八木式アンテナより受信性能がやや低い。さらに設置位置が低いことから、八木式アンテナに比べて受信感度が低くなりやすい弱点もあります。そのためデザインアンテナの設置は、基本的に強・中電界地域向けであり、建物など電波を遮る周辺環境によっては設置できないケースも出てきます。
地デジアンテナの第二世代として、2009年(平成21年)頃に普及し始めたデザインアンテナは、受信性能をやや犠牲にして八木式アンテナの弱点をカバーした、対になるアンテナ機種ともいえます。
当あさひアンテナでは、高品質アンテナ本体、設置具や同軸ケーブル(白黒2色どちらか)をセットにしたデザインアンテナ基本設置工事を、業界最安に挑む価格でご案内しております。具体的な価格は、
DXアンテナ「UAH201」(20素子相当・本体色4色)は、22,000円(税込み24,200円)より。
サン電子「WG-20」(20素子相当・本体色5色)&背面の配線などを隠して外観が整う「背面スッキリカバー」のセットは、25,000円(税込み27,500円)より。
マスプロ電工「スカイウォーリーミニ・U2SWLC3」(強電界地域専用コンパクトモデル、室内スタンド付属・本体色2色)も、25,000円(税込み27,500円)よりでご案内しております。
また受信状態がやや弱い地域向けに26素子相当モデルもご用意しているほか、対応できる条件の現場であれば、デザインアンテナの屋根裏・天井裏設置も、追加工事費はご無用の、上記の基本設置工事費用でご案内いたします。
【ケース別】こんな人には「ユニコーンアンテナ」がおすすめ
八木式アンテナとデザインアンテナ、どちらもメリット・デメリットが対称的で決めかねる、という方は、ユニコーンアンテナもご検討してください。そのポイントは、以下の通りになります。
- 家の外観は気になるけど、受信性能も妥協したくない方。
- デザインアンテナを設置したいが、電波が少し弱くて設置を断られてしまった方。
- 周囲の家のデザインと調和させたい方。
- 最新のアンテナに興味がある方。
ユニコーンアンテナは、2017年(平成29年)に登場した、マスプロ電工製のポール状アンテナ「U2CN」の商品名で、デザイン性と受信性能を高いレベルで両立した、まさに「いいとこ取り」のアンテナです。
そのポール状の本体を、八木式アンテナと同じく、屋根の上の高所でマストの先に固定する形で設置されます。スタイリッシュな外観で、設置しても住宅の外見や景観に影響が少ない。風雨を受け流す形状で経年劣化しにくく、耐用年数が長くなるなど、デザインアンテナと同等のメリットがあります。
さらにユニコーンアンテナは、設置位置が高いことから受信感度が安定しやすく、周辺の建物などの影響でデザインアンテナ設置が難しい現場でも、受信感度に問題なく設置できることが多くなります。
ユニコーンアンテナは、より受信感度を向上させ、より幅広い現場に対応できるようになった、デザインアンテナの進化系とも言えます。
一方でそのデメリットは、八木式アンテナに比べると受信感度が及ばず、強・中電界地域向けモデルになる。最新モデルであるため設置費用が割高になるなどの点が挙げられます。
当あさひアンテナでは、ユニコーンアンテナ(本体色2色)と設置具、同軸ケーブルをセットにした基本設置工事費用を、ただいま業界最安に挑む「キャンペーン価格」でご案内しております。
後悔しない八木式アンテナの選び方【専門家が教える3つの要点】
上記の各アンテナ機種のご紹介から、やはりご自宅には八木式アンテナが適しているとお考えのお客様には、次に「どの八木式アンテナ機種を選ぶか」を決めることが重要です。
上記でもご紹介した通り、一口に八木式アンテナといっても、さまざまな種類、モデルがあります。
ここでは、テレビアンテナ選びで失敗しないための、専門的な3つの要点をご紹介いたします。
要点1:お住まいの地域の「電界強度」を調べる
地デジアンテナ選びでもっとも重要なポイントが、ご自宅の一帯に届く地デジ電波レベル電波がどの程度か、つまり「電界強度(電界地域)」を知ることです。
電界強度(電界地域)は、特定の電波塔からの距離や、電波を遮る大まかな地形によって決まり、一般的には、以下の3つの地域に大きく分類されます。
- 強電界地域:電波塔が視認できるエリアで、到達する地デジ電波レベルが非常に強く(80㏈以上)、8素子から14素子の地デジアンテナや、室内用の簡易的なアンテナでも受信しやすいエリア。天井裏など屋内空間も含め、設置方法の自由度も高くなります。
- 中電界地域:強電界地域よりやや遠く、ある程度の強さ(80㏈以下から60㏈以上)の地デジ電波が届くエリア。14素子から20素子の地デジアンテナを屋外に設置すれば、ほとんどの場合は安定した受信が可能になるエリアです。
- 弱電界地域:中電界地域より遠く、到達する地デジ電波も60㏈以下とやや弱くなるエリア。安定した地デジ受信には、20素子や高性能アンテナなど、受信性能の高いアンテナを屋根の上に設置するほか、ブースターの設置も必要になるエリアです。
この電界強度によって、選ぶべき地デジアンテナの受信性能や、適した設置位置が変わってきます。お住まいがどの電界地域に含まれるかは、「一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)」のウェブサイト内「地デジ電波レベルのめやす」ページで確認できます。
ただ上記の電界強度は大まかな目安にすぎず、お住まいで実際に受信できる地デジ電波は、周辺の建物、高層建築などにも影響を受けて変動します。そのため同じお住まいでも、屋根の上では十分な受信は可能でも、壁面など低い位置では電波が遮られ、十分な受信ができないケースもあります。
お住まいの正確な電界地域や、受信に適した位置を知るには、アンテナ工事の専門業者に無料の「電波調査」を依頼するのが、もっとも確実で簡単な方法です。
当あさひアンテナでは、アンテナ工事を前提としたお客様には、お住まいに出張しての電波調査とお見積もりを、出張料やキャンセル料などすべての費用を含む「完全無料」でお引き受けいたします。
弊社の電波調査では、屋根の上や壁面の各位置など、お住まいのさまざまな位置で綿密な電波調査を行い、安定した受信ができる場所をすべてチェックいたします。その上で、現場で可能な中からお客様のご要望に最適なアンテナ工事を、最安に挑む価格でご提案いたします。
要点2:受信感度を左右する「素子(エレメント)数」を選ぶ
次に、ご自宅の電界強度に合わせて、適切な「素子数」のアンテナを選びます。
前述の通り、素子数はアンテナの受信性能を示す指標です。
素子数が多いほど高性能(高利得)になり、弱い電波も十分にキャッチできますが、その分アンテナが大きく、重くなり、価格も上がります。
逆に、強電界地域などで高性能すぎるアンテナを使うと、電波が強すぎる、余計なノイズも受信してしまうなどで、かえって地デジ放送の映りが悪くなることもあります。
お住まいの地域の電波強度に合った、過不足のない素子数のアンテナを選ぶことが、コストパフォーマンスの面でも重要です。
要点3:設置場所の環境(塩害・雪害)に合った製品を選ぶ
最後に、ご自宅の周辺の環境要因を考慮しましょう。
特に、沿岸部や積雪の多い地域では、アンテナの素材や設計が寿命に大きく影響します。八木式アンテナの場合は、以下のモデルがオススメです。
- 沿岸地域にお住まいの方:潮風によるサビを防ぐため、ステンレス製や耐食アルミ合金で作られた「塩害対策モデル」を選びましょう。メーカーによっては、ステンレスモデル、抗腐食モデルと呼ばれることもあります。
- 雪の多い地帯にお住まいの方: 雪の重みに耐えられるような頑丈な設計。また表面に雪が付着しにくい加工がされた「雪害対策モデル」がおすすめです。
また、もし八木式アンテナへのこだわりがなく、現場の受信環境で対応できるのであれば、デザインアンテナやユニコーンアンテナ、屋根裏設置なども、自然環境への有効な対策になります。
こうした地域特性に合わせたアンテナ製品を選ぶことで、取り付けたテレビアンテナを長期間、安心して使用することができます。
八木式アンテナはどこに設置できる?最適な場所と注意点
八木式アンテナといえば、戸建て住宅では屋根の上に設置されるもの、というのが、昔からのイメージです。しかし現在では、施工技術の進化から、八木式アンテナはじめ、戸建て住宅でもさまざまな位置へのテレビアンテナ工事を実現できる工法が登場しています。
ご説明した通り、八木式アンテナの弱点と言えば「取り付けの見た目」「天候や環境の影響で老朽化しやすい」という二点ですが、この弱点も、設置方法を工夫することで抑えることか可能になるのです。
一方で、設置位置によっては、八木式アンテナの長所である受信感度がやや損なわれるケースもありますので、メリットとデメリットの兼ね合いから設置位置を決めることが重要です。
以下、八木式アンテナの主な設置場所と、そのメリット・デメリットをご紹介いたします。ご自宅にとって最適な設置場所を見つけてください。
もっとも受信感度が高い定番の「屋根上」
八木式アンテナの設置ではもっとも一般的で、アンテナの受信性能を最大限に引き出せるのが、住宅の屋根の上です。
屋根の上などの高所では、周囲の障害物の影響を受けにくく、八木式アンテナの向きを電波塔に合わせることで、地デジ電波をダイレクトに受信できるため、地デジ受信ではもっとも高い受信感度が期待できます。
八木式アンテナを屋根の上に設置する一般的な工法は、屋根の頂点部に「屋根馬(やねうま)」という専用の土台を置いてマストを立て、その先に八木式アンテナを固定する。そしてステンレス製のワイヤー・ステー(支線)を、屋根の四方から屋根馬、マストまでしっかり張って支えるという方法で、安定性も高くなります。
この方法では、同じマストにBS/CSアンテナや地方局用アンテナなど、他に必要なアンテナをまとめて設置できるメリットもあります。ただし一方で、前述の通りアンテナの外観が目立ち、天候の影響を受けやすいというデメリットも考慮する必要があります。
通常、屋根馬を用いた八木式アンテナ設置は、屋根馬をバランスよく固定できる屋根の頂点部にしか設置できません。しかし当あさひアンテナでは、水平器という機器を用い、屋根馬の脚を適切に加工することで、屋根の傾斜部にマストを立て、アンテナを固定する工法も可能です。
屋根の上でも設置位置を工夫することで、外観からの死角になり、住宅の外観を保つ設置が可能となるケースもあります。
また、屋根の張り出し部(破風板)にサイドベースという金具でマストを取り付け、アンテナを立てる方法もあります。この方法でも、屋根の上と同等の高さで受信感度を確保しつつ、より丈夫な固定で、現場によっては目立ちにくい設置も可能となります。
外観を隠せる「屋根裏(天井裏)」設置の条件と注意点
住宅の外観や外装を損ねず、雨風などの影響からもアンテナを守りたいという方に人気の設置場所が「屋根裏空間」です。
この工法では、アンテナ本体を屋内へと完全に隠せるため、美観や耐候性の問題を一挙に解決できます。
ただし、地デジアンテナを屋根裏に設置するには、以下の条件をクリアする必要があります。
- 屋根裏などの空間に地デジアンテナを設置できる十分なスペースがあること。
- 屋根材や建材、断熱材が電波を通しやすい素材(スレートやアスファルトシングルなど)であること。
- 屋根などを透過して減衰した地デジ電波でも十分な強度が得られること(主に強電界地域)。
屋根材その他の建材が金属製、ウレタンの断熱材の場合や、屋根の上に太陽光パネルが設置されている場合は、電波が遮られてしまうため屋根裏設置は難しくなります。
基本的に地デジアンテナの屋根裏、天井裏設置は、薄型コンパクトで受信面が広いデザインアンテナが採用されます。八木式アンテナは受信性能では優れるものの、本体が大きいため、屋根裏などに設置する場合の条件がより厳しくなります。また設置費用も、追加の設置具などが必要な分、デザインアンテナの場合とほとんど差がなくなります。
実際に、屋根裏空間への設置に八木式アンテナが使われるのは、デザインアンテナでは受信性能が不足し、現場の条件から設置が可能なケースになります。
「壁面・ベランダ」設置の可否とポイント
他にも、八木式アンテナを家の壁面やベランダの手すり、内部空間に設置することも可能です。
サイドベースという専用の金具を使って壁面に固定する。ベランダ用の取付金具で手すりや内部空間に固定するなどします。
この場合のメリットは、屋根の上への設置に比べて目立ちにくい、風雨なども避けやすい、メンテナンスも行いやすくなるなどの点で、八木式アンテナの一般的なデメリットをカバーすることができます。
そしてこの方法を選ぶ際のポイントは、電波塔の方向に建物などの障害物がないことです。
屋根上よりは低い位置になるため、地デジの受信感度は若干落ちる傾向もありますが、現場の電波環境が良ければ十分に安定した視聴が可能です。
アンテナ設置の流れ|業者依頼とDIYの違い
テレビアンテナ設置を具体的に進めるにあたり、どのような流れになるのか気になりますよね。
この項目では、アンテナ工事の専門業者に依頼した場合の一般的な作業の流れと、DIY取りつけをご検討されている方への注意点をご説明します。
【業者依頼の場合】問い合わせから工事完了までの5ステップ
信頼できるアンテナ工事の専門業者へご依頼になれば、最短の日程でスムーズかつ安全にアンテナ設置が完了します。一般的な流れは以下の通りです。
- 問い合わせ・相談
電話(フリーダイヤル)やメール、LINEなどで業者に連絡し、お客様の現在の状況や要望を伝えます。この段階で概算の料金などを確認できます。 - 現地調査・見積もり
専門スタッフが自宅を訪問し、電波状況を専用の測定器で詳細に調査します。その結果と要望に基づき、最適なアンテナと設置場所を提案し、正式な見積書を提示します。複数の業者に見積もりを依頼する「相見積もり」も可能です - 契約・日程調整
業者の見積もり内容に納得できれば本契約となり、工事の日程を調整します。即日工事に対応してくれる業者も多く存在します。 - 設置工事
施工当日には熟練したスタッフが、安全対策を万全にした上でアンテナの設置工事を行います。基本的に工事の際にはお客様の立ち合いが必要ですが、作業のすべてを見守る必要はなく、要所以外は住宅内で待機されていても大丈夫です。工事の完了後には、テレビが問題なく映るか、各部屋で受信レベルを確認します。 - 支払い・保証書受け取り
工事の完了後は、現金やクレジットカード、電子マネーなどで工事料金を支払います。最後に、長期保証の保証書を受け取って完了です。
DIYはおすすめしない?プロが語る3つのリスク
テレビアンテナ設置に関して「工事の費用を節約するために、アンテナだけ用意して自分でテレビアンテナ工事の作業をできないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、アンテナ工事のプロとして、DIYでの設置は以下の3つの大きなリスクから、強くはおすすめできません。
- 高所からの転落事故の危険性
特に八木式アンテナの設置は、多くの場合、屋根の上など高所での作業になります。慣れない作業でバランスを崩し、転落すれば命に関わる重大な事故につながります。またアンテナそのものや機材を落としてしまうことも、肝心のアンテナの破損をはじめ、物や人に当たることで大変な事故を招く危険性があります。 - 最適な設置・調整の難しさ
一般の方が、専用の電波測定器なしに、地デジアンテナの性能を最大限に引き出す最適な場所や角度を見つけるのは至難の業となります。せっかく設置しても「一部のチャンネルが映らない」「ノイズが入る」といったトラブルが起きがちです。 - 建物を傷つけるリスク
誤った方法で金具を取り付けると、雨漏りの原因を作ってしまったり、外壁を傷つけたりする恐れがあります。結果的に、修理費用で高くついてしまうケースも少なくありません。
基本的にテレビアンテナのDIY設置は、ベランダや窓の外に、BS/CSアンテナや簡易型のコンパクトなデザインアンテナを設置する。また古いアンテナを同タイプのアンテナに交換するなど、第一に作業を安全に進めることができ、作業の内容も比較的、簡単な場合に限りおすすめできる作業になります。
悪徳業者に注意!信頼できるアンテナ工事業者の見極め方
「どこに頼めばいいか分からない」「高額請求されないか心配」
アンテナ工事業者を選ぶ作業は、多くの方にとって不安な点だと思います。
近年ではアンテナ工事業者も数が多く、業者間でサービス競争になっており、お客様にとってはお得な半面、残念ながら一部には悪質な業者がいるのも事実です。
ここでは、安心して任せられる優良なおすすめテレビアンテナ工事業者を見極めるための、4つのチェックポイントをご紹介します。
チェック1:明確な料金体系と詳細な見積もりを提示するか
信頼できる業者は、公式サイトなどで工事の料金体系、また使用機材のメーカー、モデル、型番などを明確に提示しています。
また現地調査の後には、工事内容と費用が項目ごとに細かく記載された詳細な見積書を無料で発行してくれます。
逆に「工事一式 〇〇円」といった曖昧な見積もりしか出さない業者や、見積もり自体が有料の業者には注意が必要です。追加料金が発生する可能性についても、事前にきちんと説明してくれる業者を選びましょう。
特に複数の業者に見積もりを出す「相見積もり」を行うことで、複数の業者の見積り価格を比べて、適正な価格や工事(見積もり項目)内容を判断することができます。相見積もりに対応できるという点も、優良な業者を見極める目安のひとつになります。
チェック2:豊富な施工実績と完全自社施工であるか
業者の技術力や信頼性を判断する上で、施工実績は重要な指標です。
公式サイトに、写真付きの具体的な施工事例が数多く掲載されているかを確認しましょう。
また工事を下請け業者に丸投げせず、研修を受けた自社のスタッフが責任を持って行う「完全自社施工」の業者であるかどうかも重要です。完全自社施工は、スタッフの経験、研修による施工技術に期待できることはもちろん、中間マージンなど余計なコストを抑えて工事費用の低価格化にもつながります。
当「あさひアンテナ」は、年間6000件を超える豊富な実績を誇り、すべて経験豊富な自社スタッフが完全自社施工で対応しております。
チェック3:長期保証と手厚いアフターサポートがあるか
テレビアンテナは10年以上にわたって使用する製品だけに、設置すれば終わりではありません。
後事を依頼するアンテナ業者に、万が一の故障やトラブルに備えて、長期の保証制度が整っているかを確認することも、非常に重要なポイントです。
アンテナ工事専門業者の一般的な保証期間は、5年から8年ですが、優良な業者はそれ以上の長期保証を提供しています。
例えば「あさひアンテナ」では、業界最長クラスである「10年間」の長期保証をお付けしており、工事後のアフターサポートも万全です。
チェック4:高品質な部材を使用しているか
テレビアンテナの寿命は、使用する部材の品質に大きく左右されます。
工事費用が極端に安い業者は、コストを抑えるために安価な海外製の部材を使用している可能性があります。
長く安心して使うためには、DXアンテナやマスプロ電工、日本アンテナ、サン電子といった国内大手メーカー製で、JIS規格に準拠した高品質な部材を使用している業者を選ぶべきです。
見積もりの際に、使用する部材のメーカーや型番を確認するのも良いでしょう。
当あさひアンテナでは、使用するアンテナやブースター、設置具などの機材に、すべて上記の国産大手メーカーの機材を使用し、テレビアンテナや周辺機器、必要な部材をセットにした、明快な「基本設置工事費」でご案内しております。
弊社ではアンテナなど各機材をメーカーから直接、大量仕入れすることで、スケールメリットによる大幅値引きで、個人の方や小規模業者には難しい、低価格のアンテナ設置や各種機器、工事の基本費用を実現しております。
設置後も安心!寿命とメンテナンス、トラブル対処法
テレビアンテナを設置した後も、長年にわたって快適にテレビをご視聴になるためには、アンテナの寿命やメンテナンスについて知っておくことが大切です。
ここでは、八木式アンテナのよくあるトラブルとその対処法についても解説します。
八木式アンテナの寿命は10年から15年が目安
八木式アンテナの寿命は、上記でも触れた通り、一般的に10年から15年と言われています。
ただし、これはあくまで目安であり、使用するアンテナの品質や、設置された環境によっても大きく変わります。
塩害や雪害の多い地域では、対応する八木式アンテナモデルでない場合は寿命が短くなる傾向にありますし、逆に天候が穏やかで、定期的なメンテナンスを行っていれば、通常モデルでも20年以上、問題なく安定して使えるケースもあります。
いずれにせよ、八木式アンテナは設置から10年を過ぎたら一度、専門業者に点検、メンテナンスしてもらうと安心です。
「テレビが映らない!」原因別のトラブルシューティング
テレビアンテナ設置なら何年も過ぎた頃、ある日突然テレビが映らなくなると、焦ってしまうこともあるでしょう。
そのような際にも、あわてて業者を呼ぶ前に、ご自身で確認できることもあります。
以下では、原因として考えられることと、その対処法をまとめました。
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| アンテナの向きのズレ | 強風などの影響で八木式アンテナの向きがずれている可能性があります。危険なので自分で直さず、業者に連絡してください。 |
| ケーブルの抜け・緩み | テレビやレコーダー、壁の端子に接続されているケーブルが抜けていたり緩んでいたりしないか確認し、差し直してください。 |
| ブースターの電源オフ | ブースターを使用している場合、電源部のコンセントが抜けていない、きちんと作動しているかなどを確認してください。 |
| 周辺環境の変化 | 近所に高い建物が建つなど、周辺環境の変化で電波が遮られている可能性があります。この場合もアンテナ移設など、業者への相談が必要です。 |
| アンテナ・機器の故障 | アンテナ本体やブースター、ケーブルなどが寿命や災害で故障している場合も考えられます。業者による点検・交換が必要です。 |
※上記は主な原因と対処法になります。
八木式アンテナに関するQ&A
最後に、八木式アンテナに関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 衛星放送(BS放送、CS放送)も見たい場合はどうすればいいですか?
衛星放送を視聴するためには、地デジ用の八木式アンテナとは別に、電波をキャッチするお皿のようなディッシュ部を持つしたパラボラアンテナ(BS/CSアンテナ)を設置する必要があります。
八木式アンテナとBS/CSアンテナを、同時に設置することももちろん可能です。
多くの業者では、地デジとBS/CSのアンテナ設置をセットにしたお得なプランを用意しています。
別々に依頼するよりも作業量やコストが抑えられる分、工事費が割安になることが多いので、衛星放送に興味をおもちの方は、同時に設置をご検討になるのがおすすめです。
Q2. 不要になったアンテナはどう処分すればいいですか?
古いアンテナを交換した場合など、不要になったアンテナは、自治体のルールに従って「粗大ごみ」として処分するのが一般的です。
ただし、一定の処分費が必要になるほか、アンテナを屋根から降ろす作業は非常に危険です。
安全のためにも、ご自身で処分しようとせず、新しいアンテナの設置を依頼した業者に、古いアンテナの撤去工事(処分含む)を併せてご依頼になるのがもっとも安全で効率的です。
ほとんどの業者が、有料で撤去・処分サービスを行っています。
当あさひアンテナでは、古いアンテナからの交換工事では、既設アンテナの取り外し工事(持ち帰っての処分費を含む)を、1.8メートルまでのアンテナであれば、5,000円(税込み5,500円)でお引き受けいたしております。
Q3. アンテナを設置せずにテレビを見る方法はありますか?
はい、ございます。
アンテナを設置する代わりに、インターネットの光回線でテレビの映像信号を送る「光回線テレビ」や、同じく住宅まで敷設されたケーブルを利用する「ケーブルテレビ(CATV)」を契約するという選択肢です。
これらのサービスは、アンテナが不要で天候に左右されないというメリットがありますが、毎月の利用料、視聴料がかかるというデメリットもあります。
特に長年、お住まいになるマイホームの戸建て住宅では、長期的に見ると、いったん設置すればランニングコストのかからないテレビアンテナの方が、トータルの費用を安く抑えられるケースが多くなります。
まとめ:最適なアンテナ選びで快適なテレビライフを
八木式アンテナ(Yagiアンテナ)の仕組みや進化の歴史をさらに深く学びたい方はこちら
本記事では、八木式アンテナについて、その種類や特徴などの基礎知識、設置費用や取付方法、工事業者の選び方まで、詳しく解説してまいりました。
最後に、本記事の重要なポイントを振り返っていきます。
- 八木式アンテナは昭和期からの古典的アンテナモデルですが、高い受信性能と優れたコストパフォーマンスを両立した、いまなお現役の定番テレビアンテナです。
- 「性能重視」「コスト重視」の方や、「電波の弱い地域」にお住まいの方に特におすすめです。
- アンテナ取り付けの費用相場は、本体、部材と工事費込みで25,000円程度ですが、ブースターなど必要な機材、工事などで追加費用がかかる場合があります。
- 地デジアンテナの機種選びは「現場の電界強度」「本体の素子数」「設置する環境」の3つの要点を押さえることが重要です。
- アンテナ工事業者選びで失敗しないためには「明確な料金」「施工実績と品質」「長期保証」「高品質な部材」などをチェックしてください。
現在でも地デジアンテナとして八木式アンテナをお選びになることは、多くのご家庭にとって非常に合理的で優れた選択肢です。
しかし近年では外観性、対候性に優れたデザインアンテナ、ユニコーンアンテナなどの機種も登場しており、最終的にご自宅に最適な地デジアンテナを判断するには、やはりプロの目による正確な電波調査と、現場の条件を踏まえた判断、そしてお客様のご要望が欠かせません。
当「あさひアンテナ」では、専門スタッフによる無料の電波調査とお見積もりを承っております。もちろんご希望があれば。、他業者との相見積もりや即日工事にもご対応いたします。
アンテナ工事の施工は完全自社施工で、施工コストは押さえながら、高品質の国産アンテナ機材と、経験豊富で優秀な弊社のアンテナ職人による最高品質の施工をご提供いたします。
アンテナ工事と受信状態の確認を完了した後の、料金のお支払いについては、各種のクレジットカード、電子マネーにもご対応しております。
さらに工事完了日から「10年」の長期保証で、アンテナ設置後も末永い安心をお約束いたします。
各種テレビアンテナ設置工事やその他アンテナに関するお悩み、ご相談がございましたら、当あさひアンテナのフリーダイヤル、メールフォーム、LINEアカウントまで、どのようなことでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
最適なアンテナ工事選びで、快適なテレビライフを実現するお手伝いをさせていただきます。