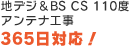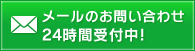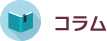地デジ・BS/110度CSアンテナの向き調整ガイド:テレビが映らない原因は?アプリで方向チェック&調整方法も解説
お住まいに地デジ、BS/CSアンテナ(BSアンテナ)を設置するだけで、長くに渡って手軽に視聴できる地上デジタル放送やBS放送、CS放送などは、いまや戸建て住宅には欠かせないものと言えるでしょう。
ただ長い間、テレビ放送を見ていると、昨日まできれいな画面で観ることができたテレビ放送が、ある日突然、正常に映らなくなることもあります。例えば、
「急にテレビの画面にノイズが張って映りが悪くなった」
「特定のチャンネルだけブロックノイズが出て、まともに見られない」
「テレビ画面がブラックアウトしてE101などの記号が表示される」
このようなテレビの視聴トラブルの原因はさまざまに考えられますが、特に設置から一定の年数がすぎたアンテナで、台風などの強風、大雪や地震など自然災害の後であれば、お住まいにあるアンテナの向き(角度)がずれてしまった可能性が高くなります。
ご存知の方も多いでしょうが、テレビアンテナは、地デジ、衛星放送とも、電波が届く方向に向けて、適切に向きを調整することで、受信性能がもっとも高くなります。
そのためアンテナの経年劣化、自然災害などでアンテナの角度がずれたときは、適切な角度の再調整を行って、角度の狂いが再発しないよう、しっかりと固定する工事が必要です。
「でも、アンテナの角度調整なんて専門知識がないと難しそう」
「業者に角度調整を頼むと、高額な費用がかかるのではないか」
アンテナの角度調整について、そうお考えの方、ご不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
しかし、地デジやBS/CSのアンテナを向けるべき正しい方角は、スマートフォンの無料アプリやインターネットのサイトなどを確認すれば、専門的な機材がなくても簡単に調べることができます。
そして、お住まいにあるテレビアンテナの種類や設置場所によっては、ご自身でアンテナの向きを調整し、受信に関する問題を解決できるケースも少なくありません。ただ一方で、作業に危険が伴う位置にアンテナがある場合は、ご自身での作業は絶対におすすめできませんので注意が必要です。
今回の記事では、アンテナの向き調整の専門知識がない方でも安心して作業が可能になるよう、年間およそ6000件の施工実績をもつアンテナ工事のプロ集団、あさひアンテナの担当者が、以下の内容や関連の情報を分かりやすく解説してゆきます。
- アンテナの向きがずれるとテレビが映らなくなる仕組み。
- スマホアプリやWebサイトを使った正しい向きの調べ方。
- アンテナの種類別の具体的な調整手順と注意点。
- 向きを調整しても直らない場合の他の原因と対処法。
- プロの業者に依頼する場合の費用相場と選び方のポイント。
この記事をお読みいただければ、アンテナの角度トラブルで業者へと連絡する前に、ご自身でできることが明確になり、コストをかけずにテレビの視聴トラブルを解決できる可能性を見出すことができます。
また業者に依頼する必要がある場合も、施工技術が確かで料金も良心的な優良業者を選ぶことができます。
本記事の情報を参考に、急なアンテナトラブルについても慌てることなく、早急に安定したテレビの視聴環境を取り戻せる道筋を見つけていただければ幸いです。
目次
- 地デジアンテナを向けるべき方向と受信の注意点は?
- BS/CSアンテナを向けるべき方向と受信の注意点は?
- もしかしてアンテナの向きが原因?まずは症状をセルフチェック
- 【準備編】アンテナを調整する前に!正しい向きの調べ方3選
- 【実践編】地デジアンテナの向きを自分で調整する手順
- 【実践編】BS/CSアンテナの向きを自分で調整する手順
- 【番外編】Wi-Fiの接続が悪い…ルーターのアンテナの向きもチェック!
- 自分でアンテナの向きを調整する際の5つの注意点【安全第一】
- 向きを調整しても映らない…考えられる他の原因と対処法
- 自分でやるのは難しい…プロの業者に依頼すべきケースと費用相場
- まとめ:アンテナの向きを正して快適なテレビ・ネット環境を取り戻そう
- アンテナ向き調整のよくある質問 (FAQ)
地デジアンテナを向けるべき方向と受信の注意点は?
現在の主なテレビ放送である「地上デジタル放送(地デジ放送)」では、日本各地の主な地点に設置された電波塔から、UHF(極超短波)という種類の電波でも470MHz(メガヘルツ)から710MHzまでの周波数帯に、デジタル化された映像信号を乗せて送信しています。
この電波を自宅の地デジアンテナで受信することで、デジタル信号が映像、音声に変換されるため、一般のお住まいでは地デジ放送のテレビ番組を見ることができます。
地デジ放送は災害などの緊急時に速報を伝達する役割もある基幹的なテレビ放送のため、日本国内であれば地デジアンテナや受信機器を用意することで、不特定多数(誰でも)無料で視聴することができます。
ただ、地デジ電波は電波塔の先端から周囲の一帯に送信されること、また地デジアンテナには、アンテナの正面側で受信性能が高くなる「指向性(しこうせい)」があるため、地デジアンテナは基本的に、お住まいの地域にある最寄りの電波塔の方向へ、その前方を正確に向ける必要があります。
なお、アンテナを向けるべき電波塔の方向や、お住まいの地デジ電波環境(強電界・中電界・弱電界の目安)は、事前に 地デジ電波の強度 地図 で確認しておくと、向き調整の目安がつかみやすくなります。
地デジ電波は単純に電波塔の先端、一般の住宅から見れば、高い位置から飛んでくるだけではありません。
現場の受信環境によっては、さまざま条件の影響を受けて、電波レベルが弱まったり、遮られたり、乱れたりすることもあります。
以下、地デジ電波の強度(レベル)や受信に影響を与える、主な要素を一覧でご紹介しています。
| 影響を与える要因 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 電界地域 | 電波塔の周辺では、電波塔からの距離や山地などの地形によって、受信できる地デジ電波の強さが変わり、主に「強電界」「中電界」「弱電界」の地域に分類されます。特に弱電界地域では、より高性能なアンテナやブースター(増幅器)が必要になる場合があります。 |
| 障害物 | 電波塔とアンテナの間に、高い山やビルなどの大きな障害物があると、障害物の付近では電波が遮られて受信レベルが低下します。この場合は、アンテナの設置場所を高くしたり、障害物を避ける位置に設置したりする工夫が必要です。 |
| 高さ | 住宅における地デジアンテナの設置位置は、屋根の上など高い位置であるほど、周辺の障害物の影響を受けにくくなり、安定した受信につながります。 |
| 天候 | 大雨や大雪などの悪天候時には、電波が水分に吸収されることで、一時的に受信レベルが低下することがあります。また地デジ電波は、年間の気候の影響によって、レベルにある程度の変動が生じます。 |
地デジ電波レベルに影響するこれらの要因を理解しておくことが、安定した地デジ受信への第一歩となります。
BS/CSアンテナを向けるべき方向と受信の注意点は?
BS放送やCS放送は、宇宙空間にある人工衛星から、地球上の広範囲に送信される電波によって、番組データ(映像信号)が送られてくる「衛星放送」です。
衛星放送の人工衛星は、BS放送の放送衛星、CS放送の通信衛星とも、赤道上空、約36,000キロにあたる位置で、地球の自転と同じ速度で動いている「静止衛星」であるため、地上からは常に空の同じ方角にある(静止している)ように見えます。
そのためBS/CSアンテナ(お皿のような形をしたパラボラアンテナ)は、日本国内のどこでも、おおむね「南南西」の上空にある、東経110度の静止衛星の方向へと、アンテナのディッシュ(電波をキャッチする円盤状の放物面反射器)を、仰角(上下)、方位角(左右)とも正確に向ける必要があります。地デジアンテナのように、地域によって電波塔の方向が変わることはありません。
なおBS放送の放送衛星、CS放送の通信衛星とも、同じ東経110度にあるため、一基のBS/CSアンテナで双方を受信できます。ただ日本列島は東西に長く、南北にも幅があるため、向ける方角は同じでも、アンテナを調整すべき角度は、日本各地で微妙な差が出ます。
この衛星放送の電波は、12GHz帯(周波数帯が12GHz(ギガヘルツ)前後)という、地デジのUHFより周波数帯が高く、光のような性質で非常に直進性の強いマイクロ波のSHF(センチメートル波)で、静止衛星から地上の広い範囲に送られてきます。
この電波は、光のように直進する性質から、長距離を送信される衛星放送には適していますが、ちょうど日光がものに遮られると影ができるように、地デジのUHFよりも障害物の影響を受けやすいという特徴があります。
この12GHz帯の電波の性質や、BS/CSアンテナの構造から、安定した衛星放送の受信に影響を与える主な要因は、以下の通りです。
| 影響を与える要因 | 内容と注意点 |
|---|---|
| 障害物 | 静止衛星の方向とBS/CSアンテナの間に山、建物、樹木、電柱、さらには洗濯物など、ささいな障害物があるだけでも12GHz帯の電波は遮断され、衛星放送のテレビ番組は映らなくなります。BS/CSアンテナを設置する際は、南南西の方向に何もない、設置後に障害物ができる可能性も低い、見通しの良い場所を選ぶことが絶対条件です。 |
| 降雨・降雪減衰 | 12GHz帯の電波は、一定以上の大きさ(波長の幅と同じ25ミリ程度)を持つ雨粒や雪に吸収・散乱されやすい性質があります。そのため、大雨や大雪が降ると電波がBS/CSアンテナに届きにくくなり、一時的に受信レベルが低下したり、まったく映らなくなったりすることがあります。これを「降雨減衰」「降雪減衰」と呼びます。 |
BS/CSアンテナのディッシュ角度調整は、地デジアンテナ以上にミリ単位での正確さが求められます。
これは、東経110度の上空から光のように届く12GHz帯の電波を、ディッシュ内側の放物面で反射させて前方の一点に集め、そこに固定されたコンバーター(変換器)の一次放射器で電波を受信するためです。
したがってディッシュ角度のわずかなズレは焦点の位置のスレにつながり、一次放射器で十分に受信できなくなるのです。
そのためBS/CSアンテナのディッシュの大きさは、受信性能にもつながり、さまざまなサイズのBS/CSアンテナが存在します。一般住宅向けは電波をキャッチできる有効直径が45センチの「45型」です。他にも50型、60型、75型、90型、120型などの種類があり、大型モデルは主にマンション、アパートなど集合住宅での共同受信用に使われます。
衛星放送の12GHz帯の電波は、日本全域で大きな受信レベルの差が生じないことも特徴です。ただ日本国内でも北部、南端、離島部などの一部地域では、静止衛星からの距離があることから、減衰により中心部に比べて電波レベルがやや弱まるため、一般住宅でも50型、60型などやや大型のBS/CSアンテナが必要となることもあります。また大型のBS/CSアンテナは、降雨減衰・降雪減衰の対策にもなります。
もしかしてアンテナの向きが原因?まずは症状をセルフチェック
お住まいのテレビで突然、テレビ画面の映りが悪くなった場合、原因は必ずしもひとつではありません。アンテナのトラブルから、電波状態の悪化や電波障害、さらにはケーブル配線やブースターなど機器のトラブルなど。そして室内のアンテナケーブルやテレビ本体のささいな不調、操作ミスなど、ご自宅でも簡単な調整ですぐ解決できるごく単純な原因であることも珍しくありません。
そのため、本格的なテレビアンテナの角度調整作業に入る前に、以下のリストでご自宅のテレビトラブルの症状をチェックし、アンテナの向きが原因である可能性が高いかどうかを確認してください。
| チェック項目 | アンテナの向きが原因の可能性 |
|---|---|
| □ ブロックノイズ(映像が四角いモザイク状になる)が出る | 高い |
| □ 特定のチャンネルだけ映らない、または映りが悪い | 高い |
| □ 天気が良い日は映るが、雨や風の強い日は映りが悪くなる | 高い |
| □ エラーコード「E201」「E202」がテレビ画面に表示される | 高い |
| □ 台風や地震の後から急に映らなくなった | 非常に高い |
| □ すべてのチャンネルがまったく映らない | 中(他の原因も考えられる) |
| □ 映像は映るが音声だけが出ない | 低い(テレビ本体や配線の問題の可能性) |
上記のチェック項目で「高い」または「非常に高い」に当てはまるものが多いほど、アンテナの向きのズレがトラブルの原因である可能性が高まります。
それでは以下の項目で、実際にアンテナの向きを調べる方法を見ていきます。
【準備編】アンテナを調整する前に!正しい向きの調べ方3選
テレビアンテナの向き調整でもっとも重要なのが、ご自宅のアンテナで正面方向を向けるべき「正しい方角(主に近隣の電波塔や静止衛星の方向)」を正確に知ることです。
この方向について、専門的な機材がなくても、誰でも手軽に調べられる方法が3つあります。
以下でそれぞれの方法をご説明いたしますので、ご自宅にてもっとも簡単な方法で、まずはアンテナを向けるターゲットとなる方向を確認してください。
- スマホアプリで簡単チェック【一番おすすめ】
- Webサイト(A-PAB)で電波塔の地図を確認
- ご近所のアンテナの向きを参考にする
方法1:スマホアプリで簡単チェック【一番おすすめ】
多くの方がスマートフォンをお持ちの現在、もっとも手軽で正確な方法が、スマホアプリの活用といえます。
特に以下のアプリは無料で利用でき、直感的な操作で地デジ、BS/CSのアンテナを向けるべき方向を調べられるため、おすすめです。
| アプリ名 | 対応アンテナ | 特徴 |
|---|---|---|
| 地デジアンテナ調整 | 地デジ | GPS機能で現在地からもっとも近い電波塔を自動で検出し、その方向を矢印で示してくれます。AR(拡張現実)機能で、カメラ映像に電波塔の方向を重ねて表示することも可能です。 |
| BSコンパス | BS/CS | 地域を設定すると、BS放送の放送衛星(東経110度・CS放送も同じ)の方向をコンパスで示してくれます。アンテナの仰角(上下の角度)と方位角(左右の角度)も確認でき、非常に便利です。 |
【アプリの基本的な使い方】
android、iOSなど、御使用のスマートフォンのOSにあわせて対応のアプリをダウンロードし、この方角を基準に、アンテナ方向の調整作業を進めていきます。
なおこれらのアプリでは角度調整のかなり正確な方向を指し示してくれますが、各お住まいの現場で最適なアンテナ角度の調整を行うには、アプリの方向を元に細かな微調整も必要になります。
方法2:Webサイト(A-PAB)で電波塔の地図を確認
スマートフォンにアプリをインストールすることに抵抗がある方や、パソコンでじっくり調べたい方には、A-PAB(一般社団法人 放送サービス高度化推進協会)の公式サイトが便利です。
このサイトでは、地デジの電波塔の位置を地図上で確認できます。
【A-PABサイトでの方向の調べ方】
- A-PABの「放送エリアのめやす」ページにアクセスします。
- ご自宅の住所や郵便番号を入力して検索します。
- 地図が表示され、受信可能な電波塔の位置がピンで示されます。
- ご自宅と電波塔の位置関係から、アンテナを向けるべきおおよその方角を把握します。
また、BS/CSアンテナの方角については、インターネット上のサイトに、日本各地の主要都市における角度の目安が掲載されていますので、これらの情報を参考にしてください。またBS/CSアンテナ商品には、本体の角度調整部や付属の一覧表などに、主要エリアの適切な角度の目安が表記されているものもあります。
方法3:ご近所のアンテナの向きを参考にする
もっともシンプルで手軽な方法が、ご近所の家の屋根に設置されているアンテナの向きを参考にすることです。
特に地デジの八木式アンテナは、ほとんどの家が同じ電波塔に向けて設置されているため、有力な手がかりになります。
【近隣のアンテナを参考にする際の注意点】
- あくまで「おおよその目安」として考えてください。
- 建物などの障害物を避けるために、隣家とご自宅で最適な方向が微妙に異なる場合があります。
- BS/CSアンテナは非常に精密な角度調整が必要なため、この方法での完全な調整は困難です。
まずはアプリやWebサイトなどでアンテナを向けるべき正確な方角を調べ、その上で近所のアンテナも参考にすると、より確実性が高まります。
【実践編】地デジアンテナの向きを自分で調整する手順
正しい方角が分かったら、いよいよアンテナの種類別で、角度の調整作業に入ります。
地デジアンテナは、BS/CSアンテナに比べて指向性(電波を受信する角度の鋭さ)が比較的、緩やかなため、安全な条件が整っていれば、ご自身での調整も不可能ではありません。
【作業を始める前の重要準備】
作業効率を上げるために、必ずテレビの「アンテナレベル(受信レベル)」を確認できる画面を表示させておきましょう。
アンテナを動かしながら、この画面の数値が最大になるポイントを探すのが調整の基本です。
アンテナレベルの表示方法はテレビのメーカーによって異なりますので、取扱説明書やメーカー公式サイトなどでご確認ください。
以下、主要メーカーのテレビにおける、アンテナレベル画面の表示方法についてご紹介します。
- Panasonic(VIERA): 「メニュー」→「設定する」→「視聴準備」→「テレビ放送設定」→「アンテナレベル」
- SHARP(AQUOS): 「ホーム」→「設定」→「視聴準備」→「アンテナ設定」→「電源・アンテナレベル設定」
- SONY(BRAVIA): 「ホーム」→「設定」→「放送受信設定」→「アンテナ設定」→「電波テスト」
ここでは、代表的な地デジアンテナ3種類について、それぞれの角度調整方法を解説します。
① 八木式アンテナ(UHFアンテナ)の調整方法
魚の骨のような形で、主に屋根の上に設置されているもっとも古典的、かつ一般的なアンテナが八木式アンテナ(八木アンテナ・八木宇田アンテナ)です。
アナログ放送の時代から使われている古典的なアンテナ機種で、地デジ化後にデザインアンテナなどの新機種が登場するまでは、住宅用のテレビアンテナとしてはほぼ一種類といっていいモデルでした。
基本的に地デジアンテナは地デジのUHF波を受信するため、すべてUHFアンテナになりますが、古典的モデルの八木式アンテナを特にUHFアンテナと称することもあります。
八木式アンテナの前方は、魚の骨のように見える矢印状の骨組みで、矢印の反対側に当たる先端です。八木式アンテナは先端の指向性(受信性能を発揮する範囲)が高い(範囲が狭い)分、電波塔に向けた正確な角度調整で高い受信性能を発揮する半面、わずかな角度のズレで受信レベルが低下しやすいという弱点もあります。
八木式アンテナの特長は、指向性の高さや素子別(受信性能別)モデルの豊富さで本体の受信感度が高く、設置される位置も高いことから、現在でも地デジアンテナ各機種の中では、受信性能がもっとも高いことです。
一方で本体が独特の形状で屋根の上に設置されることから、住宅の見栄えや景観に悪影響を与える、また風雨や雪などの影響を受けて老朽化や角度のズレが生じやすいという弱点もあります。
以下、八木式アンテナの角度調整について、おすすめの度合いや手順などを解説します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 作業の危険度 | 非常に高い |
| DIY推奨度 | 非推奨 |
| 必要な工具 | スパナまたはレンチ、軍手、スマートフォン、安全帯、ヘルメット |
| 調整のポイント | 魚の骨でいう「魚の頭」の反対側(導波器)を電波塔の方向へ向ける。 |
【調整手順】
- 高所にあることが大半の八木式アンテナでは、安全確保を最優先します。屋根の上での作業は転落の危険が伴うため、行う場合には、必ずヘルメットと安全帯などの安全装備を完全に着用し、2人以上で作業を行うことが必要です。
- 八木式アンテナをマスト(支柱、ポール)に固定しているボルトを、スパナやレンチを使って少しだけ緩めます。アンテナが手で動かせる程度で、完全に緩めないように注意します。
- アプリなどで確認した電波塔の方向へ、アンテナの正面を向けます。
- もう一人の作業員にテレビのアンテナレベル画面を確認してもらいながら、アンテナを左右に数度ずつゆっくりと動かします。なお、アンテナ角度を調整してから、受信レベルがアンテナレベル画面に反映されるまでには、数秒程度のタイムラグがあるためご注意ください。
- アンテナレベルの数値がもっとも高くなるポイントを見つけたら、その位置でアンテナが動かないように慎重にボルトを締め直して固定します。アンテナレベルの確認には、後述する簡易的なアンテナレベルチェッカーを利用すれば、角度調整から受信レベルの変化を、アンテナ近くで即座に確認できるため、角度調整を手早く進めることができます。
【重要】
八木式アンテナは屋根の上など高所に設置されていることが多く、ご自身での調整は大変に危険です。
八木式アンテナが屋上のフロア空間やベランダなど、作業の安全が確保できる位置に設置されている場合であればご自身での作業が可能なケースもありますが、屋根の上など少しでも危険性や不安がある場合は、絶対に無理な作業は行わず、プロのアンテナ工事業者に作業を依頼してください。
② デザインアンテナの調整方法
デザインアンテナ(平面アンテナ)とは、地デジ放送がスタートしたあとの2009年(平成21年)ごろに普及した、薄いパネル状の箱型で、主に建物の壁面やベランダの手すりに取り付けられるアンテナです。
カラーバリエーションも豊富で住宅の外観や景観に悪影響を与えにくく、風雨や雪などの影響にも強いため、経年劣化が進みにくく、角度のズレなども生じにくいのが特長です。
またデザインアンテナの正面側はパネル状の前面になり、八木式アンテナより指向性は低くなります。その分やや受信感度は下がりますが、角度の狂いには強くなります。
一方で本体の性能や設置位置の低さから、やや受信感度が低くなり、基本的に強・中電界地域向けモデルになるほか、近隣に高層建築や障害物があるなどの周辺環境によっては、受信感度を確保できず設置できないケースもあります。
以下、デザインアンテナの角度調整をおすすめできるケースや、簡単な手順について解説します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 作業の危険度 | 低い~中程度(設置場所による) |
| DIY推奨度 | 設置場所が安全なら可 |
| 必要な工具 | ドライバーまたはレンチ、軍手、スマートフォン |
| 調整のポイント | アンテナの平面部分を電波塔の方向へ向ける。八木式より指向性はやや緩やか。 |
【調整手順】
- ベランダの手すりや壁面の低い位置など、安全に作業できる場所にあるか確認します。
- アンテナを固定している金具で、アンテナ本体と接続する部分のボルトやネジを、少し緩めます。アンテナの固定方法は、背面中央でポール状の部分への固定や、左右のちょうつがい状の部分での固定など、モデルによって異なります。
- テレビのアンテナレベルを確認しながら、アンテナ本体を、固定部を軸にして左右にゆっくりと動かし、数値が最大になる位置を探します。
- 最適な位置が見つかったら、アンテナが動かないよう固定金具をしっかりと締め付けます。
デザインアンテナは、ベランダの手すりや周辺の壁に設置されている場合、また壁面でも比較的、低い位置に設置されている場合であれば、安全に角度調整の作業を行える場合もあります。
ただ設置位置が屋根に近い高所の場合は、やはり決して無理はせず、業者に依頼してください。
③ユニコーンアンテナの調整方法
ユニコーンアンテナとは、マスプロ電工製「U2CN」というモデルの商品名であり、円柱(ポール)状のスタイリッシュな見た目が特徴の比較的、新しい地デジアンテナです。
基本的な設置位置は八木式アンテナと同様、アンテナ本体が屋根の上に当たるポールの先になります。
その特徴は、スタイリッシュな形状から屋根の上に設置しても住宅の見た目や景観に対する影響が少ないこと。また風雨を受け流せる形状で経年劣化が進みにくく、角度のずれも起こりにくいなど、デザインアンテナと同等のメリットをもっています。
さらにユニコーンアンテナは設置位置が高いことから、デザインアンテナよりも受信感度を確保しやすいという点が最大のメリットになります。そのため受信性能と設置の見た目、耐久性すべてを重視する場合、特に周辺環境からデザインアンテナが対応できない現場で、同等のメリットを確保したい場合におすすめのモデルです。
ユニコーンアンテナの正面側は、ほぼポール状の本体のうち、下部にメーカーや機種のロゴがある側(下部のカバーが開く方向)になります。ユニコーンアンテナはデザインアンテナよりもさらに指向性が低い(受信範囲が広い)ことに加え、風雨などにも強いため、角度の狂いも生じにくくなります。
ユニコーンアンテナのデメリットは、同じ素子数(受信性能)の八木式アンテナに比べるとやや受信感度が低く、設置できるエリアが限られる(主に強・中電界地域)こと。最新モデルであるため、現在の地デジアンテナ機種では設置などの費用が割高になることです。
以下、ユニコーンアンテナの角度調整についてのおすすめ度や、作業の手順について解説します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 作業の危険度 | 高い |
| DIY推奨度 | 非推奨 |
| 必要な工具 | スパナまたはレンチ、軍手、スマートフォン |
| 調整のポイント | ロゴのある面が正面。指向性が広く、比較的ラフな調整でも受信しやすい。 |
【調整手順】
- ユニコーンアンテナが屋上フロアのマストやベランダの付近など、比較的、安全に作業できる場所にあるかを確認します。
- アンテナ下部のカバーを開いて、マストの固定部を確認します。ユニコーンアンテナではマストの先に固定部を通す形で設置されているので、固定部ののボルトを少し緩め、アンテナ本体の向きを左右に動かせるようにします。
- テレビ側のアンテナレベルを確認しながら、アンテナの固定部(ポール)を軸にして、首を左右に動かすような形でゆっくりと調整して、アンテナレベルの数値が最大になる位置を選びます。
- 最適な位置を特定できたら、アンテナが動かないよう固定部のボルトをしっかりと締め込み、下部のカバーも開かないようにきちんと閉じます。
ユニコーンアンテナは、八木式アンテナと同様に屋根の上など高所に設置することで性能を発揮するモデルです。したがって角度の調整手順は八木式アンテナとほぼ同じですが、本体がシンプルな形状で指向性も広いため、角度調整は比較的シビアではなく、作業もやや簡単になります。
しかし、いずれにせよ高所作業になることに変わりはないため、基本的にご自身での角度調整作業は推奨できません。やはり専門業者への依頼が安全です。
⓸室内アンテナの調整方法
室内アンテナは、その名称通り、室内に設置できる小型の地デジアンテナです。
置物や薄いシート状のアンテナ本体を窓際に置く、窓や壁に張るなどして、付属(または本体と一体型)のケーブルでテレビ側の端子と接続するだけで簡単に設置できます。また価格も1,000円台からと非常に安くなっています。
しかしこのような室内アンテナは、屋外に設置されるアンテナに比べると受信性能は非常に低く、基本的に地デジ電波塔に近く、電波レベルが強い強電界地域向けのモデルであり、対応エリアでも周辺環境によっては安定した受信が難しくなる場合もあります。
室内アンテナは指向性も低く、設置する際に角度調整はさほど問題になることもありませんが、室内でも窓際など、地デジ電波が届きやすい位置を選んで、高さや向きなどを調整する必要はあります。
以下、室内アンテナで可能な限り安定した受信を確保するための、設置のポイントについて解説していきます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 作業の危険度 | 非常に低い |
| DIY推奨度 | 推奨 |
| 必要な工具 | なし |
| 調整のポイント | 電波を受信しやすい窓際に置き、向きや高さを変えて最適な場所を探す。 |
【調整手順】
- テレビのアンテナレベル画面を表示させます。
- 室内アンテナをテレビと接続し、電波塔のある方角の窓際に移動させます。
- アンテナ本体の向きを少しずつ変えたり、置く高さを変えたりしながら、アンテナレベルがもっとも高くなる場所と角度を探します。
室内アンテナはもっとも安全で手軽ですが、電波の弱い地域や鉄筋コンクリートの建物では、十分な受信レベルを得られない場合があります。基本的に室内アンテナは、簡易的な地デジアンテナとしての利用がおすすめの商品になります。
【実践編】BS/CSアンテナの向きを自分で調整する手順
衛星放送を受信するためのBS/CSアンテナの調整は、地デジアンテナとはまったく異なる注意が必要になります。
前述の通り静止衛星からの電波は、東経110度上空の位置からまるでビームかスポットライトのように、日本の全域へとまっすぐに飛んできます。そしてBS/CSアンテナでは、この電波をディッシュの内型に反射させ、固定された一次放射器の一点に集める必要があるため、アンテナの向きが1度でもずれてしまうと、一次放射器から電波の焦点がずれてしまい、衛星放送がまったく映らなくなることもあります。
そのためBS/CSアンテナの角度調整は、アンテナを向ける方向の特定はさほど難しくはないものの、ディッシュの「仰角(上下の角度)」と「方位角(左右の角度)」という2つの要素を、ミリ単位で合わせる根気強い作業が求められます。
以下、BS/CSアンテナの角度調整の手順について解説していきます。
① 仰角(上下の角度)と方位角(左右の角度)を知る
まずは、専門用語の意味と、ご自宅における正しい角度を把握します。
BS/CSアンテナの角度調整で重要になるのは、以下のふたつの角度です。
- 仰角(ぎょうかく):ディッシュの上下の角度(お辞儀の角度)
- 方位角(ほういかく):ディッシュの左右の向き。
上記の通り、BS/CSアンテナのディッシュを向ける方向は、日本全域で同じ東経110度の上空ですが、ディッシュを調整すべき正確な角度は、日本国内でも東西南北のエリアによって微妙に異なってきます。
上記した「BSコンパス」などのアプリを使えば、日本の各地域におけるBS/CSアンテナの正確な角度が分かりますが、以下に国内の主要都市における目安を記載します。
| 地域 | 方位角(左右) | 仰角(上下) |
|---|---|---|
| 札幌 | 221.7° | 31.2° |
| 仙台 | 224.0° | 35.3° |
| 東京 | 224.4° | 38.0° |
| 名古屋 | 221.4° | 40.2° |
| 大阪 | 220.0° | 41.4° |
| 広島 | 216.2° | 43.4° |
| 福岡 | 213.9° | 45.2° |
| 那覇 | 215.8° | 53.6° |
※上記は主な地域の解説になります。
BS/CSアンテナの作業を始める前に、インターネット上のサイトなどで、ご自宅がある都市、地域の正しい仰角と方位角をメモしておいてください。
ただインターネットなどで確認できる地域別の仰角、方位角は、おおよその目安になります。実際には現場ごとに微調整も必要となるため、ご注意ください。
② 仰角を合わせ、仮固定する
まずは、BS/CSアンテナの上下の角度(仰角)から合わせます。
- アンテナの取り付け金具の側面を見ると、角度を調整するための目盛りが刻まれています。
- 事前に調べたご自宅の仰角の数値に、目盛りの印を合わせます。
- 角度が合ったら、仰角を固定しているボルトを、レンチを使って軽く締めておきます(仮固定)。この時点では、まだ多少、動く程度で問題ありません。
③ 方位角を合わせ、本固定する
次に、もっとも重要で根気のいる左右の向き(方位角)の調整です。
- テレビのアンテナレベル画面を表示します。
- コンパスやスマホアプリで南南西の方向を確認し、アンテナをおおよそその方向に向けます。
- そこから、アンテナ全体を左右に1ミリずつ、本当にゆっくりと動かしていきます。
- アンテナレベルの数値が反応するポイントを探します。数値が上がり始めたら、さらにゆっくりと動かし、レベルが最大になる一点を見つけ出します。
- レベルが最大になったところで、アンテナが動かないように注意しながら方位角のボルトを締めて本固定します。
- 最後に、仮固定していた仰角の微調整を行います。おおよその仰角から細かな角度調整を行い、同様にアンテナ受信レベルが最大になる一点を確認した上で、仰角のボルトも本締めします。その後、再度アンテナレベルが落ちていないかを確認すれば、BS/CSアンテナの角度調整は完了です。
このBS/CSアンテナの角度調整が難しい要因は、やはり少しの角度調整から、受信レベルがアンテナレベル画面に反映されるまでの数秒のタイムラグになります。特にBS/CSアンテナは仰角、方位角の双方を調整する必要がある上、ミリ単位の角度の違いで受信レベルが大きく変化するため、適切な角度の微調整は根気のいる作業になります。
この作業をスムーズに進めるには、地デジアンテナの場合と同様、アンテナレベルの数値をインジケーターなどで知らせてくれる「BS/CSレベルチェッカー(インジケーター)」という簡易測定器をアンテナケーブルに接続すると、その場で瞬時に電波レベルの変動が確認できるため、非常に便利です。特に細かな調整が必要なBS/CSアンテナでは、より有用性が高まります。
なお、BS/CSアンテナの場合も、お住まいでの角度調整をおすすめできるのは、屋上フロアやベランダなど、作業を安全に進めることができる位置に設置されている場合のみになります。アンテナが屋根の上など、危険を伴う場所にある場合は、専門の業者にお任せください。
【番外編】Wi-Fiの接続が悪い…ルーターのアンテナの向きもチェック!
本コラムをお読みの方の中には、テレビの映りだけでなく、最近Wi-Fiの接続が不安定といったお悩みをお持ちの方もいるかもしれません。
実は、Wi-Fiルーターのアンテナにも最適な向きがあり、これが通信速度や安定性にも大きく影響します。ここでは参考情報として、Wi-Fiの電波についてもご説明いたします。
Wi-Fiの電波は、アンテナに対してドーナツ状に広がっていく特性があります。
アンテナが垂直に立っている場合、電波は水平方向に強く広がります。
そのため、平屋やマンションのワンフロアで使いたい場合は、アンテナを垂直に立てるのが基本です。
もしルーターにアンテナが複数本ある場合は、以下のように向きを工夫すると、より広い範囲に電波を届けることができます。
| アンテナの本数 | おすすめの向き | 狙い |
|---|---|---|
| 2本 | 1本を垂直、もう1本を水平に倒す。 | 2階建ての家など、上下階にも電波を届けやtd>すくなる。 |
| 3本以上 | 垂直、水平、斜め45度など、それぞれ異なる角度に倒す。 | 360度、立体的に電波を飛ばし、家の中の死角を減らす。 |
また、ルーターのアンテナの向きと合わせて、設置場所も以下のように見直してみてください。
- 床から1m~2mの高さに置く。
- 家の中心付近に置く。
- 電子レンジやコードレス電話など、電波を干渉する機器から離す。
- 金属製の棚や水の入った水槽の近くを避ける。
これらのポイントを試すだけで、Wi-Fi環境が劇的に改善する可能性があります。
自分でアンテナの向きを調整する際の5つの注意点【安全第一】
ご自身でテレビアンテナの向きを調整する際は、思わぬ事故やトラブルを防ぐために、以下の5つの点に必ず注意してください。
特に屋根の上など高所での作業は、慣れていない方にとっては非常な危険が伴います。
「これくらい大丈夫だろう」という油断が、大きな事故につながります。
注意点1:高所作業は絶対に一人で行わない
屋根の上や2階のベランダの柵の外側など、足場が不安定な場所での作業は、転落のリスクが常に伴います。
脚立が倒れたり、バランスを崩したりした際に、一人では対処できません。
【必ず守ること】
- 作業は必ず2人以上で行う。
- 一人は脚立を支えたり、下から指示を出したりする役に徹する。
- 万が一の事態に備え、すぐに助けを呼べる体制を整える。
基本的に、アンテナ工事における高所作業をDIYで行うことは決して推奨されません。
少しでも身の危険を感じる場合は、作業を中止する、または最初からご自分での作業は選ばず、業者にご依頼になる勇気を持ってください。
注意点2:悪天候の日(雨・強風)は作業を避ける
突然のテレビ画面トラブルで、アンテナの角度を調整すれば治る見込みがある場合、早急に直してすぐにテレビを見たいと思われる気持ちは分かりますが、天候が悪い日の作業は絶対にやめてください。
予想はつくかと思いますが、理由は以下の通りです。
- 雨の日:屋根や脚立が濡れて滑りやすくなり、転倒・転落の危険性が増します。また、工具も滑りやすくなり、アンテナや家屋を傷つける原因にもなります。
- 風の強い日:強風に煽られて作業される方がバランスを崩したり、工具やアンテナ本体が落下したりする危険が高くなります。
他にも雨などの悪天候ではテレビ電波レベルが低下し、角度調整を行っても適切な受信レベルが確保できず、正確な調整ができないという危険性も想定されます。
アンテナ角度調整の作業は必ず、よく晴れた風のない日に行うように計画してください。
注意点3:必要な道具を事前に準備する
作業を始めてから「あれがない、これがない」と脚立を何度も上り下りするのは、非効率なだけでなく、作業の中断や混乱による事故のリスクも高めます。
作業をはじめる前に、必要な道具がすべて揃っているか確認しましょう。
以下、必要な道具の一覧です。
| 準備物リスト | 用途・目的 |
|---|---|
| スパナ、レンチ、ドライバー | アンテナを固定しているボルトやネジを緩めたり締めたりする |
| 軍手 | 手の保護、滑り止め |
| スマートフォン | 方角確認アプリの使用、業者への連絡 |
| テレビのリモコン | アンテナレベルの表示 |
| 安全帯、ヘルメット(高所作業時) | 転落時の安全確保 |
| BS/CSチェッカー(任意) | BS/CSアンテナ調整の効率化 |
※以上は主な道具になります。
また作業の途中に、道具をどこに置いたか忘れてしまい、混乱から事故などにつながるケースもあるため、作業中にもそれぞれの道具を置く、入れておく場所をきちんと決めておくことがおすすめです、
注意点4:アンテナやケーブルを破損させない
アンテナ角度の調整作業に夢中になるあまり、作業時に力を入れすぎてしまうことがあります。
ボルトを強く締めすぎると、アンテナ本体のプラスチック部分が割れたり、マストが変形したりする可能性があります。またボルトそのものやボルト穴の破損により、以降の角度調整や固定が難しくなることも考えられます。
また、アンテナに接続されている同軸ケーブルを無理に引っ張ったり、踏みつけたりすると、接続部の破損や内部での断線が生じてしまい、角度の狂いとは別のトラブルにより、症状が悪化することもあります。
すべての作業は、慎重に、丁寧に行うことを心がけてください。
注意点5:アンテナの「指向性」を理解する
アンテナには「指向性(しこうせい)」という性質があります。
これは「アンテナが正面方向のピンポイント(一定の範囲内)で電波をキャッチできる」という性能のことです。
特に地デジアンテナの場合、同じ素子数・素子数相当(受信性能)のアンテナ機種でも、指向性が高い(受信範囲の狭い)アンテナほど、範囲内の受信感度が高まり、ノイズも受信しにくくなるため、受信性能が高くなります。
以下、指向性別のアンテナについて簡単にご紹介します。
- 指向性が鋭い(強い)アンテナ:八木式アンテナ、BS/CSアンテナなど。特定の方向からの電波を強力に受信できますが、向きのズレに非常に敏感です。
- 指向性が緩やか(広い)アンテナ:デザインアンテナ、ユニコーンアンテナ、室内アンテナなど。比較的広い範囲の電波を拾えるため、向きの調整はややラフでも問題ない場合があります。
この指向性という特性を理解しておくと、八木式やBS/CSアンテナの調整がいかにシビアで、デザインアンテナの調整が比較的容易であるかについても理解できます。
向きを調整しても映らない…考えられる他の原因と対処法
テレビアンテナの向きを完璧に調整したはずなのに、テレビの映りが改善しないという場合は、向き以外の場所に原因が隠れている可能性があります。
以下のポイントを確認し、トラブルシューティングを進めてください。
| 考えられる原因 | 確認方法と対処法 |
|---|---|
| アンテナケーブルの問題 | テレビ側、壁側、ブースター側の接続が緩んでいないか確認。ケーブルの途中が折れ曲がっていないか、屋外部分は劣化していないか目視で確認。問題があればきちんと再接続、またはケーブルを交換する。 |
| ブースターの不具合 | アンテナの近くや屋根裏に設置されているブースター(電波の増幅器)の電源部(コンセントに繋がっている部分)のランプが消えていないか確認。抜けていれば差し直す。故障が疑われる場合は交換が必要。 |
| テレビ本体の設定 | 向き調整で受信環境が変わった可能性があるため、テレビのリモコンで「チャンネルの再スキャン(再設定)」を行う。またB-CASカードの問題がないかなども確認。テレビの電源を切り、コンセントを抜いてしばらく置く「リセット(再起動)」も有効。 |
| 周辺環境の変化 | 自宅と電波塔の間に、新しい高層マンションが建ったり、樹木が大きく成長したりしていないか確認。このような電波の遮蔽物が原因の場合、アンテナの設置場所変更や高性能アンテナへの交換が必要になる場合もある。 |
| 5G電波との干渉 | 近所に携帯電話の基地局ができた場合、5G電波がテレビ電波に干渉している可能性がある。対策として、アンテナとテレビの間に「5G対策フィルター」を取り付ける。 |
※以上は考えられる主な要因になります。
以下、各要因とその対策について、詳しく解説していきます。
原因1:アンテナケーブルの接続不良・劣化・断線
意外と見落としがちなのが、アンテナとテレビをつなぐ「同軸ケーブル(アンテナケーブル)」の問題です。
まずは、テレビの裏や壁のアンテナ端子に接続されているケーブルが、しっかりと奥まで差し込まれているか、緩んでいないかなどを確認してください。
またケーブルが強く折り曲げられている、家具などの下敷きになっている、必要な長さより極端に長すぎる場合なども、電波の送信の不具合や減衰、ケーブルの破損などにつながります。ケーブルの状態を確認して、問題がある場合は正常な使い方をするか、場合によってはケーブルを交換してください。
送信されるテレビ電波は、地デジ、2K衛星放送、4K8K衛星放送の順で周波数帯が高くなっていくため、ケーブルをはじめとした配線部のシステム機器も、その周波数帯に対応できる機器が必要となります。ケーブルなどが対応していない場合、BS放送やCS放送、特に4K8K放送の映像に乱れが出る場合もあります。
またケーブル配線でも屋外に配線されている部分は、長年の紫外線や雨風で劣化し、ひび割れや断線が起きていることもあります。
屋外ケーブルの見た目に異常がある、屋内でケーブルを交換してもトラブルが直らないなどの場合は、プロによるケーブルなどの点検が必要です。
原因2:ブースター(増幅器)の不具合・電源オフ
戸建て住宅でも、受信できる地デジ電波レベルが弱い地域や、複数の部屋で3台以上のテレビを見る場合には、十分な電波レベルを確保するために、アンテナの近くに受信した電波を増幅する「ブースター(増幅器)」と呼ばれる機器を設置しているご家庭も多くなっています。
このブースターが正常に作動していないと、その住宅で必要なレベルの電波を保持できないため、テレビ放送が正常に映らなくなります。
基本的に設置される屋外用ブースターは、アンテナ本体の近くで配線に設置される「増幅部」と、
屋根裏などの屋内配線部でコンセントに接続され、ケーブルを通じて
bsアンテナ 電源供給
を行う「電源部」の2つで構成されています。
まずは、お住まい内の電源部でパイロットランプが点灯しているか確認してください。
もし消えていたら、コンセントが抜けているか、故障している可能性があります。
他にも、本体である増幅部の故障や寿命、調整レベルの不調なども考えられますが、ブースター増幅部の確認や調整、交換などは専門知識が必要な上、高所作業になるケースも多いため、アンテナ工事の専門業者へとお任せになることを推奨いたします。
原因3:テレビ本体のチャンネル再スキャンが必要
アンテナの向きを調整したことで、電波塔から地デジ電波として受信できるチャンネルの情報、周波数帯などが、調整の以前と変わっている場合があります。
受信するテレビ側でその変化を認識できていないと、映るはずのチャンネルが映らなくなる場合もあります。
この場合は、テレビのリモコンを操作して「チャンネル設定」や「チャンネルスキャン」といった項目から、チャンネルの再設定を行ってください。
テレビが自動的に、受信している地デジ電波のチャンネルスキャン(チャンネルを確認して番号に当てはめる作業)を行い、数分程度で完了した後は、正常に映るようになることがあります。
またテレビ画面に「E100」「E101」「E102」などのエラーコードが表示される場合は、テレビ機器に挿入されているB-CASカード、またはACASチップの不具合が考えられます。
この場合はB-CASカードをテレビ本体からいったん取り外し、乾いた柔らかい布でICチップ部分を中心に優しく拭いて汚れを落とし、あらためて挿入し直すと、映りが改善することが多くなります。ただB-CASカードそのものの不具合の場合は、カードの交換が必要です。
テレビ本体に内蔵されるACASチップの不具合、その他、内部基盤やソフトウェアなどテレビ本体に問題が生じている場合は、いったんテレビの主電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いた状態で数分おき、ふたたびプラグを差して電源を入れる「リセット(再起動)」が有効なケースもあります。
なお、テレビやレコーダーなどの機器によっては、電源ボタンの長押しなど専用のリセット方法があるモデルもあるため、正確なリセットの方法は、本体付属のマニュアルやメーカー公式サイトなどで確認してください。
原因4:周辺環境の変化(建物の新築・樹木の成長)
それまで問題なくテレビ放送を視聴できていたのに、ある時期から急にテレビの映りが悪くなったという場合、電波を遮る障害物の発生など、周辺環境の変化が原因かもしれません。
具体的には、以下のような例が考えられます。
- 新しい建物の建設:自宅と電波塔、または静止衛星との間に高層マンションなどが建つ、また設置位置が低いデザインアンテナでは、すぐ前に家が建てられるなどすると、テレビ電波が遮られてしまいます。
- 樹木の成長:庭の木や近所の山の木などが大きく成長し、その枝葉がテレビ電波を遮るケースもあります。
この現象は、電波の通り道である「フレネルゾーン」が侵害されることで起こります。
地デジ電波のUHFの場合、ビルなどの障害物で電波が遮られても、乗り越えて広がる性質があるため、影響を受けるのは建物など直近の一帯のみになります。
ただ直進性の高い衛星放送の電波(12GHz帯)は、樹木や洗濯物などのわずかな障害物にも遮られてしまい、その向こう側では遮断されるため、BS/CSアンテナ設置の際には、アンテナの角度調整はもちろん、アンテナを向ける方向にわずかな遮蔽物もないことを確認することが重要です。
いずれにせよこのような遮蔽物の影響では、お住まいの庭木などの場合を除いて、障害物の撤去など個人での対処は難しく、アンテナの設置場所をより高い位置に変更するか、障害物に強い高性能なアンテナへ交換するなどの対策が必要になります。
原因5:5G電波との干渉
近年、スマートフォンの5Gサービスが普及したことで、新たなテレビの受信障害が報告されています。
これは、5Gで使われる電波の周波数帯の一部が、テレビ(特にBS放送)で使われる電波の周波数帯と近いため、互いに干渉してしまうという現象です。
ご自宅の近くに携帯電話の基地局がある場合、この干渉が原因の可能性があります。
対策としては、5Gの電波だけをカットする「5G対策フィルター」をアンテナとテレビの間に設置する方法が有効です。
自分でやるのは難しい…プロの業者に依頼すべきケースと費用相場
ここまでの項目では、ご自身でもできるアンテナ角度調整などの対処法を紹介してきましたが、要所で何度かご説明した通り、すべての問題をDIYで解決できるわけではありません。
お住まいのアンテナ設置位置などによっては、作業の危険性や専門性を考えると、無理をせずプロのアンテナ工事業者に依頼する方が、結果的に安全・確実・スピーディーな解決につながるケースも多々あります。
特にBS/CSアンテナの設置や交換をご検討中の方は、
BSアンテナ 設置の費用相場と業者選びの完全ガイド
もあわせてご覧いただくと、具体的な金額感や依頼の流れがイメージしやすくなります。
お住まいのアンテナ設置位置などによっては、作業の危険性や専門性を考えると、無理をせずプロのアンテナ工事業者に依頼する方が、結果的に安全・確実・スピーディーな解決につながるケースも多々あります。
以下の項目では、プロの業者に任せるべき条件や、料金の相場、業者の選び方について概要を解説します。
プロに任せた方が良いケースとは?
以下のような状況に当てはまる場合は、迷わず専門業者への相談を検討してください。
- アンテナが屋根の上など、高所で危険な場所に設置されている。
- 屋根が急勾配である、または老朽化していて不安がある。
- 3階建ての戸建てなど、作業に長いハシゴが必要になる。
- アンテナの向き以外の原因(ブースター故障、ケーブル断線など)が疑われる。
- 原因がどうしても特定できない。
- アンテナ本体が古く、交換が必要かと思われる。
危険が伴う条件での無理なDIY作業は、転落事故につながるだけでなく、作業のミスでアンテナや家屋を破損させてしまい、かえって修理費用が高くつくというリスクも高くなります。
少しでも作業が難しいと思われる場合は、アンテナ工事業者へのご依頼を強くおすすめいたします。
アンテナの向き調整を業者に頼んだ場合の料金相場
アンテナの向き調整などの作業を専門業者に依頼する際、お客様がもっとも気になる点といえば、やはりテレビアンテナ修理、角度調整などの工事費用ではないでしょうか。
アンテナの向き調整やその他トラブル修復のための工事は、作業内容によっても料金は変動しますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 作業内容 | 費用相場(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| アンテナの方向調整のみ | 5,000円 ~ 15,000円 | 最も基本的な作業。出張費が含まれているか要確認。 |
| 高所作業費 | 3,000円 ~ 10,000円 | 2階の屋根以上での作業の場合に加算されることが多い。 |
| ブースターの調整・交換 | 15,000円 ~ 30,000円 | 部品代+作業費。 |
| アンテナ本体の交換 | 25,000円 ~ 50,000円 | アンテナの種類や設置場所によって大きく変動。 |
これらはあくまで目安であり、正確な料金は必ず事前に見積もりを取って確認することが重要です。
複数の業者から「相見積もり」を取り、料金とサービス内容を比較検討することをおすすめします。
失敗しないアンテナ工事業者の選び方3つのポイント
安心して任せられる業者を選ぶためには、いくつかのポイントがあります。
業者をお選びの際は、以下の3点についてチェックしてみてください。
- 料金体系が明確で、見積もり後の追加請求がないか
公式サイトに料金が明記されており、見積もり時に作業内容と総額の詳細、また見積もり外の料金が発生する可能性についても、丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。「作業後に追加費用を請求された」といったトラブルを避けるためです。 - 施工実績が豊富で、口コミ評判が良いか
年間の施工件数が多い業者は、それだけ経験とノウハウが豊富です。また、Googleマップの口コミや比較サイトなどで、実際に利用した人の率直な評価を確認するのも有効です。 - 長期保証などアフターサービスが充実しているか
施工後のトラブルに備え、長期の保証制度を設けている業者は信頼できます。例えば、当あさひアンテナでは、施工に対して10年間の長期保証をお付けしており、万が一の不具合にも迅速に対応します。
まとめ:アンテナの向きを正して快適なテレビ・ネット環境を取り戻そう
お住まいで急にテレビの映りが悪くなると不安になることでしょうが、意外と簡単な原因から、単純なアンテナの向きのズレなどが原因であるケースも多く、場合によってはご自身で比較的、解決できる可能性もあります。
この記事内で解説した手順を、最後にもう一度おさらいしていきます。
- 症状の確認:まずはテレビ画面の不具合の症状から、アンテナの向きが原因の可能性が高いかどうかをセルフチェックします。
- 正しい向きを調査:スマホアプリやWebサイトなどを使い、アンテナが向くべき正しい方角を正確に把握します。
- 安全に調整:アンテナの種類に合った方法で、安全を最優先しながら調整作業を行います。高所作業など危険が伴う場合は絶対に無理な作業はしません。
- 他の原因を探る:向きを直しても改善しない場合は、ケーブルやブースター、テレビ本体の設定など、他の原因を疑います。
- プロに相談:DIYでの解決が難しい、または危険が伴う、原因が不明だと判断した場合は、迷わず信頼できる専門業者に相談します。
アンテナの向きという、ほんの少しのズレを正すだけでも、毎日のテレビ視聴やインターネット利用のストレスから解放されるケースがあります。
この記事の情報が、皆様の快適なテレビ視聴環境を取り戻すための一助となれば幸いです。
なお、当あさひアンテナでは、お住まいのアンテナ受信トラブルに対して、ご一報いただければ、アンテナの角度調整については8,000円(税込み8,800円)から。軽微な故障に対する修理は5,000円(5,500円)からでお引き受けしております。
原因がよくわからないテレビの受信トラブルについては、弊社のフリーダイヤル、またはメールフォーム、LINEアカウントまでお問い合わせいただければ、迅速にご対応いたします。
特にお電話であれば、アンテナ職人と同等の知識を持つ弊社のオペレーターが、ご自宅の症状をお伺いし、推測できる原因とお住まいでの対処法をご説明いたします。もしお電話のみで問題を解決できた場合には、料金は一文たりとも頂戴いたしません。
他にも、アンテナが老朽化で寿命を迎えている場合の、交換に伴う撤去および処分作業は5,000円(5,500円)からで承ります。各種アンテナ新規設置(交換)についても、地デジアンテナの八木式アンテナ、デザインアンテナであれば、国産大手メーカーの高品質アンテナ機器、設置具、同軸ケーブルの費用もセットで、22,000円(税込み24,200円)からの基本設置工事費用でご対応しております。
BS/CSアンテナやユニコーンアンテナ、また各アンテナの高性能、抗耐候モデルなど、さまざまな機器もご用意しているほか、もちろんブースターや分配器などシステム機器の設置、交換、修理などにも、明確な価格体系の低価格でご対応いたします。
アンテナ設置などの工事に伴う電波調査、お見積もりは、出張料やキャンセル料など含めた完全無料で実施いたします。また相見積もりはもちろん、工事をお急ぎの場合には、即日工事にもご対応しております。
弊社では自社スタッフによる完全自社施工の徹底により、練達のアンテナ職人による業界トップクラスの高品質な工事を、コストを抑えた業界最安に挑むお見積もり価格でご提案いたします。工事費用のお支払いはクレジットカードや電子マネーにもご対応しているほか、上記の通り、工事後には業界最長クラスの10年保証もご用意しているため、お客様には無用のお手間をおかけせず、工事後も末永いご安心をお約束いたします。
急な受信トラブル、アンテナ角度のズレなどに対する対応をはじめ、アンテナ工事に関するあらゆるご相談は、まずは当あさひアンテナまでお問い合わせ頂ければ幸いです。
アンテナ向き調整のよくある質問(FAQ)
Q1. マンションやアパートの場合、自分でアンテナを調整してもいいですか?
A1. この点については、お住まいの物件のアンテナ設備によって異なります。
- ご自身のベランダにBS/CSアンテナを設置している場合:
これは専有部分にあたるため、ご自身で向きを調整しても問題ないケースがほとんどです。ただし、作業の際は、階下へ物を落とさないよう安全に十分な配慮をしてください。 - 建物全体で共用のアンテナ(地デジ・BS/CS)を利用している場合:
屋上などに設置されている共用アンテナは、個人の所有物ではありません。絶対に触らず、まずはマンションの管理会社や大家さんに連絡して、テレビの映りが悪い旨をご相談ください。
どちらの場合も、念のため賃貸契約書や管理規約を確認することをおすすめいたします。
Q2. アンテナレベルの目安はどれくらいですか?
A2. アンテナレベルの最適な数値は、テレビのメーカーやお住まいの地域の電波の強さによって異なりますが、一般的には以下の数値が安定して視聴できる電波レベルやアンテナレベル画面上の目安とされています。
| 放送の種類 | 受信レベルの目安(dBμV) | テレビ画面での表示目安 |
|---|---|---|
| 地デジ放送 | 60 dBμV 以上 | メーカーによるが、目盛りの半分~緑色ゾーンの最大値 |
| BS/CS放送 | 50 dBμV 以上 | メーカーによるが、目盛りの半分~緑色ゾーンの最大値 |
ここで重要になるのは、単にアンテナレベルの数値(電波の強さ)を高くするだけでなく「電波の品質(MER、BER)」も良好な状態にすることです。
アンテナレベルの数値が最大で、かつ電波の品質が安定しているポイントを探すことが理想といえます。
ただ電波の品質については、一般の方では判断が難しくなるため、当あさひアンテナなどアンテナ工事の専門業者にご依頼になることをおすすめいたします。