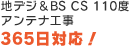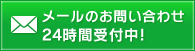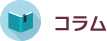テレビアンテナの古典・八木アンテナ(八木式アンテナ)とは?原理や構造から自作方法まで徹底解説:発明の歴史と技術の粋に迫る
「テレビのアンテナ」または単に「アンテナ」と言えば、皆様はどのようなものを連想されるでしょうか?
大きな皿のような形をした、主に衛星放送や宇宙観測に使われるパラボラアンテナ。また近年のテレビアンテナでは、壁に貼り付けるように設置できる薄型や、ポールのような形のアンテナも登場しています。ただそれでも一般的に、特にテレビのアンテナといえば、住宅の屋根の上で、マスト(ポール、支柱)の先に設置されている、骨組みに短い横棒がついた魚の骨みたいなアンテナ、というイメージを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
このような形のアンテナは、一般に「八木アンテナ(八木式アンテナ)」と呼ばれるもので、昭和のアナログ放送の時代から、地上デジタル放送が定着した2025年(令和7年)現在まで、テレビアンテナとして現役で使われているアンテナになります。そのため日本の幅広い世代において、アンテナと言えば八木アンテナのイメージが根強くなっています。
昭和の時代から使われているこの八木アンテナ、実は1920年代の大正時代に、当時の東北帝国大学教授、八木秀次博士と宇田新太郎博士という二人の日本人研究者によって開発された、長い歴史を持つ世界的な発明品なのです。
発明から約100年が経過した今でも、その優れた基本設計は変わらず、世界中のテレビ放送や無線通信などを支え続けています。
今回の記事では、この古くて新しい八木アンテナが持つ、技術の核心に迫ります。
その巧妙な仕組みや動作原理、知的好奇心をくすぐる歴史的背景、さらには自分で作るための設計方法など、八木アンテナそのものに関する知識や関連情報。
次に現代の地デジ用テレビアンテナとして八木アンテナを設置する際の、さまざまなモデルや設置方法の選び方、優良な業者への依頼方法など重要なポイントまで、専門家でなくても理解できるよう徹底的に解説していきます。
この記事をお読みいただければ、皆様の八木アンテナに関する「知りたい」ご要望が、きっと満たされることでしょう。
八木アンテナの仕組みと動作原理【図解】なぜ「魚の骨」の形で電波を捉えるのか?
現在の八木アンテナといえば、支柱にいくつもの横棒がついた、独特な「魚の骨」のような形状で知られています。この奇妙な形状には、電波を効率的にキャッチする(もしくは送信する)ための、極めて合理的な理由が隠されています。
このアンテナの構造は、ただの棒の集まりではありません。
八木アンテナは「放射器」「反射器」「導波器」という、それぞれが異なる役割を持つ3種類の主要な部分で構成されています。
これらのエレメントが精密に配置されることで、特定の方向(アンテナの正面側)から届く電波だけを強力に捉え、それ以外の方向からの不要な電波(ノイズ)を遮断するのです。
ここでは、上記それぞれのパーツがどのように連携し、アンテナとして優れた性能を発揮するのか、その仕組みを詳しく見ていきます。
アンテナを構成する3つの主役:放射器・反射器・導波器の役割
当コラム記事では、基本的にテレビアンテナについてご説明していることもあり、アンテナと言えば、電波をキャッチする機器というイメージがあるでしょうが、実際にはアンテナは電波(電磁波)を空間に発信する、または空間の電磁波をキャッチする電気回路をいいます。
そして八木アンテナの性能は、3種類の主要なパーツが互いに影響し合うことで生まれます。
それぞれの役割を正確に理解することが、八木アンテナの仕組みを理解する第一歩です。
現在の地デジ用テレビアンテナ(UHFアンテナ)としての八木アンテナは、中心の長い横棒の一方側にのみ、「く」の字をした魚の頭、または矢印の先端のような支柱があります。この全体に短い横棒がいくつもついているほか、長い横棒でも矢印側の端に、黒い小さな箱と横棒が一体化して、ケーブルがつながっている部品もあります。
この横棒、魚の頭、黒い箱の各部分が、上記したそれぞれの重要なパーツになります。ちなみにいくつもある短い横棒は、電波を集める「素子(そし)」と呼ばれる部品です。
まず長い横棒の部分が、電波をキャッチして送る役割を持つ「導波器(ディレクター)」という部分です。魚の頭とは反対側の何もない先端が、アンテナの正面に当たり、この方向で電波をキャッチし(または送り出し)ます。
そして導波器の中で、先端とは反対側の端に設置されている、素子と黒い箱が一体化した部分が、八木アンテナでも中心的な役割を果たす「放射器(ラジエーター)」です。この放射器は「輻射器(ふくしゃき)」とも呼ばれ、キャッチした電波を集める、または送信する電波のエネルギーを送り出す役割の部分で、黒い箱の部分はケーブルで電気エネルギーを送る「給電部(きゅうでんぶ)」という部分になります。
ケーブルを通じてテレビや無線機に接続されるこの放射器の部分が、外界と電波の世界との窓口となります。
放射器を覆う傘のように取り付けられている魚の頭の部分は「反射器(リフレクター)」といい、導波器とは他の方向からくる余計な電波(ノイズ)を反射させてカットすると同時に、放射器に集まる電波が漏れたときに、放射器側に反射させることで効率を高める役割を果たしています。
各部分の役割を、下の表にまとめました。
簡単にご説明すれば、導波器が電波を集め、放射器がそれを受け取り、反射器が余計な電波をカットすると同時に、電波の取りこぼしを防ぐ、というチームプレーで、八木アンテナは動作しているのです。
指向性と利得のメカニズム:電波を一点に集中させる技術の核心
八木アンテナが特定の方向の電波に強い理由は、「指向性」と「利得」という2つの重要な性能にあります。
指向性とは、狙った方向の電波だけを選んで送受信する能力のことです。
地デジアンテナの場合は、アンテナの正面側で受信性能を発揮する範囲の狭さ(狭いほど指向性が高い)を示し、アンテナごとに半値幅(もっとも受信性能が高い正面角度を基準に、アンテナ角度を左右にずらせて受信感度が正面の半分になる角度を示す数値)で表されます。
この指向性が高い(半値幅が狭い)アンテナほど、同じ受信性能(素子数・素子数相当)でも受信性能が狭い範囲に集中する形になり、受信効率(後述する利得)が高くなるため、実質的な受信感度が高くなります。
地デジアンテナの場合は、指向性の高いアンテナの正面を、目的の電波塔の方向へと正確に向けることにより、その方向からの電波のみを強くキャッチし、それ以外の方向から来るノイズの影響を受けにくくなり、受信できる電波の品質が高くなるのです。
利得(ゲイン)とは、アンテナが特定の方向に電波をどれだけ強く受信・放射できるかを表す指標です。
八木アンテナでは、導波器と反射器が、まるでレンズと反射板のように働くことで、放射器が受け取る電波のエネルギーを強めています。
この仕組みの核心は、各エレメントに誘導される電流の「位相」のズレにあります。
目的の方向(アンテナの正面側)から来た電波は、各エレメントで位相がそろうように誘導電流が発生し、互いに強め合います。
一方で、他の方向から来た電波は位相がずれてしまい、互いに打ち消し合います。
この巧妙な干渉の原理により、八木アンテナは驚くほど高い指向性と利得を実現しているのです。
総じて地デジアンテナとしての八木アンテナは、アンテナの向きを電波塔の方向へと正確に向けることで、もっとも受信感度が高く安定した受信を実現できるアンテナ機種と言えます。一方で老朽化などによる角度のズレで、受信感度が低下しやすくなる弱点も生じます。
技術者の探究心に応える!八木アンテナの設計と自作(DIY)ガイド
八木アンテナの魅力のひとつは、画期的な発明でありながら、基本的な構造は非常にシンプルなため、原理を理解すれば自作(DIY)も可能である点にあります。
ここでは、八木アンテナを「作る」だけでなく、実際の使い方(どこに向けるか・どんな場面で性能を発揮するか)も合わせて分かるように整理していきます。
特に職業が技術系の方や、電子工作、アマチュア無線などを趣味とされている方にとっては、自分の手でアンテナを作り上げ、精密に性能を追求していく過程は、それ自体が大きな楽しみでもあるでしょう。
この項目では、理論的な知識を実践に移したいと考える方のために、八木アンテナの設計や自作方法について、より専門的で具体的な情報を提供します。
少し難しい話になりますが、アンテナの性能を決定づけるエレメント長の計算方法から、性能を最大限に引き出すための「インピーダンス整合」という重要な技術まで、自作に挑戦するためのノウハウについて、主要なポイントを解説していきます。
【実践】基本の設計計算式とエレメント長の決め方
八木アンテナの設計は、目標とする電波、電磁波の周波数(f)に基づいて各エレメント(素子)の長さを計算することから始まります。
基本となるのは、電波の波長(λ)の長さです。
まずは、光の速さ(約300,000,000 m/s)と周波数から波長を求めます。
しかし実際のアンテナ設計では、電波が金属線上を伝わる速度が、真空中より少し遅くなる「短縮率」を考慮する必要があるため、より実用的な計算式が用いられます。
以下に、テレビ放送(UHF帯)の電波などでよく使われる、基本的な設計の計算式を示します。
{放射器の長さ (m)} \approx \frac{143}{f {MHz}}
この放射器(放射素子)の長さを基準に、反射器と導波器の素子の長さを決定します。
一般的に、反射器の素子は放射器より約5パーセント長く、導波器の素子は放射器より約5パーセント短く設計されます。
また、エレメント同士の間隔も性能を左右する重要な要素です。
一般的に、放射器と反射器の間隔は0.15λから0.25λ、放射器と導波器の間隔は0.1λから0.2λ程度が目安とされています。
これらの数値を基に、最適な性能を求めて細かな調整を加えていくことが、アンテナを自作する醍醐味ともいえます。
なお、周波数帯に対する導波器、放射器、反射器の各エレメントの長さなどの細かな計算方法については、自動的に割り出してくれるサイトやアプリなどもありますので、八木アンテナの自作に当たってそれらをご利用になることも、ひとつの方法です。
性能を左右する「インピーダンス整合」とは?バランとガンママッチの役割
精密にエレメントを設計しても、それだけではアンテナの性能を100パーセント引き出すことはできません。
最後の重要な仕上げとなるのが「インピーダンス整合」です。
インピーダンスとは、交流電気における抵抗のようなもので、アンテナと、それに接続する同軸ケーブルや受信機がそれぞれ固有の値を持っています。
このインピーダンスの値が異なると、電力(伝わっていく電波)がスムーズに伝わらず、一部が反射してしまいます。
これにより、せっかく受信した電波が損失してしまい、性能が大きく低下するのです。
このインピーダンスのミスマッチを解消し、効率的に電力を伝送するために使われるのが以下のような整合回路です。
自作アンテナに挑戦する際は、これらの整合技術を適切に用いることで、理論通りの高い性能を実現することができます。
八木アンテナにまつわる歴史と逸話|戦争利用から「呪い」の真相まで
現在の八木アンテナには、単なる工業製品の枠に収まらない、さまざまな逸話が存在します。
一世紀に渡る長い歴史をもつアンテナだけに、その誕生から今日に至るまでには、発明者の苦悩、戦争の悲劇、そしてさまざまな都市伝説に至るまで、多くの興味深い物語が刻まれています。
技術的な側面だけでなく、このような歴史や逸話を知ることで、昔ながらの屋根の上の「魚の骨」がまた違った姿にも見えてくるはずです。
この項目では、八木アンテナが辿ってきた歴史的な物語をいくつかご紹介いたきます。
なぜ日本初の偉大な発明が、皮肉にも他国で先に評価され、利用されることになったのか。
発明者が設立した企業は今どうなっているのか。
そして、まことしやかに語られる「八木アンテナの呪い」とは一体何であるのか、その真相に迫ります。
敵国に利用された悲劇の発明:第二次世界大戦とレーダー技術
上記の通り、現代の八木アンテナは、今から約100年前に、東北帝国大学(現・東北大学)工学部にて、八木秀次博士、宇田新太郎博士の共同研究によって開発されたものです。
詳しくは、1924年(大正13年)に、八木博士が実験中にその基本原理を発見し、1925年(大正14年)には、八木博士の指導の下、当時は大学院生だった宇田博士が実用化を目指し、主導的な研究を進めました。また同年12月には、八木博士がアンテナ原理の特許を出願しています。現在でも八木アンテナが、主に八木博士の名前のみを冠した名称で呼ばれるのは、これが大きな理由です。
その後、第二次世界大戦が勃発しますが、日本では八木アンテナが重要な発明と見なされず、軍部でもほとんど知られていなかったのに対し、敵国となったイギリスやアメリカでは、八木アンテナの優れた指向性を利用して、レーダーの性能を格段に進歩させ、航空機や艦船を探知する能力を飛躍的に向上させました。これにより、欧米は当時の日本軍に大打撃を与えています。
実際の逸話として、シンガポール攻略作戦の際、日本軍は入手した英国軍のレーダー資料の中にある「YAGI(八木)」の意味がわからず、捕虜の英国人に質問したところ「そのアンテナを発明した日本人の名前だ」と教えられ、驚嘆したという話が残っています。
ただこの件に関しては、日本でのレーダーの用途が主に防空のための哨戒・捜索レーダーであり、反射器が未熟な当時の八木アンテナでは、アンテナ後方にも電波を放ってしまう性質(バックローブ)があったため、探知の方向が180度入れ替わってしまうリスクもありました。
一方、欧米では地上や航空機の攻撃用照準レーダーとしての利用が主であったため、バックローブが大きな問題にならず、八木アンテナの導入と発展が進んだという面もあります。
いずれにせよ、日本初の優れた発明が戦争という悲劇により、他国の手で日本に大きな打撃を与える形として活用されたことは、技術史における重要なエピソードのひとつとして語り継がれています。
「八木アンテナ株式会社」は今どうなった?事業撤退の噂と企業の変遷
八木アンテナの特許を取得した八木秀次博士は、第二次大戦戦後の1952年(昭和27年)に「八木アンテナ株式会社」を設立しました。
この会社は、その後、テレビ放送の普及と共に急成長を遂げ、当時の家庭用テレビアンテナのトップメーカーとしてその名を知られるようになります。
しかし、時代の変化と共に事業環境も大きく変わりました。
携帯電話や衛星放送の普及、そして地デジ化に伴うアンテナ需要の変化などを受け、八木アンテナ株式会社は経営の多角化を進めます。
そして、2013年(平成25年)には日立国際電気の子会社となり、その後吸収合併される形で「八木アンテナ」の名を冠した企業は法人格としては消滅しました。
アンテナ事業そのものは、現在「日立国際電気」の一部門として引き継がれていますが、ひとつの企業を通じて日本の産業構造の大きな変化を垣間見ることができます。
都市伝説「八木アンテナの呪い」とは?その正体と背景を考察
八木アンテナにまつわる話として、時折「八木アンテナの呪い」という都市伝説が語られることがあります。
これは、「八木アンテナの発明に関わった者や企業は不幸になる」といった内容のものです。
具体的には、前述したように日本の発明である八木アンテナが、国内では正当に評価されず、海外にて日本に打撃を与える形で活用されたこと。共同発明者である宇田新太郎博士の名が広く知られなかったこと、八木アンテナ株式会社が吸収合併されたことなどが根拠として挙げられます。
また宇田博士は亡くなる前、自身の墓に八木・宇田アンテナを建てることを望んだといいます。しかし実際に博士が亡くなった後、アンテナを墓とすることは奇異にすぎることから、関係者の相談によって、墓誌に八木・宇田アンテナのデザインを彫り込むという対応がとられています。
もちろんこのような呪いは、科学的根拠のない都市伝説に過ぎません。
ただ、このような生まれた要因として、発明の功績が国内で正当に評価されなかったことへの無念や、戦争で敵国に利用された歴史的背景に対する、人々の複雑な感情が投影されているのかもしれません。
偉大な発明がたどった数奇な運命が、こうした物語性を生み出したと考えることができるでしょう。
また「八木アンテナの呪い」とは、上記したような歴史的経緯から、先進的な技術や発明に対して、国や企業、団体などの上層部がその価値を理解できず、優れた技術を放置、放棄するような対応を取った結果、大きな損失や損害を生んでしまう例えとして挙げられることもあります。
【実践編】テレビ受信環境を改善!八木アンテナの選び方・設置・費用
八木アンテナは歴史的な発明品であると同時に、2025年現在の今もなお、一般社会での生活に欠かせない地上デジタル放送(地デジ放送)用の「テレビアンテナ」として現役で活躍しています。
八木アンテナがアナログ放送の時代から現代まで、テレビアンテナとして重用される理由は、本体の指向性、受信性能の高さに加え、設置の高さを確保することで、現在の地デジアンテナ各機種と比べても、もっとも受信感度が安定しやすい、電波の受信性能が高いアンテナ機種であるためです。
特に、電波塔から遠い、周辺の山や建物などの影響で、受信できる地デジ電波レベルの弱い地域や、安定した受信を求めるご家庭において、八木アンテナの高い受信性能は非常に頼りになります。
以下の項目では、ご家庭の地デジ受信環境を改善するために、八木アンテナの導入をご検討している方へ向けたテレビアンテナとしての八木アンテナの、実用的な情報をお届けいたします。
他の地デジアンテナ機種との比較から、八木アンテナ本体や設置位置のバリエーションと、ご自宅に最適なモデルの選び方、設置にかかる費用の相場、そして信頼できる専門業者の見極め方まで、具体的な課題を解決するための知識を網羅的に解説してゆきます。
テレビアンテナとしての八木アンテナとは? 名称による違いを解説
一般的に、現在の地デジアンテナとして「八木アンテナ」は、メーカーなどの商品名としては「八木式アンテナ」「UHFアンテナ」と呼ばれることもあります。さらに、アンテナ技術の書籍やサイトなどを調べれば、同様のアンテナに「八木・宇田アンテナ」「指向性短波アンテナ」など、さまざまな呼び名を見つけることができます。
これら八木アンテナの名称の中でも、特にテレビアンテナとしての名称は、地上波テレビ放送の歴史と深く関係しています。
かつてのアナログ放送時代には、テレビ電波のチャンネル帯域によって、同じ八木アンテナでも「VHFアンテナ」と「UHFアンテナ」の2種類が使われていました。
より詳しくご説明すると、アナログ放送ではテレビ用の電波として。現在のNHK、広域民放など全国放送のチャンネルには、VHF(超短波)が、東京都の東京MX、千葉県の千葉テレビなど、一部都府県の独立放送局が放送する地方チャンネル(地方局)には、現在の地デジ放送と同じUHF(極超短波)が使われていました。
当時、テレビ用のアンテナと言えば、ほとんど八木アンテナ一種類のみでしたが、このVHF、UHFのチャンネル周波数帯に合わせて、全国的に使われるVHFアンテナのほかに、地方チャンネルを受信できる地域では、別途にUHFアンテナも使われていたのです。
当時の戸建て住宅などでは、屋根の上のマストに基本のVHFアンテナが設置されるのに加え、地方チャンネルも受信できる地域では、さらにもう一基、マストの先端にUHFアンテナも設置されることは珍しくありませんでした。
他にも、一基でVHFとUHFの双方を受信できるVHF・UHF共用タイプのアンテナも存在しました。
VHFアンテナは平べったく大型で素子数が少なく、アナログ放送の物理チャンネルのうち、1〜12チャンネルを受信していました。一方、UHFアンテナは比較的、小型で素子数が多く、13〜62チャンネルを受信していました。
そして2000年代初頭、地上波テレビ放送がアナログ放送から、地上デジタル放送(地デジ放送)に切り替えられた際に、使用される電波(地デジ電波)は、NHK、広域民放、地方チャンネルのすべてのチャンネルで、UHFでも470MHzから710MHzまでの周波数帯に統一されました。
したがって現在、八木アンテナを含む地デジ用のテレビアンテナは、すべて基本的に、UHFでも上記の周波数帯の受信に特化した「UHFアンテナ」になります。
ちなみにアナログ放送時代の地方チャンネル用UHFアンテナは、当時のUHF放送の周波数帯である470MHzから770MHzに対応し、今日の地デジ電波の周波数帯とほぼ重なっています。
そのため2000年代初頭の、アナログ放送から地デジ放送への転換期に、アナログ放送用のUHFアンテナを設置していた住宅では、当時のアンテナを残したままで、UHFアンテナをそのまま地デジアンテナとして使っている例も見られます。
ただ、そのようなアンテナの場合、地デジ放送で使われない710MHz以上の余計な電波を受信してしまうことで「700MHz帯電波障害」が発生する原因になる。また今日ではアンテナ本体の老朽化によるトラブルのリスクが非常に高くなっているため、早急に最新の地デジアンテナへと交換されることを強くおすすめいたします。
八木アンテナの名称の違いと、その意味などについては、以下の一覧にまとめています。
簡単にまとめると「八木アンテナ」「八木式アンテナ」は、呼び方が少し違うだけで、八木・宇田両博士が開発した、同じアンテナのことをを指します。また現在の地デジ用テレビアンテナ製品の名称としてもよく用いられます。
「UHFアンテナ」は、本来は文字通り、UHFの周波数帯を受信、送信できるアンテナのことです。テレビアンテナとしては、UHFを使用するアナログ放送時代の地方チャンネル用アンテナ、また現在の地デジアンテナ全般を指す名称になります。
ただ八木アンテナはアナログ放送時代から地デジ放送の開始後しばらくの期間まで、ほぼ唯一のテレビアンテナであったことから、当初は地デジ用UHFアンテナと言えば八木アンテナを指しました。その名残で、現在でも地デジ用の八木アンテナを、単にUHFアンテナと呼ぶこともあります。
上記のアンテナの名称は、現在ではすべて同じ同じ「地デジ受信用の八木アンテナ」を指すことがほとんどです。アンテナ業者と話す際など、基礎知識として知っておくと良いでしょう。
また「八木・宇田アンテナ」は、八木博士が単独で特許を取得した後、開発者両名を称えるために名付けられた正式名称。「指向性短波アンテナ」は、指向性が高く、短い波長の電波を送受信することに適した性能から名付けられた名称ですが、テレビアンテナの商品名として用いられることはほとんどありません。
八木 vs デザイン vs ユニコーンアンテナ、我が家に最適なのはどれ?
現在では、地デジアンテナの主流モデルは八木アンテナに加え、スタイリッシュな「デザインアンテナ」や「ユニコーンアンテナ」も登場しており、選択肢が広がっています。
皆様がご自宅の地デジアンテナとして、どのモデルを選ぶべきかは、お住まいの地デジ電波環境や、住宅の外観へのこだわり、自然環境やご予算によっても異なります。
以下では、それぞれのアンテナの種類、機種についての、主な特徴を比較してみました。
※上記は各モデルの主な特徴になります。
近年になって、八木アンテナの他にさまざまな形状のテレビアンテナが登場したのは、地上波テレビ放送の地デジ化により、従来より周波数帯が高い(波長の短い)UHFが使われるようになったため、アンテナの小型化が実現できたことによるものです。
テレビアンテナとしては現在でも基本のアンテナである八木アンテナに対し、デザインアンテナは2009年(平成21年)頃に普及しはじめた、金属板で電波をキャッチする「スリットアンテナ」をベースにしたパネルのような形状で、壁面やベランダなどにも設置できる薄型のアンテナ(平面アンテナ)です。
デザインアンテナは本体の構造、さらに設置位置が低いことから、受信性能では八木式アンテナより低くなります。そのため設置できるエリアや周辺環境の条件は限られますが、設置の見た目が良い上、自然環境にも強く長持ちするなど、八木アンテナの弱点をカバーできる地デジアンテナの第二世代モデルになります。
現在ではデザインアンテナは、電波塔に近く電波レベルが強い都市部を中心に、非常に人気の高いアンテナ機種になっています。
またユニコーンアンテナ(マスプロ電工製「U2CN」)は、ポール状の本体を持ち、基本的には八木式アンテナと同様、屋根の上でマストの先に固定される、2017年(平成29年)に登場した第三世代の地デジアンテナになります。
ユニコーンアンテナは独自のデザイン性で、高い位置に設置しても住宅の観た目やまわりの景観に影響しにくい、風雨などを受け流せて耐久性が高く寿命も長いなど、デザインアンテナとほぼ同じメリットを備えています。
さらにユニコーンアンテナは設置位置が高くなることで、周辺環境の影響を受けにくくなり、受信感度が安定しやすくなります。上記のデザインアンテナは設置位置が低い分、高層マンションの近隣や住宅密集地など、地デジ電波が遮られて壁面に届きにくい現場では使用できない弱点がありますが、ユニコーンアンテナであれば、そのような現場でも問題なく使用できる可能性が高くなります。
ユニコーンアンテナは、デザインアンテナのメリットはそのまま、弱点である受信感度の低さを抑え、より幅広い現場に対応できるようになった進化系モデルといえます。ただやはり八木アンテナに比べると受信性能は若干低く、使用できるエリアがやや限られること。また最新モデルであるため、設置にかかる費用も他機種より割高になる点が弱点と言えます。
総じて、デザインアンテナとユニコーンアンテナ、どちらのモデルもある程度、受信性能を犠牲にすることで、八木アンテナの弱点である、風雨や雪などの自然環境への弱さ、取り付けた見た目の悪さなどをカバーした次世代モデルといえます。
逆に言えば、テレビアンテナの本質である受信性能では、2025年現在でも、八木アンテナは現役にして最強のモデルである証とも言えます。アンテナレベルの安定を重視されるのであれば、現在でも八木式アンテナがもっとも優れた地デジアンテナであるといえます。
現在ではテレビアンテナに対するニーズも、受信性能だけでなく、お住まいのデザイン性の確保、自然環境への強さなど、多岐にわたっています。
お住まいの地デジアンテナ機種の選び方としては、まずご自宅の電波調査により、受信環境で安定した受信を実現できる機種を確認して、その中から、受信感度や見た目の良さ、耐久性などの優先順位を明確にして、最適となるアンテナや設置方法を選ぶことが、快適なテレビライフへの第一歩といえるでしょう。
失敗しない選び方:最適な「素子数」と「ブースター」の必要性
インターネットショップなどで地デジアンテナとしての八木アンテナ商品を確認すると、さまざまな製品に「8素子」「14素子」「20素子」などの表記があることにお気づきでしょう。
さらに製品の画像を見ると、各素子数別に、形状が異なっていることもわかるかと思います。この「素子数」とは、八木アンテナの性能を決定づけるもっとも重要な要素です。
素子(エレメント)とは、八木アンテナの構成する、主に本体支柱部に並ぶ短い金属棒(横棒)のことで、電波をキャッチするパーツになっています。したがっれこの数が多いほど、アンテナの利得(受信感度)が高くなるのです。
地デジ用八木アンテナの素子数の数え方は、横に長い導波器に並ぶ素子の数に加え、導波器の奥にある放射器を1素子、魚の頭のような反射器全体を1素子と数えた数値になります。
したがって八木アンテナは、素子数が多いほど導波器の部分が長くなる他、合わせて反射器の部分も大きくなるため、アンテナ本体が大型化します。
この素子数別モデルは、地デジ電波塔からの距離や、電波を遮る山など地形の影響で、お住まいの地域に届く地デジ電波の強度に合わせて、適切な素子数のアンテナを選ぶことが重要です。
以下、受信できる地デジ電波レベルの目安による地域の分類と、対応できる八木式アンテナの素子数になります。
※具体的な地デジ電波レベルでは、強電界地域は80㏈以上、中電界地域は80㏈から60㏈、弱電界地域は60㏈以下になります。ただ使われる場所によって、分類の基準が異なる場合もあります。
この素子数は、現場の電波レベルに対して少ないと受信性能が不足するのはもちろん、多すぎても受信性能が強くなりすぎ、余計な電波であるノイズ(雑音)まで受信して地デジ電波の品質が下がる場合もあるので、現場に適切な素子数を選ぶことが重要です。
さらに、受信レベルが低い弱電界地域、戸建て住宅内で複数(主に三台以上)のテレビに電波を分配する場合や、ケーブルの配線が長い場合など、アンテナで受信できる電波レベルが不足ずる場合には、アンテナの近くに「ブースター(増幅器)」の設置が必要になることがあります。
ブースターとは、アンテナが受信した電波レベル(映像信号)を、強力に増幅してくれる装置です。
現在では戸建て住宅へのテレビアンテナ設置では、ブースターの設置もほぼ必須となりますが、アンテナ工事の専門業者へと相談すれば、アンテナ設置工事に合わせて現場の電波状況を測定した上で、ブースターの要否や最適な機種、モデルなどを提案してくれます。
また実際の設置に当たっても、適切な増幅レベルの調整などもしてくれるため、業者へとお任せになれば大きな問題がありません。
八木アンテナの高性能型とローチャンネル用とはどんなモデル?
アンテナメーカーの公式サイトなどで、八木アンテナ各機種のカタログを見ていると、標準的な八木アンテナ以外にも、名称や見た目などが特殊なモデルに気づかれる方もおいででしょう。
その代表的なモデルが「高性能型(パラスタックアンテナ)」と「ローチャンネル用」です。
なお「パラスタック」は、複数のエレメント(素子)を組み合わせて利得を高める発想から来た呼び名で、現場では「スタックアンテナ」と呼ばれることもあります。
これらのモデルは、より厳しい受信環境の現場で真価を発揮します。
高性能型、または超高性能型、パラスタックアンテナなどの名称を持つモデルは、通常モデルの素子部にX字型のパーツが並ぶ、SFチックな形状も特長的なモデルです。
このXのような部分は、その上下左右に通常の素子を固定した「高性能素子」と呼ばれるパーツです。この高性能素子により、導波部の素子数が通増モデルの4倍になる上、27素子、30素子などの多素子モデルも存在します。
そのため通常モデルで換算すれば、数十素子から百数十素子に相当する高い利得を実現した、文字通りの超高性能型アンテナになります。
パラスタックアンテナは特に弱電界地域からそれ以下、電波塔の受信範囲外に当たるエリアでも、安定した地デジ受信を実現できるモデルになります。ただ、特に多素子モデルは本体の質量が大きく、重くなるほか、指向性も非常に高くなるため、設置時の固定や角度調整に緻密な作業が必要となります。
またパラスタックアンテナでは、5素子程度でも通常モデルの14素子から20素子と同等の受信性能を発揮するため、一般的な現場で、アンテナ本体の小型化に利用されることもあります。
一方、ローチャンネル用の八木アンテナは、外観や素子数、価格帯なども通常モデルと変わらず、どう違うのか疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
前述の通り、現在の地デジ電波は、UHFのうち、470MHzから710MHzまでの周波数帯が使われており、この周波数帯を6MHzずつのチャンネル(ch)に分けて、各テレビ局に割り当てています。
通常の八木アンテナ含む地デジアンテナは、このすべての周波数帯(ch)を受信できる「オールチャンネル用」と呼ばれるものです。
対して、ローチャンネル用のモデルとは、受信できる周波数帯(チャンネル帯域)をやや低い範囲(例えば13chから34ch、600MHz以下)などに限定したモデルになります。この低い周波数帯、チャンネル帯域が「ローチャンネル」と呼ばれるものです。
八木アンテナは上記の通り、素子の長さや間隔を調整することで、受信できる周波数帯を調節することが容易なため、このようなモデルを実現できます。そして、対応できる周波数帯(チャンネル帯域)を絞ることにより、オールチャンネル用に比べ、その範囲内の受信感度をより高めることができるのです。
基本的に電波は周波数帯が低いほど、減衰などが少なく扱いやすくなります。そのため地デジ放送では、国内各地の電波塔で混信などが起こらないよう、利用する周波数帯を調整しつつも、できるだけ低い周波数(チャンネル)帯が使われる傾向があります。
したがって、その地域をカバーする電波塔が、ローチャンネル帯の電波しか送信していないエリアであれば、ローチャンネル用の八木アンテナを使うことにより、より受信感度を高めることができるのです。
上記のようなモデルが存在することも、受信性能に優れる八木アンテナの特徴といえます。
八木アンテナの弱点をカバー!高耐候モデルと設置ポイントの工夫
八木アンテナは、現在のアンテナとしてはやや大型かつ、機器がむき出しになった独自の形状をもつアンテナで、現在でも受信感度を確保すべく、主に住宅の屋根の上へと設置されます。
そのため昔からの伝統的な弱点として、風雨や雪、海沿いの潮風、野鳥などの自然環境に影響を受けやすく、経年劣化により、寿命が10年から十数年程度と短くなりやすい。また指向性の高さもあって、経年劣化から角度のズレなどのトラブルも生じやすい点が挙げられます。
さらに近年では、戸建て住宅でもデザイン性にこだわったお住まいが多いことから、屋根の上で目立ってしまい、住宅の見た目に悪影響を与える八木アンテナを敬遠される方が多くなっています。また景観条例がある景観地域などでは、八木アンテナのような、景観に悪影響を与えるアンテナの設置が規制されているケースもあります。
しかし現在の各アンテナメーカーでは、八木アンテナの製品ラインナップに、主に風雨などへの耐久力に関する弱点を克服すべく工夫が凝らされたモデルも多数存在します。
例えば、潮風によるサビが進みやすい沿岸部向けには、サビに強いステンレス製や溶融亜鉛メッキ処理が施された「塩害用モデル」が有効です。また積雪が多く、アンテナに雪がこびりつく、積雪の重みを受けやすいなどの地域では、アンテナに雪が付着しにくい構造や強化された素材を用いた「雪害用モデル」が用意されています。
他にもメーカーによって、サビに強いステンレスモデルや、表面加工で腐食に強い高耐食モデルなど、さまざまな工夫を凝らした八木アンテナ製品が存在します。
現在では、住宅の外観などに大きな影響を与えず、また自然環境によるダメージも抑えることができる地デジアンテナの設置といえば、デザインアンテナ、ユニコーンアンテナの採用が主流ですが、従来の八木アンテナでも設置位置の工夫で、できるだけ住宅の見た目への影響を抑え、風雨なども避けやすくできる方法があります。
戸建て住宅におけるにおける 従来の八木アンテナの設置方法と言えば、主に屋根の上で、頂点に当たる部分に、マストを立てる四脚の器具「屋根馬」を置き、垂直に立てたマスト(支柱、ポール)にアンテナを設置して、屋根の四方からマストや屋根馬の各脚までステンレスワイヤーなどの支線(ステー)をバランスよく張ることで、しっかりと固定するというものです。
この工法であれば、屋根そのものへの工事は不要で、かなりの強度で手軽に、地デジ受信の安定する高い位置にアンテナを設置できるというメリットがあります。
一方で、高い位置でアンテナが目立ちやすく、家の見た目や景観に影響しやすい。また設置から10年以上が経ち、固定具などの老朽化が進むと、ステーの緩みや切れなどが生じて、アンテナが傾く、倒れる、ひいては屋根から落下するなどの大きなトラブルも想定されます。
ただ現在では、当あさひアンテナなど技術力の高いアンテナ業者では、水平器という機器を使って屋根馬の脚を加工することで、屋根の斜面にも屋根馬でアンテナを立てるという工法にも対応しています。
この工法であれば、片流れ屋根や差し掛け屋根など頂点がない屋根にも対応できるほか、屋根の上でも外部から死角になる位置へのアンテナ設置も行いやすくなります。
さらに近年では、屋根の縁に当たる破風板(屋根の張り出し部)や壁の最上部に、マストを固定できる「サイドベース」という部材をビスで設置することで、高さを確保しつつ、目立ちにくく積雪なども避けやすい、丈夫なアンテナ設置を実現する工法も多くなっています。
他にもやや位置が低くなる分、障害物がなく受信が安定する位置、方角を選ぶなどの注意点はあるものの、壁面でもやや低い位置や、ベランダの手すり、内部空間などに八木式アンテナを固定することで、アンテナが目立たず風雨、雪などにも影響されにくい設置が可能になります。
このように、条件が合えば屋外だけでなく室内に近い場所(屋根裏・天井裏など)へ設置して、外観を保ちながら受信環境を整える方法も検討できます。
また強電界地域であれば、小型の8素子八木アンテナをベランダの屋根から吊るす設置方法も可能です。
強電界地域で住宅の建材が地デジ電波を通しやすく、屋内でも十分な地デジ電波を受信できて設置スペースも確保できるなどの条件が整っていれば、地デジアンテナを屋根裏、天井裏の空間に設置することも可能になります。
この工法であれば、アンテナを完全に隠すことができて家の外観や外装などに影響がない上、アンテナ本体も天候の影響をまったく受けなくなり、メンテナンスフリーでアンテナの耐用年数を大幅に伸ばすこともできます。
屋根裏などへのアンテナ設置は基本的に受信面が広く、スペースも取らないデザインアンテナが利用されますが、受信環境などの条件によっては八木アンテナが使われる場合もあります。
このように、現在でも受信性能に優れる半面、外観性や対候性にやや難のある八木アンテナですが、使用する機種や設置位置の工夫で、その弱点をカバーすることも十分に可能なのです。
アンテナ工事の費用相場と業者の選び方【専門家のおすすめも紹介】
八木アンテナの設置をアンテナ工事の専門業者に依頼する場合、費用はアンテナ本体や設置具、ケーブルなどの基本機材に工事費を合わせて、おおよそ25,000円から35,000円程度が相場です。
ただしこれはアンテナ本体を取り付けて、同軸ケーブルのみによる最小限の工事を行う場合の施工費用で、ここに現場の必要に応じて、ブースターの設置や高所作業、古いアンテナの撤去作業などが加わると、それぞれの追加費用が発生します。
信頼できるアンテナ工事業者を選ぶためには、以下のポイントを確認することが重要です。
- 明確な料金体系と詳細な見積もりを提示してくれるか。
- 施工実績が豊富で、ウェブサイトなどで公開しているか。
- 工事後の保証期間が長く、内容が手厚いか。
- 完全自社施工で経験豊富なアンテナ専門の職人が施工を担当してくれるか。
例えば、当あさひアンテナは、年間6,000件を超える豊富な施工実績と、業界最長クラスの10年保証をご提供しています。
アンテナ工事の際に重要となる、事前のお住まいで最適なアンテナ機種、施工法を割り出す緻密な電波調査、およびお見積もりは、出張費やキャンセル費などを含めて完全無料。
また弊社では完全自社施工による優れた施工、および国産一流メーカーによる部材の品質、業界最安に挑む価格、サービスへの自信から、他業者との相見積もりにご対応しております。さらに工事をお急ぎのお客様のために、即日工事にもご対応いたします。
弊社ではアンテナ基本設置工事を、高品質アンテナや設置具、同軸ケーブルをセットにした工事費用でご提供しております。一例としては、
- 八木アンテナ:DXアンテナ20素子「UA20」:22,000円(税込み24,200円)から。
- デザインアンテナは、DXアンテナ20素子相当「UAH201」:22,000円(税込み24,200円)から。
- デザインアンテナ:サン電子20素子相当「WG-20」+「背面スッキリカバー」セット:25,000円(税込み27,500円)から。
- 強電界地域用コンパクトデザインアンテナ:マスプロ電工「U2SWLC3(スカイウォーリーミニ)」:25,000円(税込み27,500円)から。
- ユニコーンアンテナ:マスプロ電工「U2CN」:キャンペーン価格。
- 2K4K8K対応BS/CSアンテナ(地デジアンテナとセット設置):DXアンテナ「BC45AS」:18,000円(税込み19,800円)から。
- 高耐風2K4K8K対応BS/CSアンテナ(地デジアンテナとセット設置):DXアンテナ「BC453SG」:特別価格。
これらの他にも、八木アンテナの各素子数モデルや高性能パラスタックアンテナ、ローチャンネル用。塩害用、雪害用、ステンレスモデルなど。
デザインアンテナは26素子相当モデル。 BS/CSアンテナはブラックのカラーバリエーションや各ディッシュサイズのモデルもご用意しており、さまざまな条件のアンテナ工事に対応が可能です。
ブースターや周辺機器も高品質本体込み、またその他のオプション工事も、明確かつ低価格な価格体系でご案内しております。さらにデザインアンテナの屋根裏や天井裏空間への設置も、可能な現場でさえあれば、追加工事費はご無用の基本設置工事費のみでお引き受けいたします。
アンテナ工事のご相談やお問い合わせは、他業者との相見積もりも含めて、まずは当あさひアンテナのフリーダイヤル、メールフォーム、LINEアカウントまで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
お客様のご自宅に最適なアンテナ工事を適正価格でご提案し、必ずや価格とサービス品質の両方でご満足いただける施工をご提供いたします。
八木アンテナの未来と最新技術|5G・IoT・衛星通信への応用
発明されてから1世紀近くが経つ八木アンテナですが、21世紀の現在でも、その技術は決して過去のものではありません。
むしろ、その優れた指向性とシンプルな構造は、現代の最先端技術の分野でも新たな役割を見出しています。八木アンテナの基本原理は、今なお進化を続けているのです。
例えば現在、スマートフォンなどで注目されている、超高速通信を実現する「5G」の基地局アンテナとして、特定のエリアに効率よく電波を届けるために八木アンテナの技術が応用されています。
また、広大な農地を管理するスマート農業では、無数のセンサーと基地局を結ぶ「IoTネットワーク」の通信距離を伸ばすためにも八木アンテナの技術が活用されています。
さらに、宇宙に目を向ければ、「CubeSat」と呼ばれる超小型人工衛星に八木アンテナが搭載され、地上とのデータ通信を担うなど、その活躍の場は地球上にとどまりません。
材料技術や設計ソフトウェアの進化により、八木アンテナはこれからも私たちの未来を支える重要な技術であり続けるでしょう。
まとめ:八木アンテナは日本の技術史を象徴する偉大な発明
この記事では、八木アンテナの仕組みから歴史、さまざまなエピソードや自作の方法など、アンテナ本体の知識。そして現代の地デジアンテナとして八木アンテナを利用する場合のオススメの条件やモデル、設置方法などの実用的な選び方まで、多角的に解説してきました。
21世紀の現代でも、日本全国の多くの屋根の上に見られる、無数の魚の骨のようなアンテナが、実は日本の二人の研究者による世界的な発明であり、その巧妙な設計思想は100年近く経った今でも色褪せることなく、最先端の通信技術を支えていること。そして現在での地デジアンテナとしては、最強の受信性能を誇る、頼りになるアンテナであることをご理解いただけたかと思います。
八木アンテナは、以下の3つの価値を兼ね備えた、日本の技術史を象徴する偉大な発明品です。
- 技術的な合理性: シンプルな構造で、指向性と利得という優れた性能を実現。
- 歴史的な重要性: テレビの普及から戦争のレーダー技術まで、世界の歴史に大きな影響を与えた。
- 現代的な実用性: 地デジ受信の定番として、また5GやIoTといった最新分野でも応用される普遍性。
この記事が、あなたの八木アンテナに対する知的好奇心を満たし、またテレビアンテナ選びの一助となれば幸いです。
そして地デジアンテナの設置、交換などで、やはり八木アンテナの受信性能でなければと思われる方、またお住まいの電波レベル、周辺環境などから、適した地デジアンテナ機種や設置方法にお迷いの方は、ぜひ当あさひアンテナのフリーダイヤル、または本サイトのメールフォーム、弊社LINEアカウントまで、どうかお気軽にお問い合わせくださいませ。
ベテランの電波調査とお見積もりで、お住まいの受信環境に最適のアンテナ機種や設置位置を割り出し、お客様のご要望に最適となるアンテナ工事を、業界最安に挑むお見積もり価格でご提案いたします。