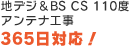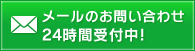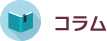テレビ電波状態・アンテナレベルが悪くなる原因は?専門家が教える基礎知識と解決策・対処法まで、テレビ電波の完全解説ガイド
お住まいのテレビで「なんだか映りが悪い」「特定のチャンネルだけノイズが入る」「まったく映らなくなりエラーコードが表示される」といった経験はありませんか。
地デジ、衛星放送など快適なテレビの視聴は、いまや日常生活に欠かせない楽しみのひとつです。
しかし突然、テレビ画面が正常に映らなくなると、テレビ視聴の楽しみも台無しになってしまいます。
その原因は、もしかしたら、お住まいの「テレビアンテナ」や、受信している「電波」の状態にあるのかもしれません。
今回のこの記事では、テレビの電波状態が悪くなる原因から、ご自身で簡単にできる確認方法、そしてアンテナの専門家が実践する解決策までを、専門外の方でも分かりやすく徹底的に解説します。
本記事の執筆に当たっては、顧客からの評価も高いアンテナ工事の専門業者「あさひアンテナ」所属のベテランアンテナ職人にお話を伺い、豊富な専門知識と現場経験に基づく、正確な情報を確認しています。
記事執筆は、技術系の記事を得意とする知識豊富なプロのライターが担当し、難しい専門用語や解説は避け、一般の方にもわかりやすい文章でまとめています。
この記事を一通りお読みになったあとには、テレビ画面の不調に対するご不安が解消され、お住まいでの対処から業者への依頼まで、具体的な対応策に踏み出すための、的確な知識が身についているはずです。
そもそも「電波」とは何か? 基礎知識を解説!
21世紀、2025年(令和7年)現在「電波」と言えば、テレビ放送の電波の他にも、スマートフォンや携帯電話、またインターネットのWi-Fiなどにも利用される、現代社会には欠かせないものです。
しかし、いざ「そもそも電波とは何か、どんなものなのか?」と問われると、具体的に説明できる人は少ないのではないでしょうか。
そもそも電波とは電磁波の一種であり、その一部ともいえます。
電磁波について詳しく説明すると難しくなりますが、簡単に言うと、電気的な力が働く空間(電場)と、磁気の力が働く空間(磁場)の相互的な影響から、光の速さで一定の波を描きながら空間を伝わるエネルギーの波動のことです。
電磁波や電波についてよく聞かれる「周波数(しゅうはすう)」とは、単位時間(1秒)ごとに描かれる波の回数のことであり、基本は「Hz(ヘルツ)」の単位で表されます。
この波長が1秒間に1,000回描かれると「1,000Hz」になり「1KHz(キロヘルツ)」の単位で表されます。
同じように1KHzの1,000倍は1MHz(メガヘルツ)になり、さらにその1,000倍ごとにGHz(ギガヘルツ)、THz(テラヘルツ)の単位になってゆきます。
そして同じ電磁波でも、周波数帯が高く、一秒に繰り返される波長の数が大きいほど、波長の幅は短くなっていく性質があります。
そして「電波」と呼ばれるものは、この電磁波の中でも比較的、周波数帯が低く波長が長いものをいいます。
電波に含まれない周波数帯の電磁波としては、周波数帯が低い順に、赤外線、可視光線、紫外線などの光がまず挙げられます。
この光よりもさらに高周波数帯の電磁波は、X線やガンマ線などの放射線になります。
電磁波の中でも周波数帯が高い紫外線や放射線などは、その特性からさまざまな利用法がある反面、人体に対しては多くの健康被害を及ぼすことでも知られています。
しかし電波は電磁波のうち、主に300GHzから3THzまで(日本の電波法では3THzまで)のものと定義されています。したがって電波は周波数帯の低さから、人体への影響はほとんどないと考えられています。
簡単にまとめると、電波とは、周波数帯によって特有の性質を持ち、空間を光の速さで伝わっていく目に見えないエネルギーの波ということができます。
そして電波は、その強弱や波長にさまざまな情報を乗せることができ、古くは無線通信やラジオ、テレビなど通信や放送から、今日のスマートフォンやWi-Fiなど、さまざまな用途で利用されています。
いまや電波とは、現代社会を支えるインフラの要と言っても過言ではないでしょう。
ちなみに、現在の日本のテレビ放送のうち、主要なテレビ放送である地デジ放送では、電波の中でも比較的、周波数帯の高い「UHF(極超短波)」のうち、波長の幅が約40センチから60センチ程度になる、470MHzから710MHzまでの周波数帯を使用しています。
このUHFはある程度、波長が広いことから、音のように広がる性質があり、障害物に遮られても、その向こう側に回り込む性質(回折)があります。
またBS放送、CS放送などの衛星放送では、短い波長域を指すマイクロ波のうち、波長の幅は1センチから10センチ、3GHzから30GHzのセンチメートル波(SHF波)と呼ばれる電波が使われています。
日本の衛星放送では、中でも周波数帯が12GHz前後で、波長の長さは25ミリ前後の電波が使われているため、衛星放送の電波は「12GHz帯」とも呼ばれます。
この12GHz帯は周波数帯が電波の上限に近いため、光のように非常に直進性が高い半面、障害物に遮られやすい性質もあります。
少し長くなりましたが、電波の基本的な知識をご理解いただくことで、以下でご紹介する各種のテレビ電波の性質や、その性質に基づくトラブルの原因についてもわかりやすくなります。
まずは自分でチェック!テレビの電波状況を確認する方法
もしお住まいでテレビ画面の映りが悪い状態になった時は、アンテナなどの専門業者に連絡する前に、まずはご自宅のテレビでも簡単にできる、電波状況のチェックを試してみることがおすすめです。
多くの場合は、テレビ本体の機能を使って、問題の原因を探るヒントを得ることができます。
この項目では、誰でもすぐに実践できる「アンテナレベルの確認」と「エラーコードのチェック」という2つの基本的な方法をご紹介します。
アンテナレベルは十分?テレビメーカー別の確認手順
アンテナレベルとは、テレビが受信している電波(アンテナからケーブルを通じて実際にチューナーまで届いている電波)の強さを示す数値のことです。
このアンテナレベルが低い状態になると、テレビ側で電波の映像信号を十分に認識できないため、テレビの映像が乱れる、まったく映らないなどの症状が起こります。
アンテナレベルは、基本的にテレビの設定画面から、地デジやBSのアンテナレベル画面を選ぶことで確認できます。
実際のアンテナレベル画面では、テレビのメーカーやモデルによっても異なりますが、数値や帯状、または色彩のインジケーターで、視覚的にわかりやすく受信レベルを確認できます。
主要なテレビメーカーごとの、正確なアンテナレベルの確認手順は以下の通りです。
お手元のリモコンを操作して、テレビでご自宅の受信レベル(アンテナレベル)を確認してみてください。
※各メーカーのテレビでも、モデルや製造年代などにより、細かな手順などが異なる場合もあります。
画面に表示されるエラーコードの意味とは?
お住まいのテレビで地デジなどのテレビ放送が映らなくなったとき、真っ暗な画面に「E201」や「E202」といったエラーコードが表示されることがあります。
このエラーコードとは、テレビ本体が、テレビを映し出せない原因を自己診断して、どのような問題を検知したかを示すものです。
つまり、テレビやアンテナにどのようなトラブルが生じているかを示す、重要な手がかりといえます。
以下に代表的なエラーコードとその意味を解説します。これらを理解しておくことで、トラブルの原因を突き止めやすくなります。
※上記は主なエラーコードです。その他にも、トラブルの原因に対応する多くのコードが存在します。
なぜ?テレビ電波が弱くなる根本原因を徹底解説
お住まいのテレビで、アンテナレベルの低下やエラーコードが表示される場合には、必ず相応の原因があります。
テレビの電波とは、上記でもご説明した通り、空間を伝わる微弱なエネルギーの波で、目に見えない非常にデリケートなものです。
電波の種類(周波数帯)にもよりますが、テレビ電波は、電波塔や人工衛星からご家庭のアンテナへと届くまでの間に、距離や気候、天候による減衰(弱まり)や障害物、別の電波(ノイズ)の混入など、さまざまな要因で弱まる、また品質が低下することがあります。
この項目では、アンテナやテレビに届くテレビ電波のレベルが弱くなる、代表的な4つの根本原因を掘り下げて解説します。
【原因①】アンテナの向きのズレや角度の問題
地デジ用、衛星放送(BS/CS)用とも、テレビアンテナには「指向性(しこうせい)」という、アンテナの真正面側で受信感度が高まる性質があり、アンテナ正面側の向きを電波塔や静止衛星がある特定の方向へと正確に向けることで、最大の受信性能を発揮します。
特に、魚の骨のような形をした地デジの「八木式アンテナ」や、お皿の形をした衛星放送用「BS/CSアンテナ」は指向性が非常に高いため、少しの角度のズレが受信レベルに大きく影響します。
これらのアンテナは本体の老朽化に加え、台風や強風、あるいは鳥がアンテナに止まった衝撃などで、向きがずれてしまい、受信感度が低下してしまうこともあります。
特にBS/CSアンテナの場合、直進性の強い12GHz帯を受信するため、受信部であるディッシュ(放物面反射器)の上下、左右の角度が数ミリずれただけでも、まったく映らなくなるほどシビアです。
【原因②】周辺環境の変化(建物・樹木・天候)
テレビアンテナを設置した当初は受信に大きな問題がなくても、時間とともに周辺環境が変化し、電波の通り道を遮ってしまうことがあります。
例えば、アンテナの近隣に高層マンションが建設されたり、自宅の庭木が大きく成長したりすると、それが壁となって電波が届きにくくなります。
地デジ電波であるUHFの場合、ある程度、障害物を乗り越える力はありますが、アンテナの正面に当たる方向で、直近に高層ビルや隣家などができると、電波が遮られやすくなります。
衛星放送の電波である12GHz帯は、直進性が強い分、わずかな障害物にも弱く、BS/CSアンテナ(ディッシュ)を向けた静止衛星の方向(東経110度)に、山や建物はもちろん、木やその枝葉、洗濯物などがあるだけでも電波が遮られてしまいます。
また、大雨や大雪の日にテレビの映りが悪くなるのは「降雨減衰」「降雪減衰」と呼ばれる現象が原因です。
地デジ電波は空間を広がって伝わる分、気候や天候の影響を受けやすく、一年を通して一定の電波レベルの変動があるほか、雨や雪の日にはレベルが大きく低下します。
そのため、一定の季節や悪天候の日には、地デジのテレビ画面が乱れることもあります。基本的に地デジアンテナでは、気候や天候による電波レベルの変化を見越して、余裕のある受信レベルの確保が重視されます。
衛星放送の場合、12GHz帯は直進性が高いため多少の気候や天候に大きな影響は受けませんが、激しい豪雨、大雪で雨や雪が大粒になると、波長の短い電波が雨や雪に吸収され、乱反射が起こってしまい、受信レベルが大きく低下します。
衛星放送の降雨・降雪減衰は、基本的に天候の回復を待つことが対策になります。ただ一般住宅の場合、受信感度が高いやや大型のBS/CSアンテナを使うことも、天候による受信障害への対策になります。
【原因③】機器の劣化や不具合(アンテナ本体・ケーブル・ブースター)
基本的に屋外に設置されているアンテナ本体やブースターの増幅部、配線ケーブルなどは、常に雨風や紫外線などの自然環境に晒されており、年月につれて劣化していくことは避けられません。
一般的に、テレビアンテナ本体の寿命は、屋外の八木式アンテナやBS/CSアンテナで10年から15年と言われています。なお耐久性の高い地デジのデザインアンテナやユニコーンアンテナでは、その寿命は15年から20年以上になります。
また、アンテナとテレビを繋ぐケーブルが劣化してひび割れる、接続部分が緩むなどしても、電波の漏洩による弱まり、ノイズ混入による質の低下などが起こり、受信不良の原因となります。
さらにお住まいで、アンテナが受信できる電波を必要なレベルまで増幅する「ブースター」という機器を設置している場合は、その電源部の電源が切れている、故障しているなどで、電波が増幅されていないケースも考えられます。
【原因④】地域の電波環境(電界地域)
地デジ放送の場合、お住まいのある地域が、近隣の電波塔からどのくらいの距離にあるか、また地形的に電波が届きやすい場所かどうかによっても、実際にアンテナで受信できる電波の強さが異なります。
地デジ電波塔から見てその周辺エリアで、距離や山などの影響によって受信できる電波レベルの強さに応じて、各エリアは「強電界地域(80㏈以上)」「中電界地域(80㏈から60㏈)」「弱電界地域(60㏈以下)」の3種類の電界地域に分類されます。
(分類の種類や基準は異なる場合もあります)
電波塔の近隣で障害物が少ない「強電界地域」であれば、到達する電波レベルが強いため比較的、簡単に受信できます。
しかし電波塔から離れている、または山間部などで電波が弱まる「弱電界地域」では、高性能なアンテナを使う、できるだけアンテナを高い位置に設置する、ブースターを追加設置するなどの工夫を凝らす必要があります。
なお衛星放送の場合、静止衛星から12GHz帯の電波が送られるため、日本全域にて安定したレベルで受信できることが特徴です。
ただ、静止衛星から距離が遠い日本北部や南端部、離島部などでは距離による減衰が起こり、やや受信レベルが弱まるため、一般住宅でもやや大型のBS/CSアンテナが必要になります。
アンテナの基礎知識|仕組みと種類を理解して最適な一台を選ぶ
テレビの電波受信トラブルについてご理解になる上で、その受信の要である「テレビアンテナ」そのものについて知っておくことは非常に重要です。
なぜただの金属の棒や円盤のようなアンテナが、遠くから飛んでくる目に見えないエネルギーである電波をキャッチできるのでしょうか。
この項目では、テレビアンテナの基本的な仕組みと、現在の主流である地デジ用・衛星放送用アンテナの種類について、それぞれの特徴を比較しながら分かりやすく解説します。
ご自宅の環境に最適なアンテナ機種を選ぶための、正確な知識を身につけてください。
代表的な地デジアンテナ3種を徹底比較【メリット・デメリット】
地上デジタル放送のUHFを受信するためのアンテナは、地デジアンテナであるUHFアンテナです。現在、戸建て住宅で使用される地デジアンテナには、主に「八木式アンテナ」「デザインアンテナ」「ユニコーンアンテナ」の3機種があります。
各アンテナ機種とも、それぞれメリットとデメリットがあり、お住まいの電波環境やデザインの好みなどのご要望によって、最適な選択が変わってきます。
以下、アンテナの種類ごとの特徴やメリット・デメリットについて一覧で解説します。
※上記は各アンテナモデルの主な特徴です。
4K8K放送に必須!BS/CSアンテナの選び方
NHKや広域民放のBSチャンネルなどが視聴できるBS放送、多彩な専門チャンネルが楽しめるCS放送(スカパー!)などの、衛星放送を受信するためには、衛星放送専用のパラボラアンテナ(BS/CSアンテナ)が必要です。
BS放送は放送衛星、CS放送(スカパー!)は通信衛星から、それぞれ12GHz帯の電波が送信されています。双方の静止衛星は同じ東経110度(南西方向)上空に位置しているため、一基のBS/110度CSアンテナでどちらも受信できます。
そして、2018年(平成30年)にスタートした、臨場感あふれる高精細な映像が楽しめる「4K8K放送」を視聴するには、それに対応したBS/CSアンテナが必須となります。
これは当時、多数の4K8Kチャンネルを追加するにあたり、それまで使われていた右旋円偏波では周波数帯が不足し、新しく4K8K用に左旋円偏波という電波を導入したためです。
したがって右旋で放送されるBSのNHK、広域民放4Kチャンネルを除く、左旋の4K8Kチャンネルを受信するには、右旋と左旋に対応するアンテナ本体や機材が必要になるのです。
現在のBS/CSアンテナが基本的にすべて2K4K8K対応型ですが、これから衛星放送用のBS/CSアンテナや配線部の機材を選ぶ際は、「4K8K対応」「3224MHz対応(配線部の機材)」などの表示、またはJEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)で認定された「SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)」「HSマーク(ハイシールドマーク)」が付与された機器を選んでください。
なおSHマークとHSマークは付与される機器の種類がそれぞれ異なり、どちらか一方のみが付与されていれば問題はありません。
BS/CSアンテナのディッシュ部は、その直径が大きいほど受信感度が高くなり、一般住宅では直径45センチの「45型」が使われます。
他にも主にマンションやアパートの共同受信用である、50型、60型、75型、90型、120型などのサイズがあります。
前述のように、一般住宅でも降雨・降雪による受信不良対策や、受信感度が低い一部エリア向けに、やや大型のBS/CSアンテナが使われることがあります。
また家庭用の45型BS/CSアンテナでは、通常の白色系のほか、太陽光に強い塗装によるブラックやベージュのカラーバリエーション。また設計の工夫で台風などにも強くトラブルが生じにくい高耐風モデルも登場しています。
原因別!自分でできるアンテナトラブル対処法【完全ガイド】
これまで解説してきたアンテナや受信に関するトラブルの原因を踏まえて、この項目では、専門業者を呼ぶ前に、ご自身でも安全に試せる対処法を、以下で具体的にご紹介します。
トラブルの原因が簡単な場合には、ここでご紹介する作業でトラブルが改善するケースも少なくありませんので、ぜひ一度お試しください。
ただし、屋根の上にあるアンテナを調整するなど、高所での作業は非常に危険ですので、絶対に無理はなさらないでください。危険を伴う作業については、最初から専門業者にお任せになることが確実です。
- テレビ・レコーダーを再起動する
- 一時的な不具合の場合、機器の電源を完全にオフにして、本体の通電を断ってから再度、電源を入れるだけでも改善することがあります。
- まずはテレビ本体の主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で数分間ほど放置してから、再度ケーブルを接続して電源を入れてください。
- テレビやレコーダーによっては専用のリセット方法が用意されている場合もあります。ただし方法によっては、初期設定や録画内容などもリセットされてしまう場合もあるためご注意ください。
- B-CASカードを挿し直す
- 「E100」「E101」「E102」などのエラーコードが表示される場合、B-CASカードの接触不良が考えられます。
- テレビの電源を切った状態でB-CASカードを抜き、ICチップの金属部分を乾いた柔らかい布で優しく拭いてから、正しい向きで奥までしっかりと挿し直してください。
- 近年の4K8KテレビではB-CASカードの代わりに、同様の機能を持つACASチップが内蔵されているモデルもあります。このようなモデルで上記のエラーコードが表示される場合は、前述の再起動を試してください。
- ケーブルの接続を確認する
- テレビの裏にあるアンテナ入力端子(チューナー端子)からアンテナケーブルが抜けていたり、緩んでいたりしないかを確認します。
- 壁のアンテナコンセント端子や、分配器、ブースターなど、すべての接続箇所を一度抜き差ししてみることも有効です。
- チャンネルを再スキャン(再設定)する
- テレビを最初に設置した際に、受信できるテレビ電波を確認して行うチャンネルスキャンで設定されたチャンネル設定と、受信できる電波の内容に違いが生じると、各チャンネルが映らなくなることがあります。
- 引っ越し後や、地域の放送局で受信できるチャンネルの周波数帯に変更があった場合などに必要な作業です。
- テレビの設定メニューから「チャンネル設定」や「放送受信設定」を選び、お住まいの地域を選択してチャンネルスキャンを実行してください。
自分で解決できない時はプロに相談!信頼できる業者の選び方
上記でご紹介したご自分での対処法を試しても、症状や改善しない場合や、そもそもの原因が特定できない場合、さらにはアンテナの向き調整など危険な高所作業が必要な場合には、決してご無理をなさらず、専門のアンテナ工事業者へとご相談になることが最善の選択です。
プロのアンテナ工事業者へとご依頼になることで、安全かつ確実に問題を解決できます。
ただテレビのアンテナ修理も、実際には依頼する業者によって、施工の技術力や料金体系はさまざまです。
この項目では、プロの専門業者へとご依頼になるメリットと、アンテナ修理の費用を抑え、ご依頼後に後悔しないための信頼できる優良な業者の選び方について解説します。
プロにアンテナ調査・修理を依頼するメリット
アンテナ工事の専門業者に依頼する最大のメリットは、その専門性と安全性にあります。
- 正確な原因究明
- プロのアンテナ職人は「アンテナレベルチェッカー」と呼ばれる専用の測定器を使って、電波の強度や品質を正確に数値で把握します。
- これにより、経験や勘だけに頼らない、客観的なデータに基づいた実際の電波状態、受信状況チェックと原因の究明が可能です。
- 最適な機材での確実な修理
- 原因に応じて、アンテナの交換、ブースターの設置、ケーブルの張り替えなど、最適な方法で修理を行います。
- 的確な原因の特定に基づき、確かな技術で施工するため、アンテナトラブルの再発リスクを大幅に減らすことができます。
- 高所作業の安全性確保
- 屋根の上でのアンテナ調整作業は、一般の方が行うと、転落などの重大な事故につながる危険が伴います。
- 専門業者は作業の安全を確保するための講習や法令に基づいた装備など安全対策を徹底しており、危険な作業も安心して任せることができます。
失敗しない業者の見分け方【あさひアンテナの強みから学ぶ】
数あるアンテナ工事業者の中から、本当に信頼できるパートナーを見つけるには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。
ここでは、本記事にもご協力いただいたベテランのアンテナ職人が所属し、顧客満足度5年連続No.1の実績を誇る「あさひアンテナ」の強みを例に、良い業者を見分けるための具体的な基準をご紹介します。
- 長期保証の有無を確認する
- テレビアンテナは長期間使用する設備です。施工後の保証期間は、業者の技術力と責任感の表れと言えます。
- あさひアンテナでは、業界最長クラスとなる工事後から10年の長期保証を提供しており、万が一のトラブルにも安心して対応してもらえます。
- 完全自社施工であるか
- 依頼した会社が下請け業者に工事を丸投げする場合は、中間マージンが発生して費用が割高になる、下請け業者の技術に施工品質が左右される、責任の所在が曖昧になるなどのケースもあります。
- あさひアンテナは、問い合わせから施工まですべて経験豊富な自社の専門スタッフが行う「完全自社施工」を徹底。高品質な工事を適正価格で提供しています。
- 豊富な実績と迅速な対応力
- 多くの工事を手掛けている業者は、それだけ多様な現場に対応してきた経験とノウハウが豊富です。
- あさひアンテナは、年間6,000件以上の豊富な施工実績を誇ります。また、フリーダイヤルへのお電話一本での即日対応や、メールフォーム、LINEアカウントでの気軽なご相談、簡易お見積もりも可能で、顧客の「困った」に迅速に応える体制が整っています。
【豆知識】アンテナと電波の未来|Beyond 5G/6Gでどう変わる?
この項目ではテレビアンテナの話題から発展して、社会と生活を根底から変えようとしているアンテナと電波技術の未来について触れてみましょう。
現在普及が進む5G、そしてその先にある「Beyond 5G/6G」と呼ばれる次世代の通信技術では、これまで以上に高い周波数帯の電波(ミリ波やテラヘルツ波)が使われます。
これらの電波は、一度に大量のデータを送れる反面、直進性が強く障害物に弱いという特徴があります。
そのため、アンテナ技術も大きな進化が求められており、特定の場所に電波を集中させる「ビームフォーミング」技術や、より小型で高性能なアンテナが不可欠になります。
こうした技術の進化は、自動車の自動運転の精度向上や、まるでその場にいるかのような超高精細なVR体験など、私たちの暮らしをさらに豊かで便利なものに変えていくでしょう。
地デジで受信トラブルが起こる主な要因とは?
この項目では、地デジ放送の仕組みや、使われている電波の性質から、電波障害などの受信トラブルが起こる主な要因について解説していきます。
現在の地上デジタル放送(地デジ放送)では、前述の通り、UHFの電波を、日本各地にある地デジ電波塔の先端から送信しています。
このUHFはビルなどに遮られても向こう側で広がるなど、比較的、障害物に強い性質を持っていますが、それでも完璧ではありません。障害物の直近では広がった地デジ電波が届かず、受信レベルが大きく下がることもあります。
そのため地デジアンテナは、基本的に電波塔の先端に近く、周辺が開けて障害物に影響されにくい、屋根の上など高い位置に設置するほど受信レベルを確保しやすくなります。
地デジアンテナの受信トラブルの多くは、アンテナ前方が電波塔の方向からわずかにずれてしまうことが原因です。
前述の通り地デジアンテナには「指向性」がありますが、その詳しい性能は「半値幅(はんちばは)」という角度で示されます。これはアンテナ真正面の最大となる受信感度を基準に、アンテナ角度を左右にずらして受信感度が半減する角度を示したものです。
同じ受信性能(素子数・素子数相当)の地デジアンテナでも、この指向性が高い(半値幅が狭い)モデルほど、受信性能が狭い範囲に集中し、他方向からのノイズも受信しにくくなることから、受信感度が高くなります。
一方で地デジアンテナの正面側で、電波塔の方向がこの半値幅から外れてしまうと、受信レベルは急激に低下します。
その他にも地デジ放送では、以下のような要因が複雑に絡み合って受信トラブルを引き起こすことが考えられます。
※上記は主な地デジ受信トラブルの要因になります。
衛星放送(BS/CS)受信で受信トラブルが起こる主な要因とは?
衛星放送は、地上から約36,000km上空にある静止衛星から日本全域に送られてくる、前述した12GHz帯の電波を利用しています。
この電波は光のように直進性が極めて高く、静止衛星から地上までの遠距離も十分に届く半面、わずかな障害物にも遮られてしまうのが最大の特徴です。
そのため、BS/CSアンテナの設置では、ディッシュ(皿)の仰角(上下の角度)と方位角(左右の角度)を、東経110度に位置する静止衛星の方向へ寸分の狂いなく合わせる必要があります。
さらにディッシュを向けた静止衛星の方向に、電波を遮るわずかな障害物も観られないという点も重要な条件になります。
その他、衛星放送特有の主な受信トラブル要因としては、以下のものが挙げられます。
※以上は主な衛星放送受信トラブルの要因になります。
まとめ|快適なテレビ視聴のために原因を正しく見極めよう
お住まいで急にテレビの映りが悪くなる問題は、大きなストレスをもたらすものですが、その原因はひとつではありません。
この記事でも解説したように、原因はアンテナ本体から電波の状態、周辺環境、ご自宅の機器まで、さまざまな要因が考えられます。
トラブルを早急に解決し、快適なテレビ視聴を取り戻すための第一歩は、その原因を正しく見極めることです。
以下、記事でご紹介した情報を、あらためて簡単にまとめます。
- まずは自分でチェック:アンテナレベルやエラーコードを確認し、現状を把握してください。
- 原因を推測する:アンテナの向き、周辺環境、機器の劣化など、思い当たる原因がないか考えてみてください。
- 簡単な対処法を試す:再起動やケーブルの再接続など、安全にできることを試してみてください。
- 無理せずプロに相談:高所作業や専門的な調査が必要な場合は、迷わず信頼できる業者にご依頼ください。
テレビやアンテナ、電波の受信について正しい知識を持つことで、急なトラブルにも冷静に対処でき、最適な解決策を見つけることができます。
本記事が、あなたの快適なテレビライフを取り戻すための一助となれば執筆者としても幸いです。
もしトラブルの原因がわからない、またはテレビアンテナ本体の不具合など、お住まいでの対処が難しい場合は、本記事にもご協力いただいた「あさひアンテナ」のフリーダイヤル、メールフォーム、LINEアカウントなど、優良な専門業者の窓口まで、早急にお問い合わせになることをおすすめします。