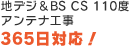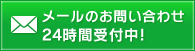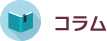地デジ用の八木式アンテナは時代遅れ?その性能・費用相場・選び方と料金の安いテレビアンテナ工事業者を専門家が徹底解説!
21世紀の現在でも、戸建て住宅に設置される地上デジタル放送用のテレビアンテナといえば、屋根の上にマスト(ポール、支柱)で立てられる魚の骨のような外観のアンテナを連想される方が多いでしょう。
このような形のアンテナは、単に「地デジ用UHFアンテナ」と呼ばれることもありますが、正式には「八木式アンテナ(八木アンテナ、八木・宇田アンテナ)」という名称が存在します。
このタイプのテレビアンテナは、日本で地上波のテレビ放送(アナログ放送)がスタートした昭和の時代から使われ続けている、非常に古典的なモデルになります。
2000年代前半、地上デジタル放送がスタートした頃までは、衛星放送用のパラボラアンテナを除けば、この八木式アンテナが、戸建て住宅などに設置されるモデルとして、ほぼ唯一のテレビアンテナでした。
したがって2025年(令和7年)でも、屋根の上にこのタイプのアンテナを使っている住宅は数多く見られます。そして一般住宅で使用されている地デジアンテナ機種としては、現在でも八木式アンテナが最大のシェアを誇っています。
一方で現在では、八木式アンテナに比べて設置の外観がスタイリッシュになるデザインアンテナ、ユニコーンアンテナといった、新たな地デジアンテナ機種も登場しています。
そのため新築住宅のアンテナ取り付け工事や、お住まいに既設のアンテナの交換をお考えで、最新のアンテナ機種について調べられた方であれば、昔ながらの八木式アンテナなど時代遅れのモデルであり、アンテナの選択肢としては眼中にない方もおいででしょう。
確かに、八木式アンテナは昭和の昔から変わらない見た目のため、現代のデザイン性を重視する戸建て住宅の外観、さらには風雨などによるアンテナの老朽化を気にされる方には敬遠されがちな面もあります。
しかし八木式アンテナは、実はその性能とコストパフォーマンスの高さから、発明から約100年が経ったいまでも、アンテナとしての基本性能では「最強のアンテナ」として、多くのご家庭で選ばれ続けているのです。
さらに現在では、八木式アンテナの弱点であるアンテナの外観、自然環境への弱さをカバーできる、さまざまなモデルや設置方法も登場しています。
記事の内容では、八木式アンテナの基礎知識から、デザインアンテナなど新機種との価格、性能、特徴などの徹底比較、そしてお住まいでのアンテナ工事で後悔しないためのアンテナ機種の選び方までの網羅的な最新の情報を、技術系の知識を持つライターが専門用語などはできるだけ避け、一般の方にも分かりやすく執筆しました。
また本記事の執筆にあたっては、アンテナ工事の専門業者「あさひアンテナ」に所属する経験豊富なプロのアンテナ職人へと取材を行い、さまざまな受信条件とお客様のご要望に対応し、最適の地デジアンテナ設置を実現してきた多数の施工経験をもとに、他機種と比較した八木式アンテナの特性について、実際的で正確な解説を執筆しています。
本記事を最後までお読みいただけば、八木式アンテナか、デザインアンテナなどの新モデルか、お客様のお住まいや受信環境に最適となるアンテナ機種はどれなのか、自信を持ってご判断いただけるようになります。
そもそも八木式アンテナとは?100年愛される理由
八木式アンテナは、2025年現在でも、一般の戸建て住宅などで地上デジタル放送(地デジ放送)を受信するための、もっとも標準的なテレビアンテナです。
そのため、単に地デジ電波(UHF)を受信するためのテレビアンテナの総称でもある「UHFアンテナ」と呼ばれることもあります。
上記の通り、八木式アンテナは昭和のアナログ放送時代から、2000年代初頭の地デジ放送の黎明期まで、一般的にはほぼ唯一の地上波テレビ放送用アンテナでした。
現在の地デジ用UHFアンテナである八木式アンテナは、基本的に矢印型の支柱に短い横棒がいくつも並んでいる特徴的な形状で「魚の骨」の形に例えられます。
昭和の昔から使われ続け、現在でも多くの戸建て住宅の屋根の上に見られることから、日本国内であれば誰しもが一度は目にしたことがあるでしょう。
このアンテナは、いまからおよそ100年前、1924年(大正13年)から1925年(大正14年)に、東北帝国大学(現在の東北大学)工学部の八木秀次博士と、当時は大学院生だった宇田新太郎博士によって原理が発見され、実用化された非常に歴史あるアンテナです。
八木式アンテナに限らず、アンテナは基本的に、送受信する電波の周波数帯(波長の幅)によって大きさが左右されます。
八木式アンテナは、周波数帯が低い(波長の幅が広い)電波の送受信には、横幅が大きくなりすぎるため実用には向きません。
ただHF(短波)、アナログテレビ放送に使われたVHF(超短波)、現在の地デジ電波であるUHF(極超短波)については、実用的なサイズで利用できます。また超短波や極超短波のアンテナとしては世界初のものでもあります。
ただ同じ八木式アンテナでも、受信する電波がVHFかUHFかなど、周波数帯の違いによってその形状やサイズはやや変わってきます。
八木博士がその原理を発見して特許を取得したため、主に八木アンテナ(八木式アンテナ)と呼ばれていましたが、その後、多くの実験を重ねて実用化に貢献した宇田博士の功績も含めて「八木・宇田アンテナ」の正式名称で呼ばれるようになりました。
他にも、送受信できる電波や、指向性(アンテナの正面側、一定範囲のみで受信性能が高まる)といった性質から「指向性短波アンテナ」と呼ばれることもあります。
この八木式アンテナは約100年もの間、基本的な構造はそのまま、日本のテレビアンテナをはじめ、アマチュア無線や業務無線、また第二次世界大戦中の欧米のレーダー開発など、世界中で使われ続けている理由は、その設計が非常にシンプルながら高い指向性を持ち、電波を受信する上で極めて効率的だからに他なりません。
「魚の骨」には意味がある!電波を捉える巧妙な仕組み
特に現在の地デジ用アンテナとしての八木式アンテナは、一見するとただの金属の棒が並んでいるだけの形に見えます。しかし、その骨の一本一本には、電波を効率よく集めるための重要な役割があるのです。
ここでは地デジアンテナとしての八木式アンテナを例に挙げますが、基本的に八木式アンテナは、主に以下の3つの部分から構成されています。
※上記は八木式アンテナの基本的な構造です。
上記の内、導波器は「ディレクター(director)」、輻射機は放射器または「ラジエーター(radiator)」、反射器は「リフレクター(reflector)」とも呼ばれます。
実際の地デジ用八木式アンテナで説明すると、導波器は魚の骨の背骨(席椎骨)に当たる、短い横棒が並ぶ中心的な横の支柱になります。
反射器は導波器の片方の端にある、魚の頭か矢印の先端に見える部分です。魚の骨のような外観とは異なり、この反射器のある側が、アンテナの後方に当たります。
輻射器は導波器の後部、反射器との間にある部分で、給電器と呼ばれる小さな黒い箱と素子が一体化し、ケーブルに接続されている部分です。
またアンテナ全体に規則的に並ぶ、肴の小骨のような短い横棒は「素子(エレメント)」と呼ばれる部分で、この部分が地デジ電波を集める、または余計な電波を反射する役割を持っています。
地デジアンテナの八木式アンテナでは、アンテナの前方にあたる反射器とは反対側の先端を、電波塔の方向に向けることで、素子を通じて導波器を伝わる形で、電波が集められます。集められた電波は輻射機に吸収され、給電部を通じてケーブルに送られます。
反射器は、輻射機を通り過ぎた地デジ電波を反射して送り返す他、後方などから届く無関係の電波(ノイズ)を受信しないよう反射する重要な役割を持っています。
これらの各パーツが電波の波長に合わせて精密に配置されることで、特定の方向(電波塔の方向)から届く電波だけを強力に受信し、安定した地デジ放送の視聴を可能にしているのです。
この計算され尽くした機能美こそが、八木式アンテナの強さの秘密です。
ちなみに、地デジアンテナの受信性能を示す「素子数」とは、八木式アンテナに設置された素子の数を示すもので、この数(導波器の受信素子の数と、輻射器、反射器をそれぞれ1素子と数える)によって受信性能が異なります。
地デジ用の八木式アンテナには、受信性能別に8素子、14素子、20素子があり、それぞれ並べられる素子数が異なるため、素子数が多いモデルほどアンテナ本体も大型化します。
また八木式アンテナより後に登場したデザインアンテナなど、外部から素子が見えないモデルの受信性能は、八木式アンテナの素子数に換算した「素子数相当」で表されます。
地デジアンテナ機種の受信性能の目安になっていることも、八木式アンテナの基本性能が非常に優れている証といえます。
日本発の世界標準!IEEEマイルストーン認定の歴史と信頼性
八木式アンテナの正式名称は上記の通り「八木・宇田アンテナ」ですが、その功績は世界的に高く評価されています。
1995年(平成7年)には、この八木・宇田アンテナが電気・電子技術分野で歴史的な偉業を称える「IEEEマイルストーン」に認定されました。
これは、家庭用ビデオ(VTR)や電卓、新幹線などと並ぶ快挙であり、私たちの生活に大きな影響を与えた技術の証です。
また2016年(平成28年)には、国立科学博物館の重要科学技術史資料(未来技術遺産)の第00210号として、世界最初の超短波アンテナとして評価され、登録されています。
このように八木式アンテナは、単に昔ながらの古いアンテナではありません。
世界に誇り、21世紀の現在でも通用する日本の技術遺産であり、その信頼性は歴史が証明しているのです。
【結論】八木式アンテナはどんな人におすすめ?
ここまで八木式アンテナの誕生や利用に関する歴史的経緯や基礎知識を解説してきましたが、お客様にとっては「結局、自宅の地デジアンテナとして八木式アンテナは適しているのぁ?」という点が、もっとも気になるところでしょう。
結論から申し上げると、新築などのアンテナ工事におけるテレビアンテナ選びは、皆様がアンテナに「何を優先するか」といったポイントよって変わります。
以下の項目で、お住まいの環境や、お客様のご要望と照らし合わせながら、ご自身がどちらのタイプに当てはまるかを確認してみてください。
八木式アンテナを選ぶべき人(性能・コスト重視派)
以下のような方は、お住まいの地デジアンテナとして、八木式アンテナが最適な選択となる可能性が高いです。
- 電波の弱い地域にお住まいの人
- 本体の指向性が高く、屋根の上など高所に設置されるため受信感度を確保しやすく、地デジ電波塔から遠いエリア、また山間部やビルが密集している地域など、電波が届きにくい場所でも安定した受信が期待できます。
- アンテナ設置の初期費用をできるだけ抑えたい人
- 古典的なアンテナ機種で、設置の工法も確立されていることから、他の地デジアンテナ機種に比べて本体価格・工事費ともに安価な傾向があります。
- 天候に左右されず、常に安定したテレビ視聴を最優先したい人
- 高い受信性能により余裕のある受信レベルが確保できるため、電波レベルが低下する悪天候時でも、地デジの映像が乱れにくくなります。
他のアンテナを検討すべき人(外観・環境重視派)
一方で、ご要望やお住まいが以下のような条件に当てはまる場合は、地デジアンテナとしてデザインアンテナなど他の機種の選択肢をご検討になることをおすすめします。
- 家の外観を絶対に損ねたくない人
- 建物のデザインにこだわりがあり、屋根の上で「魚の骨」のようなアンテナがが目立つことに抵抗がある場合です。
- 台風や積雪、鳥のフン害などが特に心配な人
- 八木式アンテナは独自の形状と屋根の上の設置位置から、強風や大雨、積雪、潮風、鳥が留まるなど自然環境の影響を受けやすく、老朽化が進みやすため、災害リスクが高い地域や鳥害に悩む場合は不向きなことがあります。
- 屋根の上に設置した場合の八木式アンテナの寿命は、現場の自然環境による違いも出ますが、おおむね10年から15年程度です。
- 八木式アンテナは指向性が高く、その点も受信性能の高さにつながっていますが、一方で老朽化などによりわずかな角度の狂いが出ても受信感度が下がりやすいという弱点にもつながります。
- 景観条例などでアンテナの設置に制限がある地域にお住まいの人
- 景観地域など特定の地域では、景観条例などがあり、設置できるアンテナの位置や種類を含めた、建物の外観に関するルールが定められている場合があります。そのため八木式アンテナの設置が制限される場合もあります。
- また地域の条例などとは別に、住宅密集地など隣家との間隔が狭いお住まいでは、八木式アンテナだとアンテナの一部が隣家の敷地にはみ出してしまう「越境問題」が生じる可能性もあり、注意が必要です。
八木式アンテナのメリット・デメリットを正直に解説
後悔のない地デジアンテナ選びのためには、その機種の良い面と悪い面の両方を正しく理解することが不可欠です。
この項目では、地デジアンテナとして八木式アンテナを選んだ場合のメリットとデメリットを、実際に数多くのアンテナ工事を行ってきた専門家のご意見を元に、率直に解説していきます。
メリット:今なお「最強」と言われる3つの理由
八木式アンテナが2025年現在も含め、長年にわたり支持される理由は、主に以下の3つの圧倒的なメリットにあります。
- 高い受信性能で安定視聴を実現
- 本体の指向性が高く受信性能が向上し、さらに設置位置が屋根の上など高く障害物に影響されにくいため、他の地デジアンテナ機種に比べて、受信感度(利得)が格段に高いくなるのが最大の特徴です。
- 本体の素子数(受信性能)別モデルも多彩なため、比較的、受信環境のいい「強・中電界地域」はもちろん、到達する電波レベルが弱い「弱電界地域」でも、20素子以上のモデルにより安定した受信環境を構築できます。
- 後述するパラスタックアンテナ(超高性能型)や、地デジ電波でも低めの周波数帯に特化したローチャンネル用モデルを採用することで、微弱電界地域への対応やより受信感度を高めることも可能です。
- 圧倒的なコストパフォーマンス
- シンプルな構造で製造コストが安く、アンテナ本体も他のタイプに比べて安価です。
- また昔から使われ続けているモデルのため、取り付け工事の方法も確立され、工事や設置具などのコストも安価になっています。
- したがって専門業者による設置工事費を含めても、20素子相当モデルの本体や設置具など基本的な機材の料金を含めた工事費用の総額は、22,000円から30,000円程度が相場となり、設置費用の負担を抑えられます。
- 環境に合わせた豊富な選択肢
- 地域の電波状況に合わせて素子数(骨の本数)を選べるだけでなく、弱点である自然環境への弱さを抑えるため、海沿いの塩害や雪の影響にも強い特殊なモデルも存在します。
- 受信感度との兼ね合いを考慮する必要もありますが、壁やベランダの内外など設置位置を工夫することでも、住宅の見た目への影響や、風雨などの影響を抑えることができます。
- このように機種や設置の選択肢が多いため、あらゆるお住まいの環境で最適なパフォーマンスを発揮できます。
デメリット:設置前に知っておきたい4つの注意点
一方で、八木式アンテナの設置をご検討になる際には、以下のような特有のデメリットも考慮する必要があります。
- 家の外観・景観に影響しやすい
- 基本的に八木式アンテナは、受信感度がもっともよくなる屋根の上に設置され、その特徴的な形状が目立つため、現在のスタイリッシュな住宅のデザイン性を損なう可能性があります。
- 前述のように八木式アンテナは周辺の景観にも影響を与えるため、景観地域などでは高い位置に八木式アンテナを設置できない場合もあります。
- 天候(風・雪)の影響を受けやすい
- 金属の部品がむき出しの形で、風雨などを受ける面積も大きいため、台風などの強風でアンテナの向きが変わったり、倒壊したりするリスクがあります。
- 設置から十数年を過ぎて老朽化した八木式アンテナでは、特にトラブルのリスクが高まります。
- 積雪地域では、アンテナ本体に雪がこびりついて機能の低下やサビ、また雪の重みなどの雪害で破損する可能性も考慮しなければなりません。
- 海沿いなどでは潮風の影響を受けて、アンテナ本体の錆が進みやすいことにより、老朽化しやすくなります。
- 鳥害(フン・巣作り)のリスクがある
- 八木式アンテナは鳥が止まりやすい形状のため、フンで屋根や外壁が汚れる、酸性のフンで腐食する、巣を作られるなどのトラブルも考えられます。
- 鳥がとまった際の重みでアンテナの向きがずれてしまうケースも少なくありません。
- 経年劣化によるメンテナンスが必要
- 屋外に設置されて気候の影響を受けやすいのはアンテナ全般に当てはまる問題ですが、八木式アンテナは機器部が露出した構造と屋根の上に設置されることで、雨風や紫外線の影響を受けやすくなります。
- 屋外に設置された八木式アンテナの一般的な寿命は10年から15年とされており、トラブルを避けるためには、ある程度の年数ごとに定期的な点検や、アンテナの交換が必要になる場合があります。
デザインアンテナ・ユニコーンアンテナと徹底比較!あなたに最適なのはどれ?
現在、地デジアンテナの主流は八木式アンテナに加え、壁面に設置する薄型の「デザインアンテナ」や、八木式アンテナと同様、屋根の上に設置されるポール状の「ユニコーンアンテナ」の3種類です。
この項目では、各地デジアンテナの種類(機種)を「性能」「外観」「費用」「耐久性」などの観点から比較し、あなたに最適なアンテナを見つけるお手伝いをします。
【早見表】性能・外観・費用・耐久性を一覧でチェック
まずは、三機種の地デジアンテナをの特徴を以下の一覧でご紹介します。
※上記は各UHFアンテナ機種の主な特徴になります。
八木式アンテナの特長はここまででもご説明してきましたが、日本でテレビ放送(アナログ放送)がはじまった当初、当時のテレビ電波(VHF)を受信できる実用的なアンテナが八木式アンテナのみだったことから、テレビアンテナとして普及しました。
八木式アンテナを後継の地デジアンテナと比べた場合の、その主な特徴は、指向性が高い点になります。
指向性とは、アンテナの正面側にあたる一定範囲のみで受信性能が高くなる性質をいいますが、八木式アンテナは同じ素子数(相当)の他機種と比べても、受信性能を発揮する前方の範囲(半値幅)が狭く、その分だけ、範囲内での受信性能が向上するのです。
このアンテナ前方で電波塔の方向を正確に狙うことで、ノイズを受信しにくくなり、他機種に比べて八木式アンテナは電波の高い受信レベルを実現できるのです。
デザインアンテナ(平面アンテナ)は、アナログ放送から地デジ放送への転換が進められた2009年(平成21年)頃に普及した第二世代の地デジアンテナです。
壁面やベランダな度に設置できるパネル状の薄型アンテナで、地デジ化によりテレビ電波がVHFより波長の短いUHFになったことから、実用的なサイズが実現されたモデルです。
デザインアンテナは八木式アンテナの弱点をカバーするために登場したアンテナともいえ、その特徴は、壁などに目立たず設置でき、カラーバリエーションも豊富で、住宅の外観や景観に悪影響がないこと。そして風雨などの影響にも強く、寿命が15年から20年以上と長くなり、トラブルも生じにくい点です。
一方で、指向性の低さから本体の受信性能が八木式アンテナより弱く、設置位置の低さも受信に不利なことから、設置できるエリアや現場が限られるデメリットもあります。
デザインアンテナは基本的に強・中電界地域向けモデルになるほか、近隣に高層ビルがある、また住宅密集地などで、電波が遮られる現場では使用できないこともあります。
対応できる現場であれば非常にメリットの多いデザインアンテナですが、設置に当たっては事前の電波調査で、安定した受信が実現できるかどうかの確認が重要となります。
ユニコーンアンテナは、2017年(平成29年)にマスプロ電工より登場したポール状の地デジアンテナ「U2CN」の商品名で、地デジアンテナの第三世代とされています。
デザインアンテナの弱点である受信性能の弱さを克服するための進化系モデルともいえ、基本的に八木式アンテナと同じく、屋根の上など高い位置でマストに固定されます。
そのシンプルな外観から、屋根の上など高い場所でも住宅の見た目や景観に影響しにくい、風雨を受け流せる形状で老朽化が進みにくいなど、デザインアンテナとほぼ同等のメリットを備えています。
さらに設置位置が高くなることで、周辺の障害物に影響されにくく、ビルの近隣などでデザインアンテナが対応できない現場でも、問題なく使用できるケースが多くなります。
一方でデメリットとしては、八木式アンテナに比べると受信性能は及ばず、基本的に強・中電界地域向けモデルであること、最新モデルであるため設置費用が他機種より割高なことが挙げられます。
ただ、周辺の遮蔽物などによりデザインアンテナが対応できない現場で、外観性や耐久性にこだわる地デジアンテナ設置をお求めの場合には、非常に有力な選択肢となります。
後悔しない!八木式アンテナの選び方【専門家が教える3つのポイント】
「自宅の環境で、どのアンテナ機種やモデルがもっとも適しているか分からない」
「業者に進められるアンテナのモデルが本当に最適かどうか気になる」
そのような方のために、この項目では、ご自宅に最適な八木式アンテナを、自信を持ってお選びになるための、3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:地域の電波強度に合わせた「素子数」モデルを選ぶ
八木式アンテナの「素子(そし)」とは、上記でもご説明した通り、アンテナの「魚の骨」にあたる短い横棒のことです。八木式アンテナには、主に8素子、14素子、20素子のモデルがあり、この素子の数が多いほど、アンテナの受信感度は高くなります。
お住まいの地域が電波塔からどのくらいの距離にあるか(電波強度)によって、最適な素子数モデルは異なります。以下、現場の電波状況に対応できるモデル一覧です。
※以上はおおまかな目安です。
電界地域とは、地デジ電波塔からの距離と、山地など電波を遮る地形を目安に、到達する電波レベルを目安に、電波塔周辺のエリアを分類したものになります。
分類法や目安は使われる場所で異なる場合もありますが、基本的に電波塔から近く、山地などに電波が遮蔽されにくいエリアの順に、強・中・弱の電界地域に分類されます。
ただ、電界地域に関係なく、高層ビルの陰に当たる一帯などでは、電波が遮られて地デジ受信レベルが大きく低下することもあります。もっとも八木式アンテナは屋根の上に設置されるため、このような障害物の影響を受けにくいアンテナ機種になります。
また同じお住まいでも、障害物の影響を受けにくい屋根の上や、ビルや住宅密集地の隣家などに電波を遮られやすい壁面、ベランダでは受信レベルが異なる場合もあります。
ご自宅の各位置における電波強度は、専門業者が使用する測定器(アンテナレベルチェッカー)で正確に調べることができます。
ただ一般のお客さまでも、インターネット上の「A-PAB 放送エリアのめやす」などのウェブサイトで、大まかなエリアを確認することも可能です。
ポイント2:「ブースター」は必要?判断基準を解説
「ブースター」とは、八木式アンテナを固定するマストの下部など、テレビアンテナのすぐ近くでケーブル配線に接続され、アンテナが受信したテレビ電波を増幅させる装置のことです。
たとえ現場の環境に適切なアンテナ機種を選んでも、以下のようなケースではテレビに届く受信レベルが低下し、テレビの映りが悪くなる場合があり、対策としてブースターの設置が必要になります。
- 複数の部屋でテレビを視聴する場合
- ケーブルの途中で電波レベルを等分に分配することで、テレビ一台あたりに届く電波レベルが弱まるため。
- 通常、戸建住宅内に三台以上のテレビを設置する場合には、電界地域に関係なく、ブースター設置が必須になります。
- アンテナからテレビまでの配線が長い場合
- 住宅が広いなどで、アンテナからテレビまでのケーブル配線が長いほど、電波(映像信号)が減衰するため。
- 弱電界地域などで、受信レベルが基準値ギリギリの場合
- 受信レベルを安定させるため、電波の増幅が必要となります。
お住まいのテレビアンテナにブースターが必要かどうかは、専門業者が電波状況を測定して判断することがもっとも確実です。
ただ現実的には、現代の戸建て住宅ではほとんどの場合、三台以上のテレビが設置されることもあり、新築などの戸建て住宅におけるアンテナ工事とブースター設置は、ほぼセットの工事といえます。
ポイント3:設置環境に合わせた「特殊モデル」も検討しよう
上記でも少し触れましたが、八木式アンテナには基本的な設計のモデルだけでなく、特定の環境に合わせて、対応する性能を高めた特殊なモデルも存在します。
以下のようなモデルの採用により、自然環境への弱さなどのデメリットを補い、より受信感度を安定させるなど、快適な視聴環境を実現できる可能性があります。
※上記は各モデルの主な特徴になります。
パラスタックアンテナは、一箇所の上下左右に素子を固定した「高性能素子」を利用した八木式アンテナ高性能モデルです。28素子や30素子などの多素子モデルもあるため、実質的に数十から百数十素子に値する性能を実現できます。
そのため地デジ電波が微弱な地域でも安定した受信を実現できますが、特に多素子モデルは大型になり、指向性も非常に高くなるため、自然環境の影響による角度のズレなどのトラブルには注意が必要です。
またパラスタックアンテナであれば、5素子モデルでも通常モデルと同様の受信性能をもつため、アンテナを小型化して目立たせないために採用される場合もあります。
ローチャンネル用モデルは、地デジ電波の周波数帯である、UHFの470MHzから710MHzまでの周波数帯の内、470MHzから600MHz程度に特化することで、受信性能を向上させた地デジアンテナです。
地デジ放送では、日本各地のほとんどの電波塔で、上記したやや低めの周波数帯(チャンネル帯)が使われるため、該当する多くのエリアであれば、ローチャンネル用の八木式アンテナを使うことで、より受信感度が安定しやすくなるのです。
八木式アンテナの設置|費用相場と信頼できる業者の見つけ方
受信性能から機種、特殊なモデルなど、お住まいに最適なテレビアンテナを選んだら、最後のステップは「設置工事」です。
ここでは、読者の皆様がもっとも気になるポイント、取り付け工事の費用相場と、安心して任せられる優良な専門業者の選び方を解説します。
アンテナ設置にかかる費用総額の目安(本体+工事費)
テレビアンテナ設置にかかる費用は、「アンテナ本体や機材の代金」と「工事費(作業費)」で構成されます。
作業別の料金体系は業者によって異なりますが、一般的な費用の内訳は以下の通りです。
※上記は主な工事の種類とその費用の目安になります。
DIYは絶対NG?専門業者に依頼すべき5つの理由
アンテナ工事について「少しでも費用を抑えたい」と、ご自身でのDIY設置を考える方もいるかもしれません。
しかし、少なくともお住まいの複数の部屋にテレビ電波を送り、安定したレベルの電波を供給するアンテナ設置工事は、専門的な知識と技術を要する難しい作業です。
特に八木式アンテナの設置では、危険な高所作業を行うケースが大半になるため、専門業者への依頼を強く推奨します。
以下、アンテナ工事のDIY作業についてまわる、主なリスクをご紹介します。
- 高所作業による転落・落下の危険
- もっとも大きなリスクです。機材や家屋、家財の破損だけでなく、命に関わる重大な事故につながる可能性があります。
- 専門知識と専用工具が必須
- 建物の構造や電波に関する知識、レベルチェッカーなどの専門工具がなければ、アンテナを正しく設置できません。
- ミリ単位での精密な方向調整が必要
- アンテナの向きがわずかでもずれると、テレビは映りません。最適な角度を見つけるのはプロでも細心の技術を使って行う作業です。
- 万が一の際の保証がない
- DIYで設置した場合、アンテナの故障や家屋の損傷が起きてもすべて自己責任となります。
- 結果的に高くつく可能性がある
- うまく設置できずに結局は業者に依頼することになったり、屋根を傷つけて修理費が発生したりなど、業者に依頼するより費用が高くつくケースも少なくありません。
作業の安全が確保できるベランダなどにBS/CSアンテナを設置し、一台のテレビに接続するだけなど、シンプルな工事であればDIYが可能なケースもあります。
しかし、お住まい全体のテレビアンテナ工事では、安全・確実性、そして業者の保証などを含めた長期的なコストを考えると、専門業者に依頼することがもっとも賢明な選択といえます。
失敗しないアンテナ工事業者の選び方【あさひアンテナの事例】
大切なお住まいでのテレビアンテナ工事を安心して任せることができる、優良なアンテナ工事業者を見つけるためには、以下のポイントをチェックしてください。
- 料金体系が明確で、現地調査や見積もりが無料か。
- 施工実績が豊富で、公式サイトのブログなどで施工例を公開しているか。
- 下請けを使わない「完全自社施工」であるか。
- 工事完了後「10年」など長期の工事保証があるか。
- 利用者の口コミや評判が良いか。
例えば、本記事にご協力いただいた優秀なアンテナ職人が所属し、関東・関西エリアで年間6,000件以上の施工実績を誇る「あさひアンテナ」は、これらの条件を満たす優良業者の一例です。
完全自社施工による適正価格、経験豊富なベテランスタッフによる高い技術力、そして業界最長クラスの10年保証を提供しており、多くの顧客から信頼を得ています。
事前の電波調査、お見積もりは完全無料(出張料、キャンセル料など諸費用込み)で、相見積もりや即日工事にも対応しています。
このようなサービスの品質が高い業者を基準に、複数の会社から見積もりを取って比較検討されることをおすすめします。
八木式アンテナに関するよくある質問(Q&A)
この項目では、「あさひアンテナ」などアンテナ工事業者に対して実際に寄せられることの多い、八木式アンテナに関するお問い合わせとその回答を、Q&A形式でお答えしていきます。
Q1. 寿命はどのくらい?メンテナンスは必要?
一般的に、屋外に設置される八木式アンテナの寿命は10年から15年が目安です。
ただし、この寿命を過ぎれば必ずアンテナが使えなくなるというわけではなく、20年以上、問題なく使用し続けられるケースも珍しくはありません。
一方で、沿岸部の塩害や豪雪地帯では寿命が10年より短くなる場合もあるなど、設置環境によってアンテナの寿命は変動します。
アンテナの寿命とは、アンテナ本体だけでなく固定用のマストやワイヤーなども含めて、耐久力が低下し、角度がズレるなどのトラブルが生じやすくなる年数と考えてください。
八木式アンテナの場合、寿命を大きく過ぎて老朽化が進むと、アンテナが屋根の上で倒れる、屋根から落下するなどの大きなトラブルも想定されるため、設置から10年を目安に、専門家による点検を受けることをおすすめいたします。
Q2. アンテナの向きはどうやって調べるの?
地デジアンテナを向けるべき、お住まい近隣の電波塔の方向をご自身で知るためには、近隣の家の地デジアンテナがどちらを向いているかを参考にするのがもっとも簡単な方法です。
また、「A-PAB 放送エリアのめやす」などのウェブサイトで、最寄りの電波塔の位置を調べることもできます。
ただし、これらはあくまで目安です。近隣の障害物などの影響も含めて、お住まいのさまざまな位置で最適な受信感度を確認するためには、専門業者が使用する「アンテナレベルチェッカー」という測定器を使った、精密な電波調査が不可欠です。
Q3. 屋根裏やベランダにも設置できる?
地デジアンテナを屋根裏や天井裏に設置することは、条件次第で可能です。
屋根裏や天井裏への設置は、テレビアンテナが外部から見えなくなり、住宅の外観や外装に影響しないほか、アンテナ本体も雨風などの影響を受けなくなり、メンテナンスフリーで寿命が大幅に伸びるという大きなメリットがあります。
ただし、地デジ電波は一般的や屋根材や壁際、断熱材なら透過しますが、透過の際に減衰するため、屋根裏などでも十分な電波レベルを確保できる強電界地域であること、屋根材や断熱材に金属やウレタンなど電波を遮る素材が使われていないこと、アンテナを設置できる十分なスペースがあることなど、いくつかの条件をクリアする必要があります。
なお、基本的に屋根裏などの地デジアンテナ設置には、設置スペースをとらないデザインアンテナが使用されます。
受信性能の関係から八木式アンテナが使用される場合もありますが、設置スペースの条件か厳しくなるほか、専用の設置具などが必要なため設置費用もデザインアンテナと大きな差がなくなります。
ベランダ設置は、八木式アンテナをベランダの手すり、内部空間などに設置する方法です。強電界地域であれば、小型の8素子モデルを軒先から吊り下げる設置も可能です。
ベランダへの設置は、住宅の見た目に影響しにくい、風雨を避けやすくメンテナンスも行いやすいなどのメリットがあります。一方で周辺の障害物などの影響を受けやすく、受信感度が屋根の上よりもやや低くなる可能性もあります。
いずれの場合も、専門業者に電波状況を調査してもらった上で、設置の可否を判断することが確実といえます。
まとめ:最適なアンテナ選びで快適なテレビライフを
今回の記事では、八木式アンテナについて、アンテナ工事のプロによる解説をもとに、その仕組みから選び方、設置方法までを詳しく解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 八木式アンテナは、高い受信性能と優れたコストパフォーマンスを誇る、21世紀のいまなお現役の定番アンテナである。
- 電波が弱い地域や、設置費用を抑えたい場合には、最適な選択肢となる。
- 一方で、住宅の外観や耐候性を重視する場合は、デザインアンテナなども含めてアンテナ機種の検討が必要。
- アンテナ選びでは「素子数(受信性能)」「ブースターの要否」「設置環境」の3つのポイントを押さえることが重要。
- 設置の作業には危険が伴うため、DIYは避け、信頼できる専門業者に依頼することがもっとも安全で確実。
お住まいのテレビアンテナ選びは、ご自宅の電波環境、外観へのこだわり、そしてご予算という3つの要素のバランスを考えることが大切です。
この記事で得た知識を基に、ご自身の優先順位を整理し、お住まいの条件に最適なアンテナを選んでください。
もし迷った場合は、まずは「あさひアンテナ」などの専門業者に無料の見積もりを依頼し、プロの意見を聞いてみることから始めるのが、満足できるアンテナ工事を実現するための一番の近道です。
あさひアンテナでは、フリーダイヤルの他、24時間365日受け付けのメールフォーム、LINEアカウントも用意しているので、アンテナ工事に関する疑問点をお持ちであれば、まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談になることをオススメいたします。