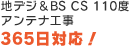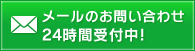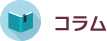テレビが映らないのはアンテナの故障か? 正確な原因を突き止める手順と修理工事の費用、自分でできる対処法・完全解説ガイド
この記事をお読みの皆様は、観たいテレビ番組が始まる時間や、空き時間に何気なくテレビをつけたときに、電源が入っているにも関わらず、テレビ画面が真っ暗で何も映らないといったご経験はないでしょうか?
またはテレビ画面がモザイク状に乱れる、映像が固まるなどして満足に番組を見ることができない。さらには真っ黒な画面に「E202」などの見慣れないエラーコードが表示されると「自宅のアンテナが故障したのでは?」とご不安を覚えられる方も多いでしょう。
しかし、あわてて修理業者を呼ぶ前に、まずは落ち着いてください。
テレビが正常に映らない原因は、実はアンテナの故障以外にもさまざまなものが考えられるのです。
実際にはテレビ本体や周辺の配線などのごくささいなトラブルが原因であるケースの方が多く、配線などの簡単な確認や操作ですぐ直ってしまうことも珍しくはありません。
この記事では、テレビアンテナや受信の仕組みに関する専門知識がない方でも、急にテレビが映らなくなった原因を順を追って突き止め、ご自身でも対処できる方法を分かりやすく解説します。
万が一、本当にアンテナの故障が原因で、アンテナの修理や交換などの工事が必要になった場合でも、記事内で信頼できる業者の選び方や費用の相場をはじめ、確かな技術による修理をできるだけ低価格かつスムーズに進めるための情報を解説します。
本記事の内容は、アンテナ工事のプロ集団である専門業者「あさひアンテナ」に所属する優秀なアンテナ職人に取材を行い、専門知識と現場経験に基づく確かな情報をもとに、テレビ画面の乱れに対する対処法をまとめたものです。
取材および記事の執筆は技術系の知識を持つプロのライターが担当し、難しい技術上の専門知識、専門用語を避け、一般の方でもわかりやすく執筆しています。
いま現在、突然のテレビ画面トラブルに困っておられる方も、本記事の情報を参考に、早急に問題を解決していただければ、筆者としても幸いです。
まずは落ち着いて!アンテナ故障を疑う前に試す6つのセルフチェック
プロのアンテナ職人の解説によると、専門業者が確かな技術で設置したテレビアンテナは、設置から10年以上すぎて老朽化が進んでいるか、よほど大きな災害にでも見舞われない限り、そう簡単にトラブルが生じるものではありません。
もしお住まいで急にテレビの映りが悪い状態になる、映らなくなるなどの問題が起こった場合、その原因は、以下でご紹介するような、ごく初歩的な不具合であるケースが大半を占めるそうです。
したがって、アンテナ修理の専門業者を呼ぶのは、これからご紹介する6つのトラブルの要因と、それに対応する対処法をすべて試してからでも遅くはありません。
これらのチェックひとつで、意外とあっさりトラブルが解消されることもあります。
まずは以下の一覧から、ひとつひとつ確認していってください。
※上記は基本的な確認ポイントになります。
チェック1:テレビ・レコーダーの電源プラグは抜けていないか
余りに基本的すぎて「まさか」と思われる人がいるかもしれませんが、これは意外とよくある原因のひとつです。当たり前すぎることほど、心理的な盲点になってしまうことは、ミステリーの題材に使われることもあります。
お部屋に掃除機をかける、バッテリーを充電するなどで一時的にテレビのコンセントを抜いたまま忘れてしまう、または掃除や模様替えなどの作業中に電源ケーブルを引っ張ってしまったり、ペットがケーブルにじゃれつくなどの要因で、コンセントから電源プラグが抜けかかっていることも考えられます。
まずはテレビ本体と、レコーダー機器を使用している場合はレコーダーの電源プラグも確認してください。
コンセント側だけでなく、機器本体に接続されている部分も、しっかりと端子の奥まで刺さっているか、両方を確認することが大切です。
チェック2:配線ケーブルの抜け・ゆるみはないか
電源ケーブルとほぼ同様の要因で、テレビの裏側にあるチューナー端子や壁のアンテナコンセント端子に接続されているアンテナケーブルのプラグ部が、緩んだり抜けかかったりしていることも原因として考えられます。
ケーブルの端にある「F型接栓」と呼ばれる金属の端子部分を指でつまんで、ネジの部分を時計回りに軽く回してみてください。もし緩んでいる場合は、しっかりと締まるまで回します。
他にも端子に固定されずただ差し込む形式のF型プラグ、プッシュプラグのついたケーブルもあり、この場合は特にケーブルを引っ張った際などに緩みやすくなります。プラグを端子にねじ込むようにして、しっかりと差し直してください。
他にも、ケーブルの部分が家具の下敷きになっていたり、急角度に折り曲げられたりしている場合も、電波の送信不良や断線の原因となるため、配線の状態も合わせて確認してください。
チェック3:B-CASカードは正しく挿入されているか
地上デジタル放送、衛星放送のBSデジタル放送やCSデジタル放送など、デジタル放送の受信に不可欠な「B-CASカード」の接触不良も、テレビが映らなくなる原因です。
B-CASカードはデジタル放送の映像信号に施された暗号化を解除するカードキーのような役割を果たしており、テレビなどデジタル放送受信機の背面、側面などの専用スロットに差し込まれています。
このB-CASカードも長期間、差し込んだままで使用していると、徐々にホコリや湿気でICチップ部分の接触が悪くなり、テレビなど機器側でカードを認識できなくなることがあります。
特にB-CASカードの不具合の場合、映らなくなったテレビ画面に「E100」「E101」「E102」などのエラーコードが表示されることが多くなります。
このような場合は、一度テレビなど機器本体の電源を切り、スロットからB-CASカードを抜いてみてください。
そして、金色のICチップ部分を中心に、カード全体を乾いた柔らかい布で優しく拭いてください。その後、カードの向きを間違えないように注意しながら、あらためてカチッと音がするまで、しっかりとスロットの奥まで挿し直します。
その上で、あらためてテレビなどの主電源を入れて、正常に映るかどうかを確かめてください。
なお、最近の4K、8Kテレビでは、B-CASカードが使用されず、同様の機能を持つ「ACASチップ」が本体に内蔵されているモデルもあります。
このようなモデルで上記のエラーコードが表示された場合、後述するテレビの初期化が効果を発揮することが多くなります。
チェック4:リモコンの入力切替は正しいか
レコーダーやゲーム機、ストリーミングデバイスなど、テレビに外部入力で複数の機器を接続している場合、気づかないうちに入力切替が変わってしまっていることがあります。
試しに、リモコンの「入力切替」ボタンを押してみてください。
メーカーやモデルによって異なりますが、入力切替を押すごとに、画面の上端などに「HDMI 1」「ビデオ」「地デジ」など、各テレビ放送や外部入力に応じた画面が表示されます。(画面に表示された選択肢から選ぶモデルもあり)
ここで「地デジ」や「テレビ」「BS」「CS」などご覧になりたいテレビ放送の画面が正しく選択されているかを確認してください。
チェック5:チャンネルの再スキャン(再設定)を試す
新しいテレビを最初に使う際には、テレビにアンテナケーブルを接続した後、受信できるテレビ電波から各放送局のチャンネル(周波数帯)を確認して、適切なチャンネル番号に当てはめていく「チャンネルスキャン」を行う必要があります。
お引越しで受信できる地デジ電波が異なる場所にテレビを移動した後や、お住まいの地域でテレビ電波の周波数帯変更、放送局追加などの変化があった場合、テレビ本体がチャンネル情報を正しく受信できず、テレビ放送を映し出せなくなることがあります。
この場合は現在、受信できているテレビ電波のチャンネルをあらためて設定し直す「チャンネルの再スキャン(再設定)」を行うことで改善される可能性があります。
基本的な手順は、テレビのメニュー画面から「設定」>「チャンネル設定」などの項目を選び、「チャンネルスキャン」や「再スキャン」を実行してください。
操作方法はメーカーによって異なりますので、テレビの取扱説明書やメーカー公式サイトなども併せてご確認ください。
チェック6:テレビの再起動を試す
テレビ画面が映らないトラブルだけでなく、リモコンで操作しても正しく動作しないなど、テレビ本体の動作不良が見られる場合は、テレビの内部基盤や動作プログラムなどの一時的な不具合が考えられます。
この場合は、テレビの「再起動」と呼ばれる作業を行うと、テレビの内部機器などがリセットされ、不具合が解消されることがあります。
再起動の手順は、一般的にテレビなどの本体にある主電源をオフにし、電源プラグもコンセントから抜いた状態で、数分ほど待ちます。
その後、あらためて電源プラグをコンセントに差し込み、主電源を入れます。
このように一次的にテレビなど機器への給電を断ち、内部基盤などが初期化されることで、一時的な不具合であれば解消されることがあるのです。
またテレビやレコーダーによっては電源ボタン長押し、設定画面からの操作など、独自の初期化・リセットなどの手順があり、こちらも不具合に効果があるケースもあります。
ただ機種や方法によっては、機器の設定や録画内容なども初期化されてしまい、録画が視聴できなくなるケースもあるため、取扱説明書などの内容をよくご確認の上、ご注意ください。
画面の「E202」はアンテナが原因?エラーコード別の対処法
上記のセルフチェックを一通り試しても状況が改善しない場合、テレビ画面に表示されているエラーコードが重要な手がかりになります。
エラーコードとは、テレビなどの受信機器がテレビ放送を映し出せない場合、その原因を自己診断し「なぜ映らないのか」を対応するコードで教えてくれるメッセージです。
このエラーコードは、お客様がトラブルの原因に見当をつける他、業者へのお問い合わせで、現場の状況を伝える上でも大きな手掛かりになります。
この項目では、テレビ画面トラブルで特に多く見られるエラーコードの原因と対処法を見ていきます。まずは以下の一覧をご確認ください。
※エラーコードは上記の他にもさまざまな種類があります。
上記の三種類のコードは、主にアンテナからテレビまで十分な電波が届いていない場合に表示されるエラーコードになります。
現在のテレビなど機器では、コードと同時におおよその原因を示すメッセージが表示されるため、原因特定の参考になります。
ただその一方で、あくまでエラーコードは機器の自己診断であるため、特に上記の3種類など原因が近いエラーコードの場合、実際の原因と表示されるコードにずれが生じる場合もあります。
例えば、電波レベルの低下やまったく届いていないなど「E201」「E202」が表示される場面で「E203」が表示されるなどのケースもあるため注意が必要です。
以下、アンテナから届く電波レベルに関係する、上記の各エラーコードの詳細と、表示される場合の主な原因について解説します。
E202:電波レベル低下のサイン【もっとも多い原因】
「E202」エラーが表示されるトラブルは、テレビが映らない原因としてもっとも一般的に見られるものです。
これは、アンテナからテレビに電波(映像信号)がまったく届いていない、もしくは極めて微弱でテレビ放送を映し出せないことを示しています。
この場合の原因はひとつとは限らず、以下のような原因が複合的に重なっている可能性も考えられます。
- 台風や大雨などの悪天候による一時的な電波の乱れ。
- アンテナの向きが強風などでズレてしまった。
- アンテナケーブルの接続不良や断線。
- アンテナ本体やブースター(増幅器)の故障。
- アンテナ本体の老朽化による倒壊など大きな故障。
E201:電波が弱い・アンテナの向きズレの可能性
「E201」は、アンテナからテレビに届いている電波の強度が弱く、テレビ画面を映し出せない場合に表示されます。
大雨や大雪の際で地デジ放送や衛星放送の電波が乱れ、レベルが低下している場合に、一時的に表示されることもあり、天候が回復すると自然に直ることも少なくありません。
しかし、このエラーが頻繁に表示される場合は、アンテナの向きが少しズレてしまい、受信感度が低下している可能性があります。
また、電波が弱い地域では、電波を増幅する「ブースター」という機器の設置、すでに設置されている場合は増幅レベルの調整などが必要になる場合もあります。
特に地デジアンテナの場合、気候などの変動にも影響されにくい、余裕のある受信レベルの確保が必要なため、悪天候で地デジ放送の画面が頻繁に乱れる場合は、アンテナ機種や設置位置の再考、またはブースター設置などを考える必要があります。
E203:チャンネルが放送休止中
「E203」が表示された場合は、基本的に機器の故障ではありませんのでご安心ください。
これは、単純に選択しているチャンネル(放送局)が放送休止中である、または存在しないチャンネルを選んでいる状態を示しています。
まずはリモコンで他のチャンネルに変えてみてください。
他のチャンネルが問題なく映れば、テレビやアンテナに異常はありません。
それでも直らない…考えられるアンテナ周りの故障原因
以上のセルフチェックも行い、エラーコードも確認したけれど、それでもテレビが映らない状態が改善されない。
この段階に至ると、アンテナ本体やケーブル配線部の周辺機器などに、何らかの物理的な問題が発生している可能性が高くなります。
その場合、アンテナ工事の専門業者、プロのアンテナ職人による専門的な調査が必要になる可能性が非常に高くなります。
ただ、この場合にも、考えられる主な原因を知っておくことで、業者へと相談する際にもスムーズに話を進めることができます。
以下、テレビアンテナや周辺機器の故障で考えられる主な原因の例を解説していきます。
原因1:アンテナ本体の向きのズレ・角度の変化
ほとんどの場合、お住まいのテレビアンテナは、住宅の屋根の上やベランダなどに設置されるため、常に風雨などの自然環境に晒されることになります。
最初にご説明した通り、プロのアンテナ職人が施工したテレビアンテナは、多少の風雨などに影響を受けることはありませんが、長年のご利用では徐々に耐久力が低下します。
そして一般的な地デジの八木式アンテナ、衛星放送のBS/CSアンテナなどでは、設置より10年から15年程度がすぎるとアンテナの寿命を迎えます。
寿命を迎えたアンテナがすぐに故障して使えなくなるわけではありませんが、耐久力の低下により、各部にトラブルが生じやすくなるのです。
特に台風や強風、積雪の重み、あるいはアンテナに鳥がとまった衝撃やフンによる腐食の影響で、アンテナが正面側を向いている方角が、わずかにズレてしまうことがあります。
基本的にテレビアンテナは、アンテナの正面側でのみ受信感度が高まる「指向性(しこうせい)」という性質を持っています。
そのため地デジアンテナは、正面側が近隣の電波塔がある方向に向くよう、左右の角度を調整する必要があります。
さらに衛星放送を受信するBS/CSアンテナは、静止衛星からの直進的な電波をキャッチするため指向性が非常に高く。アンテナでも円盤状のディッシュを上下、左右の角度とも、静止衛星の方向(東経110度・南西方向上空)に向けて正確に合わせる必要があります。
このBS/CSアンテナの角度調整は非常にシビアで、正確な角度から数ミリずれただけでも、衛星放送の電波を正しく受信できなくなってしまうのです。
原因2:アンテナ本体の経年劣化・破損(寿命は約10年~15年)
上記でもご説明した通り、テレビアンテナにも寿命があります。
実際の寿命は機種や設置方法、設置場所の環境にも大きく左右されますが、一般的に、テレビアンテナの寿命は設置より約10年から15年と言われています。
ただ地デジアンテナの種類でも自然環境への耐性が強いデザインアンテナ、ユニコーンアンテナ等であれば、寿命は15年から20年以上になります。
いずれにせよ、テレビアンテナは屋外という過酷な環境に設置されるため、長年の間に固定部をはじめ、各部の部品がサビたり、プラスチック部分が紫外線で劣化して破損したりすることがあります。
これにより、アンテナの角度の狂いや、受信性能の低下などの故障が発生する可能性も高くなってくるのです。
設置から寿命(耐用年数)をすぎたアンテナが故障した場合、修理してもまたすぐに別の箇所が故障する可能性が高くなるため、アンテナごと交換を推奨されるケースが多くなります。
原因3:ブースター(増幅器)の不具合・電源オフ
受信できる地デジ電波が弱い地域や、複数の部屋でテレビを見るために、アンテナで受信した電波を各部屋に分配しているご家庭では、アンテナが受信した電波を増幅する「ブースター」という機器がアンテナ付近に設置されていることがあります。
一般的な屋外用ブースターは、アンテナの付近に本体である増幅部が接続されます。
そして増幅部に電源を供給する電源部は、屋根裏や室内などに設置され、電源コンセントとアンテナケーブルに接続されて、ケーブルを通じて増幅部に給電しています。
このブースター増幅部が故障したり、電源部がコンセントから抜けていたりすると、ブースターが機能しないため、テレビに十分な電波が届かなくなります。
ブースターの電源部は、屋根裏や浴室の天井裏、マルチメディアボックス内などに置かれて、コンセントに接続されていることが一般的です。
一度、電源部の電源ランプが点灯しているか、コンセントに正しく接続されているかを確認してください。
増幅部(本体)については、アンテナの設置位置にもよりますが、屋根の上など高所に設置されていることが多く、調整や交換などにはプロの技術が必要となります。
原因4:分配器やケーブルの劣化・損傷
テレビアンテナが受信した一定レベルの電波を、複数のケーブルを通じて、各部屋のテレビ端子へと均等なレベルに分ける役割を持つのが「分配器」です。
この分配器や、アンテナから分配器、そして各部屋へとつながるアンテナケーブルなどの機材も、経年により劣化します。
これらの機材が劣化すると、送信される電波の漏洩による減衰(弱まり)や、ノイズ混入による電波(信号)品質の劣化が生じ、テレビが正常に映らなくなる要因になります。
特にお住まいの屋外で露出しているケーブルは、紫外線や雨水の影響で被覆が破れ、内部が腐食してしまうことがあります。
このような事態に至ると、電波が正しく伝わらなくなり、テレビが映らなくなる大きな原因となります。
アンテナ修理は自分でできる?DIYの限界とプロに任せるべき理由
ここまでのチェックで、アンテナ本体の角度のズレや故障、ケーブル配線の問題など、アンテナや周辺機器のトラブルである可能性が高くなると、大掛かりな修理が必用になってきます。
そしてお客様の中には、修理の費用を抑えるため、アンテナ修理などの作業を、ご自身によるDIYで検討される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし結論から申し上げると、基本的にアンテナ修理のDIY作業は、決しておすすめできません。
というのも、テレビアンテナの修理には、単なる設置とは異なり、より専門的な知識と技術が必要なことはもちろん、重大な危険も伴うからです。
室内にてテレビ裏のケーブルを交換したり、B-CASカードを差し直したりするレベルであれば、一般の方でも特に問題はありません。
しかし、アンテナ本体が設置されている屋根の上や高所での作業は、絶対に個人では行わないでください。
屋根の上は足場が不安定で、転落すれば命に関わる重大な事故につながる危険性が非常に高くなります。
本記事にご協力いただいたアンテナ職人も、アンテナ工事技術の他に、作業の安全に関する綿密な講習も受け、ヘルメットや安全帯など法令に則った装備を身に着けた上で、最低でも二人体制で工事を行うことを徹底しています。
万全の対策によって、事故のリスクを最小限に抑えることができるのが、本物のプロなのです。
また、アンテナや周辺機器の構造をよく理解しないまま作業を行うと、修理したつもりが、破損部を大きくするなど、症状をさらに悪化させてしまうこともあります。
結果的に専門業者に依頼することになり、最初から修理を依頼するよりもかえって費用が高くついてしまうといった結果にもなりかねません。
安全と確実性を第一に考えるなら、アンテナの不具合については、プロの専門業者へとお任せになるのが最善の選択です。
アンテナ修理はどこに頼む?依頼先3つのメリット・デメリット比較
一般のお客様にとって、身近にアンテナの修理を依頼できる業者は、大きく分けて以下の3種類が挙げられます。
それぞれに業種特有のメリットとデメリットがあるため、ご自身の状況や、修理に当たって何を重視するかによって最適な選択肢は異なります。
まずは以下の比較表を参考に、じっくりと検討してみてください。
※以上は各業者別の主な特徴になります。
以下、各業者のアンテナ修理の特徴に関して、詳しく解説していきます。
アンテナ工事専門業者:高品質で適正価格、迅速な対応が魅力
アンテナ工事を専門に扱っている業者であるため、修理を含めたアンテナ工事の技術力や専門知識が非常に豊富です。
最新のアンテナや配線部の構造、各エリアの電波状況などにも詳しいため、あらゆるトラブルに的確に対応できます。
また専門業者の多くは下請けを使わない「完全自社施工」を行っているため、下請け業者などに必要となる中間マージンが発生せず、工事料金が適正価格に抑えられているのも大きなメリットです。
地域密着で、連絡からの即日対応など迅速に対応してくれる業者も多く、急なトラブルでも安心です。
ただし、業者数が多く、業者によってサービス品質にやや差があり、中には質の低い業者もあるため、信頼できる優良業者を自分で見極める必要があります。
家電量販店・ホームセンター:窓口の安心感と注意点
ジョーシンやヤマダ電機、ケーズデンキ、またはカインズといった、誰もが知っている大手家電量販店、ホームセンターにもアンテナ修理を依頼できることがあります。
このように身近な大手企業に依頼できるという安心感は、それだけでも大きなメリットです。また普段からご利用になっている近隣の店舗であれば、店舗独自のポイントを使ったり貯めたりできる場合もあります。
ただし、重要な注意点として、このような店舗に依頼した場合、実際にアンテナ工事を行うのは店舗や会社のスタッフではなく、店舗と提携している近隣の下請け業者であることがほとんどです。
このような下請け業者は、基本的にアンテナ工事の専門家ではなく、店舗で受け付けるエアコンや家電製品の設置、その他の電気工事を全般的に引き受ける業者です。
そのため、アンテナ工事については専門性が低い可能性もあり、担当する下請け業者によって、施工品質に差が出ることが多くなります。
料金面でも、店舗から下請け業者に依頼する際の仲介手数料など中間マージンが発生し、専門業者へと直に依頼する場合よりも費用が割高になる傾向があります。
さらに事前の見積もりなどで工事をキャンセルした場合も、下請け業者の利益を確保するため、一定の出張料長が発生する場合もあるため、事前の確認が必要です。
また店舗での受付から即日工事が難しく、特にエアコン工事の繁忙期などで業者のスケジュールが埋まっている場合、アンテナ工事の日程が先送りされ、日数がかかるケースも多くなります。
地域の電気屋さん:近くて安心だが費用は割高な場合も
近隣の商店街などにあり、昔から地域に根差している「町の電気屋さん」は、近隣の住人に対してきめ細かなサービスを提供できることが強みです。
電気工事全般についての免許や専門知識もあり、近隣の人々との顔が見える関係性から、お住まいの家電や電気関係について、全般的に相談しやすいという安心感があります。
しかしこのような店舗は、上記した家電量販店などの下請け業者であるケースも多く、アンテナ工事を専門としているわけではありません。したがってアンテナ工事については、使用する機材などが古く、最新の技術や複雑なトラブル、高所作業などへの対応力が十分でない場合もあります。
また工事費用も店主の裁量による部分が大きく、顔見知りであればある程度、割引を受けられるケースがある一方、部品の仕入れコストなどの関係で、全体的な費用が専門業者より割高になる可能性がある点も考慮が必要です。
【料金表】アンテナ修理・交換にかかる費用相場
お客様にとって、アンテナ修理を依頼する際に、もっとも気になるポイントが、アンテナ修理にかかる工事の費用だと思います。
悪質な業者による不当な高額請求を避けるためにも、あらかじめ、修理の作業内容ごとの費用相場を把握しておくことが非常に重要です。
以下の修理工事の料金表はあくまで一般的な目安ですが、業者から見積もりを取る際の参考にしてください。
※上記は一般的な工事業者における費用の平均相場です。
以下では、各工事についての詳細を解説していきます。
アンテナの方向調整:8,000円~15,000円
テレビアンテナ本体に故障がなく、アンテナ正面の向きのズレだけが原因によるトラブルの場合の作業です。
専用の測定器を使って、電波の受信レベルが最大になるようにアンテナの角度をミリ単位で調整します。さらに場合によっては金具などの交換も行って、角度のズレが再発しないよう、しっかりと固定し直します。
工事の料金には、出張費や基本的な作業費が含まれますが、屋根の形状や通常より高い屋根などの場合は、高所作業費が追加されることもあります。
アンテナ本体の交換:15,000円~40,000円(アンテナ本体代込み)
アンテナ本体が経年劣化や破損で寿命を迎えている場合の作業です。
この場合の費用は、新しいアンテナ本体の料金とその設置・調整費用(基本設置工事費)に、古いアンテナの撤去・処分費用を加えた価格になることが多くなります。
アンテナの撤去、処分費用はおおむね5,000円から10,000円程度で、撤去と同時に不要なアンテナの持ち帰り処分も行ってくれるため、お客様は粗大ゴミ処分などの費用や手間を省くことができます。
またテレビアンテナの設置費用については、基本的に新規設置の場合と同じです。
具体的な設置費用は、地デジアンテナでは一般的な八木式アンテナか、主に外壁に設置するデザインアンテナ、屋根の上に設置して双方のメリットを融合できるユニコーンアンテナか、もしくは衛星放送用のBS/CSアンテナかによって本体価格が異なります。
さらに、屋内やベランダ内部など特殊な設置方法を選ぶ場合にも、価格が変動することがあります。
ブースター・分配器など周辺機器の交換:15,000円~35,000円
ブースターや分配器といった、ケーブル配線部に設置されるアンテナまわりのシステム周辺機器が故障した、もしくはケーブルそのものが劣化した場合の交換作業です。
費用には、新しい機器、機材の代金と交換作業費が含まれます。
例えばブースターの場合では、地デジのみ対応のUHFブースターか、地デジと衛星放送に対応して、混合器の機能も持つUHF/BSCS混合型、さらには4K8K型かによって価格が変わってきます。
同じく分配器やケーブルなども、分配数や衛星放送、4K8Kに対応できる品質の機材では価格がやや高くなってきます。
いすれにせよこれらの工事が、アンテナ交換と同時に行うことで、出張費などを一度で済ませることができ、総額を抑えられるケースが多くなります。
修理費用を安く抑えるには?火災保険の活用と相見積もりのコツ
上記の費用一覧から、アンテナの修理にコストがかさみそうと心配になる方も多いと思います。そこでこの項目では、アンテナ修理費用を賢く抑えるためのポイントを2つご紹介します。
その2点とは「火災保険の活用」と「相見積もり」です。
台風や強風、大雪、雹(ひょう)といった自然災害や、近隣の爆発や落下物など想定外の事故によってお住まいのアンテナが故障した場合は、ご加入されている火災保険(住宅総合保険)がアンテナ修理費用に適用される可能性があります。
多くの火災保険には、地震を除くほとんどの自然災害に対応できる「風災・雪災・雹災補償」が付帯していますが、念のためにお住まいの保険の契約書類などをご確認の上、該当する場合は保険会社に連絡してみてください。
なおアンテナ修理の保険申請には、修理を担当した業者による「見積書」や「被害状況がわかる写真」などの書類が必要になります。
また注意点として、火災保険を適用できるのは、あくまで自然災害か想定外の事故によるアンテナ破損である点です。老朽化による自然的な故障などについては、火災保険の適用外になるためご注意ください。
なお、本記事にもご協力いただいた優秀なアンテナ職人が所属する「あさひアンテナ」では、アンテナ修理に伴う火災保険申請のお手伝いも行っています。
同社では保険の専門知識を持つスタッフが常駐しており、アンテナ修理に併せて保険申請に必要な書類、写真などをすべてあさひアンテナ側で用意します。
さらに保険の申請書類作成、保険会社との交渉についても、担当スタッフが万全のサポートでご対応しています。
災害などによるアンテナ故障で、火災保険の適用をお考えのお客様は、あさひアンテナにアンテナ修理、火災保険申請のご相談を合わせてご相談になることがおすすめといえます。
またアンテナ修理をはじめ、各種のアンテナ工事をご依頼になる際は、現地調査や見積りが完全無料の業者を複数お選びになり、すべての業者から見積もりを取る「相見積もり」を行うことをおすすめします。
最低でも2、3社から見積もりを取ることで、お住まいの地域や工事のついての費用相場を把握できて、不当に高額な請求をしてくる業者を避けることができます。
他にも、工事費用だけでなく、施工や機材の品質、工事後の保証などを含めて総合的に最もお得な業者を選ぶことができる、またスタッフの対応などからその業者のお客様に対する姿勢を判断することができます。
あさひアンテナでは、もちろん事前の現地電波調査やお見積もりは完全無料(出張料、キャンセル料などの諸費用込み)で、他業者との相見積もりも歓迎しています。
同社では業界最安に挑む見積もり価格を追求しており、もし他業者であさひアンテナより安い見積もり価格が出た場合には、施工や機材の品質はまったく落とさず、より安い再見積もりにも可能な限り対応しています。
【プロが解説】失敗しない!信頼できるアンテナ修理業者の選び方
数あるアンテナ業者の中から、本当に信頼できる一社を見つけ出すのは大変な作業です。
そこでこの項目では、年間6,000件以上のアンテナ工事を手がけている「あさひアンテナ」のアンテナ職人が、その経験に基づいて、優良なアンテナ工事業者を見極めるための5つのチェックポイントをお教えします。
これらのポイントを押さえて業者をお選びになれば、きっとご満足いただける結果につながるはずです。
Point1:年間6,000件以上など施工実績が豊富か
あさひアンテナの年間6,000件以上など、豊富な施工実績は、それだけ多くの顧客から選ばれ、信頼されている証拠です。
施工実績が豊富な業者は、それだけ多くの現場を経験しているため、さまざまなトラブルに対しても、的確な判断と高い技術力で対応してくれます。
その業者の公式サイトに具体的な施工件数や、ブログなどで写真付きの施工事例が数多く掲載されているかをご確認ください。
Point2:完全自社施工で、熟練の職人がいるか
下請け業者に工事を丸投げせず、すべて自社のスタッフで対応する「完全自社施工」の業者は信頼できます。
責任の所在が明確であり、教育の行き届いた経験豊富な職人が工事を担当してくれるため、技術力もマナーも安心です。
また、下請け業者を使う場合の中間マージンが発生しないため、適正な価格で高品質な工事が期待できます。
あさひアンテナでは、もちろんすべてのアンテナ工事を、本記事にご協力いただいたアンテナ職人をはじめ、優秀な社員スタッフによる完全自社施工にこだわっています。
Point3:業界最長クラスの10年保証などアフターサービスが充実しているか
テレビアンテナの役割は、お住まいに設置されてからが本番と言えます。
前述の通り、アンテナは屋外でさまざまな自然環境の影響を受けて老朽化が進んでいくため、業者による工事後の保証がしっかりしているかどうかは非常に重要なポイントです。
業者の提供する保証期間が長いことは、その業者がそれだけ自社の施工技術に自信を持っている証拠とも言えます。
特に、台風などの自然災害による故障まで保証対象に含んでいる業者は、非常に信頼性が高いと考えていいでしょう。
一礼して、あさひアンテナでは、業界最長クラスである、工事完了日からの10年保証をご提供しています。
Point4:見積もり後の追加料金がない明朗会計か
料金体系が分かりやすく、料金の透明性が高い業者を選んでください。
公式サイトに作業ごとの詳細な料金が明記されているか、そして何よりも、その業者が「見積もり確定後の追加料金は一切なし」と約束しているかを確認してください。
事前に提示された金額以上の請求をされる心配がないため、安心して依頼することができます。
あさひアンテナでも、見積もりのご提示後、原則としてそれ以外の追加工事費用を加算することはない明朗会計を徹底しています。
テレビアンテナ故障に関するよくある質問
ここでは、テレビアンテナの故障に関して、お客様から特によく寄せられることの多い質問に対して、お答えしていきます。
Q. 賃貸マンション・アパートでテレビが映らない場合はどこに連絡?
賃貸物件にお住まいの場合は、まずは本記事で紹介した「セルフチェック」を試してみてください。
それでも改善しない場合は、ご自身でアンテナ業者を呼ばずに、必ず大家さんや物件の管理会社に連絡してください。
その理由は、原因が個人のテレビや配線ではなく、建物全体の共用アンテナ設備にある可能性があるためです。
その場合のアンテナ修理費用は、大家さんや管理組合の負担となるのが一般的です。
先に個人で勝手に業者を手配してしまうと、費用を自己負担しなければならなくなる可能性があるのでご注意ください。
Q. 一部のチャンネルだけ映らない原因は?
すべてのチャンネルではなく、特定のチャンネルだけが映らない、あるいは映りが悪いというケースもあります。
この場合、主に以下のような原因が考えられます。
- アンテナの向きが微妙にズレて、特定の放送局の電波だけをうまく受信できていない。
- お住まいの地域で、そのチャンネルの電波がもともと弱い。
- 放送局側で一時的な電波障害が発生している。
対処法としては、まずテレビの「チャンネル再スキャン」を試してみるのが有効です。
それでも改善しない場合は、アンテナの微調整が必要になる可能性があるため、専門業者に相談することをおすすめします。
特に東京都の東京MX、埼玉県のテレビ埼玉など、その都府県のみを放送範囲としている地方チャンネル(地方局)は、NHK、広域民放とは別の電波塔から送信されているケースもあり、地方チャンネルだけ電波の方向や受信レベルが大きく異なる場合もあります。
そのため電波レベルをある程度、減衰させる「アッテネーター」を使用してすべてのチャンネルが平均的なレベルになるよう調整する他、場合によってはメインの地デジアンテナとは別に、地方局用の地デジアンテナを別個に設置する必要が出る場合もあります。
まとめ:アンテナ故障は原因を正しく見極め、最適な業者に相談しよう
本記事の内容で、突然お住まいでテレビが映らなくなった場合の対処法はご理解いただけたでしょうか。
実際にお住まいで急にテレビ画面のトラブルが生じると、つい動揺してしまうかと思いますが、そのようなときこそ、まずは落ち着いて原因を切り分けることが大切です。
この記事でご紹介した手順を元に、ぜひご自宅で発生しているトラブルの状況と照らし合わせてみてください。
以下、本記事の内容をあらためて簡単にまとめます。
- まずはセルフチェック:電源プラグや配線、B-CASカードなど、ご自身で簡単に確認できる5つのポイントを試す。
- 原因の見極め:エラーコードを確認し、アンテナ周りの問題が疑われる場合は、DIYは避けて専門家を頼る準備をする。
- 信頼できる業者選び:実績・自社施工・長期保証・明朗会計の4つのポイントを基準に、複数の業者を比較、検討する。
もしご自宅での対処で解決できないアンテナトラブルであっても、ほとんどの場合、あさひアンテナなどの専門家の手を借りることで、迅速かつ安全に問題を解決できます。
お住まいでの対処では解決できないアンテナトラブルが生じた際には、まずはあさひアンテナのフリーダイヤルやメールフォーム、LINEアカウントなど、信頼できるアンテナ工事業者のお問い合わせ窓口までご相談になることをおすすめいたします。
優れたアンテナ工事業者をお選びになることで、お住まいのアンテナトラブルを早急に解決してください。