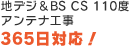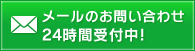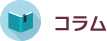テレビのアンテナレベルが低い原因と確認、対処の方法は? 地デジ・衛星放送の受信レベル強度を上げる方法を専門家が徹底解説!
お住まいに各種のテレビアンテナを設置して、地デジ放送やBS放送、CS放送のテレビ番組をご視聴になるのは、長年のご視聴でもコストがかかりません。そのためテレビを見る方法としては、2025年(令和7年)現在でも、もっとも一般的な方法です。
ただその場合、ときに電波の受信環境の変化や、アンテナ本体、または配線部の機器に不具合が起こるなどして、テレビが正しく映らなくなることもあります。例えば、
「自宅でテレビの映りが突然悪くなった」
「地デジ放送と衛星放送、どちらか一方だけが映らなくなった」
「特定の季節や雨が降ったときだけテレビ画面が乱れる」
「テレビで特定のチャンネルだけブロックノイズが入る」
「テレビ放送がまったく映らなくなり、画面に『E202』エラーが表示された」
お住まいで上記のようなトラブルに直面し、インターネットなどで原因を調べていると、必ずといっていいほど「アンテナレベル」という言葉に行き着くかと思われます。
こうした症状の多くは、アンテナレベルが低いことが原因になっているケースも少なくありません。
聞きなれない言葉で、一体どうすればトラブルを解決できるのか、業者に依頼して高い修理費用が掛かるのではないかと、ご不安になられる方もおいでかもしれません。しかし、どうかご安心ください。
アンテナレベルとは、簡単に言えば、アンテナで受信できる、もしくはテレビに届いている電波の強さ(レベル)のことです。このアンテナトラブルの問題は、テレビの視聴トラブルではもっとも一般的な原因のひとつなのです。
この記事では、テレビのアンテナ、放送や電波の専門知識がない方でもご理解いただけるように、アンテナレベルについて、以下の点を網羅的にわかりやすく解説していきます。
- そもそも「アンテナレベル」とはどういうものか。
- アンテナレベルの正常な基準値。
- ご自宅のテレビでのアンテナレベル確認方法。
- アンテナレベルが低下する主な原因。
- ご自身で今すぐ試せるアンテナレベル改善策。
- アンテナレベルの問題で専門業者に依頼すべきケースの見極め方。
アンテナレベルの低下によるトラブルは、多くの場合、簡単な調整で問題は解決します。
しかし、中にはアンテナ本体やケーブル配線部の故障や不具合で、プロの修理業者による、専門的な修理や調整が必要なケースも少なくはありません。
この記事をお読みいただければ、ご自宅でアンテナレベルのトラブルが生じた場合に、トラブルの状況を正しくご判断いただけます。さらにもっとも効率的でコストを抑えた解決策も見つけることができるでしょう。
まずは落ち着いて、ご自宅のテレビで、アンテナレベルを確認するところからはじめてください。
そもそもアンテナレベル(受信レベル)とは?
テレビの「アンテナレベル」とは、一般的には、ご自宅に設置された地デジ用、衛星放送用のテレビアンテナが受信したテレビの電波を、お住まいにあるテレビのチューナーが、どれくらいの強さで受け取っているかを示す数値のことです。
もっと簡単に言えば、アンテナで受信したテレビの電波がケーブル配線部を通じて、お住まいにあるそれぞれのテレビまで届いた時点の、実際の電波レベルを表すものといえます。
アンテナレベルは、他にも「受信レベル」や「受信強度」とも呼ばれ、いわば「テレビに届いている電波の強さや品質を表す成績表」のようなものです。
このアンテナレベル(電波の受信レベル)の数値は、テレビ放送の画面を安定して映し出すため、非常に重要となるものです。
地デジ放送、衛星放送とも、テレビ放送(現在のデジタル放送)では、テレビの映像信号をデジタル信号に変換した後、デジタル信号を電波の波長に変換して送信しています。
各住宅などにあるテレビアンテナで、このテレビ電波を受信した後、同軸ケーブル(アンテナケーブル)を通してテレビなどに受信機器のチューナーまで送ります。
このチューナーで映像信号を抽出し、デジタル信号をあらためてテレビの映像と音声に変換することで、テレビ放送が映し出されています。
したがってアンテナレベルが低すぎると、チューナーに十分な強さや品質の映像信号が届いていないことになります。結果、テレビの映像にブロックノイズ(四角いモザイク状の乱れ)やフリーズ(テレビ画面が静止してしまうこと)が発生したり、ブラックアウトしたテレビ画面に「E202」などのエラーメッセージが表示されて、テレビ放送がまったく映らなくなったりします。
逆に、チューナーに届いた電波レベルが強すぎる場合も、テレビ側で正常に映像信号を処理できず、ノイズの原因となることがあります。
アンテナレベルの単位は、一般的な電波の強さを示す「dB(デシベル)」や、テレビ画面に表示される、各メーカー独自の指標(0から100までの数値など)で表されます。
快適にテレビ放送をご視聴になるためには、このアンテナレベル(電波の強さ)を適切な範囲内に保つ必要があるのです。
地デジ・BS/CS放送を快適に視聴できるアンテナレベルの目安
アンテナレベルとは何であるかについては、ご理解いただけたかと思います。
それでは、地デジ放送、衛星放送でそれぞれ安定したテレビの視聴のためには、具体的にどれくらいのアンテナレベルがあれば良いのでしょうか。
一般的に、テレビのチューナーに届く時点で必要な電波の強さ(dBμV)には、以下のような推奨値があります。
※上記は一般的な目安になります。
ただしこれらの数値(㏈)は、テレビ電波に限らず、一般的な電波の強さを示す単位(数値)であり、主に専門の測定器(レベルチェッカー)で測定される際のものです。
ご家庭のテレビ画面で確認できるアンテナレベルは、上記の通り各メーカーが独自の基準で数値化しているため、メーカーごとの目安を確認することが重要です。
主要テレビメーカー別の推奨アンテナレベル一覧
繰り返しになりますが、テレビで表示できる地デジ・BSの「アンテナレベル画面」については、お使いのテレビメーカーによって、表示の方法や推奨される数値が異なります。
以下に日本の主要なメーカーにおける、テレビのモデル別で、必要となるアンテナレベルの目安をまとめましたので、ご自宅のテレビと照らし合わせてみてください。
※これらの数値はあくまで目安です。またモデルによっては画面の見方や必要な数値が異なる場合もあります。
詳しくはテレビの取扱説明書や、メーカーの公式サイトなどをご確認ください。
「信号強度(電界強度)」との違いは?
アンテナレベルと似た言葉に「信号強度(電界強度)」があります。
これは地デジ放送で、特定の地デジ電波塔において、地デジ電波が届く周辺エリアにおいて、各エリアで地デジアンテナを使って受信できる電波の強さを示す指標です。
地デジ電波(UHF(極超短波)でも470MHzがら710MHzまで)は、電波塔から距離が離れるほど減衰します。また山地などの地形や障害物によっても遮られるため、電波塔の周辺でも地域ごとに電波レベルや信号強度は異なります
主に電波塔周辺の電波レベルは、電波塔から近いほど減衰量が低いために強くなり、電波塔から離れる、また山地などで電波が遮られる地域では弱くなります。
このような受信条件による電波レベルの違いによって、電界地域は、主に以下の三種類に分類されます。
※上記は一般的な分類ですが、電界地域には明確な定義がないため、使われる場所によっては分類の種類や信号強度の基準が異なる場合もあります。
つまり信号強度はアンテナで受信する「入力」の値、アンテナレベルはテレビに届く「出力」の品質と考えると分かりやすいでしょう。
上記の電界地域のうち、弱電界地域では、高性能なアンテナや電波を増幅するブースターが必要になる場合があります。
またこの電界地域は、電波塔からの距離や山地などの影響による大まかな地域の目安でしかないため、例えば強電界地域でも、電波を遮る高層ビルなどの真後ろの一帯や、住宅密集地で家と家の間の狭い空間などには地デジ電波が届きにくくなり、受信レベルが大きく低下することもあるためご注意ください。
【STEP1】まずは現状把握!アンテナレベルの確認方法【メーカー別】
アンテナレベルが低下している原因を探る前に、まずはご自宅のテレビにて、アンテナレベルが現在どのくらいの数値なのかを確認してみましょう。
アンテナレベルの画面は、地デジ(UHF)と衛星放送(BS)によって異なりますが、アンテナレベル画面を表示する操作は、テレビのリモコンだけで簡単に行えます。
ただメーカーによって操作方法が異なりますので、お使いのテレビに合わせてご確認ください。
以下、主な家電メーカーにおけるテレビのモデル別に、アンテナレベル画面の表示方法をご説明していきます。
パナソニック (VIERA)
- リモコンの「サブメニュー」または「便利機能」ボタンを押します。
- 表示されたメニューから「視聴オプション」を選択します。
- 地デジまたはBSの「アンテナレベル」を選択し、決定ボタンを押します。
- 画面にアンテナレベルが表示されます。
ソニー (BRAVIA)
- リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 「設定」または「設定・その他」を選択します。
- 「放送受信設定」に進みます。
- 「アンテナ設定」または「地上デジタル/BSアンテナレベル」を選択すると、レベルが表示されます。
シャープ (AQUOS)
- リモコンの「ホーム」または「設定」ボタンを押します。
- メニューから「(視聴)準備」→「テレビ放送設定」を選択します。
- 「アンテナ設定」を選択します。
- 地デジまたはBSの「電源・アンテナレベル」または「受信強度表示」を選択すると、レベルが表示されます。
東芝 (REGZA)
- リモコンの「設定」ボタンを押します。
- 「放送受信設定」または「視聴準備」を選択します。
- 「地上デジタル設定」または「BS/CSデジタル設定」を選択します。
- 「アンテナレベル」を選択すると、確認画面が表示されます。
その他のメーカーの場合
上記以外のメーカー(三菱、日立など)や、また上記メーカーのテレビでも、モデルによって操作方法が異なる場合があります。
その際は、テレビ本体に付属している取扱説明書をご確認ください。
もし取扱説明書が見当たらない場合は、メーカーの公式サイトにある商品の公式ページやサポートページで、お使いのテレビの型番を検索すると、電子版の取扱説明書を閲覧できます。
【STEP2】アンテナレベルが低い・0になる主な原因9選
テレビのアンテナレベルを確認して、安定した受信に必要な推奨値よりも低いことがわかったら、次はその原因を探っていきます。
実際の原因は、テレビ本体周りのごく簡単なもので、お住まいへの簡単な対処で解決できるものから、アンテナや周辺機器、放送電波そのものの問題で、プロのアンテナ工事業者による専門的な対応が必要なものまで、さまざまなものになります。
ご自宅の状況に当てはまるものがないか、以下の各項目をひとつずつ確認してみてください。
原因1:ケーブルの接続不良・抜け・断線
もっとも基本的で、意外と多い原因が、室内のアンテナケーブル(同軸ケーブル)の接続トラブルです。
テレビの裏側にあるアンテナ端子や、壁のアンテナコンセントの端子、レコーダーの接続端子の接続部分が緩んでいたり、ケーブルが抜けかかっていたりしないかを確認してください。
また、アンテナケーブルは断面が円の状態を保っていないと、電波を正常に送信できないことがあるため、ケーブルが家具の下敷きになっていたり、曲げ半径を越えて急激かつ強く折り曲げられていたりいないかも確認してください、このような場合、ケーブルが内部で断線して使えなくなっている可能性もあります。
原因2:B-CASカードの接触不良や不具合
現在のデジタルテレビ放送(地デジ・BSCSとも)を視聴するために不可欠なカードキーともいえる「B-CASカード(または一部の4K8Kテレビに内蔵されるACASチップ)」が、テレビなどの受信機器で正しく認識されていないと、アンテナレベルが正常でもデジタル放送のテレビ画面は映りません。
B-CASカードはテレビやレコーダーなど受信機器(テレビの場合は側面や裏面など)にあるスロットに挿入されています。このカードが正しくスロットに奥まで挿入されていない、ICチップ部分にホコリや汚れが付着するなどすると、接触不良でテレビ側がカードを認識できない場合があります。
原因3:テレビやレコーダーの一時的な不具合
テレビやレコーダーも精密な電子機器のため、長時間、使用していると内部の基盤やプログラムが不安定になり、一時的な不具合を起こすことがあります。
この場合、受信機器本体に問題があるため、アンテナからの電波が正常でも、テレビ画面や受信レベルが正しく表示されないことがあります。
原因4:アンテナの向きのズレ
屋根の上やベランダなどに設置されている地デジや衛星放送のアンテナには、アンテナの真正面側でのみ受信感度が高まる「指向性(しこうせい)」という性質があります。
そのため、アンテナの正面側を、地デジ電波塔や静止衛星の方向へと正確に向けることで、受信感度がもっとも高くなります。
しかし、アンテナの長期使用による老朽化をはじめ、台風などの強風や積雪の影響、鳥がとまった衝撃、地震などで、アンテナの角度がわずかに向きがズレてしまうことがあります。
その結果、アンテナの正面側が最適な角度から外れてしまい、電波の受信レベルが低下してしまうこともあります。特に、衛星放送を受信するBS/CSアンテナは、光のように直進的な電波をキャッチするため指向性が非常に高く、ディッシュ・放物面反射器(皿のような円盤部)を上下・左右を静止衛星の方向へ向けた角度が、数ミリずれただけでも受信レベルが大幅に低下、あるいは0になってしまいます。
原因5:アンテナ本体や周辺機器の劣化・故障
屋外に設置されているアンテナは、雨風や雪、海沿いの潮風、日光や紫外線などにさらされ続けているため、設置からの歳月と共に劣化していきます。
一般的にアンテナの寿命は、八木式アンテナやBS/CSアンテナで約10年強と言われています。この寿命が過ぎたアンテナが必ず故障するわけではありませんが、寿命を過ぎたアンテナは、角度のズレをはじめ、本体のサビや破損、ケーブルの被覆の破れなどが生じやすくなり、受信性能が低下することもあります。
また、アンテナからテレビまでのケーブル配線部に設置される、テレビ電波を増幅するブースターや、電波を分ける分配器といった周辺機器に、故障や不具合が生じている可能性も考えられます。
原因6:周辺環境の変化(建物の建設・樹木の成長)
テレビアンテナを設置した当初は問題なくても、その後、近隣に高層マンションが建設されたり、庭の木が大きく成長したりすることで、電波塔や衛星からの電波が遮られてしまうことがあります。
これは「遮蔽(しゃへい)障害」と呼ばれ、受信レベル低下の大きな原因となります。
特に衛星放送の場合、静止衛星から送られる電波は「12GHz帯(周波数帯が12GHz前後)」と呼ばれ、波長が25ミリ程度と短く、光のような直進性を持っています。
そのため、BS/CSアンテナを静止衛星の方向へと正確に向ける際、静止衛星から電波がまっすぐ届くその方向に、山や建物などはもちろん、木やその枝、干されている洗濯物など、わずかな障害物があっても、アンテナに影が落ちるような形になり、受信レベルが大きく下がることがあります。
原因7:悪天候(大雨・大雪・強風)による影響
大雨や大雪の際にテレビの映りが悪くなるのは、雨粒や雪が電波を吸収・散乱させてしまう「降雨減衰」「降雪減衰」という現象が原因です。
地デジ放送の場合は、大雨や大雪に電波が吸収されて受信レベルが低下するほか、季節による空間の状態(湿度や空気の膨張)によっても電波の伝わりやすさが変化し、一年を通して一定の電波レベルの変動が生じます。
衛星放送の12GHz帯の電波は、通常の気候、天候の影響は受けにくくなっていますが、大粒となる激しい雨や雪では、短い波長の吸収や散乱が生じて、アンテナ名側での受信レベルが大きく低下します。
この降雨減衰、降雪減衰は一時的な現象で、天候が回復すれば受信レベルも元に戻ることがほとんどです。ただ地デジ放送で気候、天候の影響を受けやすい場合は、より受信性能に高いアンテナや、受信しやすい位置への変更、ブースターの設置などで、気候や天候による電波レベル変動にも影響されない、余裕のある電波レベルを確保する必要があります。
原因8:分配器による電波の減衰
お住まいの複数の部屋にあるテレビの映り具合が違う。例えばリビングのテレビは映るのに、寝室のテレビだけ映りが悪いといったケースでは、ケーブル配線部にある分配器が関係している可能性があります。
分配器はお住まいのテレビアンテナから送られる電波を複数の部屋に分けるための機器ですが、元の電波レベルを等分に分けて分配しているため、各部屋に送られる電波レベルは元の電波の数分の一(分配数によって変わる)になり、分配数が増えるほど各部屋にあるテレビに送られる電波レベルは弱くなります。
テレビの台数を増やしたタイミングでテレビ画面の映りが悪くなった場合は、この原因が考えられます。またテレビ電波は、長いアンテナケーブルを送られるほど減衰していくため、お住まいにアンテナから遠くケーブル配線が長い部屋があると、その部屋だけテレビ画面が乱れやすくなることがあります。
原因9:お住まいの地域が電波の弱いエリア(弱電界地域)
前述のように、お住まいの場所が地デジの電波塔から遠かったり、山や丘に囲まれていたりすると、そもそも受信できる電波が弱い「弱電界地域」である可能性があります。
他にも電界地域を問わず、高層ビルや隣家など障害物の影響によって、お住まいの受信レベルが低下することもあります。
この場合、標準的なアンテナでは十分な受信レベルを確保できないため、高性能なアンテナやブースターを設置する、またはお住まいでも屋根の上など障害物に影響を受けにくく、受信感度が高まりやすい高所への設置が必要になります。
【STEP3】自分で試せる!アンテナレベルを上げる応急処置7選
アンテナレベル低下の原因について、その見当がついたあとは、まずはご自身でもできる簡単な対処法を試してみてください。
アンテナ工事の専門業者を呼ぶ前に、以下の方法で意外と簡単に改善するケースも少なくありません。
作業の安全にはくれぐれも注意しながら、簡単なものから順番に試してみてください。
対処法1:テレビ・レコーダーを再起動する
テレビなど受信機器の一時的な不具合が原因の場合、機器のの再起動によってリセットすることで、不具合が改善することがあります。
- テレビやレコーダーの主電源を切ります。
- 機器の電源プラグをコンセントから抜きます。
- そのまま1分から数分ほど待ちます。
- 再度、電源プラグを差し込み、電源を入れます。
テレビの再起動(リセット)とは、機器本体の通電を一時的に断って初期化することで、内部基盤などの不具合を解消する作業になります。
ただテレビやレコーダーなどの機器によっては、電源ボタンの長押しなど、独自のリセット方法もあるため、機器の取扱説明書、公式サイトなどの確認して、専用のリセット方法があれば、そちらも試してみてください。
対処法2:B-CASカードを差し直す
B-CASカードのトラブルでデジタル放送が映らない場合は、まずは以下の方法でカードの接触不良を解消してください。
- テレビの電源を切り、B-CASカードをスロットから抜きます。
- カードの裏面にある金色のICチップ部分を、乾いた柔らかい布で優しく拭きます。
- カードの向きを確認し、奥までしっかりと差し直します。
- テレビの電源を入れ、映りを確認します。
B-CASカードのトラブルの場合は、テレビ画面に「E101」「E201」「E203」のエラーコードが表示されることが多くなります、
またB-CASカードそのものが破損している場合は、カードを発行している「B-CAS社」の公式サイトに問い合わせて、有償でカードを再発行することが必要です。
なおACASチップを内蔵する4K、8Kテレビで同様のトラブルが発生した場合は、上記したテレビの再起動を試してください。
対処法3:アンテナケーブルを接続し直す
室内のアンテナケーブル接続部の緩みで、十分な電波が送られていないことが原因でないかどうかを確認します。
- テレビの電源を切ります。
- テレビ本体、レコーダー(使用している場合)、壁のアンテナ端子に接続されているすべてのアンテナケーブルを一度抜きます。
- それぞれの端子にホコリなどがないか確認します。
- ケーブルの芯線が折れ曲がっていないか確認し、各端子にまっすぐ、しっかりとねじ込む(または差し込む)ように接続し直します。
またアンテナケーブルを急角度に折り曲げている、家具や家電の下敷きになっているなどの状態があれば、それらを解消します。もしケーブルが断線しているようなら、新しいケーブルに交換してください。
対処法4:チャンネルを再スキャン(再設定)する
テレビなどの受信機器を最初に使用する際、また引っ越しで受信する電波塔が変わる、チャンネルの周波数帯再編や放送局追加など受信できるチャンネル情報が変わった際には、テレビで「チャンネルスキャン(初期スキャン・再スキャン)」を行って、テレビにチャンネル情報を登録する必要があります。
このチャンネル情報が更新されていないことで、一部のチャンネルが映らないケースもあるため、再スキャンによって、受信しているチャンネル情報を最新の状態に更新します。
一般的なテレビ機器におけるチャンネルスキャンの方法は、おおよそ以下の通りです。
- リモコンの「メニュー」や「設定」ボタンを押します。
- 「チャンネル設定」や「放送受信設定」などの項目を選択します。
- 「地上デジタル自動設定」「チャンネルスキャン」などを選択し、画面の指示に従って実行します。
- お住まいの地域を選択し、スキャンが完了するまで待ちます。
メーカーやモデルなどによる、正確なチャンネルスキャンの方法が不明の場合は、やはりテレビの取扱説明書やメーカー公式サイトをご確認ください。
対処法5:ブースターの電源を確認・再投入する
ご自宅のアンテナ配線部にブースター(増幅器)が設置されている場合は、その電源部を確認します。
一般的なアンテナブースターでは、本体である増幅部はアンテナの近くに、増幅部に電源を供給する電源部は、配線部でもテレビの近くや分配器の周辺、屋根裏などに設置されていることが多くなります。
ブースター電源部の確認は、主に以下の手順で行います。
- ブースター電源部の電源プラグがコンセントにしっかり刺さっているか確認します。
- 電源ランプが点灯しているか確認します。消灯している場合は、コンセントを差し直したり、電源を入れ直したりしてみてください。
- 屋根裏など確認が難しい場所にある場合は、無理せず専門業者に相談してください。
また増幅部の不具合や増幅レベルの調整不足で、お住まいに必要な電波レベルが確保できていない可能性もあります。ただ増幅部は屋根の上や壁面の高所などのアンテナ付近に設置されていることが多く、また適切な調整には周辺の電波レベル確認など専門的な知識、機材を用いた作業が必要です。
ご自宅での作業が難しい場合は、無理をなさらずアンテナ工事の専門業者にお任せください。
対処法6:分配器の接続先を変えてみる
これは、お住まいに複数台のテレビが設置されており、特定のテレビだけ映りが悪い場合に有効な問題の切り分け方法です。具体的な方法は以下の通りです。
- 分配器の「出力」端子に接続されているケーブルを特定します。
- 映りが悪いテレビにつながるケーブルと、正常に映るテレビにつながるケーブルを差し替えてみます。
- 差し替えたことで映りが改善した場合、分配器の特定の出力端子が劣化している可能性があります。
お住まいの分配器は、主にお住まいの屋根裏や天井裏、マルチメディアボックスなどに設置されていることが多くなります。ご自宅での確認が難しい場合は、やはりアンテナ工事の専門業者にお任せください。ア
またアンテナからテレビまでのケーブルケーブル配線が長すぎる場合も、テレビ電波が減衰して、その先のテレビだけでテレビ画面が乱れる要因になります。この場合の対策は後の項で詳しく解説します。
対処法7:【上級者向け】アンテナの方向を微調整する
※この作業は事故やアンテナ不具合の悪化などの危険を伴うため、ベランダの手すりなど、作業の安全が確保できる場所にアンテナが設置されている場合にのみ、自己責任で行ってください。屋根の上など、事故の危険性が高い場所にあるアンテナの調整は、絶対に行わないでください。
これは前述した通り、お住まいにある地デジや衛星放送のアンテナが、最適の角度からズレることで生じた受信レベル低下について、適切な角度(向き・方向)にアンテナを調整し直すことで、アンテナレベルを回復する方法です。
具体的な手順は、おおよそ以下の通りです。
- 二人一組になり、一人がテレビのアンテナレベル画面を確認し、もう一人がアンテナを調整します。
- アンテナを固定しているナットを少しだけ緩めます。
- アンテナの向きを上下左右に1、2ミリずつ、非常にゆっくりと動かします。
- テレビを見ている人からアンテナレベルがもっとも高くなる位置を教えてもらい、その位置でナットをしっかりと締めて固定します。
この作業では、地デジアンテナの場合は、電波塔のおおよその方向に左右の角度(方位角)を合わせるだけですみますが、BS/CSアンテナの場合は、静止衛星のある東経110度(南西上空)に、ディッシュの左右、上下(仰角)をミリ単位で正確に合わせる、緻密な作業が必要になります。
またアンテナの角度調整では、少し角度を動かした後、テレビのアンテナレベル画面で受信レベルが反映されるまでに数秒の時間差が出るため、ミリ単位で角度を調整した後、その角度のアンテナレベルに反映されるまで待ち、さらに角度を調整して最大値を見出すという、地道で根気のいる作業が必要です。
後述する簡易的なアンテナレベルチェッカーを使えば、角度調整からすぐレベルの変化を確認できる上、アンテナ角度調整の担当者が手元でレベルを確認できるため、一人でも角度調整が楽に行えます。
ただいずれにせよ、屋根の上にアンテナがあるなど、ご自身での角度調整が難しい環境の場合はもちろん、確実な作業に自信が持てない場合は、決してご無理はなさらず、アンテナ工事の専門業者にお任せください。
ケース別!こんな時はどうする?
この項目では、ここまででご説明した一般的な原因や対処法には当てはまらない、やや特殊なケースとその解決策をご紹介します。
特定のチャンネルだけ受信レベルが低い・映らない場合
特に地デジ放送の場合、すべてのチャンネルではなく、一部のチャンネルだけ映りが悪いというケースは珍しくありません。
これは、放送局の電波塔ごとに電波の周波数や送信方向が異なるために起こります。
地デジ放送では前述の通り、放送信号を送る電波として、UHFのうち一定の周波数帯を使用しています。この周波数帯を6MHzずつのチャンネルに分け、このチャンネルを各放送局に割り当てています。
しかし同じUHFの電波でも、周波数帯が高いチャンネルほど、空間やケーブルを伝わる際に減衰しやすいという性質があります。そのため、電波塔からお住まいの地デジアンテナ、屋内のテレビまでに地デジ電波が届いた際、周波数帯の高い一部のチャンネルだけ、電波レベルが低下して画面が乱れるケースがあるのです。
また、特に全国で視聴できるNHK、広域民放と、特定の都府県でのみ放送を行う地方チャンネル・地方局(例えば東京都の東京MX、千葉県の千葉テレビ、兵庫県のサンテレビジョンなど)では、送信される電波塔が異なる場合があります。
通常、地デジアンテナの設置では、NHKや広域民放の受信を中心にアンテナ角度を調整します。
しかしお住まいから見てNHK、広域民放の電波塔と、地方チャンネルの電波塔が、距離、方向とも大きく異なる場合は、NHK、広域民放と、地方チャンネルの電波レベルが大きく異なる場合は、NHK、広域民放に比べて、地方チャンネルの受信レベルが大きく異なる場合や、地方チャンネルが受信できないケースも出てきます。
上記のような問題がある場合、まず地デジアンテナの方向を調整して、すべてのチャンネルがバランスのいいレベルで受信できるように、専門的な技術とアンテナレベルチェッカーを用いて、的確に調整することが対策になります。
他にもブースターによる電波レベルの増幅や、逆にある程度、電波レベルを減衰させる「アッテネーター(減衰器)」という機器を取り付けて、強すぎるチャンネルの電波レベルをやや弱めるという対策が取られます。
他にも、広域民放・NHKと地方チャンネルの電波塔の方向が違い過ぎて、一基の地デジアンテナでは受信が難しい場合、ビルなどに反射したり乗り越えて広がったりした際に、方向が変わった地デジ電波(反射波・回折波)を探し出して受信するという方法もあります。
ただそれでもすべてのチャンネルの安定した受信が難しい場合は、NHK・広域民放の主な地デジアンテナとは別途に、地方チャンネルの電波塔に向けた、地方局用の地デジアンテナを設置することが必要になります。
2階のテレビだけ映りが悪い場合
前述の通り、お住まいの地デジアンテナから遠い部屋ほど、ケーブルの長さから電波が伝送される途中の減衰(損失)量が大きくなります。
例えば1階のテレビは問題ないのに2階のテレビだけ映りが悪いといった場合、2階までの配線が長いため電波レベルが弱まっていることが考えられます。(これはあくまで一例で、住宅の構造によっては、必ずしも一階より二階まで配線が長いとは限りません)
この場合には、アンテナ直下により強力なブースターを設置して全体の電波レベルを底上げする。または映りが悪い部屋のテレビの前に、小型で手軽に利用できる「室内用ブースター」「ラインブースター」を追加設置することで、その部屋のみの電波レベルを改善できる可能性があります。
アンテナレベルが高すぎる場合(80dBμV以上)の対処法
テレビなどのチューナーに入力される電波は弱すぎても問題ですが、逆に強すぎてもテレビの許容範囲を超えてしまい、映像が乱れる原因になります。
これは電波塔が非常に近い「強電界地域」で、高性能なアンテナやブースターを使用して、高いレベルのテレビ電波を確保している場合に起こりがちです。
この場合の対処法は、以下の通りです。
※上記は基本的な対処法になります。
ブースターは悪天候による電波レベルの低下なども考慮して、室内すべてのテレビで十分な電波レベルが確保できるように、増幅レベルを調整します。しかしお住まいの構造によっては、そのために、一部のお部屋で到達する電波レベルが強くなりすぎる、というケースも考えられます。
この場合は上記の通り、アッテネーターセッツが対策となります。また近年のテレビなど受信機器には、チューナーに入力される電波レベルをある程度、減衰させるアッテネーター機能がついているものもあり、この機能を作動させることも、同様の対策となります。
【STEP4】改善しない場合はプロに相談!業者依頼の判断基準と費用相場
ここまで紹介した方法を試してもテレビの映りが改善しない場合は、ご自身での対処が難しい原因が潜んでいる可能性が高くなります。
アンテナ本体の故障や屋根上での作業、専門的な測定器が必要なケースなど、ご自分で無理に対処しようとすると、転落など事故の危険が伴う、またはアンテナなど機材をさらに破損させて、状況を悪化させてしまう危険性もあります。
お住まいでのテレビ受信トラブルについて、以下のサインが見られる際は、迷わずテレビアンテナの修理・調整に対応できるプロのアンテナ専門業者へと相談ください。
業者に依頼すべき5つのサイン
- 高所での作業が必要な場合
屋根の上や壁面の高い位置に設置されたアンテナの点検や調整は、十分な技術や装備のない一般の方では、転落事故などのリスクがあり非常に危険です。 - 原因が全く特定できない場合
ここまででご紹介したすべて対処法を試しても状況が改善しない場合、複合的な要因など、専門家でないと特定できない原因である可能性が考えられます。 - アンテナや周辺機器が10年以上経過している場合
機器の寿命による故障の可能性が高く、交換には専門的な知識と技術が必要になります。 - ブースターの設置や分配器の交換が必要な場合
適切な機器の選定や設置場所、調整方法の見極めには、やはり電波やアンテナ機器に関する専門知識が不可欠です。 - 台風や大雪、地震の後に映らなくなった場合
テレビアンテナの向きが大きくズレたり、破損したりしている可能性が高く、この場合も専門家による点検が必要です。
アンテナ修理・交換にかかる費用相場
アンテナ工事業者へ依頼する際に、お客様がもっとも気にされる点が、テレビアンテナの各種修理にかかる費用だと思われます。
この項目では、お客様が安心してご依頼になれるよう、アンテナ修理・調整など作業内容ごとの一般的な費用相場をまとめました。
ただし、これはあくまで目安であり、使用する部材や現場の状況、担当する業者によっても、実際の工事費用は変動します。
※上記は主な修理・調整の種類になります。現場の状況によっては、複数の工事の組み合わせや、その他、特殊工事費が加算されるケースもあります。
失敗しないアンテナ専門業者の選び方
アンテナ工事業者も数が多く、優良な業者も多い一方で、中には下請け業者を使うため、中間マージンで余計な費用が掛かり、施工の技術や時期が安定しない業者、さらには不当な高額料金を請求する悪質な業者も存在します。
安心して任せられる優良な業者を選ぶためには、以下のポイントを確認してください。
- 料金体系が明確か:工事費、部材費、出張費などの内訳がはっきりしており、作業前に必ず見積もりを提示してくれる業者を選んでください。特に複数の業者に見積もりを出し、比較検討の上で最適の業者を選ぶ「相見積もり」がおすすめです。
- 豊富な実績と良い口コミがあるか:公式サイトの施工事例や、第三者の口コミサイトなどで評判を確認することが重要です。
- 長期保証があるか:工事後のトラブルに対応してくれる長期保証(8年〜10年が目安)があると安心です。
- 現地調査と見積もりが無料か:正式にご依頼になる前に、無料で現地調査や見積もりを行ってくれるか、相見積もりに対応しているかどうかを確認してください。
- スタッフの対応が丁寧か:電話やメールでの問い合わせに、専門用語を使わず分かりやすく丁寧に答えてくれるかも、業者の姿勢を見極める上で大切な判断基準です。
アンテナの受信レベルでお困りならあさひアンテナへご相談ください
アンテナやテレビ受信のトラブルに関して「自分で試したけど直らない」「原因が特定できなくて不安」「テレビアンテナの修理はどこに頼むのかわからない」などの問題でお悩みの際には、ぜひ当あさひアンテナまでご相談ください。
弊社は、アンテナ工事のプロフェッショナルとして、お客様のテレビ視聴に関するあらゆるお悩みを解決いたします。以下、弊社の強みについてご紹介します。
強み1:年間6,000件以上の施工実績と顧客満足度99%
あさひアンテナは関東・関西エリアを中心に、年間6,000件以上のアンテナ工事を手掛けています。
豊富な経験と高い技術力で、お客様からは満足度99%という高い評価をいただいております。
この数字が、私たちの信頼の証です。
強み2:経験10年以上のベテラン技術者が最新機材で対応
弊社の工事は、業界歴10年以上の経験豊富なベテラン技術者が担当します。
完全自社施工により余計なコストをカットして、高品質な工事を低価格でご提供いたします。
電波状況を正確に測定する「スペクトラムアナライザ」などの最新機材を駆使し、目に見えない電波の問題を的確に診断。
どんな難易度の高い状況でも、最適な解決策をご提案いたします。
強み3:安心の10年保証と24時間365日のアフターサポート
弊社の各種アンテナ工事には、安心の「10年保証」が付帯しています。
万が一、工事後に不具合が発生した場合でも迅速に対応いたします。
またお客様からのお問い合わせには、フリーダイヤルのほか、弊社メールフォーム、LINEアカウントでも24時間365日受け付けており、いつでもお客様の不安に寄り添える体制を整えております。
強み4:電波調査・お見積もりは完全無料!
「とりあえずトラブルの原因だけ知りたい」「修理の費用がどれくらいかかるか不安」という方もご安心ください。
当あさひアンテナでは、現地での詳しい電波調査とお見積もりを完全無料で行っております。
調査後、お見積もりにご納得いただけない場合は、費用は一切かかりません。
まずはお気軽にお問い合わせください。
実際の工事についても、アンテナや機材の設置に関しては、国内大手メーカー製の高品質機材や必要な部材をセットにした低価格の工事費用でご案内しております。
その他、修理、調整や追加工事などの価格体系、使用する機材のメーカー、モデルも弊社サイトで明確に記載しており、お客様には料金や工事品質の面でもご不安がないよう努めております。
アンテナ受信レベルに関するQ&A
最後にアンテナ受信レベルに関して、お客様からよくいただくご質問にQ&A形式でお答えします。
Q1. レベルチェッカーは自分で購入したほうがいいですか?
A. 一般のご家庭では、必ずしも購入する必要はありません。
レベルチェッカーはプロ用の測定器で、数万円と高価なものが多く、使用頻度も限られます。
アンテナの方向調整など、年に一度あるかないかの作業のために購入するのはコストパフォーマンスが高いとは言えません。
正確な測定と調整が必要な場合は、専門業者に依頼するのがもっとも確実で効率的です。
ただ前述の通り、アンテナレベルチェッカーには、アンテナケーブルに接続する簡易的な製品もあり、このような製品は、地デジ用・BS/CS用の各機器で1,000円台からで購入できます。
お住まいでベランダなど安全に作業を行える位置に、デザインアンテナやBS/CSアンテナなどをDIYで設置する場合や、角度調整を行う場合には、このような機器がたいへん役に立ちます。
Q2. ブースターとアッテネーターの違いは何ですか?
A. 上記でも少し解説いたしましたが、役割が正反対の機器です。
それぞれの役割を以下の表にまとめました。
ご自宅の電波状況に合わせて、適切な機器を使用することが重要です。
ブースターは電波を増幅する電子機器のため、機構が複雑で価格も高くなります。一方、アッテネーターはケーブルに接続して、抵抗によってある程度、電波レベルを低下させる機器です。そのため小さな筒状の電源も必要ないシンプルな構造で、価格も比較的、安価になります。
Q3. 4K/8K衛星放送の受信レベルが低いのですが…
A. アンテナや配線機器が、衛星放送の4K/8K放送に対応していない可能性があります。
4K/8K放送は、従来の2K衛星放送に使われていた電波、右旋円偏波とは異なる、左旋円偏波と呼ばれる電波を使用しています。
この左旋の電波は、BS/CSアンテナで受信された後、ケーブルに送信される際に、従来の右旋の電波よりも高い周波数帯で送信されます。
そのため、右旋の4K/8K放送を受信するためには、BS/CSアンテナが2K4K8K(右旋・左旋)対応である必要があるほか、配線部のケーブルやブースター、分配器、壁のテレビ端子など、電波の通り道にあるすべての機器が「4K8K(3224MHz)対応」の製品である必要があります。
これらの機器に、ひとつでも4K8K未対応の機器があると、そこで左旋の電波が著しく減衰してしまい、テレビでの受信レベルが低下する原因となります。
Q4.地デジ放送の受信レベルが低下する要因とは?
A. 地デジ放送は、前述の通り、UHF(極超短波)という電波帯を使用しております。
この電波は、空間を長く伝わるほど電波レベルが低下する一方、40センチから60センチ程度の波長の幅があるため、ある程度は障害物を乗り越えて広がる特性があります。
しかし、以下のような要因で受信レベルが低下することがあります。
これらの要因が複合的に影響している場合も多いため、原因の特定には専門的な知識が必要です。
なお、地デジのUHFは、地デジ電波塔の先端から周辺へ広がるように送信されているため、一般の住宅では、屋根の上など周辺の障害物に影響されにくい、高い位置ほど受信レベルが安定しやすくなります。
逆に壁面やベランダなどの低い位置では、電波塔から近距離のエリアでも、周辺の高層ビルや隣家などに電波が遮られてしまい、受信レベルが大きく低下するケースもあるため、注意が必要です。
Q5.衛星放送の受信レベルが低下する要因とは?
A. 衛星放送(BS放送、CS放送)は、宇宙空間に位置する人工衛星(誠意衛星)から、日本の全域に12GHz帯という非常に高い周波数の電波を発信しています。
この12GHz帯の電波を、BS/CSアンテナのディッシュ部で受け止めて受信するのですが、12GHz帯の電波は光のような性質を持ち直進性が非常に高く、静止衛星の位置から地上のアンテナまでまっすぐ届いているため、地デジのUHFとは異なる要因で、電波レベルが低下するという特徴があります。
衛星放送はその性質から地デジ放送に比べると、アンテナでの受信レベルは安定しやすい傾向がありますが、アンテナ角度のズレや障害物の影響は地デジ放送よりも大きくなるため、注意が必要です。
また特に悪天候による受信不良は衛星放送の特性上、避けられない場合もあり、基本的な対策は天候の回復を待つのみになりますが、それ以外の原因は適切な対処で改善が可能です。
まとめ:アンテナレベルの不調は原因究明がカギ!自分で解決できない場合は無理せずプロに相談を
お住まいで地デジや衛星放送の映りが悪くなったときは、まずはアンテナレベルを確認することが問題解決の第一歩です。
この記事で紹介した手順に沿って、ご自身でもできる簡単な対処法から試してみてください。
ケーブルの再接続やテレビの再起動だけで、意外と簡単に問題が解決することもあります。
しかし、さまざまな対処法を試しても改善が見られない場合は、お住まいにあるアンテナ本体の向きのズレや機器の故障、周辺環境の変化など、原因の特定や対処について、専門的な知識や技術、そして作業の安全を確保する装備などが必要な原因が考えられます。
特に屋根の上など高所でのアンテナ調整・修理の作業には大変な危険は伴います。
そのような場合は、無理に自分で解決しようとせず、早めに信頼できるプロのアンテナ専門業者へとご相談されることが、もっとも安全で確実な解決策と言えるでしょう。
もし、お客様が関東・関西エリアにお住まいで、急なアンテナトラブルのご相談先にお困りの際は、まずは当あさひアンテナのフリーダイヤル、メールフォーム、LINEアカウントまでお問い合わせください。
最短即日の迅速なご対応に、完全自社施工の高い施工技術と業界最安に挑む工事費用、そして業界最長クラスの10年保証で、ご自宅のテレビ視聴官業について、末永い安定と安心をご提供いたします。