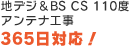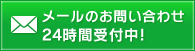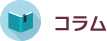地デジやBSアンテナの正しい方向は? テレビ画面が映らない時にアンテナの向きを自分でチェック・調整する方法を徹底解説
ご自宅にて普段から地デジ放送、衛星放送などをご覧になっているテレビで、急にテレビ放送が正常に映らなくなるトラブルに見舞われたご経験はありませんか?
例えば、
「台風が過ぎ去った後、急にテレビの映りが悪くなった」
「屋根の上のアンテナには特に異常がないのに、テレビの画面がブロックノイズで乱れる」
「テレビ放送が映らなくなったテレビの画面に『E202』という記号が出ている」
などのトラブルが生じた場合、ある程度、アンテナの基礎知識がある方であれば、アンテナの角度が本来の方向からずれてしまい、受信感度が下がったのではないかと思い至るでしょう。
そしてアンテナ修理の専門業者に頼むと費用が高そうだし、できれば自分で直してみたいと思われる方もいらっしゃるかと思われます。
ただ、実際にはテレビアンテナなど触ったこともないし、具体的にアンテナをどの方向を向ければいいのか見当もつかないとお悩みの方のために、この記事をご用意しました。
本記事は、アンテナ工事のプロ集団である専門業者「あさひアンテナ」に所属する、経験豊富で優秀なアンテナ職人に「アンテナの角度調整」に関するさまざまなお話を伺い、アンテナはじめ技術系の知識を持つライターが、分かりやすくまとめたものです。
記事内では、アンテナに関する専門知識をまったくもたない方でも、安全にテレビの映りを改善できるよう、原因の特定から解決策までを分かりやすく解説しています。
具体的には、スマートフォンアプリを使って、アンテナを向けるべき方向の簡単な調べ方から、具体的な調整の手順、そしてどうしても直らない場合の業者選びのコツまで、一般の方でも記事内ですべてわかるようまとめました。
この記事を一通りお読みいただければ、ある日突然、発生したテレビの不調に対しても、余計なコストを抑えて、一刻も早く快適にテレビを視聴できる日常を取り戻せるようになります。
まず確認!テレビが映らない原因は本当にアンテナの向き?
テレビアンテナや受信の仕組みを知っている方で、特に気候が荒れた後などに突然、テレビの映りが悪くなると、アンテナの向きがズレてしまったと思いがちです。
そしてアンテナの調整が必要という前提で、ご自身でアンテナのある屋根に登ろうとしたり、すぐ業者に対処を依頼しようとしてしまうかもしれません。
ただ、すぐにアンテナを確認する前に、いくつか確認すべき点もあります。
確かにアンテナ本体のトラブルで実際によく見られるのは、アンテナの角度がズレてしまって電波が十分に受信できなくなるケースです。
しかし、テレビが映らなくなる原因には、アンテナの向き以外にもさまざまな要因があり、全体的に見れば、アンテナ本体の問題よりも、その他のささいな要因でテレビが映らなくなるケースの方がかなり多いのです。
そこでテレビが映らなくなった際には、あわててアンテナの確認に走る前に、まずは、ご自宅のテレビに表示されているエラーコードを確認し、室内の簡単なチェックから始めることが必要なのです。
ご自分で高所に登るような危険な作業や、業者を呼んでの無駄な手間や費用を避けるためにも、まずは冷静な原因の切り分けが、トラブル解決への一番の近道です。
地デジアンテナの向きとその他の受信トラブルの要因とは?
まずは以降の説明をわかりやすくするために、地デジ、衛星放送の別に、その放送や受信の仕組み、正確なアンテナ方向調整の方法、そしてアンテナの向き以外で受信トラブルが発生する主な要因について解説していきます。
基本的な受信の仕組みやトラブルの要因をご理解いただくことで、アンテナの向き調整をはじめ、的確なトラブル原因の特定と対処が可能になります。
以下、まずは地上デジタル放送(地デジ放送)についてご説明いたします。
現在の日本における基本的なテレビ放送で、アンテナなど受信設備を整えれば不特定多数の誰でも視聴できる地上デジタル放送(地デジ)は、東京都墨田区の東京スカイツリーをはじめ、日本各地に設置された、その地域の「電波塔」から映像信号を乗せて発信される地デジ電波(UHF(極超短波))という電波を受信することで、視聴できます。
地デジ放送のUHF(周波数帯は470MHzから710MHzの間)は、波長の幅は約40センチから60センチ程度で、電波塔の先端から、周辺エリア一体でおおむね下方向に当たる一般住宅の地デジアンテナ(UHFアンテナ)まで、音が広がるようにして届いています。
そして地デジアンテナの側は、基本的にアンテナの正面方向を電波塔の方向へ正確に向ける必要があります。地デジアンテナには性能や機種によって違いはあるものの、アンテナの正面側でのみ電波を強く受信できる「指向性(しこうせい)」という性質があるためです。
指向性の高さ(受信できる範囲の狭さ)は、アンテナの機種(形状)や受信性能によって変動し、モデルごとに「半値幅(はんちはば)」という数値で表されます。
この半値幅とは、アンテナの受信性能がもっとも高くなる真正面を基準に、正面から左右に角度をずらして、受信性能がちょうど半分になる角度を表した数値です。
基本的に、同じ機種の地デジアンテナでも、素子数・素子数相当で表される受信性能が高いモデルほど、半値幅は狭くなります。また同じ受信性能のモデルでも、形状などから半値幅が狭い機種ほど余計なノイズを受信しにくくなり、半値幅の範疇での受信感度は高くなります。
一方で、指向性が高い(半値幅が狭い)地デジアンテナほど、わずかな向きのズレでも、受信感度が大きく落ちてしまう面もあります、。
地デジアンテナで角度調整が重要な理由は、以上の通りです。
しかし、地デジ放送が映らなくなる、または映りが悪くなる原因は、アンテナの向き以外にもいくつか考えられます。その主な例は、以下の一覧の通りです。
※上記は主な地デジ受信、視聴トラブルの要因になります。
地デジ放送が突然、正常に映らなくなった場合には、上記の各種要因を元に、正確な原因を突き止めることが先決です。
BS/CSアンテナの向きとその他の受信トラブルの要因とは?
BS放送やCS放送の衛星放送は、その名称通り、宇宙空間で地球の周りを自転に合わせて周回しているため、地上からは常に空の同じ位置に見える人工衛星「静止衛星」から送信されている「12GHz帯(周波数帯が12GHz前後)という非常に周波数帯が高く、そのため直進性の高い電波を受信します。
この静止衛星は、BS放送の放送衛星、110度CS放送(スカパー!)の通信衛星とも、日本の南西方向(東経110度)の上空に位置しています。
衛星放送はこの静止衛星から、日本の全体に12GHz帯を照射するようなイメージで電波を送信していると考えればわかりやすいでしょう。
そして地上では一般住宅などに、皿のような放物面反射器(ディッシュ)をもつパラボラアンテナの「BS/CSアンテナ」を設置して、この12GHz帯をキャッチすることで衛星放送を受信しています。
光のような直進性を持つ12GHz帯は、まずBS/CSアンテナのディッシュ内部で電波をキャッチし、正面の一点に集中させる形で反射して、焦点に固定された一次放射器に集めることで受信しています。
したがって、ディッシュに反射した電波を正確に一次放射器へと集めるため、ディッシュの仰角(上下)、方位角(左右)とも、東経110度の方向へとミリ単位で正確に合わせる必要があります。
この上下、左右の角度とも、数ミリでもズレてしまうと電波が一次放射器に集まらなくなり、衛星放送の受信感度が大きく低下するのです。
また12GHz帯の電波は波長の場が25ミリ程度で直進性が高く、静止衛星から長距離の送信に適している半面、山や建物だけでなく、樹木やその枝葉、洗濯物などわずかな障害物にも遮られやすいため、BS/CSアンテナを向ける東経110度の方向に、障害物がまったくないことも重要になります。
つまり衛星放送のBS/CSアンテナは、地デジアンテナよりもさらに精密な角度調整が必要なアンテナということになります。
その他、アンテナ角度の狂いの他にも、衛星放送が正常に受信できない、映らない要因には、主に以下のような原因が考えられます。
※上記は衛星放送における受信、視聴トラブルの主な要因になります。
衛星放送は地デジ放送とは放送の仕組みや電波の性質がまったく異なり、アンテナも専用のものが必要であるため、トラブルの要因も独自のものになります。
テレビ画面のエラーコードで原因を切り分ける
上記した各種のトラブルから地デジ放送や衛星放送が正常に映らなくなった場合、テレビなどの受信機器は、画面に「エラーコード」を表示します。
エラーコードとは、テレビ放送を映し出せない場合、受信機器がその原因を特定して対応するコードを表示し、ユーザーにトラブルの原因を示す機能です。
このエラーコードでも、受信トラブルの際に表示される代表的なコード「E202」と「E201」の違いを理解しておくことも、原因特定の重要な手掛かりになります。
このふたつのエラーコードの違いは、以下の通りになります。
※エラーコードには、他にも様々な種類が存在します。
もし「E202」が表示されているなら、アンテナの向きが大きくズレている可能性が高いと言えます。
他にも、テレビ局の放送休止を示す「E203」というエラーコードも存在します。
ただこれら3つのエラーコードは、どれも受信トラブルに関するエラーコードになります。
したがってテレビの自己診断によっては、アンテナトラブルで電波が届いていない場合に「E203」が表示されるなど、実際の受信の問題とエラーコードが微妙に異なる場合もあります。
その点にはどうかご注意ください。
アンテナを触る前に!意外と多い5つの見落としポイント
地デジや衛星放送が急に映らなくなる原因は、アンテナ本体の問題ではなく、テレビ本体や周辺の配線など、意外に簡単なケースであることも少なくはありません。
そのためアンテナのある高所に登る前に、まずは室内で簡単に確認できることを試してください。
意外と単純な見落としが原因であり、以下のような室内でのチェックで、すぐにトラブルが解決することも珍しくはありません。
- ケーブルの抜け・緩みを確認する
- テレビやレコーダーの裏にあるアンテナ入力端子から、ケーブルが抜けていたり緩んでいたりしないかを確認してください。壁のアンテナコンセント端子側も要チェックです。
- ケーブルが急角度に強く折り曲げられている、家具や家電の下敷きになっているなどの状態も、電波の送信不良や内部断線などの原因になるため、チェックしてください。
- B-CASカードを挿し直す
- 一度B-CASカード(またはminiB-CASカード)を抜き、ICチップの汚れを乾いた布で拭いてから、奥までしっかりと挿し直してみてください。
- B-CASカードは現在の地デジ放送、衛星放送などデジタル放送を受信する際に、映像信号の暗号化を解くために必要なICカードで、これがないとデジタル放送は映りません。
- B-CASカードの不具合の場合、主にテレビ画面に「E100」「E101」「E102」のエラーコードが表示されます。
- また近年の4K、8Kテレビには、B-CASカードを使用せず、同様の機能を持つ「ACASチップ」を内蔵しているモデルもあります。このようなモデルで上記のエラーコードが表示される場合、後述するテレビのリセット・再起動が有効です。
- チャンネルの再スキャン(再設定)を行う
- テレビを最初に設置する際には、テレビ本体が受信できている電波の各チャンネルを確認し、適切なチャンネル番号に当てはめる「チャンネルスキャン」という作業が必要です。
- 引越し後や、地域の電波状況に変化があるなどして、受信できるチャンネルの電波と、テレビのチャンネル設定に齟齬があると、各チャンネルが映らなくなることがあります。
- このような問題があると思われる場合は、テレビの設定メニューから、チャンネルの「再スキャン」を試して、現在のテレビ電波に応じたチャンネル設定を再設定してみてください。
- ブースターの電源を確認する
- お住まいでアンテナの電波を増幅する「ブースター」を使用している場合、ブースターの電源部がコンセントから抜けていないか、電源ランプが消えていないかといった点を確認してください。
- ブースターの電源部は、本体である増幅部とは別個にアンテナ配線部へと設置され、主に屋根裏や天井裏、マルチメディアボックス内などで電源コンセントに接続されています。
- テレビの再起動(リセット)を行う
- テレビ本体の内部基盤など、本体の不具合で地デジ、衛星放送などのテレビ放送が正常に映らなくなる場合もあります。
- この場合は、テレビの主電源を切り、電源コンセントも抜いた状態で数分おいて通電を断ち、その後に電源コンセントを指し直して主電源を入れる「再起動(リセット)」で不具合が解消されるケースもあります。
- またテレビなどのメーカーやモデルによっては、上記の他に独自のリセット方法もある場合があるため、本体の取扱説明書やメーカーの公式サイトなどでご確認の上、独自の方法がある場合はそちらも試してください。
【自分でやる前に】アンテナの向き調整に必要な基本知識と安全対策
上記でご説明した、室内での簡単なチェックでトラブルが改善しない場合、いよいよアンテナ本体の調整を検討することになります。
しかしその前に、アンテナ角度調整作業の基本となる知識と、何よりも大切な安全対策について必ず理解しておいてください。
なぜアンテナの向きが重要なのか、そして作業にはどのような危険が伴うのかを知ることが、安全で確実な調整への第一歩です。
地デジアンテナとBS/CSアンテナは向ける方向がまったく違う
上記の基礎知識でもご説明した通り、アンテナの角度調整を始める前に、問題が生じているアンテナが「地デジアンテナ」か「BS/CSアンテナ」かを理解することが不可欠です。
前述の通り、この二種類のアンテナは電波の送信元や受信の仕組みがまったく異なるため、角度の調整方法もまったく違ってきます。
以下、各アンテナの違いや角度調整のポイントをあらためて一覧にまとめました。
※上記は各アンテナの主な違いになります。
この違いを念頭に置いて、まずはお住まいにおける、地デジアンテナ、BS/CSアンテナの正しい方向を探す作業に進んでください。
命が最優先!高所作業で絶対に守るべき安全対策チェックリスト
テレビアンテナ調整、特に屋根の上にあるアンテナを調整する作業は、転落などの重大な事故につながる危険性の高い作業です。
基本的に、ご自身での屋根上作業は絶対におすすめしません。
ご自宅でのアンテナ角度調整は、ベランダや壁面、屋上フロアなど、足場が安定していて安全が確保できる場所での作業に限ってください。
その場合も、作業前には以下のチェックリストを必ず確認し、安全を最優先してください。
- 天候は良いか? (雨や雪、特に風が強い日は絶対に作業を行わない)
- 一人ではないか? (万が一に備え、必ず2人以上で作業する)
- 適切な服装か? (ヘルメット、滑りにくい靴、作業用手袋などを着用する)
- ハシゴは安全か? (使用する場合は、地面にしっかりと固定し、安定しているか確認する)
作業に対して少しでも「危ない」「怖い」と思われたら、絶対にご無理をなさらず、アンテナ工事の専門業者にご依頼ください。
【地デジアンテナ編】スマホで簡単!向きを調べる4つの方法
ご自宅の地デジアンテナを向けるべき「最寄りの電波塔」の方向は、現場によって異なりますが、専門的な機材がなくても簡単に調べることができます。
特に、普段お使いのスマートフォンが強力な助太刀になります。
ここでは、地デジアンテナを向けるべき方向(近隣の電波塔の方向)を確認するための、手軽な方法から正確な方法まで、4つの方法をご紹介します。
方法1:【一番手軽】近所の家のアンテナを参考にする
もっとも簡単な方法は、ご近所の家で屋根の上に観られる「魚の骨」のような形をした八木式アンテナの先端(魚の頭のような反射器とは反対側の先端)が、どちらの方向を向いているかを確認することです。
多くの場合、同じ地域のアンテナは同じ電波塔を向いています。
また壁面に設置されるデザインアンテナも、設置されている壁面の方角が、ある程度、適切な方向の参考になります。
ただし、地形や近隣の環境などによって、近隣の家では受信している電波塔が異なるケースや、反射した電波を受信しているケースもあるため、ご自宅のアンテナとは向けるべき方向が異なる場合もあります。
この方法は、ご自宅の地デジアンテナの方向を確認する、あくまで大まかな目安として考えてください。
方法2:【超おすすめ】無料アプリ「地デジアンテナ調整」を使う
お手持ちのスマートフォンで専用のアプリを使えば、より正確に近隣の地デジ電波塔の方向を知ることができます。
特におすすめのアプリが「地デジアンテナ調整」という無料アプリです。
以下、このアプリを使用する手順について解説します。
- お使いのスマホにアプリをインストールします。
- アプリを起動し、位置情報の利用を許可します。
- 画面の指示に従い、現在地を設定すると、最寄りの電波塔がリストアップされます。
- 電波塔を選択すると、スマートフォンのカメラが起動し、AR(拡張現実)機能によって、実際の風景の中に電波塔の方向が矢印で示されます。
このアプリを使えば、専門家でなくても直感的に、お住まいで地デジアンテナを向けるべき正しい方向を知ることができます。
方法3:【PCで確認】公式サイト「A-PAB」で電波塔マップを調べる
お住まいのパソコンで調べたい場合や、スマートフォン、タブレットなどで近隣の電波塔のより正確な位置や数、受信範囲などを確認したい場合は「A-PAB(一般社団法人放送サービス高度化推進協会)」の公式サイトが便利です。
以下、同サイトで近隣の電波塔の位置を確認する手順をご説明します。
- A-PABの「地デジ放送エリアのめやす」ページにアクセスします。
- ご自宅の住所や郵便番号を入力して検索します。
- 地図上に、受信可能な電波塔(送信所)の位置が表示されます。
- 各電波塔をクリックすることで、その電波塔からの電波が、中電界地域以上のレベルで受信できる範囲が、地図上に色付きで表示されます。
この地図を確認すれば、ご自宅から見てどの方向にアンテナを向ければよいかが一目瞭然になります。
なお各電波塔がカバーする範囲や主な方向は、電波塔の規模や現場の環境によっても異なりますので、お住まい近隣の電波塔をクリックしてみて、周辺に色付きで表示される範囲にご自宅の場所が含まれるかどうかを確認してください。
方法4:【地域別】主要な電波塔の方向一覧(東京・大阪・名古屋など)
日本国内でも主要な都市圏にお住まいの場合、以下の代表的な電波塔(親局、基幹局、送信所)の方向が目安になります。
正確な方角はご自宅の位置によって異なりますので、参考程度にご確認ください。
※上記の他にも日本の各エリアに基幹局が存在します。
また各エリアでは、基幹局からの電波が届きにくいエリアに、基幹局からの電波をキャッチして増幅し、周辺に送信し直す中継局(サテライト局)が数多く設置されています。
この中継局からの電波を受信しているエリアも多くなりますので、正確には上記した「A-PAB」サイトでのご確認が確実と言えます。
【BS/CSアンテナ編】向きは南西!正確な角度を調べる2つの方法
衛星放送を受信するBS/CSアンテナを向けるべき方向は、前述の通り、静止衛星が位置する東経110度の上空、基本的に「南西」方向の上空になります。
しかし、BS/CSアンテナは地デジアンテナよりもはるかに指向性が鋭いため、大まかな方角に合わせるだけではまったく受信できません。
東経110度の方向は常に一定ですが、日本は東西に長く、南北にも幅があるため、地域によって東経110度を指すBS/CSアンテナの角度は微妙に変わってくるのです。
したがってBS/CSアンテナの角度調整には、お住まいの地域ごとに変化する、正確な「方位角(左右の角度)」と「仰角(上下の角度)」を知る必要があります。
方法1:【必須アプリ】無料アプリ「BSコンパス」で一発測定
BS/CSアンテナの角度調整に欠かせないのが、無料のスマートフォンアプリ「BSコンパス」です。
このアプリを使えば、専門的なレベルチェッカーがなくても、お住まいのエリアごとに正確な東経110度の角度を簡単に調べることができます。
以下は「BSアンテナ」を使用する手順になります。
- スマホに「BSコンパス」をインストールして起動します。
- 位置情報を許可すると、現在地における最適な「方位角」と「仰角」が画面に表示されます。
- AR機能を使えば、カメラを空にかざすだけで、衛星のある方向を視覚的に確認できます。
アプリを使用してBS/CSアンテナの角度を調整する場合、アンテナの仰角を先にアプリの数値に合わせて仮固定し、その後、方位角を調整する手順がスムーズです。
スマートフォンを用いれば、画面に表示されるコンパスをアンテナにあてがう形で、実際の角度調整が行いやすくなります。
方法2:アンテナメーカーの公式サイトで角度を確認する
DXアンテナやマスプロ電工、日本アンテナといった主要なアンテナメーカーの公式サイトには、日本の各地域ごとのBS/CSアンテナ角度(仰角、方位角)を調べられるページがあります。
各サイトでのBS/CSアンテナ仰角、方位角の確認方法は、主に以下の通りです。
- メーカーの公式サイトにアクセスします。
- 「方向調整」「設置シミュレーション」などのページを探します。
- ご自宅の住所を入力すると、その地点での正確な「方位角」と「仰角」が表示されます。
サイトによっては、日本の主要都市での仰角、方位角の一覧表を掲載している場合もあります。
ただ実際には、この仰角、方位角に合わせるだけでなく、現場ごとに角度の微調整を行う必要もあるのでご注意ください。
また、マスプロ電工製などBS/CSアンテナの一部モデルには、本体の角度調整部に、主要都市における仰角の目安が刻印されている製品もあるので、そのような製品もご利用になるとで便利です。
実践!アンテナの向きを自分で調整する5ステップ【レベル確認が最重要】
地デジアンテナ、BS/CSアンテナとも、アンテナ正面を向けるべき正しい方向、角度が判明したら、いよいよ調整作業に入ります。
この場合の最重要ポイントは、必ずテレビの「アンテナレベル」画面を見ながら、少しずつアンテナを動かすことです。
ただおおよその勘に頼って動かすのではなく、数値の変化をリアルタイムで確認しながら、低いアンテナレベルが最大値になる、もっとも受信状態の良いポイントを探し出すことが必要です。
この項目では、安全が確保できるベランダなどでの角度調整作業を前提に、作業の手順を5つのステップで解説します。
ステップ1:テレビの「アンテナレベル」確認画面を表示する
まず、作業を始める前に、テレビのアンテナレベル(受信強度)が確認できる画面を表示します。
テレビ機器には、アンテナから届いている電波の強度(アンテナレベル)を表示する機能がありますが、この画面へのアクセス方法はメーカーによって異なります。
以下、主要なメーカーのテレビにおける、アンテナレベル画面表示の方法をご紹介します。
※各メーカー製のテレビでも、モデルによって手順が異なる場合もあります。
テレビの取扱説明書などをご確認の上、アンテナレベルが常に確認できる状態にしてから作業を始めましょう。
なお、多少の費用は掛かりますが、アンテナのケーブル部分に接続して、受信できるアンテナレベルをその場ですぐに確認できる簡易型の「アンテナレベルチェッカー」があると、アンテナレベルの確認と角度調整の作業がより簡単になります。
簡易型であれば地デジ用、BS用の別に1,000円台でも購入できるため、このような製品をご利用になるのもいいでしょう。
ステップ2:アンテナを固定しているボルト・ナットを少し緩める
アンテナの近くでレンチなどの工具を使い、アンテナをマスト(支柱)に固定しているボルトやナット、または角度調整部のボルトなどを、アンテナが手でゆっくり動かせる程度に少しだけ緩めます。
緩めすぎると、アンテナが急に動いたり、落下したりする危険がありますので、慎重に行ってください。
ステップ3:アンテナレベルが最大になる方向へ少しずつ動かす
ここがもっとも根気のいる作業です。
室内の確認者と声を掛け合いながら、アンテナを数ミリ単位でゆっくりと動かします。
- 地デジアンテナの場合:主に左右(方位角)のおおまかな調整になります。
- BS/CSアンテナの場合:左右(方位角)と上下(仰角)の両方を正確に調整します。
実際の角度調整では、アンテナを1、2ミリ程度わずかに動かしてから、その角度の受信レベルが、テレビのアンテナレベル画面に反映されるまでに数秒のタイムラグがあります。
したがって決してあせらず「少し動かす → 数秒待つ → レベルを確認する」を繰り返してください。特にBS/CSアンテナでは時間をかけた慎重かつ緻密な作業が必要です。
この作業により、テレビ側でアンテナレベルの数値がもっとも高くなるか、またはバーの色が緑や青になる最適なポイントを探します。
ちなみに上記した簡易型のアンテナレベルチェッカーがあれば、アンテナ角度を調整しながらその場で即座にアンテナレベルを確認できるため、BS/CSアンテナの場合でも、手間を大幅に軽減できて、一人での角度調整作業も簡単になります。
ステップ4:レベル最大の位置でボルト・ナットをしっかりと固定する
アンテナレベルが最大になるアンテナ角度のベストポジションが見つかったら、アンテナがその位置から動かないように慎重に押さえながら、緩めたボルトやナットを工具でしっかりと締め直して固定します。
この時、締め付けの力でアンテナの向きがズレないように注意してください。
また過度に力を入れて締めすぎると、ボルトなどを破損して以降の角度調整ができなくなる場合もあるため、その点にもご注意ください。
ステップ5:すべてのチャンネルが問題なく映るか最終確認する
テレビアンテナを固定したら、最後にお住まい内のテレビのリモコンで、すべてのチャンネルの映り具合を確認して、どのチャンネルも問題なくきれいに映るかを確認します。
もしチャンネルが全般的に、また特定のチャンネルだけ映りが悪い場合は、再度ステップ3に戻り、微調整が必要になるかもしれません。
向きを調整しても直らない…考えられる他の原因と対処法
慎重にテレビアンテナの向きを調整したにもかかわらず、テレビの映りが改善しない場合は、映りの悪い原因がアンテナの向き以外にある可能性が高くなります。
このような場合は、ご自分で対処するのが難しいケースがほとんどですので、ご無理はなさらず以下の原因を疑ってください。
原因1:アンテナ本体やブースター(増幅器)の経年劣化・故障
屋外に設置されているアンテナやブースターは、常に風雨や紫外線などの厳しい環境にさらされています。
一般的に、屋外に設置される地デジアンテナの八木式アンテナ、BS/CSアンテナの寿命は10年~15年程度と言われています(デザインアンテナやユニコーンアンテナの場合は15年から20年以上)。
アンテナ設置工事から10年以上の年月が経過している場合は、アンテナ本体や、電波を増幅する電子機器のブースターが寿命を迎え、故障している可能性も考えられます。
この場合は、機器の交換が必要になるため、専門業者への相談が必須になります。
原因2:アンテナケーブルの断線や接続部の腐食
アンテナ本体と同じく、屋外のアンテナから、屋根裏などを経由して、テレビのある各部屋までを引き回されているアンテナケーブルも徐々に劣化します。
ケーブルの被覆が破れて断線したり、接続部分が水の浸み込みなどで錆びて接触不良を起こしたりしている可能性があります。
これも一般の方による見た目では判断が難しく、確認や交換作業には専門的な知識が必要です。
原因3:周辺環境の変化(高い建物の建設、木の成長など)
以前は問題なく映っていたのに、最近になって急に映りが悪くなった場合、テレビアンテナと電波塔や静止衛星との間に、電波を遮る障害物が現れた可能性もあります。
特に電波が障害物に遮られやすい衛星放送では、このようなトラブルが生じやすくなります。
このようなトラブルの具体例としては、以下のものが考えられます。
- 近所に電波塔や静止衛星の方向を遮る高層マンションが建設された。
- 自宅や隣家の庭の木や枝葉が成長してアンテナ前方を遮っている。
- 特に衛星放送では、近隣の工事などで、静止衛星の方向にクレーン車などが停止している。
このような場合は、可能であれば庭木など障害物の撤去の他、アンテナの設置場所をより高い位置に変更する、受信性能の高いアンテナに交換するなどといった対策が必要になります。
自分でやるのは無理…プロの業者にアンテナの向き調整を依頼する場合
屋根の上のアンテナで高所作業が必要な場合や、実際にアンテナの向きを調整しても不具合が直らない場合は、迷わずプロのアンテナ工事業者に相談してください。
プロの業者であれば、ほとんどのアンテナトラブルに対し、安全かつ確実に問題を解決してくれます。
しかし一般のお客様には、「業者にテレビアンテナ修理などを頼むと高額な料金を請求されそう」とご不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの項目では、工事費用、施工技術とも安心して依頼できる有料業者を選ぶための、実際の料金相場と業者の選び方のポイントを解説します。
アンテナの向き調整にかかる料金相場は?
アンテナ工事(故障などトラブルへの対処)の料金は、実際の作業内容によって大きく変動します。
事前に大まかな相場を知っておくことで、不当に高額な見積もりを見抜くことができます。
以下、アンテナトラブルの場合の、主なアンテナ修理の作業内容と費用の相場をご紹介します。
※上記はあくまで目安です。正確な料金は必ず複数の業者から見積もりを取って比較検討してください。
例えば、本記事に貴重な解説をいただいたアンテナ職人が社員として所属する優良なアンテナ工事専門業者「あさひアンテナ」では、上記の各種工事について、
- アンテナ角度調整:8,000円(税込み8,800円)
- 既設アンテナ撤去(処分費込み):5,000円(税込み5,500円)
- UHFブースター設置(本体・機材代金込み):20,000円(税込み22,000円)
- UHF/BSCS混合ブースター設置(〃):25,000円(税込み27,500円)
と、上記の相場でも低価格で対応しています。
同社が優秀なアンテナ職人による高品質な工事を、低価格で提供できる理由は、次の項目で詳しくご紹介いたします。
失敗しない!信頼できるアンテナ工事業者の選び方3つのポイント
数あるアンテナ工事業者の中から、テレビアンテナの角度調整や修理はどこに頼むべきか、安心して任せられる優良業者を見つけるためには、いくつかのチェックポイントがあります。
以下の3つのポイントを参考に、悪質な業者を避けて、信頼できるパートナーをお選びください。
ポイント1:施工実績が豊富で、完全自社施工であること
業者の公式サイトなどで、年間の施工件数を確認してください。
実績が豊富であることは、それだけ多くの現場を経験し、さまざまなトラブルに対応できる技術力とノウハウがある証拠です。
例えば、年間6,000件以上の施工実績を誇る「あさひアンテナ」 のように、具体的な数字を公開している業者は信頼性が高いと言えます。
また、工事を下請け業者に丸投げせず、全ての工程を自社のスタッフで完結させる「完全自社施工」の業者を選んでください。
下請け業者を使う場合の中間マージンが必要なく施工コストを抑えられる上、施工担当者の経験が豊富で技術レベルが安定しており、責任の所在が明確なため、低価格ながら質の高い工事が期待できます。
もちろん「あさひアンテナ」でも完全自社施工を徹底しています。
ポイント2:料金体系が明確で、見積もり後の追加請求がないこと
優良なアンテナ工事業者は、公式サイトに料金体系を明確に記載しています。
また、アンテナ工事の事前調査、見積もりについて「出張費・見積もり無料」を掲げているかどうかも重要なポイントです。
必ず作業前に詳細な見積書を提示してもらい、作業内容と費用の内訳を丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。見積もり後の不当な追加請求がないことを明言している業者であれば、より安心です。
あさひアンテナでは現地に出張しての電波調査、見積もりは完全無料(出張料やキャンセル料など各種費用含む)のほか、他業者との相見積もり、工事をお急ぎの場合の即日工事にも対応しています。
また工事費用の価格体系、使用する記載のメーカー、型番などはすべて公式サイトに記載されており、原則として見積もり後の追加請求は行わないことも明言しています。
ポイント3:長期の工事保証などアフターサービスが充実していること
アンテナ工事後の保証制度は、その業者の技術力への自信の表れです。
その業者の保証期間が長いほど、それだけ長期にわたってトラブルが生じる可能性が低く、施工品質に自信をもっていると考えられます。
例えば、業界最長クラスである10年間の長期保証を提供している「あさひアンテナ」 のような業者は、万が一工事後に不具合が発生した場合でも、責任を持って対応してくれるでしょう。
アフターサービスの充実度も、業者選びの重要な判断基準になります。
まとめ:アンテナの向きは自分で直せる!でも安全第一、無理せずプロに相談を
今回のコラムでは、テレビが映らなくなった際のアンテナの向きの確認方法と、自分で調整する手順について詳しく解説しました。
以下、本コラム記事の内容をあらためて簡単にまとめます。
- まずは室内から! ケーブルの抜けやB-CASカードなど、てれび本体まわりの簡単なチェックから始めてください。それだけでトラブルが解消される場合もあります。
- 向きの確認はスマホアプリで! 「地デジアンテナ調整」や「BSコンパス」などのアプリを使えば、専門家でなくてもアンテナを向けるべき正しい方向がわかります。
- 調整はテレビのアンテナレベルを見ながら! 必ず数値を確認し、少しずつ動かすのが成功のコツです。簡易型のアンテナレベルチェッカーがあればより簡単かつ確実が作業が可能です。
- 安全が最優先! 少しでも危険を感じる高所作業は絶対に行わないでください。危険作業に関しては、決してご無理なさらずプロにご依頼ください。
地デジアンテナ、BS/CSアンテナとも、テレビアンテナの向き調整は、重要なポイントさえ押さえれば、ご自分で解決できる可能性が大いにあります。
しかし、実際の作業がうまくいかない場合や、屋根の上などで作業に危険が伴う場合は、決して無理をしてはいけません。
そんなときは、豊富な実績と長期保証で信頼できる専門業者に相談することが、もっとも安全で確実な解決策になります。
例えば本記事にご協力いただいたアンテナ職人が所属する「あさひアンテナ」では、9:00から21:00まで受け付けのフリーダイヤルの他、公式サイトのメールフォーム、LINEアカウントでは24時間いつでもお問い合わせを受け付けているため、お手軽に相談を持ち掛けることができます。
もしものテレビ画面、アンテナ角度のトラブルの際には、本記事の情報を参考に、一日も早く快適なテレビご視聴環境を回復していただければ、筆者としても幸いに思います。