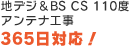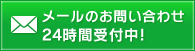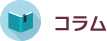【プロが解説】アンテナの方向はアプリで解決できる?自分でできる正しい向きのチェックと調整方法・業者の料金相場を徹底解説
「台風が過ぎて以降、テレビの映りが乱れることが多い」
「特定のチャンネルだけブロックノイズが出て、画面がまともに映らない」
「たまに画面に『E101』と表示されて、地デジのチャンネルがまったく映らなくなる」
「最近テレビがちゃんと映らないと思ったら、以前に比べて自宅のアンテナの方向が変わっている気がする」
お住まいのテレビで、そのような経験はないでしょうか。
それはもしかしたら、台風や雪などの自然環境や、アンテナの老朽化によって、ご自宅のテレビアンテナの方向がズレてしまったせいかもしれません。
地デジアンテナ、BS/CSアンテナとも「指向性」と呼ばれる性質があるため、向けるべき正しい方向から角度がズレてしまうと、テレビ電波を十分に受信できなくなることがあるのです。
テレビが正常に映らない状況はお困りでしょう。しかし、すぐに業者を呼ぶことも、費用などのご心配があるのではないでしょうか。
そこで本記事では、アンテナに関する専門知識がなくても、ご自身で問題を解決するための一連の手順を徹底的に解説します。
スマートフォンアプリを使った簡単な方向の確認方法から、安全な調整作業の具体的な手順、そして手に負えない場合の優良な業者の選び方と費用相場まで、お客様のための情報をすべて網羅しました。
本記事は、技術的な知識を持つライターが、アンテナ工事の専門業者「あさひアンテナ」の優秀なスタッフに取材を行い、豊富な現場経験と専門知識に基づくお話から、アンテナの方向がズレた場合の対処について、網羅的な情報をわかりやすくまとめたものです。
この記事を最後までお読みいただければ、余計なコストをかけずに、いち早くテレビの問題を解決し、ご家族で快適にテレビを視聴できる日常を取り戻すことができます。
現在、上記のようなトラブルでお困りのお客様は、まずは本記事をご確認の上、適切な対処法を見つけてください。
テレビが映らない!まず確認すべきアンテナ方向以外の原因チェックリスト
お住まいで急にブロックノイズなどが出てテレビの画面が乱れる、エラーコードが出て映らなくなるといった症状が出た場合、多くの方はアンテナの角度のずれをはじめ、アンテナの不具合や故障ではないかと思われることでしょう。
しかしお住まいでのテレビアンテナの確認や調整は、特に屋根の上など高所での作業になることが多く、大変な危険を伴います。
実は、お住まいでテレビ画面の映りが悪い、エラーコードが出て映らないなどの問題が起きたとき、その原因は、実際にはアンテナなどの大きなトラブルではなく、テレビ本体や周辺の配線など、ごくささいな不具合が原因であるケースが大多数なのです。
即座に「アンテナの向きが原因だ!」と決めつけてアンテナの確認など大変な作業に乗り出す、またはあわてて業者に連絡する前に、まずは室内で簡単に確認できることから試してみてください。
意外と単純なことで、テレビの映りはあっさりと改善することがあります。
リモコン一つで簡単チェック!最初に試すべき対処法
まずは、工具や複雑な作業は不要で、ご自宅でも安全かつ簡単に試せる基本的な対処法から始めましょう。
テレビ画面の乱れについては、以下の手順を試すだけで、すぐに問題が解決してしまうケースも少なくありません。
- テレビ本体の再起動
- 一度テレビの主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2〜3分ほど待ってから、再度プラグを差し込み、電源を入れ直してください。
- これだけで、テレビ内部の基盤、プログラムの誤動作など、一時的なエラーであれば、解消されることがあります。
- チャンネルの再スキャン(再設定)
- テレビのリモコンにある「メニュー」や「設定」ボタンを押します。
- 「チャンネル設定」「放送受信設定」などの項目から「チャンネルスキャン」「再スキャン」を選択します。
- テレビのチャンネル設定の不具合や、受信できる電波の周波数帯変更などで電波が受信できない場合は、お住まいの地域に合わせて再度チャンネル設定を行うことで、受信状況が改善される場合があります。
- B-CAS(ビーキャス)カードの抜き差し
- テレビの主電源を切り、本体や側面や背面に挿入されているB-CASカードを一度抜きます。
- カードのICチップ部分を、乾いた柔らかい布で優しく拭いてください。
- カードを正しい向きで奥までしっかりと挿し直してから、テレビの電源を入れます。
- デジタル放送(地デジ・BS/CSデジタル)の受信に必要なB-CASカードの不具合(「E100」「E101」「E102」などのエラーコード)であれば、この手順で復旧できることが多くなります。
- 最新の4K8Kモデルなど、B-CASカードの代わりに「ACASチップ」を内蔵しているモデルで上記のエラーコードが出た場合は、前述したテレビ本体の再起動を試してください。
- 配線ケーブルの確認
- テレビの裏側にあるアンテナ入力端子と、壁のアンテナ端子を繋いでいるケーブルを確認します。
- ケーブルがしっかりと接続されているか、抜けかかっていないかを確認してください。
- レコーダーや分配器などを経由している場合は、それらの接続もすべて確認しましょう。
- 接続するケーブルが長すぎる、急角度に折り曲げられている、家具などの下敷きになっているなどの問題がないかも確認してください。
以下、チェック項目を一覧表でまとめました。
| チェック項目 | 確認内容 | 解決のポイント |
|---|---|---|
| テレビの再起動 | 電源プラグを抜き、数分待ってから再度入れる。 | 内部のエラーリセット |
| チャンネル再スキャン | テレビの設定メニューからチャンネルを再設定する。 | 放送局情報の更新 |
| B-CASカード | カードの抜き差しとICチップ部分の清掃。 | 接触不良の改善 |
| 配線ケーブル | テレビ、壁、周辺機器の接続が緩んでいないか確認。 | 物理的な接続の確認 |
※上記は基本的な対処方法になります。
こんな症状ならアンテナが原因かも?方向ズレのサイン
上記した基本的な対処法を試しても改善しない場合、お住まいにあるアンテナ本体の不具合や、角度に問題がある可能性が高まります。
特に、以下のような症状が見られる場合は、アンテナの方向がズレているため、アンテナが十分な電波を受信できていないサインである可能性が高まります。
| 症状の例 | 考えられる原因 |
|---|---|
| 特定のチャンネルだけ映らない、または映りが悪い | アンテナの向きが少しズレて、一部の周波数帯(チャンネル)の電波をうまく受信できていない可能性があります。 |
| ブロックノイズが頻繁に発生する | 受信している電波レベルが必要な水準ギリギリの状態で、電波が不安定になっていることが考えられます。 |
| 天気が良い日は映るが、雨や風の日は映らない | アンテナの向きが最適な位置からわずかにズレており、天候による電波の減衰に耐えられなくなっている可能性があります。 |
| エラーコード「E201」「E202」が表示される | 「E201」は電波の強度不足、「E202」は電波が受信できていない状態を示すエラーコードで、アンテナの方向ズレが直接的な原因であることが多くなります。 |
※上記は主な目安になります。
これらの症状に心当たりがある場合は、次のステップに進み、アンテナが向くべき正しい方向を確認してみてください。
【準備編】アンテナが向くべき正しい方向をスマホで簡単特定する方法
テレビアンテナの調整作業を始める前に、もっとも重要になるのが「アンテナをどちらの方向に向けるべきか」を正確に知ることです。
ここで間違った方向に向けてしまうと、すべての作業が無駄になってしまいます。
地上デジタル放送を受信するための「地デジアンテナ(UHFアンテナ)」と、衛星放送(BS放送、CS放送)を受信するための「BS/CSアンテナ(パラボラアンテナ)」では、目標となる場所(電波の発信元)がまったく異なります。
そのため以下ではそれぞれを分けて、確認の方法を解説していきます。
地デジアンテナ:最寄りの「電波塔」を探そう
地上デジタル放送の電波は、各地に建てられた「送信所」や「中継局」などの電波塔の先端から、UHF(極超短波)と呼ばれる種類の電波にデジタル映像信号を乗せて発信されています。
例えば関東地方(首都圏)では、東京都墨田区に位置する送信所、東京スカイツリーから送信される地デジ電波が、周辺一帯の広範囲をカバーしています。
そして距離により電波レベルが弱まる、山などの地形で地デジ電波が届きにくくなる一帯には、スカイツリーや他の電波塔からの電波をキャッチし、増幅して周辺へと送信する「中継局」が設置されており、このリレー形式で、放送エリアの大半をカバーしているのです。
また一般のご家庭に設置される各種の地デジアンテナは、地デジのUHFを受信するためUHFアンテナとも呼ばれますが、現在の大半の機種には、アンテナの正面側、一定の範囲でのみ受信感度が高まる「指向性(しこうせい)」という性質があります。
この指向性によりアンテナの一定方向に受信性能が集中し、他方向からのノイズ(雑音、余計な電波)を受信しにくくなることで、高い受信性能を実現しているのです。
しかし一方でこの指向性から、地デジアンテナは正面側を電波塔の方向へと正確に向ける必要があり、指向性の高いアンテナほど、わずかな角度のズレで受信できる電波の強度が大きく低下するという面もあります。
そのため地デジアンテナの設置に当たっては、ご自宅からもっとも近い、またはもっとも強い電波を送信している電波塔の方向へ正確に向ける必要があるのです。
お住まいで地デジアンテナの前方を向けるべき、適切な電波塔の方向を調べる方法は、主に以下の3つが挙げられます。
方法1:ご近所のアンテナの向きを参考にする
もっとも手軽で簡単な方法が、近隣の住宅の屋根に設置されている地デジアンテナの向きを確認することです。
特に、魚の骨のような形をした「八木式アンテナ」は、多くの家で同じ方向を向いているはずです。
また壁面などに設置されるデザインアンテナ(平面アンテナ)も、多くの場合は同じく電波塔の方向を向いた壁面に設置され、正面に当たる平面状の部分を、電波塔の方向に向くよう調整されています。
その方向が、その地域における電波塔の方向の目安となります。
ただし、これはあくまで簡易的な方法です。
地形や建物の影響で、隣の家と自宅とでは最適な電波塔が異なる場合もあるほか、住宅によっては近隣のビルなどに反射した反射波、乗り越えて広がる際に方向が変わった回折波などを受信しているケースもあるため、この方法は参考程度に留めておいてください。
方法2:Webサイト「A-PAB」で正確な位置を調べる
より正確な情報を得るためには「一般社団法人 放送サービス高度化推進協会(A-PAB)」が運営するウェブサイトの利用がおすすめです。
このサイト内には「地デジ放送エリアのめやす」というページがあり、以下のように簡単な操作で、ご自宅のエリア周辺にある電波塔の位置を地図上で確認できます。
A-PABでの確認手順
- 「A-PAB 放送エリアのめやす」ホームページにアクセスします。
- ホームページの項目で「地上波放送(地デジ・ワンセグ)」から「地デジ放送エリアのめやす」を選択します。
- 表示された欄にご自宅の住所、または郵便番号を入力します。他にも局名(電波塔の名前)、都道府県別の局一覧から探すこともできます。
- 画面上にご自宅近隣の地図が表示され、ご自宅の位置と、近隣にある受信可能な電波塔の位置(送信所)が示されます。
- ご自宅からもっとも近い、または推奨される電波塔の方向を確認します。表示された電波塔をクリックすることで、その電波塔からの電波が一定以上のレベル(中電界地域以上)で届く範囲を、地図上の色で確認することもできます。
この方法であれば、スマートフォンのブラウザからも簡単に近隣の電波塔を調べることができます。
ただ注意点としては、お住まいから距離的にもっとも近い電波塔であっても、電波を送信している主な方向が違う、また電波の出力が違うため距離は遠くてもより大型の電波塔から届く電波の方が強いというケースも考えられます。
そのため電波塔の距離だけでなく、上記した方法でその電波塔からの電波が届く範囲を確認することが重要です。
さらに個々の現場では、周辺の高層ビルなど障害物の影響を受けて、近隣の電波塔からの電波でも十分に届かない場合もあります。
このWebサイトによる確認も、あくまでおおよその目安と考えることをおすすめします。
方法3:スマホアプリ「地デジアンテナ調整」などを使う
スマートフォンをお持ちの方には、アンテナ角度調整用に開発された専用アプリの活用が非常に便利です。
GPS機能やAR(拡張現実)機能を使い、直感的に地デジ電波塔の方向を示してくれます。
例えば、日本三大アンテナメーカーの一社でもある「日本アンテナ」が提供する「地デジアンテナ調整」というアプリでは、現在地から見た電波塔の方向を、地図やカメラ映像上に表示してくれます。
アンテナ角度を調整する際に、スマートフォンの画面を確認しながら作業できるため、非常に効率的です。
以下、地デジ電波塔の確認方法を一覧でまとめました。
| 確認方法 | 手軽さ | 正確性 | おすすめな人 |
|---|---|---|---|
| ご近所のアンテナ | ★★★ | ★☆☆ | まず大まかな方角を知りたい人。 |
| Webサイト(A-PAB) | ★★☆ | ★★★ | パソコンやスマホで正確な位置を地図で確認したい人。 |
| スマホアプリ | ★★★ | ★★★ | スマホを片手に直感的に方向を知り、調整作業をしたい人。 |
※上記は主な地デジ電波塔の位置確認方法になります。
BS/CSアンテナ:宇宙の「衛星」がある南西方向が基本
衛星放送(BS放送、CS放送)では、地上の電波塔からではなく、地上からはるか上空、宇宙空間に位置する人工衛星(BSの放送衛星、CSの通信衛星)から、日本の全域に電波が送られてきます。
この人工衛星は静止衛星と呼ばれ、赤道上空、約36,000kmの位置にて地球の自転と同じ速度で動いているため、地上からは常に空の同じ位置に静止しているように見えます。
日本から見ると、BS放送衛星、主なCS通信衛星の方向は、どちらも「南西上空(東経110度)」となります。
そしてこの静止衛星から日本の全域まで送られるテレビ電波は、地デジのUHFよりも格段に周波数帯が高く、12GHz前後になるため「12GHz帯」とも呼ばれる電波になります。
この12GHz帯は波長の短さ(25ミリ程度)から、光のように直進性が高く、遠距離への送信に適しています。その反面、日光がものに当たると影ができるように、ごくわずかな障害物にも遮られやすい非常にデリケートな性質を持っています。
「方位角」と「仰角」とは? 知っておきたい基本用語
BS/CS放送が映らない場合のアンテナの調整では、地デジアンテナよりもさらに精密に、静止衛星の方向に向けた角度合わせが必要となります。
そこで重要になるのが、「方位角」と「仰角」という2つの角度です。
BS/CSアンテナは、上記した静止衛星から日本全体を照らし出すライトのように、直進的に送信されてくる12GHz帯を、皿のようなディッシュ(放物面反射器)でキャッチし、ディッシュ内部で正面の一点に集まるように反射させます。
そしてその焦点に固定された「一次放射器」によって、集中した電波を受信する仕組みです。
したがってこの焦点を一次放射器に合わせるため、方位角と仰角を中心とした、より正確な角度調整が必要となるのです。
以下、それぞれの角度について詳細を解説します。
- 方位角(ほういかく)
- ディッシュの左右の向きを示す角度です。
- 真北を0度として、時計回りに東が90度、南が180度、西が270度となります。
- 静止衛星は常に南西方向(東経110度)に位置しますが、日本は東西に長い幅があるため、地域によって静止衛星の方向に合わせる角度が異なり、おおよそ210度から220度前後になります。
- 仰角(ぎょうかく)
- ディッシュの上下の向き(見上げる角度)です。
- 地面と水平な状態を0度として、アンテナをどれだけ上に向けるかを示します。
- この角度も日本の南北の地域によって異なり、南の地域ほど高く、北の地域ほど低くなります。具体的な角度は、おおよそ36度から57度程度の範囲になります。
このディッシュの角度が、日本各地に応じた東経110度の仰角、方位角から少しでもズレてしまうと、ディッシュに反射した12GHz帯が一次放射器から外れてしまい、衛星放送を受信できなくなってしまいます。
必須アプリ「BSコンパス」で自宅の正確な角度を調べる
お住まいの地域ごとの正確な方位角と仰角を調べるには、上記と同じくく日本アンテナが提供しているスマートフォンアプリ「BSコンパス」が非常に役立ちます。
このアプリは無料で利用でき、簡単な操作で、地域ごとの正確な東経110度の仰角、方位角をはじめ、以下の方法でBS/CSアンテナの角度調整に必要な情報を得ることができます。
BSコンパスでの確認手順
- アプリを起動し、GPS機能で現在地を設定します。
- 画面に方位磁石と、BS放送衛星(CS通信衛星も位置は同じ)のあるべき方向が矢印で表示されます。
- スマートフォンをアンテナの取り付け金具のあたりで水平に持ち、本体をゆっくり回して矢印が真上に来るように合わせます。
- その方向が、ご自宅から見た正しい「方位角」です。
- 同時に、その地域での正しい「仰角」も画面に表示されます。
このアプリを使えば専門的な知識がなくても、方位磁石が表示されたスマートフォンをあてがうことで、誰でも簡単に自宅のBS/CSアンテナを向けるべき正確な方向(仰角、方位角)を知ることができます。
その他にも、同じく日本アンテナの公式サイトをはじめ、インターネット上のサイトで、日本各地の適切な仰角、方位角の一覧を確認できます。またBS/CSアンテナには、角度調整部に日本の主要都市における仰角、方位角が表記されている機種もあります。
ただスマートフォンを使うことができれば、やはり「BSコンパス」を使うことが確実と言えます。
【実践編】アンテナ方向を自分で調整する完全手順
地デジ・BS/CSアンテナとも、受信感度を安定させるために向けるべき方向がわかったら、いよいよ実際の調整作業に入ります。
ただし、高所での角度調整作業は危険が伴うため、行う場合は安全確保が最優先です。
ここでは安全にアンテナの調整作業を進めるための注意点から、必要な道具、そしてアンテナの種類ごとの具体的な調整手順までを詳しく解説します。
【最重要】作業前に必ず確認!安全のための5つの注意点
DIYでのアンテナ角度調整はコストを抑えられますが、事故が起きては元も子もありません。
作業を始める前に、以下の点を必ず守ってください。
| 注意点 | 具体的な行動 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 1. 高所作業の危険性を認識する | 2m以上の高所で作業する場合は、ヘルメットや安全帯を必ず着用する。 | 万が一の転落時に、頭部への衝撃を和らげ、重大な事故を防ぐためです。 |
| 2. 必ず2人以上で作業する | 1人が屋根の上でアンテナを調整し、もう1人が室内でテレビのアンテナレベルを確認する役割分担が理想。 | 作業効率が上がるだけでなく、事故の際にすぐ助けを呼べるためです。 |
| 3. 悪天候の日を避ける | 雨の日や風の強い日は絶対に作業しない。雨上がりで屋根が濡れている場合も避ける。 | 足元が滑りやすく、強風でバランスを崩すなど、転落リスクが非常に高くなるためです。 |
| 4. 動きやすい服装と滑りにくい靴 | 体にフィットし引っかかりにくい服装、靴底がゴム製の滑りにくい靴を着用。軍手も推奨。 | 安全な体勢を維持し、不意の転倒を防ぐためです。 |
| 5. 感電のリスクを避ける | アンテナの近くに電線がある場合は特に注意。ブースター電源部のプラグは抜いておく。 | アンテナや工具が電線に触れると感電する危険があるためです。 |
※上記は主な注意点になります。
基本的に、DIYでの角度調整は、ベランダや屋上フロアなど、足場が確保できて安全に作業を行える位置に設置されたアンテナの場合のみ、作業をおすすめします。
屋根の上など不安定な高所に設置されているアンテナの場合は、作業中の転落事故はもちろん、アンテナや機材を落として屋根材や家財などを破損してしまう、さらには無関係の人やものを傷つけてしまうなどのリスクも高いため、決して行わないでください。
危険な高所でのアンテナ角度調整は、高所作業専門の技術を持ち、万全の装備も整えた、アンテナ工事の専門業者にお任せください、
これだけは揃えたい!アンテナ調整に必要な道具リスト
スムーズにアンテナ角度調整の作業を進めるために、事前に以下の道具を準備しておいてください。
| 道具 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| スパナ / モンキーレンチ | アンテナを固定しているボルトやナットを緩めたり締めたりするために使用します。 | アンテナの種類に合ったサイズが必要です。 |
| スマートフォン | 方向確認用のアプリ(地デジアンテナ調整、BSコンパスなど)を使用します。 | 事前に必要なアプリをダウンロードし、充電もフルにしておきます。 |
| テレビとリモコン | アンテナレベルを確認するために必要です。 | 室内で確認する人と手早く連携が取れるようにしましょう。 |
| 脚立 / はしご | ベランダや屋根など、高所のアンテナにアクセスするために使用します。 | 安定した場所に設置し、昇り降りに注意しましょう。 |
| 軍手 | 手の滑りを防ぎ、怪我を防止します。 | |
| ビニールテープ | 作業後にボルト部分などを保護(防水)するためにあると便利です。 |
※上記は必要となる主な道具になります。他にも後述する簡易型のアンテナレベルチェッカーがあれば作業が便利になります。
地デジアンテナの調整手順|テレビの「アンテナレベル」が鍵
基本的な機材を揃えたら、まず、地デジアンテナ主要機種の角度調整について解説します。
地デジアンテナの調整でもっとも重要な指標となるのが、テレビの機能で表示できる「アンテナレベル」です。
これは、アンテナからテレビのチューナーまで届いている電波の強さ(品質)をテレビ画面の数値やグラフで示したもので、この数値を最大レベルにすることが調整のゴールとなります。
アンテナレベルの表示方法
- テレビのメーカーやモデルによって異なりますが、一般的にリモコンの「設定」や「サブメニュー」から「地デジ放送受信設定」「UHFアンテナ設定」といった項目を選ぶと確認できます。
- 調整作業中は、この画面を常に表示しておきます。
以下、機種別の角度調整の流れについて解説します。
八木式アンテナ(魚の骨型)の場合
八木式アンテナとは、一般的には屋根の上などの高所で、マスト(ポール、支柱)の先に固定されている、古典的な魚の骨のようなアンテナです。
現在でも受信性能ではもっとも優れていて、指向性も高い(正面の受信範囲も狭い)アンテナ機種ですが、それだけにわずかな角度のズレで受信感度が低下しやすいという特徴もあります。
以下、八木式アンテナの角度調整の手順を解説します。ただくれぐれも実際の作業は、安全を確保できる位置にアンテナが設置されている場合に限ってください。
- アンテナをマスト(支柱)に固定しているボルトを、レンチを使って少しだけ緩めます。アンテナが手で動かせる程度の固さが目安です。
- 室内でアンテナレベルを確認している人と連絡を取りながら、アンテナ全体をゆっくりと左右に動かします。
- 事前に調べた電波塔の方向を中心に、テレビ画面でアンテナレベルの数値がもっとも高くなるポイントを探します。
- 数値が最大になった位置でアンテナの動きを止め、緩めたボルトをしっかりと締め直して固定します。
- 最後に、すべてのチャンネルが問題なく映るかを確認して作業完了です。
デザインアンテナ(箱型)の場合
デザインアンテナは平面アンテナとも呼ばれ、一般的に住宅の壁面やベランダに設置される薄い箱型(パネル状)の地デジアンテナです。
八木式アンテナに比べると本体性能や設置位置からやや受信感度が低くなりますが、住宅の見た目に影響しない上、風雨などの影響も受けにくく長持ちするというメリットがあります。
受診性能に応じて指向性もやや低いため、多少の角度のズレには強く、角度調整も行いやすいという面もあります。
以下、デザインアンテナの場合の角度調整の手順になります。
- 壁面やベランダの取り付け金具にある、角度を調整するためのボルトを少し緩めます。
- 基本的な手順は八木式アンテナと同じです。アンテナの正面を電波塔の方向に向け、アンテナレベルが最大になるように左右の角度を微調整します。
- デザインアンテナは、主に背後の中心部に通った短いマストを軸に、正面側を左右に調整します。ただ機種によっては、左右に蝶番上の固定部があり、どちらか一方を固定し、扉を開けるようにして調整するモデルもあります。詳しくはアンテナの取扱説明書をご確認ください。
- デザインアンテナは八木式に比べて可動範囲が狭い場合がありますが、その範囲内でもっとも受信状態の良い位置を探します。
- 最適な位置が決まったら、角度調整部のボルトをしっかりと締めて固定します。
- やはりすべてのチャンネルの映りを確認して、問題がなければ終了です。
BS/CSアンテナの調整手順|数ミリのズレも許されない精密作業
BS/CSアンテナの調整は、アンテナを向ける方向は日本全国で東経110度上空に固定されていますが、各地域で仰角、方位角の調整が必要となり、地デジアンテナよりも格段に精度が求められます。
わずか1度のズレでも受信できなくなる場合があるため、決してあせらず慎重に作業を進めてください。
またBS/CSアンテナの注意点として、角度調整の他にも、静止衛星の方向とアンテナのディッシュを結ぶ電波の経路に、山や建物をはじめ、樹木やその枝、電柱や電線、洗濯物などのわずかな障害物があっても電波が遮られてしまい、受信できなくなることがあります。
そのためアンテナ角度調整の前に、静止衛星のある東経110度、南西方向の上空から、アンテナの位置までの直線状に、そのような障害物がないかを確認する必要があります。
その上で、具体的な角度調整作業の手順は、以下の通りになります。
- 仰角(上下の角度)の調整
- アンテナの取り付け金具側面にある仰角の目盛りを、アプリ「BSコンパス」などで調べた地域の角度に合わせます。
- ボルトを締めて、この角度を一旦仮固定します。
- 方位角(左右の角度)の調整
- テレビのアンテナレベル画面を表示させ、室内で確認する人と連携します。
- 方位角を固定しているボルトを少し緩め、アンテナを左右に動かせるようにします。
- アプリで調べた南西方向を中心に、本当に1ミリずつ動かすようなイメージで、アンテナをゆっくりと左右に振ります。
- 実際に方位角を1ミリほど動かした後、その角度の受信レベルがテレビのアンテナレベルに反映されるまで、数秒のタイムラグがあります。そのため少し調整した後、数秒待ってアンテナレベルを確認することを繰り返して、数値が最大になる一点を根気よく探すことが重要です。
- 固定と最終確認
- アンテナレベルが最大になった位置で、方位角のボルトをしっかりと締め付けます。
- この時、ボルトを締める力でアンテナの向きがズレないように注意が必要です。
- 次に仮固定していた仰角のボルトを緩め、少しずつ角度を動かして、あらためてアンテナレベルが最大になるよう微調整を行い、最適な角度を確認できたら、あらためて仰角のボルトもしっかりと締め込みます。
- 最後に、BS放送(契約している場合がCS放送も)の各チャンネルが問題なく映ることを確認して、作業は完了です。
以上のようにBS/CSアンテナの角度調整は、アンテナを向ける方向はある程度わかりやすい半面、正確な角度調整の手順が複雑になります。
またおおよその仰角、方位角はアプリなどで特定できる一方、最大の受信レベルを確保するためには、現場ごとの微調整も必要となるため注意が必要です。
DIYのアンテナ角度調整に「アンテナレベルチェッカー」は必要か?
DIYでアンテナの角度調整を行う際に、実際の受信レベルを正確に測定できる「アンテナレベルチェッカー(サテライトファインダー)」という専用の測定器を使う選択肢もあります。
このアンテナレベルチェッカーには、以下のようにただ受信レベルを目盛りで確認できるだけの簡易的な製品から、電波の品質まで細かく割り出せるプロ仕様の機器もあり、性能に応じて価格も変わってきます。
| 種類 | 価格帯 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 簡易タイプ | 1,000円〜3,000円程度 | ・安価で手に入る。 ・アンテナのすぐそばでレベルを確認できる。 ・室内と連携する手間が省ける。 |
・表示が大まかで精密な調整には不向きな場合がある。 ・電源供給が必要なモデルもある。 |
| プロ仕様 | 数万円〜数十万円 | ・非常に正確な測定が可能。 ・電波の品質(MER/BER)も測定できる。 |
・高価すぎる。 ・操作や表示の読み取りに専門知識が必要。 |
※上記はおおよその機器の分類になります。
結論として、方位角をおおよそ電波塔の方向に向ければ十分となる、一般的な地デジアンテナのDIY角度調整であれば、テレビに表示されるアンテナレベル機能で十分に対応可能です。
しかし、BS/CSアンテナの角度調整のように手順が多く、非常にシビアな調整が必要で、また一人で作業を完結させたい場合には、簡易タイプのチェッカーがあると作業効率が格段に上がります。
地デジアンテナの場合も、
このような機器は角度調整において絶対に必要というわけではありませんが、千円台からの投資で時間と手間を大幅に削減できる可能性があるため、購入をご検討される価値はあるでしょう。
調整しても映りが改善しない…考えられるアンテナ方向以外の原因
もし、ご自宅でアンテナの方向を丁寧に調整しても、テレビの映りが改善しない場合は、原因は他にあるのかもしれません。
アンテナのトラブルは、単なる方向のズレだけでなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っているケースも考えられます。
ここでは、専門家でなければ特定が難しい、アンテナの方向以外にテレビ画面が乱れる主な原因を、3つご紹介します。
原因1:アンテナ本体の故障・経年劣化(寿命は約10年)
屋外に設置されているテレビアンテナは、雨や風、紫外線に常に晒されており、時間と共に劣化していきます。
アンテナの一般的な寿命(耐用年数)は、八木式アンテナやBS/CSアンテナで約10年から15年と言われています。
なお対候性の高いデザインアンテナやユニコーンアンテナの場合は、15年から20年以上になります。
また特に、沿岸部で潮風に当たる場所、野鳥や積雪の多い地域では、サビや腐食、鳥が留まるなどの影響によるアンテナ劣化がより早く進むことがあります。
アンテナ内部の部品が故障したり、八木式アンテナの素子(電波を集めるために並んでいる短い横棒の部分)が折れたりしていると、いくら方向を合わせても電波を正常に受信することはできません。
設置から10年以上経過しているアンテナの場合は、角度のズレが生じやすくなるだけでなく、全体的な老朽化によってアンテナ本体の交換が必要な可能性が高くなります。
原因2:ブースターや分配器など周辺機器の不具合
アンテナで受信した電波は、ケーブルを通ってテレビに届くまでに、以下のようにさまざまな周辺機器を経由します。
| 機器名 | 役割 | 故障時の症状 |
|---|---|---|
| ブースター(増幅器) | アンテナが受信した電波を増幅して、安定した受信レベルを確保する。 | すべてのチャンネルで映りが悪くなる、またはまったく映らなくなる。 |
| 分配器 | 1本のアンテナからの電波を、複数の部屋のテレビに分ける。 | 特定の部屋だけ、またはすべての部屋で映りが悪くなる。 |
| アンテナケーブル | アンテナや各機器を接続する。 | ケーブルの劣化や断線、接続部の緩みにより、映りが不安定になる。 |
※上記の他にも現場の条件によっては、混合器や分波器、アッテネーターなどの機器が設置される場合もあります。
これらの機器もアンテナと同様の屋外や、天井裏などに設置されていることが多く、経年劣化や雨水の侵入などで故障することがあります。
特に、電波を増幅する電子機器であるブースターが故障すると、各テレビの受信レベルは著しく悪化します。
原因3:周辺環境の変化による電波の遮断
アンテナを設置した当初は問題がなくても、その後の周辺環境の変化によって地デジや衛星放送の電波が遮られてしまうことがあります。
- 建造物の影響:近隣に高層マンションやビルが建設された場合、電波塔からの電波が直接、遮られてしまいます。また前述の通り静止衛星からの電波は、わずかな障害物にも遮られやすくなります。
- 樹木の影響:自宅や隣家の庭木など成長し、枝葉がアンテナと電波塔や静止衛星の間に入り込むと、やはり電波を遮ってしまいます。特に樹木が雨に濡れた場合などは、地デジ電波を吸収しやすくなります。
- 天候の影響:一部の季節や大雨、大雪の際は、空気中の水分が地デジ電波を吸収して弱めることがあります。衛星放送の場合は、一定以上に激しい雨や雪が12GHz帯を吸収し散乱させる「降雨減衰」「降雪減衰」という現象が起こって、一時的に受信レベルが大きく低下することがあります。
これらのケースでは、アンテナの方向調整だけでは解決できず、アンテナの設置場所をより高い位置に変更する、より受信性能の高いアンテナや高性能ブースターに交換するなど、専門的な対策が必要になります。
難しい作業はプロに依頼!アンテナ工事業者の選び方と費用相場
DIYでの調整を試みても改善しない場合や、屋根の上など危険な場所での作業にご不安を覚えられる場合は、決してご無理をなさらず専門のアンテナ工事業者へとご依頼になるのが、もっとも安全で確実なご選択といえます。
しかし、いざ業者を探すとなると「具体的にどこに頼めばいいのか分からない」「高額な請求をされないか不安」といった点で戸惑われる方も多いでしょう。
この項目では、安心して任せられる優良な業者を見極めるためのポイントと、適正な費用相場について解説します。
アンテナ工事の費用相場は?作業内容別に解説
まずは、テレビアンテナの調整、修理などの工事にかかる費用の目安を知っておくことが、不当な高額請求を避けるための第一歩です。
料金は作業内容によって大きく異なりますので、以下の相場表を参考にしてください。
| 作業内容 | 費用相場(税込) | 作業内容の詳細 |
|---|---|---|
| アンテナ方向調整 | 5,000円 ~ 15,000円 | アンテナの向きを調整し、受信レベルを最適化する作業。 |
| アンテナ修理 | 5,000円 ~ 15,000円 | 素子やケーブル接続部など、軽微な故障で費用が安く済む場合の修理。 |
| 地デジアンテナ交換 | 20,000円 ~ 50,000円 | 古いアンテナを撤去し、新しいアンテナ(八木式、デザインなど)を設置する。 |
| BS/CSアンテナ交換 | 18,000円 ~ 45,000円 | 新しいBS/CSアンテナを設置・調整する。現在は4K8K対応モデルが中心。 |
| ブースター設置・交換 | 15,000円 ~ 30,000円 | 電波を増幅するブースターを新設、または交換する。 |
| 高所作業費 | 5,000円 ~ 10,000円 | 3階建ての屋根など、特殊な足場が必要な場合に発生する追加料金。 |
| アンテナ撤去・処分費 | 5,000円 ~ 10,000円 | 不要になったアンテナを撤去し、処分する作業。 |
※上記は主なアンテナ調整、修理の作業費です。
注意点
- 上記の金額はあくまで目安です。使用するアンテナの種類や部材、建物の構造によって変動します。
- 必ず作業前に、業者から内訳が明記された正式な見積書を提示してもらってください。
悪徳業者に注意!信頼できる業者を見極める4つのポイント
数あるアンテナ工事業者の中から、信頼できるパートナーを見つけるためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。
以下の4つのポイントを基準に、複数の業者を比較検討することをおすすめします。
ポイント1:料金体系が明確で、作業前の無料見積もりがあるか
優良な業者であれば、ウェブサイトやパンフレットに、アンテナ各機種の設置や修理、オプション工事などの料金体系を明確に記載しています。
また工事費に付随するアンテナ本体や部材などの機材についても、メーカー、モデルまで正確に明記されています。
工事費用については「アンテナ工事一式 〇〇円〜」といった曖昧な表示ではなく「基本工事費」「アンテナ本体代金」「追加作業費」など、何にいくらかかるのかが分かるようになっているかを確認しましょう。
さらに重要なのが、工事を契約する前に、必ず無料の現地調査と見積もりに対応してくれる業者を選ぶことです。
実際に現地の電波状況や建物の構造を確認した上で、まずは現場に最適な工事の提案と、作業内容および総額が記載された見積書を提示してもらいます。
そして、お客様がその内容にご納得できなければ、無料でキャンセルできる業者を選んでください。
見積もり後に追加費用が発生する可能性についても丁寧に説明してくれる、または見積もり外の料金は加算しないと明言してくれる業者であれば、より信頼できます。
ポイント2:施工実績が豊富で、ウェブサイトに事例が掲載されているか
豊富な施工実績は、そのまま技術力と経験の証となります。
公式サイトなどで年間の施工件数や累計件数などを公開している業者は、それだけ多くの現場を経験しているため信頼できます。
また、公式サイトに具体的な施工事例が写真付きで多数掲載されているかも重要な判断材料です。
「どのような建物で」「どのようなアンテナを」「どのように設置したか」が分かる事例を見ることで、その業者の技術レベルや仕事の丁寧さを推し量ることができます。
またご自宅で必要な工事に近い施工例を確認することで、実際の工事がどう仕上がるかの参考にもなります。
ポイント3:長期の工事保証やアフターフォローが充実しているか
テレビアンテナ工事は、設置して終わりではありません。
万が一、施工後に不具合が発生した場合や、台風などで再び向きがズレてしまった場合に、担当した業者が迅速に対応してくれる保証制度があるかどうかをご確認ください。
業者の保証期間が長いほど、その業者が自社の施工品質に自信をもってい証拠です。
業界の標準保証期間は3年から5年程度ですが、中には8年や10年といった長期保証を提供している優良業者も存在します。
保証内容(自然災害による故障が含まれるかなど、何が保証対象になるのか)もしっかりと確認しておいてください。
ポイント4:問い合わせ時の対応が丁寧で、専門知識があるか
実際に電話やメールで問い合わせをした際の、スタッフの対応も非常に重要な判断基準です。
- こちらの状況や質問を親身になって聞いてくれるか?
- 専門用語ばかり使わず、素人にも分かりやすく説明してくれるか?
- 質問に対して、的確な回答がすぐに返ってくるか?
丁寧で誠実な対応ができる業者は、社員教育がしっかりしており、顧客満足度を大切にしている証拠です。
最初のお問い合わせ時だけでなく、現地調査や見積りの際のスタッフの身だしなみや言葉遣いが整っていない業者。
さらにお客様のご質問にはっきりわかりやすく答えようとせず、強引に契約を進めてくるなど、少しでも不安や不信感を覚えるような対応があれば、その業者への依頼は見送ることが賢明です。
【PR】年間6,000件の実績!「あさひアンテナ」が選ばれる理由
上記の説明に対して「信頼できる業者と言われても、具体的にどこがいいのか分からない…」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
そんな方におすすめしたいのが、本記事にご協力いただいた優秀なスタッフが所属しており、関東・関西エリアにて圧倒的な実績を誇るアンテナ工事のプロ集団「あさひアンテナ」です。
同社は年間6,000件以上、創業以来の累計施工件数は30,000件を超え、現在も多くのご家庭で選ばれ続けています。
お客様から信頼されるその理由は、技術力はもちろんのこと、お客様の「ご不安」に徹底的に寄り添う独自のサービスにあります。
理由1:下請けなし!経験豊富な職人による「完全自社施工」の安心感
あさひアンテナでは、問い合わせの電話対応から、現地調査、施工、そしてアフターフォローまで、すべて経験豊富な自社の職人が一貫して担当します。
下請け業者を一切使わない「完全自社施工」にこだわることで、技術レベルのばらつきを防ぎ、常に高品質なサービスを提供。
さらに下請け業者への中間マージンも発生しないため、適正な価格で工事が可能です。
誰が工事に来るのかが明確で、工事完了後には担当職人の署名入り保証書をお渡しする「顔の見える安心感」があります。
理由2:業界最長クラス!自信の証である「10年間の長期保証」
施工品質への絶対的な自信があるからこそ、あさひアンテナは業界でも最長クラスとなる「10年間の長期保証」を実現しています。
工事後に万が一トラブルが発生しても、迅速かつ無償で対応。
長期保証のため保証書を紛失してしまった場合でも、社内の顧客情報データベースと照合して、確認が取れ次第、保証書がある場合と同様に対応するなど、お客様の長期的な安心を第一に考えたサポート体制を整えています。
理由3:「今日中に直したい」に応える最短即日のスピード対応
「テレビが急に映らなくなって、今日中に何とかしたい!」という緊急のニーズに応えるため、あさひアンテナは最短即日での工事対応を可能とする展開を行っております。
アンテナ工事の職人スタッフが関東・関西の各エリアを効率的に回り、ご連絡をいただいた後、お客様のご自宅からもっとも近い職人が駆けつけることで、スピーディーな問題解決を実現します。
フリーダイヤル対応には現場の専門知識を持つスタッフが常駐しており、いつでも気軽に相談できるのも大きな魅力です。
テレビが映らないなどのトラブルの場合は、まずはお客様の状況や受信環境などをお伺いし、考えられる原因とご自宅でも可能な対処法をご説明いたします。
このご説明だけで問題が解決できた場合は、料金は発生いたしませんので、テレビなどの急なトラブルの際は、まずはあさひアンテナのフリーダイヤル、または24時間受付のメールフォーム、LINEアカウントまでお気軽にお問い合わせください。
豆知識:台風被害なら火災保険が適用されるケースも
もし、アンテナの不具合や故障の原因が、台風や強風、大雪といった自然災害(地震を除く)か、近隣の爆発や落下物など予想外の事故である場合、ご加入の火災保険が適用される可能性があります。
多くの火災保険には、「風災・雹(ひょう)災・雪災補償」などの保証が付帯しており、住宅の設備であるテレビアンテナの修理・交換費用が補償の対象となるケースが多いのです。
以下、アンテナ故障に対する火災保険申請の詳しい手順についてご紹介します。
保険申請のポイント
- 保険会社へ連絡:まずはご加入の保険会社や代理店に連絡し、アンテナ修理が補償の対象になるか、申請に必要なものは何かを確認します。
- 被害状況の写真を撮る:修理を依頼する前に、アンテナが破損している状況や、周辺の被害状況などを写真に撮っておきましょう。
- 専門業者に見積もりを依頼:業者に修理を依頼すると同時に、保険会社に提出するための、正式な見積書と被害状況報告書などを作成してもらいます。
なお、「あさひアンテナ」では、アンテナ修理に伴い、火災保険申請に必要な写真、書類をすべて会社側でご用意するサポートも行っています。
さらに契約や法律上、お客様がご自身で行う必要がある、申請書類の作成、保険会社との交渉などについても、保険の専門知識を持つスタッフによる、万全のサポート体制が用意されています。
なお火災保険の申請については、損害額が、保険ごとに設定された自己負担額(免責金額)を下回る場合は適用外となることもあります。ただそれでも、アンテナ修理に高額な修理費用がかかる際には大きな助けとなります。
視線災害などによるアンテナ故障に際して、まずは一度、ご自身の保険内容を確認してみることをおすすめします。
地デジ放送の受信レベルが下がる要因とは?
ここまでの記事でもいくつがご紹介しましたが、地デジ放送は、その放送の仕組みや使用されるUHF帯の性質から、アンテナの方向がズレる以外にも、さまざまな要因で受信レベルが低下することがあります。
以下、アンテナ角度以外で地デジ受信レベルが下がる主な要因を一覧でまとめました。トラブル時の参考にしてください。
| 要因 | 解説 |
|---|---|
| 電波塔からの距離 | 電波塔から遠い「弱電界地域」などでは、そもそも届く電波レベルが弱いため、高性能なアンテナ(素子数・素子数相当が高いもの)が必要です。 |
| 障害物による遮蔽 | アンテナから近く、電波塔の方向に高層ビルや山、樹木などがあると、電波が遮られて弱まることがあります。 |
| 気候や天候の影響 | 暑さで空気が膨張する季節では電波が伝わりにくくなるほか、大雨や大雪などの水分は電波を吸収するため、一時的に受信レベルが低下することがあります。 |
| 電波ノイズの干渉 | 近くに強い電波を発する施設(携帯電話の基地局など)がある、家電製品からノイズが発生するなどのケースでは、地デジ受信に影響が出ることがあります。 |
| システム機材の問題 | アンテナ本体だけでなく、ケーブル、ブースター、分配器などの劣化や故障も、十分な電波を送信できなくなり、受信レベルが低下する大きな原因です。 |
| テレビ本体の不具合 | 前述した再起動が有効な軽度の不具合のほか、内部基盤の経年劣化による機能低下や故障という可能性もあります。テレビの寿命は一般的に10年程度です。 |
※上記は地デジ放送の受信レベルが低下する主な要因です。
衛星放送(BS/CS)の受信レベルが下がる要因とは?
衛星放送についても、12GHz帯の電波がもつ性質やBS/CSアンテナでの受信の仕組みなど独自の性質から、地デジ放送と異なるさまざまな要因で、受信レベルが低下することがあります。
以下、BS/CSアンテナの角度のズレ以外で考えられる、衛星放送の受信レベル低下の要因を一覧にまとめました。
| 要因 | 解説 |
|---|---|
| 障害物による遮蔽 | 静止衛星のある南西方向の空に、建物、木の枝、電線、さらには洗濯物など少しの障害物がかかっていても、12GHz帯の電波は簡単に遮断されます。 |
| 降雨・降雪減衰 | 衛星放送の電波は波長が短いため、一定以上の大雨や大雪の影響を顕著に受けます。その場合、一時的に受信レベルが大幅に低下し、「E202」エラーが出やすくなります。 |
| 4K8K放送の特性 | 新4K8K衛星放送の一部4K8Kチャンネルで使われる「左旋円偏波」は、従来の「右旋円偏波」より高い周波数帯のため、古いアンテナやケーブル、分配器などでは受信・伝送できません。4K8K対応機器への交換が必要です。 |
| 電源設定の問題 | テレビやレコーダーの設定で、BS/CSアンテナへの電源供給が「オフ」になっていると、アンテナの「コンバーター」が作動しないため電波を受信できません。 |
| システム機材の問題 | 地デジ放送と同様、ケーブルや分配器などが衛星放送の周波数帯に対応していない、または劣化していると、受信レベルが低下します。 |
※上記は地デジ放送の受信レベルが低下する主な要因です。
まとめ|アンテナの方向トラブルは手順に沿って安全・確実に解決しよう
お住まいで急にテレビの映りが悪くなると、皆様はあわててしまうこともあるかと思います。しかしそのようなときこそ、まずは落ち着いて原因を切り分けることが大切です。
この記事で解説した手順に沿って、ひとつずつ確認していきましょう。
以下、本記事の概要をあらためて簡単にまとめます。
- ステップ1:まずは室内で簡単チェック
- テレビの再起動や配線の確認など、安全な場所でできることを最初に試してください。
- これだけで問題が解決することも少なくありません。
- ステップ2:自分で調整されるなら、準備と安全を最優先に
- スマホアプリなどを活用して、アンテナが向くべき正しい方向を正確に把握します。
- 高所での作業は必ず2人以上で行い、ヘルメットを着用するなど、安全対策を徹底してください。
- 屋根の上での作業など、危険を伴う作業は、決してご自宅では行わないでください。
- ステップ3:少しでもご不安があれば、無理はせずプロにご相談
- アンテナを調整しても改善しない場合や、作業に危険を感じる場合は、迷わず専門業者に依頼してください。
- 料金体系が明確で、長期保証があり、実績豊富な信頼できる業者を選ぶことが重要です。
テレビのアンテナトラブルは、正しい知識と手順で対処すれば、必ず解決できます。
ご自宅での対処が難しい場合は、「あさひアンテナ」などの優良な業者へと、早急にご相談になることをおすすめします。
この記事が、お客様が快適にテレビを視聴できるアンテナ環境と日常を取り戻すお役に立てれば、筆者としても幸いです。