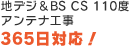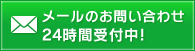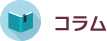【プロに聞く】テレビのチャンネル設定(チャンネルスキャン)ができない原因と対処法をメーカー別に解説
皆様が新しいテレビを購入されたとき、または引っ越しでテレビを移動したとき、あるいは突然テレビが映らなくなったときなど。
第一のステップとして「チャンネル設定」という作業が必要だと知って、少し戸惑ってしまった経験はありませんか。
テレビに付属の説明書(マニュアル)はどこにしまったか分からず、リモコンのたくさんのボタンや、難しいテレビの設定画面を前に、途方に暮れてしまう方も少なくはないでしょう。
「チャンネル設定の仕方が分からない」
「どこから操作すればいいのか迷ってしまう」
「テレビアンテナ工事などの専門業者に頼むのは費用も手間もかかるから、できれば自分で解決したい。」
しかし設定画面からチャンネルスキャンを試してみても、なぜかうまくいかない。
お住まいでそのような状況に陥ってしまい、焦りや不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
どうかご安心ください。
この記事では、テレビのチャンネル設定の基礎知識から、実行してもうまくいかない原因、そして誰でも簡単にできる対処法を、テレビの主要メーカー別に徹底解説します。
本記事は、テレビなど家電製品に関する詳しい知識を持つライターが執筆を担当しています。さらに執筆に当たっては、アンテナ工事専門業者「あさひアンテナ」に所属し、テレビ本体のトラブルに対処した経験も豊富なスタッフによる、正確な知識と経験に基づく監修も受けています。
したがって、記事内容の正確さについては折り紙付きといってもいいでしょう。
この記事を一通りお読みいただければ、無事にチャンネルスキャンを進めることができて、いつものようにテレビ番組を視聴できる日常を取り戻せるでしょう。
まずは基本から!テレビのチャンネル設定が必要になるのはどんな時?
チャンネル設定とは、テレビを設置してアンテナケーブルと接続した後、テレビ本体がテレビ電波から受信できるチャンネルを確認して、チャンネル番号に当てはめていく作業を言います。
テレビが自動的にチャンネルをスキャン(詳しく調べる)、サーチ(探す)することから、メーカーによっては「チャンネルスキャン」「チャンネルサーチ」とも呼ばれます。
そして、そもそもなぜ、どのようなときに、このテレビのチャンネル設定(チャンネルスキャン)が必要になるのでしょうか。
普段のテレビ利用で、チャンネル設定を行うべき主なケースには、以下の4つが挙げられます。まずはご自身の状況が、どれに当てはまるかを確認してみてください。
| 設定が必要なケース | 状況 |
|---|---|
| 1. テレビを新しく購入・買い替えた時 | 工場から出荷された新しいテレビは、日本のどの地域で使われるか決まっていません。 そのため、ご家庭で初めて電源を入れた際に、その地域で受信できる放送局の情報をテレビに登録する必要があります。 |
| 2. 引っ越しをした時 | 住む地域が変わると、受信できる放送局や使用されている周波数(チャンネル)が変わります。 以前住んでいた場所の設定のままでは、新しい地域の放送(チャンネル)を受信できないため、再設定が必須です。 |
| 3. 放送電波の変更があった時 | お住まいの地域で、テレビの電波を送信している中継局の周波数が変更されることがあります。 この場合、テレビ側も新しい周波数に合わせるために再スキャン(再設定)が必要になります。 |
| 4. テレビの受信トラブルが起きた時 | 「特定のチャンネルだけ映らない」「エラーメッセージが表示される」といったトラブルが発生した場合、 テレビ内部の設定情報が何らかの原因でリセットされてしまった可能性があります。 この場合は、チャンネルを再設定することで改善することがあります。 |
※上記はチャンネル設定が必要となる主なケースです。
これらの状況では、テレビによって「チャンネルスキャン」や「チャンネルサーチ」と呼ばれる作業を行い、テレビに最新の放送局情報を読み込ませることが必要です。
【図解で簡単】テレビのチャンネル設定(再スキャン)基本の4ステップ
同じテレビの初期設定であるチャンネル設定の作業でも、メーカーや機種によって、チャンネルスキャンやチャンネルサーチといった名称があるように、リモコンのボタン名やメニューの表示もそれぞれ異なります。
しかし、基本的な作業は同じであるため、設定作業の流れもほとんど同じです。
まずは、各種どのテレビにも共通する大まかな手順を掴んでおいてください。
1. 設定画面を開く
- リモコンの「メニュー」や「ホーム」、「設定」といったボタンを押して、テレビの設定メニュー全体を表示させます。
2. チャンネル設定を選ぶ
- 設定メニューの中から「初期設定」「放送受信設定」「設置設定」などの項目を探します。
- さらにその中にある「チャンネル設定」や「チャンネルスキャン」「チャンネルサーチ」といった項目を選択します。
3. お住まいの地域を設定
- 画面の指示に従い、お住まいの都道府県や郵便番号などを入力します。
- この情報をもとに、テレビがスキャンする電波の候補を絞り込みます。
4. 自動スキャンを開始
- 「自動設定」「初期スキャン」「再スキャン」などの項目を選択すると、テレビが自動で受信可能なチャンネルを探し始めます。
- 電波内の各チャンネルを確認していくため、スキャンには数分かかる場合がありますが、完了するまでそのまま待ってください。
以上が基本的な流れです。
この4ステップを覚えておけば、どのメーカーのテレビでも落ち着いて対応できるはずです。
※なお、機種や受信環境によっては自動スキャンでチャンネルが見つからない場合があります。その際は、手動でチャンネルを追加・設定する方法を試す必要があります。
チャンネル設定方法:AQUOS・VIERA・BRAVIA・REGZA
ここからは、国内の主要テレビメーカー4社(シャープ、パナソニック、ソニー、東芝)の具体的なチャンネル設定手順を解説します。
お手元のリモコンをご用意の上、お使いのテレビメーカーの項目をご確認ください。
| メーカー名 | ブランド名 | 主な操作開始ボタン |
|---|---|---|
| シャープ | AQUOS (アクオス) | ホーム |
| パナソニック | VIERA (ビエラ) | メニュー |
| ソニー | BRAVIA (ブラビア) | ホーム |
| 東芝 | REGZA (レグザ) | 設定 |
以下、メーカー別の詳しい手順を解説していきます。
シャープ(AQUOS)のチャンネル設定手順
シャープのAQUOS(アクオス)は、リモコンの「ホーム」ボタンから設定を開始するのが一般的です。
- リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- ホーム画面が表示されたら、左右ボタンで「設定」または歯車のマークを選び、「決定」を押します。
- 設定メニューの中から「視聴準備」を選択し、「決定」を押します。
- 「テレビ放送設定」を選択し、「決定」を押します。
- 「チャンネル設定」を選択し、「決定」を押します。
- 「地上デジタル」を選択し、「地上デジタル – 自動」を選び、「決定」を押します。
- 「する」を選択すると、チャンネルスキャンが開始されます。
- スキャンが完了すると、受信できたチャンネルが一覧で表示されます。
パナソニック(VIERA)のチャンネル設定手順
パナソニックのVIERA(ビエラ)は、リモコンの「メニュー」ボタンが設定の入り口です。
- リモコンの「メニュー」ボタンを押します。
- 画面に表示されたメニューから「設定する」を選び、「決定」を押します。
- 「初期設定」を選び、「決定」を押します。
- 「設置設定」を選び、「決定」ボタンを3秒以上長押しします。
- チャンネル設定画面が表示されたら、「地上デジタル」を選び、「決定」を押します。
- 「再スキャン」を選び、「決定」を押すとスキャンが始まります。
- 完了後、受信したチャンネルの一覧が表示されたら設定は終了です。
ソニー(BRAVIA)のチャンネル設定手順
ソニー(sony)のBRAVIA(ブラビア)も、多くのモデルで「ホーム」ボタンから設定を行います。
- リモコンの「ホーム」ボタンを押します。
- 画面右上の「設定」または歯車のマークを選び、「決定」を押します。
- メニューの中から「放送受信設定」を選び、「決定」を押します。
- 「チャンネル設定」を選び、「決定」を押します。
- 「地上デジタル」を選び、「決定」を押します。
- 「地上デジタル自動チャンネル設定」または「再スキャン」を選び、「決定」を押します。
- スキャンが開始され、完了すると自動的に元の画面に戻ります。
東芝(REGZA)のチャンネル設定手順
東芝のREGZA(レグザ)は、リモコンに「設定」ボタンがあるモデルが多いのが特徴です。
-
- リモコンの「設定」ボタンを押します。
- 設定メニューから「初期設定」や「視聴準備」を選び、「決定」を押します。
- 「チャンネル設定」を選び、「決定」を押します。
- 「地上デジタル自動設定」を選び、「決定」を押します。
- 「再スキャン」を選択し、「決定」を押します。
- お住まいの地域設定を確認する画面が出たら、内容を確認して「はい」を選択します。
- チャンネルスキャンが開始され、終了すると設定完了です。※三菱やTCLなど、メニュー構成が異なる機種でも「設定 → 放送受信 → チャンネル設定(スキャン)」の流れは共通なので、近い項目名を探して進めてください。「設定できない…」は解決できる!原因別の対処法チェックリスト
上記の基本的な手順通りに進めても、テレビのチャンネル設定が完了しない場合、テレビ電波が正常に届いていないため、テレビの映りが悪い状態であるなど、何か他の原因が隠れている可能性があります。
以下のチェックリストを上から順に確認していくことで、問題の原因を特定し、解決に導くことができます。
原因①:アンテナケーブルの接続は正しい?
もっとも基本的ですが、意外と見落としがちなのがアンテナケーブルの接続です。
まずは以下の点を確認してみましょう。
| 確認ポイント | 詳細 |
|---|---|
| テレビ側の接続 | テレビの背面にある「地上デジタルアンテナ入力」または「UHFアンテナ入力」、または「BS/CSアンテナ入力(衛星放送)」という端子に、ケーブルが奥までしっかりと差し込まれているか確認します。 |
| 壁側の接続 | 壁にあるアンテナ端子にも、ケーブルが緩みなく接続されているか確認します。ネジ式の端子の場合は、しっかりと締まっているか指で確かめてください。 |
| ケーブルの状態 | ケーブルが途中で急角度に折れ曲がっていたり、家具などの下敷きになっていたり、ペットにかじられるなどして損傷したりしていないか、全体を目で見て確認します。 |
| 分配器やレコーダー経由の場合 | レコーダーや分配器などを介してケーブルを接続している場合は、それらの機器の接続もすべて確認します。「入力」と「出力」を間違えて接続しているケースもよくあります。 |
※上記は主なチェックポイントになります。
アンテナケーブルの不調については、ケーブルを一度抜き、再度しっかりと差し込み直すだけで問題が解決することも多くなります。
原因②:B-CASカードの接触不良や向きの間違い
地上デジタル放送の視聴には、デジタル信号の暗号化を解除する「B-CASカード(またはmini B-CASカード)」が、テレビ本体に正しく挿入されている必要があります。
このカードに問題があるとデジタル信号を解読できないため、テレビのチャンネル設定自体がうまくいかないことがあります。
このB-CASカードのトラブルの場合、テレビ画面に「E100」「E101」「E102」のエラーコードが表示されることが多くなります。
- カードの向きを確認する
- カードには矢印が印刷されています。テレビ本体の挿入口付近に示されている矢印の向きと合わせて、正しく挿入されているか確認してください。ICチップ(金色の部分)の向きも重要です。
- 一度抜き差ししてみる
- 静電気やホコリなどでカードが接触不良を起こしている可能性があります。テレビの電源を切った状態でカードを一度抜き、乾いた柔らかい布でICチップ部分を優しく拭いてから、再度しっかりと奥まで差し込んでみてください。
- カードが正しいか確認する
- 複数のテレビやレコーダーをお持ちの場合、別の機器のカードと入れ替わっていないか確認しましょう。
- B-CASカードには、BS/CSと地デジに対応する赤カード、地デジ専用の青カード、オレンジのCATV専用カードの3種類があります。同じ種類であれば機器で入れ替えても問題はありませんが、別々のカードを入れ替えると一部の放送が映らなくなることもあります。
- またB-CASカードそのものが破損して機能しなくなる場合もあります。この場合は他のテレビに挿入されている同じ種類のB-CASカードと差し替えることで、問題を切り分ける手掛かりになります。
- B-CASカードが破損している場合には、発行元の「B-CAS社」に申請して、有償でカードを再発行してもらう必要があります。
- 近年の4K8Kテレビなどでは、B-CASカードの代わりに、テレビ本体に内蔵されて同じ機能を持つ「ACASチップ」が使われている場合があります。このよう機器で上記のエラーコードが出た場合は、後述するテレビの再起動・リセットが対策になります。
原因③:エラーコード(E201/E202)が表示される|電波レベルの問題
チャンネル設定中や通常のテレビチャンネルを選択した場合に「E201」や「E202」といったエラーコードが表示される場合、テレビ本体に届いているテレビ電波の強度(アンテナレベル)に問題がある可能性が高くなります。
以下、各エラーコードの意味を解説します。
| エラーコード | 意味 | 主な原因 |
|---|---|---|
| E201 | 電波レベルの低下 | 電波の強度が少し不足している状態です。 大雨などの悪天候で一時的に発生することがあります。 |
| E202 | 信号が受信できません | 電波を全く受信できていないか、非常に弱い状態です。 アンテナの向きのズレや、ケーブルの断線、アンテナ自体の故障などが考えられます。 |
※上記は各エラーコードで考えられる主要な原因です。
多くのテレビには、受信している電波の強度を確認する機能(アンテナレベル画面)が備わっています。
リモコンの「設定」メニューから「放送受信設定」→「アンテナ設定」などの項目に進むと、現在のアンテナレベルを数値やグラフで確認できます。(詳しい画面内容や数値の基準は、テレビのメーカーやモデルによって異なります)
このレベルがメーカーの推奨値よりも低い場合は、アンテナの受信レベルが低下しているため、アンテナの向きの調整や、電波を増幅する「ブースター」という機器の設置が必要になることがあります。
逆に、電波が強すぎて映りが悪くなる場合は、電波を適切なレベルに減衰させる「アッテネーター」機能を使うことで改善する場合があります。
なお、上記は基本的に地デジ放送(地上デジタル放送)の場合になります。
衛星放送(BS/CS)の場合は、宇宙空間の静止衛星から日本全域に電波を送信しているため、受信レベルは安定する傾向にあります。
一方で、アンテナ角度のわずかなズレ、アンテナを向けた方向に障害物が発生する、豪雨や大雪で電波が遮られる(降雨減衰・降雪減衰)などで受信レベルが大きく低下し、受信できなくなる場合もあります。
※ポータブルテレビの場合、屋内では電波が弱くてスキャンが失敗することもあります。まずは設置場所を窓際に移す/アンテナ線を差し直すなど、基本の確認から進めましょう。
テレビ本体の不具合の場合には「再起動(リセット)」を行う
現在のテレビ機器は、テレビを見る以外にも、録画やインターネット閲覧などさまざまな機能を持っており、コンピューターを内蔵して各機能を制御しています。
つまりパソコンやスマホ同様の精密な電子機器であるため、長時間の使用などで、内部基盤やプログラムの不具合などにより、一時的に正しく動作しなくなることがあります。
このような問題から、チャンネル設定が正しく進まないというケースも考えられます。
その場合は、テレビの「再起動(リセット)」が有効となる可能性が高くなります。
これはテレビ内部の通電を断ち、内部基盤などの機能を停止させることで機器を初期化し、不具合を含めてリセットする作業になります。
テレビのメーカーやモデルを問わず共通する再起動・リセットの手順は以下の通りです。
- テレビ本体の主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- そのまま数分程度待つ。
- 再度、電源プラグをコンセントに入れて、主電源を入れる。
この作業により、内部基盤などの初期化が行われ、軽微な不具合であれば解消されることがあります。
なお、テレビなどの機器によっては、設定画面からの操作など、独自の初期化方法を持つ場合もあります。
このような方法も不具合に効果がありますが、一方ででチャンネル設定を含むテレビのユーザー設定や。録画などの記録も初期化されるケースもあるため、まずはテレビの取扱説明書やメーカー公式サイトなどを確認してください。
それでも解決しないときは…?無理せずプロに相談しよう【PR】
ここまで紹介した対処法を試してもテレビが映らない、あるいはアンテナで十分な電波を受信できない状態で、アンテナ角度の調整や修理など、専門的な作業が必要だと思われる場合は、無理をせず専門業者に相談することをおすすめします。
特に、屋根の上などにあるアンテナの調整は高所作業となり、一般の方が行うと大変な危険を伴うため、決してご自分では行わないでください。
また安全な位置にあるアンテナでも、専門知識のない方が手を入れてしまうと、破損の状態を悪化させるなどの恐れもあります。
アンテナ工事の専門業者であれば、専用の測定器を使って現場の電波状況を正確に診断し、原因を特定してくれます。アンテナの破損や不具合に対しても、的確な修理を行ってくれます。
例えば、本記事の監修を担当した優秀な専門スタッフ(アンテナ職人)が所属するアンテナ工事のプロ集団であり、関東・関西エリアでアンテナ工事を手掛ける「あさひアンテナ」は、以下のような強みを持つ、業界内でも信頼できる優良業者のひとつです。
- 年間6,000件以上の豊富な施工実績
- さまざまな住宅環境や電波状況に対応してきた経験とノウハウがあります。
- 完全自社施工による高品質な工事
- 経験10年以上のベテランスタッフが、責任を持って施工にあたります。
- 業界最長クラスの10年保証
- 工事後の万が一のトラブルにも長期間対応してくれるので安心です。
- 無料の電波調査・見積もり
- 費用が発生する前に、まずは専門家による正確な状況判断を無料で受けられます。見積もり後のキャンセルも無料です。
アンテナ本体の大きな故障など、ご自宅では解決できない問題は、プロの知識と技術を頼てアンテナ修理などをご依頼になることが、もっとも安全で確実な方法になります。
まずはあさひアンテナのフリーダイヤル、メールフォーム、LINEアカウントまで、お気軽に電波調査や現場確認を依頼し、状況を相談してみてはいかがでしょうか。
【参考】地デジ放送の受信不良の要因とは?
チャンネル設定がうまくいかない根本的な原因として、地デジの電波受信そのものに問題があるケースも少なくありません。
地デジ放送(地上デジタル放送)は、「UHF(極超短波)」という電波のうち、470MHzから710MHzまでの周波数帯を、映像信号を乗せる電波として使っています。
この電波を、日本各地に設置された地デジの電波塔(東京スカイツリーなど)から周辺の一帯に送信して、各家庭の地デジアンテナ(UHFアンテナ)に届けています。
このUHFの電波は、波長の幅が40センチから60センチ程度である程度、広がりやすく、ビルなどの障害物を乗り越える力もある一方、長距離を送信されるほど弱まっていくなど、いくつかの性質を持っており、それが受信不良の原因となることがあります。
以下、地デジ放送で受信不良が発生する、主な要因について一覧で解説します。
| 受信不良の主な要因 | 解説 |
|---|---|
| アンテナの向き(指向性) | 地デジアンテナには真正面側で電波を受信しやすい向き(指向性)があります。アンテナが電波塔の方向からわずかでもズレてしまうと、受信レベルが大きく低下します。強風やアンテナに鳥が止まることなどで、角度が少しずつズレてしまうこともあります。 |
| 電波塔からの距離とアンテナ性能 | お住まいの地域が電波塔から近いか遠いか(電界地域)によって、必要なアンテナの受信性能(素子数)が変わります。電波の弱い地域で性能の低いアンテナを使っていると、安定した受信が難しくなります。 |
| 障害物による電波の遮断 | UHF波にはある程度、障害物を乗り越える性質もありますが、アンテナのすぐ近くに高い建物や隣家などがあると、障害物を乗り越えた電波も届きにくくなって受信レベルが弱くなります。お住まいの近隣に高層マンションが建設されると、急にテレビの映りが悪くなるのはこのためです。 |
| 天候の影響 | 地デジ電波は、気候や天候に影響を受け、電波レベルが変動します。特に雨や雪などの悪天候では電波が吸収されるため、一時的に受信レベルが大きく低下することがあります。 |
| 配線や機器の劣化・不具合 | アンテナ本体だけでなく、屋外のケーブルや、複数の部屋に電波を分ける分配器、電波を増幅するブースターといった周辺機器が、紫外線や雨風で劣化・故障していて電波が届かない可能性もあります。 |
| テレビ本体の不具合 | 前述した軽度な不具合の他、非常に稀なケースですが、テレビに内蔵されているチューナー(受信機)自体が故障していることも考えられます。 |
※上記は地デジ受信不良の主な要因になります。
地デジの受信不良はこれらの要因が複合的に絡み合って発生する場合も多く、正確な原因の特定には専門的な知識と測定器が必要になります。
【参考】衛星放送(BS/CS)の受信不良の要因とは?
衛星放送(BS放送、CS放送)のチャンネル設定がうまくいかない場合は、地デジ放送とは異なる原因を考える必要があります。
衛星放送では、宇宙空間で赤道軌道上を周回し、地上からは空の同じ位置に見える人工衛星(静止衛星)から、日本の全域に「12GHz帯(周波数帯が12GHz前後)」という非常に高い周波数の電波を送信しています。
この12GHz帯の電波は光のように直進性が高く、静止衛星から地上までまっすぐ届く半面、わずかな障害物(大粒の雨や雪なども含む)にも遮られやすいなどの性質があります。
この直進性の高い電波を、住宅に設置された、お皿のような形のパラボラアンテナで受信して、ディッシュ内部の放物面に反射させ、一点に集める形で受信しています。
このような放送の形式、アンテナの構造から、衛星放送では、地デジ放送とままったく異なる要因での受信不良が起こり得るのです。
以下、衛星放送特有の受信不良の原因について、一覧でご紹介します。
| 受信不良の主な要因 | 解説 |
|---|---|
| アンテナの精密な角度 | BS/CSアンテナは、南西方向上空、東経110度に位置する静止衛星に向けて、1ミリ単位での非常に精密な角度調整が必要です。 この角度が少しでもズレると、12GHz帯の電波をまったく受信できなくなります。 台風などの強風で角度がズレてしまうことが、もっとも多いトラブル原因です。 |
| 障害物による電波の遮断 | 12GHz帯の電波は光のように直進性が高く、アンテナと静止衛星の間に建物、樹木、電線、さらには洗濯物など、わずかな障害物があるだけでも電波が遮られ、受信できなくなります。 |
| 降雨減衰・降雪減衰 | 電波の周波数が高く、波長の幅が短い(25ミリ程度)分、大粒の雨や雪の影響を地デジよりも強く受けます。 大粒の雨や雪に電波が吸収され、乱反射が生じて受信が困難になり、衛星放送が映らなくなることもあります。 |
| アンテナへの電源供給 | BS/CSアンテナは、テレビまたはブースター電源部から電気を供給されて動作します。 テレビの設定で「BSアンテナ電源設定」などが「オフ」になっていると、アンテナが機能せず衛星放送を受信できません。 |
| 4K8K放送の対応 | 新しい4K8K放送を視聴するには、アンテナだけでなく、ケーブルや分配器、ブースターなどもすべて4K8K対応の製品(3224MHz対応)に交換する必要があります。 一部でも古い機器が混ざっていると、正常に受信できません。 |
※上記は衛星放送特有の主な受信トラブル例になります。その他、地デジ放送と同じく、配線部の機材やテレビ本体の不具合などで映らなくなる場合もあります。
衛星放送の受信トラブルは、精密な角度調整が必要なBS/CSアンテナの向きに狂いが生じたことが原因であるケースが大半を占めます。
特にアンテナが屋根の上などに設置されている場合、ご自身での調整は非常に難しいため、専門業者へのご依頼を推奨します。
チャンネル設定はトラブル解決の第一歩
テレビのチャンネル設定(チャンネルスキャン、チャンネルサーチ)は、一般の方には難しい作業に思われるかもしれません。
しかし、基本的な手順はどのメーカーも共通しており、この記事で紹介した4ステップに沿って操作すれば、ほとんどの場合はご自身で完了させることができます。
もし設定がうまくいかない場合も、あわてる必要はありません。
大半はテレビ周辺のささいな不具合が原因であるため、まずは「ケーブルの接続」「B-CASカードの確認」「テレビの再起動」といった簡単なチェックから試してみてください。
テレビ画面にエラーコードが表示される場合は、電波の受信レベルに問題がある可能性が高くなります。
またエラーコードには、記事内でご紹介したほかにもさまざまな種類があり、コードの意味を確認することが、トラブルの原因を探る重要な手掛かりになります。
さまざまな対処法を試しても解決しない、あるいはテレビアンテナの調整といった危険な作業が必要になった場合は、決して無理をせず、信頼できる専門業者にご相談ください。
プロに任せることで、安全かつ迅速に問題を解決し、快適なテレビ視聴の時間を取り戻すことができます。
関東、関西にお住まいの方であれば、あさひアンテナのフリーダイヤル(9:00-21:00)のほか、24時間受付のメールフォーム、LINEアカウントで手軽にお問い合わせも可能です。
あさひアンテナではフリーダイヤルなどへのお問い合わせも、現場経験も豊富なオペレーターがご対応します。
テレビが正常に映らない、チャンネル設定がうまく進まないといったご相談に対しては、まずはお住まいのエリアやアンテナ設備、テレビのご視聴環境などをお伺いし、まずは考えられる原因と、お住まいで可能な対処をすべてご案内します。
このご案内でトラブルが解消された場合は、料金は1円も発生いたしませんので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
もちろんアンテナの故障など、ご自宅での対処が難しいトラブルの場合は、ご依頼いただければあさひアンテナの優秀なスタッフがお住まいへと急行し、早急に原因を特定した上で、必要な工事について、業界最安に挑む見積もり料金でご提案いたします。
この場合も、お客様が正式に工事のご契約をされるまでは、料金はいっさい発生いたしませんのでご安心ください。
この記事がお客様のために、安定したテレビ視聴環境を実現するための一助となれれば、筆者としても幸いです。