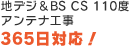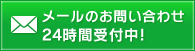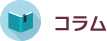【プロに聞く】テレビアンテナ設定完全ガイド:受信レベルが不安定で映らない原因と対処法、アンテナレベルの確認方法を全て解説
お住まいのテレビで画面にノイズが走る、エラーコードが表示されるなどして正常に映らなくなると、本当にお困りのことと思います。
テレビやアンテナの説明書を読んでも専門用語ばかりで、具体的に何をどうすれば良いのか途方に暮れてしまう方も多いのではないでしょうか。
いまそのような状態でお困りの方は、どうかご安心ください。
この記事では、テレビのアンテナ設定でお困りのお客様のために、専門知識がなくても分かるように手順を徹底解説します。
本記事の執筆に当たっては、アンテナ工事の専門業者「あさひアンテナ」に所属する熟練のアンテナ職人に取材を行っています。そしてさまざまな条件における適切なアンテナ設定の方法について、実経験に基づく的確な方法を伺いました。
記事の執筆は技術系の知識を持つプロのライターが担当し、写真や図をたくさん使用して、一般の方でもわかりやすく解決できる方法をご紹介しているので、きっとお客様のお役に立てるはずです。
この記事をお読みいただければ、多くの場合はご自身で問題を解決できるだけでなく、もし対処が難しく専門業者に頼むことになっても、トラブルの状況を正確に伝えることで、スムーズに依頼や作業を進めることができます。
まずはあせらず、できることからひとつずつ試していきましょう。
一般住宅でのテレビアンテナ設置に必要な基本設定とは?
まずは、ご家庭で設置される主要な二種類のテレビアンテナ、地上デジタル放送(地デジ放送)を受信するための地デジアンテナ(UHFアンテナ)と、衛星放送(BS放送、CS放送)を受信するためのBS/CSアンテナ(パラボラアンテナ)について、それぞれ設置する際に必要な基本設定をご説明します。
地デジ放送、衛星放送とも、放送の仕組みや電波の種類がまったく異なるため、受信するアンテナの種類もそれぞれ別個のものが必要となります。
またそれぞれの放送に応じて、アンテナにも独自の初期設定が必要となります。
以下の項目では、地デジアンテナ、BS/CSアンテナそれぞれの設置時に必要となる基本設定と基礎知識についてご説明します。
地デジアンテナ設置に必要な設定とは?
地上デジタル放送(地デジ放送)は、現在の日本における基幹的なテレビ放送であり、日本国内で地デジアンテナやフルセグ・ワンセグ受信機器を使用することにより、不特定多数の誰もが無料で受信、視聴できます。
一般の住宅でもテレビアンテナ設置工事の際には、まず基本のアンテナとして地デジアンテナを設置し、さらに衛星放送も視聴する場合には、BS/CSアンテナも追加設置するという流れになります。
地デジ放送は、かつてのアナログ放送と同じく、日本各地に設置されている地デジ電波塔から、周辺の一帯にUHF(極超短波)を送信しています。
このUHFという電波は、いくつかの独自の性質を持っています。
この性質を理解することが、適切なアンテナ設定の第一歩となります。
以下、UHFの主な性質と、対応するアンテナ設置のポイントを以下で解説します。
※上記は地デジ電波やUHFアンテナの主な性質になります。
これらの性質を踏まえ、一般の住宅に地デジアンテナを設置する際は、以下の3つのポイントが重要になります。
- 電波塔の方向を確認する
お住まいの地域にある電波塔の位置を確認し、アンテナをその方向に向けます。
これは、地デジアンテナには機種、モデルを問わず、アンテナの正面側でのみ受信性能を発揮する「指向性」という性質があるためです。
なお、お住まいの近隣にある電波塔の位置は、スマートフォンのアプリやウェブサイト(「A-PAB(一般社団法人放送サービス高度化推進協会)」公式サイト内の「地デジ放送エリアのめやす」など)で簡単に調べることができます。 - 障害物のない場所を選ぶ
電波塔の方向に、高いビルや山、大きな木などがない場所を選びます。
地デジ電波は、ある程度の波長の幅から障害物を乗り越えて広がることもできます。しかし障害物がアンテナのすぐ近くにある場合には、電波が障害物を乗り越える性質も及ばず、受信レベルが大きく低下するケースも見られます。 - 受信レベルが最大になる角度に調整する
地デジアンテナを設置して、テレビと接続したら、テレビのアンテナレベル表示機能を見ながら、受信レベルがもっとも高くなるように、アンテナの方位角(左右の角度)を微調整します。
この作業は、もっとも高く安定した視聴環境を確保するために非常に重要です。
一般的な戸建て住宅などでは、地デジアンテナは屋根の上など、できるだけ高い位置に設置する方が、周辺の障害物の影響を受けにくく、角度調整も行いやすいため、アンテナで安定した電波の受信レベルを確保しやすくなります。
一方で電波塔からやや近い距離で、電波塔の方向に障害物がないなどの条件が整っていれば、壁面などの低い位置に、人気の高いデザインアンテナを設置するなどの工事も可能になります。
BS/CSアンテナ設置に必要な設定とは?
衛星放送はその名称の通り、地球の周囲、約36,000キロ上空を自転に合わせて周回しているため、地上からは常に空の同じ位置に見える人工衛星(静止衛星)から、日本の全域に放送電波を送信する仕組みです。
地デジ放送とは放送の仕組みから電波、使用するアンテナの種類まで異なるため、アンテナ設定のポイントも変わってきます。
衛星放送で使われる12GHz帯の電波は、長距離を送信されるため、地デジのUHF電波よりもさらに周波数帯が高く、光のような直進性を持つのが特徴です。
そのため、BS/CSアンテナの設定には、地デジアンテナよりも精密さが求められます。
以下、地デジ放送と衛星放送、およびそれぞれのアンテナ設定の違いについて一覧で紹介します。
※上記はそれぞれの放送の主な特徴になります。
衛星放送用のBS/CSアンテナを設置する際の、重要な設定ポイントは以下の通りです。
- アンテナの仰角・方位角を正確に合わせる
BS/CSアンテナは、お皿のようなディッシュ(放物面反射器)の内側で、静止衛星から送信されてくる12GHz帯の電波を反射させ、ディッシュ前方の中心に固定された受信部(一次放射器)に集めています。
このような構造のため、静止衛星がある南南西の空(東経110度)へ向けて、ディッシュの仰角(上下の角度)と方位角を、1度単位のズレなく正確に向ける必要があります。 - わずかな障害物も避ける
静止衛星から送られる12GHz帯の電波は、光のような性質からわずかな障害物にも遮られやすく、静止衛星からアンテナまでの間に、建物や木はもちろん、ベランダの洗濯物や電柱、電線などがあるだけでも遮られてしまいます。
そのためBS/CSアンテナを設置する時点で東経110度の方向に障害物がないだけでなく、将来的に建物が立てられる、木が伸びるなどで障害物が発生する可能性も考慮して設置場所を選ぶことが大切です。 - テレビ側でアンテナへの電源供給を設定する
12GHz帯の電波は、衛星放送のような長距離送信に適している半面、そのままでは周波数帯が高すぎるため、アンテナケーブルで送信しにくいという性質もあります。
そのためBS/CSアンテナは、受信した12GHz帯の電波をMHz帯に変換するための「コンバーター」という装置を内蔵しています。
このコンバーターは電気機器であるため、動作させるために、テレビやレコーダーの設定画面から、BSアンテナへと電源を供給する設定を「オン」にして、チューナー端子からケーブルを通じて電源を供給する必要があります。
その他、ケーブル途中にに設置されるブースターの電源部から、BS/CSアンテナに電源を供給する方法もあります。
衛星放送独自の受信障害については「降雨減衰」「降雪減衰」が挙げられます。
これは、豪雨や大雪など、雨や雪の粒が大きくなる天候では、12GHz帯の電波にとっては無数の小さな障害物が降り注いでいるのと同じことになり、12GHz帯の電波が吸収され、乱反射も生じで、BS/CSアンテナで十分に受信できなくなる現象です。
この場合の対策は、天候の回復を待つことが基本になります。
また、2018年にスタートした衛星放送の4K8K放送では、一部の4K8Kチャンネルに、従来の12GHz帯である「右旋円偏波」ではなく、「左旋円偏波」という新しく追加された電波が使われています。
この右旋と左旋、双方の電波を受信し、ケーブルで送信するためには、対応する専用の2K4K8K(右旋左旋)対応BS/CSアンテナや、4K8K(3442MHz)対応ケーブル、ブースター、分配器などの機器が必要になります。
ただ2025年現在では、民間放送局の4K放送からの撤退が進んでおり、周波数帯の再編によって左旋で放送されるチャンネルが少なくなっています。
そのため左旋放送の4K8Kチャンネルを特にご覧にならない場合は、2018年以前の旧式(2K対応)BS/CSアンテナや設備を使っているお住まいでも、すぐにアンテナや機材を交換する必要はありません。
まずは現状把握!テレビのアンテナレベルを確認する方法
もしお住まいで「テレビ画面にブロックノイズが出て正常に映らない」「真っ暗になった画面に『E202』エラーが表示される」など、テレビの映りが悪いトラブルが発生した場合は、やみくもに対処するのではなく、まずは現状を正確に把握することが解決への近道です。
そのためにもっとも重要となるのが「アンテナレベル」の確認です。
アンテナレベルを確認することで、電波がテレビに正常に届いているかどうかを客観的な数値によって判断できます。
この項目では、アンテナレベルとかは何か、その確認方法や適切な目安について、以下で詳しく解説していきます。
アンテナレベルとは?数値の目安は?
「アンテナレベル」とは、アンテナが受信し、実際にテレビまで届いているテレビ電波の強さ(品質)を数値化したものです。
この数値が高ければ電波状態は良好、低ければ何らかの問題で電波が弱まっているとわかります。
このアンテナレベルは、リモコンを操作することで、簡単に確認できます。
テレビのメーカーやモデルによってアンテナレベル画面の表示は違っており、その基準値も異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
ご自身のテレビでアンテナレベルを確認して、目安より低い場合は、到達する電波レベルが不足している可能性が高いと考えられます。
このアンテナレベルの不足は、ブロックノイズやエラーコードの表示など、テレビが正常に映らない原因にもなります。
【メーカー別】リモコンで簡単!アンテナレベルの確認手順
アンテナレベルは、テレビのリモコンを使って、設定画面から適切な項目を選んで行くだけで確認できます。
ここでは、主要なメーカー、モデルごとの確認手順を以下にまとめました。
ただメニュー画面の名称はモデルや年代によって若干異なる場合があります。
※上記は主要メーカーの基本的なアンテナレベル確認方法になります。また地デジ放送とBS放送(CS放送含む)のアンテナレベル確認は項目が異なってきます。
上記の手順でアンテナレベル画面を表示し、現在の数値を確認してみてください。
【自分でできる】アンテナ設定・テレビが映らない時の簡単対処法5ステップ
アンテナレベルが低い、またはテレビが正常に映らない場合でも、アンテナ工事の専門業者を呼ぶ前に、ご自宅でも試せる簡単な対処法がいくつかあります。
ここでは、特別な工具や知識がなくても、屋内で完結する5つのステップをご紹介します。
テレビ画面に問題が出た場合は、これらを最初から順番に試してみてください。
ステップ1:テレビ・周辺機器の電源コードを抜いて再起動する
現在のテレビやレコーダーは、パソコンやスマートフォンと同様、内部基盤で制御される精密な電子機器のため、一時的な不具合で動作が不安定になることがあります。
パソコンやスマートフォンの不具合が再起動で解消されることもあるように、テレビやレコーダーも再起動するだけで問題が解決することがあります。
テレビなど機器の一般的な再起動の方法は、以下の通りです。
- テレビ本体の主電源をオフにする。
- テレビやレコーダー、ブースターなど、接続されているすべての機器の電源コードをコンセントから抜く。
- その状態で2、3分ほど待ってから、再度、電源コードを接続し、テレビの電源を入れる。
これはもっとも簡単で効果が出やすい方法なので、必ず最初に試しましょう。
なお、メーカーやモデルによっては、電源ボタンの長押しなど、独自のリセット方法をもつ機器もあり、こちらも効果を期待できます。ただ機器によっては、設定や録画などの内容も初期化されてしまうケースもあるためご注意ください。
ステップ2:B-CASカードを正しく挿し直す
地デジ放送や衛星放送(BS/CS)などデジタル放送の視聴には、テレビなど受信機器に挿入されたB-CASカード(またはACASチップ)による、暗号化の解除と認証が必要です。
このカードの接触不良が原因で、テレビがカードを認識できず、デジタル放送が映らなくなる場合があります。
B-CASカードの不具合の場合、テレビ画面に「E100」「E101」「E102」のエラーコードが表示されることが多くなります。
このような場合は、以下の手順でB-CASカードの清掃と差し直しが有効になります。
- テレビの電源をオフにする。
- テレビの側面や背面にあるB-CASカードを、ツメを押しながらゆっくりと引き抜く。
- カードの裏面にある金色のICチップ部分を、乾いた柔らかい布で優しく拭く。
- カードの向きを間違えないように、奥までしっかりと挿し直す。
上記の手順で接触不良が解消されれば、テレビの映りも正常化されます。
なお最近の4Kテレビなどでは、B-CASカードではなく、本体に内蔵されて同様の役割を果たす「ACASチップ」が採用されています。
このようなモデルの場合は、ステップ1の再起動を試してみてください。
ステップ3:アンテナケーブルの接続を確認する
お住まいで急にテレビの映りが悪くなる原因として意外と多いのが、アンテナケーブルの接続不良です。
掃除や模様替えの際に、ケーブルを引っ張るなどして、接続端子が緩んだり抜けたりすることがあります。
以下、ケーブルの各接続部別のチェックポイントを一覧でご紹介します。
※上記は主なチェックポイントになります。
壁側の端子(テレビ コンセント)の規格違いや接触不良が原因になるケースもあるため、あわせて確認してみてください。
壁からテレビまでのすべての接続箇所(接続端子)を、指で軽く押し込むようにして確認してください。静電気などで端子部が汚れている場合は、B-CASカードの場合と同じく、柔らかい布で清掃することも有効です。
またケーブルが家具の下敷きになっていたり、強く折れ曲がっていたりすることも、送信不良や断線の原因になるため、その点もチェックしてください。
ステップ4:チャンネルの再スキャン(初期スキャン)を行う
テレビなどの受信機器を新しく設置する際には、受信できるテレビ電波のチャンネルをテレビ側で自動的に確認して、適切なチャンネル番号に当てはめていく「チャンネル設定(チャンネルスキャン・チャンネルサーチ)」という作業が必要です。
そして引っ越しで受信できるテレビ電場が変わった後や、地域の放送局でチャンネル(周波数帯)の再編があった場合、テレビ内のチャンネル設定と、新しいチャンネル情報の食い違いから、一部のチャンネルが映らなくなることがあります。
その場合は、チャンネルの再スキャンによって、現状のチャンネルに合わせたチャンネルの再設定を行ってください。
チャンネル再スキャンの手順は、テレビのメーカーやモデルによって手順やメニューの名称は異なる場合もありますが、おおむね以下のような手順になります。
- リモコンの「設定」メニューを開く。
- 「チャンネル設定」や「放送受信設定」といった項目を選択する。
- 「地上デジタル自動設定」や「チャンネルスキャン」を選び、画面の指示に従って実行する。
再スキャンには数分かかる場合がありますが、完了すると受信可能なチャンネルが自動で再設定されます。
ステップ5:リモコンの「入力切替」を確認する
アンテナやテレビ電波、テレビ本体に特に問題がなくても、テレビの入力設定が間違っているとテレビ放送の画面は映りません。
これは単純な操作ミスですが、それだけに意外と気づきにくい原因のひとつです。
この場合の対処方法は、以下の通りです。
- リモコンの「入力切替」ボタンを押す。
- 画面に表示される入力一覧から「地上デジタル(地デジ)」(または「BS」「CS」)を選択する。
実際には、テレビに接続されているレコーダーやゲーム機を使った後に、入力が「HDMI(外部入力)」などに切り替わったままになっているケースが多く見られます。
アンテナレベルが低い・E202エラーが出る主な原因と解決策
ご自宅内でもできる、上記5つのステップを試しても改善しない場合、問題は屋外にあるアンテナ本体やその周辺(配線部や電波環境など)にある可能性が高くなります。
ここでは、より根本的なトラブルの原因とその解決策について解説します。
ただし、アンテナが設置されている屋外での作業、特に屋根の上など高所での作業は大変危険ですので、無理は禁物です。
以下、主な原因を一覧でご紹介します。
※上記は主なトラブル要因の概要です。詳しくは以下の項目でそれぞれ個別に解説していきます。
原因1:アンテナの向きがズレている
アンテナの老朽化に加え、台風や強風、地震、あるいは鳥がとまった衝撃などで、アンテナの向き(適切な方向)がわずかにズレてしまうことはよくあります。
地デジアンテナ、BS/CSアンテナとも指向性が高いため、少しの角度のズレが受信レベルを大きく低下させます。特にBS/CSアンテナは、ミリ単位のズレが受信感度に大きく影響します。
ベランダなど手の届く範囲で安全に作業ができる位置にアンテナが設置されている場合は、二人一組でテレビのアンテナレベル画面を見ながら、少しずつアンテナを動かして最適な向きを探すことも可能です。
この方法では、アンテナの角度を調整してから、アンテナレベル画面に反映されるまでに数秒の差が出るため、特に仰角、方位角をミリ単位で調整するBS/CSアンテナの場合は、根気のいる作業になります。
ただ1,000円台からで購入できる簡易型のアンテナレベルチェッカーを使用すれば、アンテナ近くですぐに受信レベルを判断できるため、作業がたいへん楽になります。
また、アンテナが屋根の上にあるなど高所での作業は、転落など大きな危険が伴うため、絶対に自分で行わず、専門の業者に依頼してください。
原因2:電波を遮る障害物・周辺環境の変化
テレビアンテナを設置した当初は問題なくても、時間とともに周辺の環境が変化することで、受信状況も変わる場合があります。
具体的には、以下のような例が挙げられます。
- 近所に高層マンションが建設された。
- 自宅の庭木が大きく成長し、アンテナにかかるようになった。
- 隣の家がアンテナの方向に増築した。
このような場合、電波塔や静止衛星から届く電波が物理的に遮られてしまい、お住まいのアンテナでの受信レベルが低下します。特に衛星放送は、わずかな障害物にも弱くなります。
解決策としては、障害物の影響を受けない場所へのアンテナ移設や、より受信性能の高いアンテナへの交換、電波を増幅するブースターの設置などが考えられます。
これらの対策には専門的な判断と作業が必要になるため、プロの業者へとご相談になるのが賢明です。
原因3:アンテナやケーブル、周辺機器の劣化・故障
テレビアンテナ本体や関連機器にも寿命があります。
使用するモデルや現場の環境にもよりますが、一般的に、アンテナ本体や同軸ケーブル、ブースターなどの寿命は10年から15年程度と言われています。
アンテナや配線部の機材を長年使用している場合、雨風によるサビや腐食、ケーブルの被覆の破れ、内部機器の故障などが原因で、電波を正常に受信、または伝送できなくなっている可能性があります。
この場合は、原因となっている老朽化した機器を特定し、新しいものに交換する必要があります。
この作業も、アンテナが見るからに錆びついている、倒れているなどの場合でない限り、ご自身でのチェックや特定は難しいため、専門業者へのご依頼をおすすめします。
引っ越し後にテレビが映らない?設定・接続のチェックリスト
お引っ越しは、テレビが映らなくなるトラブルがもっとも発生しやすいタイミングです。
アンテナ機材から受信できるテレビ電波の種類まで、受信環境が大きく変わるため、トラブルの原因も多岐にわたります。
そのような場合は、ご新居の住居形態に合わせて、以下のポイントを確認してみてください。
戸建て住宅の場合のチェックポイント
新しい戸建て住宅でテレビが正常に映らない場合、以下の点を確認してください。
- そもそもアンテナは設置されていますか?
最近の新築戸建てでは、外観を重視してアンテナを設置していないケースも多くなります。まずは屋根の上や壁面などを確認してください。 - アンテナ以外の視聴方法ではありませんか?
光回線テレビやケーブルテレビを契約しないとテレビを視聴できない物件もあります。不動産会社や前の住人に確認が必要です。 - チャンネル設定は新居の地域になっていますか?
前の居住地から持ってきたテレビの場合、チャンネル設定が古いままになっていることがあります。チャンネルの再スキャンを試してください。
集合住宅(マンション・アパート)の場合のチェックポイント
マンションやアパートでは、建物全体でひとつの大型アンテナを共有している(共聴システム)のが一般的です。
そのため、個人で対処できることは限られます。
- 壁のアンテナ端子はどの放送に対応していますか?
「地デジは映るけどBS/CSが映らない」という場合、建物がBS/CS放送に対応していない可能性があります。 - 建物全体でトラブルが発生していませんか?
共聴設備の故障やメンテナンスの場合、全部屋でテレビが映らなくなります。 - まず誰に相談すべきですか?
集合住宅でのアンテナトラブルは、まず大家さんや管理会社に連絡するのが鉄則です。独断で業者を呼ぶ前に、必ず状況を報告し、指示を仰いでください。
以下、戸建て住宅・集合住宅それぞれのチェックポイントと相談先をまとめました。
※上記は主なチェックポイントになります。
ここまで試してもダメならプロに相談!業者依頼の判断基準と費用相場
これまで紹介した方法をすべて試してもやはりテレビが映らない場合、原因はアンテナ本体や配線など、専門的な知識や技術が必要な場所にある可能性が高くなります。
特にアンテナの修理は、屋根の上などの高所作業になることが多く、一般の方が行うには大変な危険を伴います。
安全かつ確実に問題を解決するためにも、無理をせず専門のアンテナ工事業者に相談してください。
以下、プロのアンテナ工事業者を依頼する場合の、優良業者を選ぶためのチェックポイントについてご紹介します。
アンテナ工事の費用相場と優良業者の選び方3つのポイント
業者に頼むと費用が高額になりそうで、ご不安を覚えられる方もいるかもしれません。
安心して業者へと依頼するために、アンテナ工事の費用相場と、信頼できる業者の選び方を知っておくことが大切です。
以下、各種アンテナ工事の一般的な費用相場を解説します。
※上記は各種工事の平均的な相場になります。
またテレビアンテナ修理はどこに頼むべきか、優良な業者を選ぶ際には、以下の3つのポイントをチェックしてください。
- 明確な料金体系と無料見積もり
作業前に必ず現地調査と見積もりを行い、料金の内訳を丁寧に説明してくれる業者をお選びください。
「見積もり外の追加料金は一切かからない」と明言しているかという点も重要なポイントです。
例えば本記事にご協力いただいた「あさひアンテナ」では、現地出張しての電波調査とお見積もりを完全無料(出張料・キャンセル料など関連費用すべて含む)で実施しています。また他業者との相見積もりや、急なトラブルに対しての即日工事にも対応が可能です。
あさひアンテナでは電波調査も精密で、他業者ではデザインアンテナ設置を断られた現場でも、受信の安定するポイントを特定し、デザインアンテナの取り付けを実現した事例が多くあります。
このようにあさひアンテナでは、現場の受信環境で可能なテレビアンテナの取り付け方法をすべて割り出し、お客様のご要望に最適となるアンテナ工事を、業界最安に挑む見積もり価格でご提案します。もちろん見積もり後に追加料金が加算されることもありませんのでご安心ください。 - 豊富な実績と完全自社施工
年間数千件といった豊富な施工実績は、技術力と顧客からの信頼の証です。
また、下請けに丸投げせず、研修を受けた自社の職人が責任を持って施工する「完全自社施工」の業者は、品質が安定しており安心です。
さらに完全自社施工の業者では、下請け業者を使う場合に発生する中間マージンなどもカットできるため、適正な工事費用の実現にもつながっています。
例えば、年間6,000件以上の実績を持つ「あさひアンテナ」では、経験豊富なベテランスタッフによる「完全自社施工」を徹底しており、低価格ながら高品質な工事で評価されています。 - 長期保証とアフターサービス
工事後のトラブルに対応してくれる保証制度が充実しているかもご確認ください。
工事後の保証期間の長さは、その業者が、実績に基づく高い自信を持っているという証拠でもあります。
一般的なアンテナ工事業者では、5年から8年程度の長期保証を用意していることが多くなりますが、前述したあさひアンテナでは、施工品質の高さから、業界最長クラスの10年保証を提供しています。
これらのポイントを押さえて複数の業者から見積もり(相見積もり)を取り、見積もり料金だけでなく、施工品質や保証、サービスなどの総合的なコストパフォーマンスで比較検討されることをおすすめします。
テレビのアンテナ設定に関するよくある質問(Q&A)
この項目では、テレビのアンテナ設定に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 特定のチャンネルだけ映りが悪いのはなぜ?
A. 地デジ放送の電波塔は、NHK、広域民放、また一部の都府県にある東京MXや千葉テレビ、サンテレビなど地方チャンネルを送信していますが、一部の電波塔では、それぞれの電波塔が異なる場合があります。
特に地方チャンネルは、NHKや広域民放の電波塔とは異なるケースが多くなります。
そのため、異なるチャンネルを送信する電波塔や、お住まいの位置やアンテナの向きによっては、特定の電波塔から送られるチャンネルの電波だけが弱まり、映りが悪くなることがあります。
特に現場から見て、地方チャンネルの電波塔と、それ以外の電波塔の方向が大きく異なる場合には、メインの地デジアンテナとは別に、地方チャンネル用の電波塔を設置する必要が出る場合もあります。
他にも、地デジ電波の各チャンネルは、チャンネルごとに周波数帯が微妙に異なります。そして電波は周波数帯が高いほど減衰しやすいため、同じ電波塔から送信されるチャンネルでも、一部のチャンネルで電波レベルの差が生じ、電波レベルの弱いチャンネルだけが乱れる場合もあります。
このようなケースへの対処としては、アンテナの方向をほんの少し調整して、すべてのチャンネルが同じレベルで受信できるようにしたり、ブースターでテレビ電波を増幅する、逆に「アッテネーター(減衰器)」という機器を使用して、強すぎるチャンネルの電波を適度に弱めたりすることで、画面の状況が改善する可能性があります。
Q. アンテナレベルは高すぎてもダメって本当?
A. はい、本当です。
電波は弱すぎても映りませんが、逆に強すぎても(主に90㏈以上)テレビのチューナーが正常に信号を処理できなくなり、ブロックノイズが出たり映らなくなったりします。
この現象を「オーバーロード」と呼びます。
電波塔が非常に近い地域などで発生しやすく、その場合は、上記したアッテネーターという機器を使って、電波を適切な強さに弱める必要があります。
また現在のテレビなど受信機器では、入力されるテレビ電波が強すぎる場合、入力される時点で適度にレベルを弱めるアッテネーター機能を備えているものもあり、設定画面からこの機能をオンにすることでも対処できます。
Q. BS/CSアンテナの電源設定の方法は?
上記の通り、BS/CSアンテナにはコンバーターを作動させるための電源設定が必要となり、設定を行わないと衛星放送を受信できません。
この電源設定は、ブースターの電源部から供給するか、テレビなどの「BS電源設定」によってテレビから供給するかの方法になります。
ブースター電源部から供給する場合は、ブースター設置に際に業者に依頼すれば、適切に設定してくれます。
テレビなどでBS電源設定を行う場合は、基本的にテレビの設定画面から、BS電源設定などの項目を選択し「オン」または「オート」に設定します。
なおテレビからBS/CSアンテナに電源を供給する方法には、一台の特定のテレビから常時給電する方法と、複数のテレビやレコーダーなどで衛星放送を見る際のみ随時給電する方法があります。
現在は随時給電の方法が主流になっており、この場合は衛星放送を見るテレビすべての設定を「オート」にします。逆に常時給電の場合は、給電する特定のテレビのみ「オン」にしますが、この場合、そのテレビの主電源がオフになっていると給電されないため、他のテレビでも衛星放送を視聴できなくなるため注意が必要です。
またこの給電方法に応じて、お住まいで使用する分配器も、一端子給電型(常時給電用で特定の出力端子のみ電気を通すモデル)と、全端子通電型(随時給電用ですべての出力端子が電気を通すモデル)を使い分ける必要があります。
まとめ:まずは自分でできることから!難しい場合は無理せずプロに相談を
この記事では、テレビが映らない時のアンテナ設定やトラブルシューティングについて、初心者や一般の方にも分かりやすく解説しました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいします。
- テレビが映らない時は、まずリモコンで「アンテナレベル」を確認する。
- 電源の再起動やケーブルの再接続など、屋内でできる簡単な対処法から試してみる。
- 屋根の上での作業や、原因が特定できない複雑なトラブルは、無理せず専門業者に相談する。
- 業者を選ぶ際は、「料金の明確さ」「実績」「長期保証」の3点を必ずチェックする。
お住まいで突然、テレビが正常に映らなくなると動揺してしまいますが、そのようなときこそ、落ち着いてひとつずつ原因を切り分けていけば、必ず解決策は見つかります。
この記事を参考に、まずはご自身でできることからチャレンジしてみてください。
そしてご自身での対処が難しいと感じたら、迷わずプロの力を借りるのが、もっとも安全で確実な方法です。
本記事でご紹介した「あさひアンテナ」では、アンテナ設置だけでなく、さまざまなアンテナトラブルへの対処についても、受付から最短即日で対応しており、高品質な工事と低価格の費用で、早急な復旧をお約束しております。
関東、関西にお住まいのお客さまであれば、まずはあさひアンテナのフリーダイヤル、または24時間受付のメールフォーム、LINEアカウントへとご相談になることをおすすめいたします。
本記事の内容をご参考に、トラブルに見舞われたお客様が、一日も早く快適なテレビライフを取り戻せることを願っております。