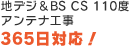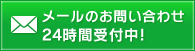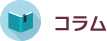「アンテナで受信できない!」「テレビが映らない!」を完全解決:原因の特定から自力での対処法、業者選びまでプロが徹底解説
お住まいで普段、特に問題なくご覧になっているテレビが、ある日突然、正常に映らなくなるというトラブルに見舞われたことはありませんか?
「いつも通りテレビをつけたら、突然、テレビの画面が真っ暗になった」
「画面の中央に『E202』というエラーコードが表示されているけど、どういう意味?」
「テレビの画面がモザイク状に乱れて、満足に見ることができない」
「もうすぐ観たい番組が始まるので、業者を呼ばずに、自分で今すぐ直せる方法はないかな?」
そのような状況で、特にテレビアンテナや配線に関する知識がないと、何が原因でどこから手をつければ良いのか分からず、お困りになることも多いでしょう。
本記事では、そのような「アンテナからのテレビ電波が受信できない」というトラブルでお困りの方に向けて、アンテナに関する専門知識を持つプロが、原因の特定からご自身でできる対処法まで、手順を追って分かりやすく解説します。
この記事は、テレビアンテナなど技術系の知識を持ち、多くの関連記事を手掛けてきた専門ライターが執筆しています。
さらに記事の内容に関しては、年間6,000件以上の施工実績を誇る優良なアンテナ工事業者「あさひアンテナ」で多くの施工を担当しているベテランのアンテナ職人から直接お話を伺い、実際の現場経験に基づく確かな情報をもとに、専門的な解説は避け、一般の方にもわかりやすくまとめております。
この記事を最後までお読みいただければ、主に以下のことについて概要が分かります。
- テレビ画面に表示されるエラーコードの意味。
- 業者を呼ぶ前に自分で試せる5つの確認ステップ。
- アンテナが受信できなくなる主な原因。
- 専門の業者に依頼すべきかどうかの判断基準。
アンテナ職人の解説によると、お住まいで起こる「急にアンテナから電波が受信できなくなった」「テレビ画面が映らなくなった」というトラブルは、実際はアンテナなどの大きな故障ではなく、ご自宅での簡単な確認や設定の見直しで解決できる、ささいな不具合が原因であることが大半だと言います。
もしお住まいでテレビ画面のトラブルが発生したときは、まずは落ち着いて、この記事でご紹介する手順を、ひとつひとつ試してみてください。
まずは落ち着いて!業者を呼ぶ前に自分で試せる5つの確認ステップ
お住まいで急にテレビ画面が映らない、またテレビの映りが悪いという症状が出たとき、すぐにアンテナやテレビの故障と決めつけるのは早計です。
実際の事例では、電波の受信やテレビの設定などにささいな不具合が生じているだけで、お住まいでのごく簡単な対処だけで解決できるケースも非常に多いのです。
そこで、まずはお住まいでテレビ放送が映らなくなった際に、誰でも簡単に確認できる以下の5つのステップを試してみましょう。
専門業者などへと連絡するのは、以下でご紹介する基本的な確認をすべて行っても改善しない場合でかまいません。
- テレビ画面のエラーコードを確認する。
- テレビやレコーダーを再起動する。
- アンテナケーブルとB-CASカードを挿し直す。
- チャンネルの再スキャン(初期スキャン)を行う。
- 周辺機器(ブースター等)の電源を確認する。
次の項目から、それぞれのステップを具体的に解説していきます。
ステップ1:テレビ画面のエラーコードを確認する(E202・E201など)
地デジ放送や衛星放送などのテレビ放送が受信できないとき、画面には「E202」のようなエラーコードが表示されることがほとんどです。
このコードは、テレビなどの受信機器がさまざまなトラブルに際し、その原因を自己診断した結果を私たちに伝えてくれる重要な手がかりになります。
まずは、画面に表示されているエラーコードの種類を確認しましょう。
現在のテレビなど機器では、エラーコードと同時に内容を示すメッセージが表示されます。特によく表示されるケースが多いエラーコードの意味は、以下の通りです。
※上記の他にもエラーコードは多数の種類が存在します。
「E202」はもっとも一般的なエラーで、アンテナからテレビへと電波がまったく届いていない状態を示します。一方、「E201」は電波はある程度の届いているものの、映像を映すには強さが足りない状態です。
どちらもアンテナ本体や、テレビまでのケーブル配線部の不具合、または近隣の電波障害などの原因が考えられます。
このようにエラーコードの意味を確認することで、トラブルの原因をある程度は推測することができます。
ステップ2:テレビやレコーダーを再起動する
エラーコードを確認した次に試すべき、もっとも簡単で効果的な手順が、テレビなどの「再起動」です。
パソコンやスマートフォンの調子が悪いときに再起動するのと同じ仕組みで、テレビやレコーダーも一時的なシステムエラーや内部回路の誤動作などで正常に機能しないことがあります。そのような場合に有効な手段です。
一般的なテレビ、レコーダーなどの機器に共通する、正しい再起動の手順は以下の通りです。
- テレビ本体の主電源をオフにする。
- テレビの電源プラグをコンセントから抜く。
- ブルーレイレコーダーなど、接続している機器の電源も同様にコンセントから抜く。
- そのまま1分〜数分ほど待つ。
- 再び電源プラグをコンセントに差し込み、テレビの電源を入れる。
ポイントは、ただリモコンで電源をオフにするだけでなく、コンセントを抜いて完全に放電させることです。
このシンプルな作業で、機器内部の通電を完全に断つことによってシステムがリセットされ、軽度な不具合であれば、問題が解消されるケースは少なくありません。
なお、テレビやレコーダーなどのモデルによっては、設定メニューから「初期化」を選ぶことや、電源ボタンを長押しするなど、独自のリセット・初期化を行えるモデルも存在します。しかし場合によっては、その手順により録画データやユーザー設定などが消えてしまう可能性もあるので、詳しくは本体の取扱説明書などを確認した上で、問題がない場合のみ行ってください。
ステップ3:アンテナケーブルとB-CASカードを挿し直す
再起動を行ってみても問題が改善しない場合は、機器本体と各種ケーブルなどの物理的な接続を見直してみましょう。
意外と見落としがちですが、アンテナケーブルなどの緩みやB-CASカードの接触不良などが原因であることも多いのです。
- アンテナケーブルの確認
- 壁のアンテナコンセント端子とテレビ(またはレコーダー)のチューナー端子を繋ぐアンテナケーブルのプラグ部分が、しっかり奥まで差し込まれているか確認します。
- ケーブル部分が家具の下敷きになっていたり、急角度に折り曲げられたりしていないかチェックしましょう。これも電波の送信不良や内部断線の原因になります。
- 経年劣化でケーブルが傷んでいる場合もあるため、見た目に問題がなくても一度、プラグを抜き差ししてみることをお勧めします。
- B-CASカードの確認
- テレビの側面や背面にあるスロットに挿入されている、B-CASカード(デジタル放送の受信に必須のカード)を一度ゆっくりと引き抜きます。
- カードでも特にICチップの金属部分を、メガネ拭きのような柔らかい布で優しく拭きます。
- カードの裏表と向きを間違えないように、カチッと音がするまでしっかりと奥まで挿入し直します。
- B-CASカードの代わりに内蔵のACASチップが使われている近年のモデルの場合は、上記した再起動を試してください。
これらの特にケーブル接続部分などは、掃除や家具の移動などで意図せず緩んでしまうことがあります。
それぞれを丁寧に確認し、確実に接続し直してください。
ステップ4:チャンネルの再スキャン(初期スキャン)を行う
テレビを最初に設置する際には、届いているテレビ電波の「チャンネルスキャン(初期スキャン)」を行い、電波内の各チャンネルを適切なチャンネル番号に割り当てる「テレビのチャンネル設定」を行う必要があります。
そしてお引っ越しで受信できる電波塔が変わる、電波塔の周波数帯変更や放送局の追加など電波の変化によって、テレビが記憶しているチャンネル情報が古くなってしまい、テレビが正常に映らなくなることがあります。
その場合は「チャンネルの再スキャン」を行うことで、最新の電波(チャンネル情報)を取得し、正しく受信できるようになります。
チャンネルスキャンの操作方法はテレビのメーカー、モデルによっても異なりますが、一般的にはおおよそ以下の手順で行います。
- リモコンの「メニュー」や「設定」ボタンを押す
- 設定画面から「チャンネル設定」や「放送受信設定」といった項目を選ぶ
- 「地上デジタル自動設定」や「初期スキャン」を選択して実行する
スキャンには数分かかる場合がありますが、テレビがその地域で受信可能なチャンネルを自動で探し出して再設定してくれます。
特定のチャンネルだけが映らなくなった場合に、特に有効な方法です。
ステップ5:周辺機器(ブースター等)の電源を確認する
アンテナとテレビの間のケーブル配線部には、受信した電波を強くするための「ブースター(増幅器)」という機器が設置されていることがあります。
特に複数の部屋でテレビを見ているご家庭や、電波塔から遠い、障害物が多いなどで、地デジ電波レベルが弱い地域では必須の装置です。
このブースターは電気で動作するため、電源が入っていなければ全く機能しません。
ブースターには、アンテナの近くに設置される「本体(増幅部)」と、天井裏や室内でコンセントに接続される「電源部」のふたつの部分があります。
まずは、テレビ周りのコンセントや、天井裏、屋根裏の点検口近くに、見慣れないACアダプターやブースター電源部が接続されていないか確認してみてください。
もしブースターの電源部があれば、そのランプが正しく点灯しているかチェックしてみてください。何かの拍子で電源部のコンセントが抜けていただけ、というケースも珍しくはありません。
なぜ?テレビが受信できなくなる7つの主な原因
上記の、ご自身で試せる5つのステップで解決しなかった場合、問題はもう少し根深いところにあるかもしれません。
ここでは、急にアンテナでテレビ電波が十分に受信できなくなり、テレビが映らなくなった場合の、代表的な原因を7つに分類して解説します。
原因を正しく理解することが、復旧するための適切なアクションにつながります。
- 原因① アンテナ本体の向きのズレ・劣化・故障。
- 原因② ケーブルや分配器など周辺機器の不具合。
- 原因③ ブースター(増幅器)の電源オフや故障。
- 原因④ 悪天候(大雨・強風・大雪)による一時的な電波の乱れ。
- 原因⑤ 周辺の建物や電波障害の影響。
- 原因⑥ テレビ本体の故障。
- 原因⑦ 放送局側のトラブルやメンテナンス。
原因① アンテナ本体の向きのズレ・劣化・故障
ほとんどの場合、屋根の上やベランダなど吹きさらしの空間に設置されているテレビアンテナは、常に風雨に晒されています。
さらにテレビアンテナは、地デジ用、衛星放送(BS/CS用)とも、アンテナの正面側でのみ高い受信感度を発揮する「指向性(しこうせい)」という性質があります。
そのためそれぞれのアンテナ正面の向きを、近隣の電波塔や静止衛星の方向へと向けて、正確に角度調整する必要があるのです。
このアンテナの角度が、台風や強風、地震などの影響でズレてしまう、老朽化に寄り部品が破損したりすることで、受信感度が大きく低下することもあります。
特にBS/CSアンテナは、ディッシュの上下、左右の角度を正確に静止衛星の方向(東経110度)に合わせることが重要で、数ミリずれただけでも受信できなくなるほどシビアです。
また、テレビアンテナの寿命は、機種および設置場所、その地域の気候や環境によっても変動しますが、一般的には10年から15年とされています。
アンテナ設置から長い年月か経過している場合、サビや腐食による経年劣化で受信性能が低下している可能性も考えられます。
以下、アンテナ機種別の一般的な寿命(耐用年数)の一覧です。
※上記は各モデルの一般的な寿命です。
特に耐用年数の短い八木式アンテナ、BS/CSアンテナ等では、設計や素材、表面加工などにより耐候性能を高めた、塩害用、雪害用、ステンレス製、高耐風モデルなどが存在し、それらのモデルを使用することで、耐用年数を延ばすことが期待できます。
また現場の受信環境などで可能であれば、アンテナをベランダの内外や屋根裏空間など、風雨を避けやすく、メンテナンスを行いやすい位置に設置することも、アンテナ老朽化の有効な対策になり得ます。
原因② ケーブルや分配器など周辺機器の不具合
テレビアンテナ本体が正常でも、そこからテレビまで電波を送信する経路(ケーブル配線部)に問題があり、電波が送信できていない場合もあります。
例えばアンテナケーブル(同軸ケーブル)が、屋外で紫外線や雨風に晒されて劣化し、外部被膜が避けて剥離している、また内部で芯線が断線しているなどのケースです。
また上記したブースターの他、アンテナからの信号を複数の部屋に分ける「分配器」や、地デジとBS/CSの電波を分ける「分波器」など、配線部に設置される周辺機器が故障することも、電波の送信に問題が出る原因のひとつです。
これらの機器は、普段は目にすることが少ない場所に設置されているため、トラブルの原因としては見過ごされがちです。
原因③ ブースター(増幅器)の電源オフや故障
先ほども触れましたが、特に電波を増幅する重要な役割を果たしているブースターのトラブルは、受信不良の大きな原因となります。
電源が入っていないという単純なケース以外に、電源を要する電子機器であるブースター本体が故障してしまうこともあります。
特に屋外に設置されているブースターは、アンテナ同様に風雨の影響を受けやすいため、寿命もアンテナとほぼ同じ10年から15年程度です。
また、ブースターの性能が低かったり、利得(増幅レベル)の調整が不適切だったりすると、電波レベルが不足する、さらにノイズまで増幅してしまうなどで、かえってテレビの画質を悪化させることもあります。
原因④ 悪天候(大雨・強風・大雪)による一時的な電波の乱れ
大雨や大雪は、テレビの電波を吸収・散乱させて弱めてしまう性質があります。
地デジ電波は、一年を通した気候の変化で若干のレベルの変動があるほか、雨や雪では大きくレベルが低下するため、余裕のある受信レベルの確保が重要です。
また特に、周波数が高い(波長が短い)衛星放送の電波(12GHz帯)は、ある程度大きな雨粒、雪粒の影響で遮られやすく、激しい雨や雪では一時的に「降雨減衰」「降雪減衰」と呼ばれる受信レベルの低下が起こります。
また、強風でアンテナが揺れることなどでも、受信が不安定になることがあります。
これらの天候による影響は、アンテナの不具合が生じない限りは、一時的なものであるケースがほとんどです。
天気が回復すれば自然に元通り映るようになることが多いので、あわてずに様子を見てください。
ただ地デジ放送で悪天候による受信不良が頻繁に起こる場合は、受信レベルの確保が十分でないため、アンテナの角度、設置位置の調整や高性能モデルへの交換、ブースターの設置や調整などをおすすめします。
原因⑤ 周辺の建物や電波障害の影響
地デジ放送の電波は、近隣にある電波塔の先端から、ご家庭の地デジアンテナまで、一定の波長の幅を持って、広がりようにして飛んできます。
地デジ電波はビルなどある程度の障害物であれば、向こう側に回り込んで広がる性質もありますが、その性質も完全ではありません。
したがって電波塔の方向、すぐ近くに高層マンションなどのビルが建設されると、地デジ電波が遮られてしまい十分に受信できなくなることがあります。
特に壁面用のデザインアンテナなど低い位置に設置されるアンテナの場合は、すぐ近くの隣家に遮られて電波が届かないケースもあるため注意が必要です。
さらに静止衛星から地上まで送信されるBS放送、CS放送の電波(12GHz帯)は、光のように直進性が高いため、わずかな障害物にも遮られてしまいます。
したがってBS/CSアンテナを向けた静止衛星の方向に、ビルなどの建物はもちろん、電柱や電線がある、樹木が伸びる、洗濯物が干されるなどの要因でも、電波が遮られて受信感度が低下することもあります。この点にも注意が必要です。
また地デジ電波では、目に見えないその他の電波(ノイズ)の干渉も、受信不良を引き起こす原因のひとつになります。
古いタイプの地デジアンテナ(アナログ放送時代のUHFアンテナ)が、携帯電話の基地局が発する電波などを受信してしまい、それをブースターが増幅することで、周辺一帯に電波障害を引き起こす「700MHz帯電波障害」は、総務省や各携帯電話キャリア会社(700mhz利用推進協会)が、現在も対策を進めている問題です。
またご家庭内でも、電子レンジやコードレス電話などが発生させる電磁波がノイズ源となり、Wi-Fiやテレビの受信に悪影響を与えることがあります。
ご家庭内ではこれらの機器を、できるだけテレビやアンテナケーブルから離すなどの対策が必要です。
原因⑥ テレビ本体の故障
ご家庭のテレビアンテナやケーブル配線にまったく問題がなくても、テレビ本体のチューナー(電波を受信する部分)が故障している可能性も考えられます。
以下のような症状がある場合は、テレビ本体の不具合を疑ってみましょう。
- 「音は出るのに画面が真っ暗」
- 「アンテナレベルを確認しても0のまま全く反応がない」
- 「他のテレビは問題なく映るのに、そのテレビだけが映らない」
軽度の不具合であれば上記した再起動で回復する場合もありますが、復旧しない場合は、テレビのメーカーや購入した家電量販店などに相談する必要があります。
原因⑦ 放送局側のトラブルやメンテナンス
非常に稀なケースですが、放送局側で送信設備のトラブルや緊急メンテナンスが行われている可能性もゼロではありません。
特定の放送局(チャンネル)だけが映らない場合、その放送局の公式サイトや公式SNSなどで障害情報が出ていないか確認してみるのもひとつの方法です。
もし本当に障害が発生している場合は、その復旧を待つしかありません。
地デジ放送で受信トラブルが起こる要因とは?
地上デジタル放送(地デジ放送)は、現代の日常生活にもっとも身近なテレビ放送ですが、その電波には特有の性質があり、それが受信トラブルの原因となることがあります。
地デジ放送の電波は「UHF(極超短波)」という周波数帯が使用されており、これは上記の通り広がりやすく、障害物に比較的強いという長所がある一方で、いくつかの弱点も抱えています。
地デジ受信の基本は、地デジアンテナ(UHFアンテナ)を地域の電波塔(東京スカイツリーなど)の方向へと正確に向けることです。前述の通り地デジアンテナには「指向性」があり、特定の方向からの電波を強く受信します。
アンテナ機種や受信性能によっても多少の差がありますが、この角度調整が少しでもズレると、地デジの受信レベルは大きく低下してしまいます。
また、地デジ電波は基本的に、高い位置に当たる電波塔の先端から、周辺に下るようにして送信されます。したがって地デジアンテナは、屋根の上などできるだけ高い位置に設置するほど、ビルなど遮蔽物の影響を受けにくく、受信感度が安定しやすくなります。
以下、地デジ放送で受信トラブルが発生する、主な要因を一覧で紹介します。
※上記は地デジ受信トラブルの一般的な要因です。
これらの要因が単独、または複合的に絡み合うことで、地デジ放送の受信トラブルは発生します。特に、地デジアンテナの性能がご自宅エリアの電界地域に合っていないと、安定した地デジ受信は難しくなります。
衛星放送(BS/CS)で受信トラブルが起こる要因とは?
赤道軌道上を周回し、地上からは空の一点に静止して見える人工衛星(静止衛星)から地上まで電波を送信している衛星放送は、地デジとはまったく異なる仕組みと電波の性質を持っています。
前述の通り、BS放送の放送衛星、CS放送の通信衛星とも、使用される電波は「12GHz帯」という、非常に周波数が高く、光のように直進する性質が強い電波です。
そのため衛星放送では、受信トラブルの原因も地デジ放送とは少し異なります。
例えばBS/CSアンテナ(パラボラアンテナ)は、静止衛星の方向から光のように直進してくる12GHz帯の電波を、まず皿状のディッシュ内側で反射させます。
そして前方に固定された一次放射器の一点に電波を集中させて受信しているため、南西方向(東経110度)の上空にある静止衛星に向けて、ディッシュの仰角、方位角(上下と左右の角度)を1ミリの狂いもなく、正確に合わせる必要があります。
この角度調整の精密さが、衛星放送の安定受信の鍵となります。
さらに12GHz帯の電波は光のような性質から、ささいな障害物にも遮られやすいため、ディッシュを向ける電波の通り道に、一切の物理的な障害物が存在しないことも重要になります。
以下では、衛星放送で受信トラブルが起こる、主な要因について一覧で紹介します。
※上記は衛星放送の受信トラブルでも一般的な要因です。
特に、BS/CSアンテナからテレビまでの間に障害物が何もないか、そしてテレビやレコーダーの「BSアンテナ電源」設定が適切な設定(「オン」または「オート」)になっているかどうかは、衛星放送が急に映らなくなったときに真っ先に確認すべきポイントです。
【状況別】こんな時はどうする?ケース別対処法
ここまでは、急な受信トラブルなどでテレビが映らなくなる一般的な原因と対処法を解説してきましたが、読者の皆様が実際に直面されている状況はさまざまかと思われます。
ここでは、現場におけるより具体的なケースに絞って、最適な対処法をアドバイスします。
ご自身の状況に、もっとも近い項目を参考にしてください。
アパート・マンションなど集合住宅でテレビが映らない場合
アパート、マンションなどの集合住宅にお住まいで、テレビ画面のトラブルが生じた場合、まずは問題の切り分けが重要になります。
集合住宅ではテレビアンテナは各部屋で個別に設置されているのではなく、屋上などに設置された共用の大型アンテナ(共聴アンテナ)を利用していることがほとんどです。
したがって、集合住宅の各部屋でテレビが映らないときの、具体的な対処は以下の通りになります。
- まず自分で確認すること
- 自分の部屋の中のケーブル配線、B-CASカード、テレビの設定など、これまでに解説した「自分で試せる5つのステップ」を実行します。
- 同じ建物に住む友人や隣人に、室内で正常にテレビが映るかどうか確認してみるのも原因の切り分けに有効です。
- 管理会社や大家さんに連絡すべきケース
- 自分の部屋の設備に問題がないのに映らない場合。
- 他の部屋でも同様にテレビが映らない場合。
- 大雨や台風の後など、建物全体のアンテナに不具合が生じた可能性が高い場合。
共用設備の問題は、各部屋にお住まいの個人では対処できません。
まずは自室内の原因を探り、それで解決しなければ速やかに管理会社や大家さんへと連絡し、共用アンテナ設備を確認してもらいましょう。
地デジは映るのにBS/CSだけが映らない場合
これは非常によく見られるトラブルで、主な原因はBS/CSアンテナの受信システムに限定されることがほとんどです。
この場合は、以下の点を確認してみてください。
- BS/CSアンテナへの電源供給
- テレビやレコーダーの設定メニューから「BSアンテナ電源」または「衛星放送アンテナ設定」などの項目を探し、「オン(ON)」または「オート」になっているかを確認します。これが「オフ」だとアンテナのコンバーターが動作せず、衛星放送を受信できません。
- 一般的に「オン」は特定のテレビからBS/CSアンテナに常に電源を供給し続ける方法、「オート」は複数のテレビで衛星放送を視聴する際のみ給電する方法になります。
- また特定のテレビから常に電源を供給する方式では、そのテレビの主電源がオフの場合にコンバーターが作動しません。また複数のテレビから一度に電源を供給すると、ケーブルがショートする場合もあります。
- お住まいの複数のテレビで衛星放送をご覧になる場合を含め、基本的には電源設定は「オート」がおすすめです。
- ケーブルの接続
- 壁のアンテナコンセント端子が、地デジとBS/CSで分かれている場合、アンテナコンセントとテレビ側で、それぞれ正しい端子に接続されているかどうかを確認します。
- ひとつの端子から両方の電波が送られている場合、ケーブルの途中に「分波器」という機器が接続され、地デジと衛星放送の電波がきちんと分けられているか、やはり適切なチューナー端子に接続されているかを確認します。
- アンテナの向き
- BS/CSアンテナがベランダなど安全に近づける位置に設置されている場合は、BSディッシュの向きが強風などでズレていないか、目視や角度調整の目盛り部などで確認します。
- 「BSコンパス」など、画面上のコンパスでBS/CSアンテナの的確な角度を確認できるアプリがあれば、より正確にディッシュの角度を確認できます。
多くの場合、BS、CSなどの衛星放送が急に映らなくなる原因は、テレビ側からの電源供給の設定ミスであるケースです。
一度、テレビから設定メニューを確認し直してみてください。
特定のチャンネルだけが映らない場合
地デジ放送などですべてのチャンネルではなく、一部のチャンネルだけが映らない場合、主にそのチャンネルの電波だけが弱いことが原因と考えられます。
放送局によって、送信所の場所や電波の強さが異なるケースがあるため、このような現象が起こります。
- アンテナレベルの確認
- まずは、映らないチャンネルに合わせた状態で、テレビのアンテナレベルを確認します。
- 他の映るチャンネルと比較して、レベルが著しく低い場合は、電波不足が原因です。
- 地デジ放送の場合、各チャンネルの周波数帯の違いから、周波数帯の高いチャンネルほど減衰して弱まりやすくなります。
- また東京都の東京MXや埼玉県のテレビ埼玉などの地方チャンネルは、NHKや広域民放とは別個の電波塔から送信されている場合があり、現場から見れば電波の強さや方向が大きく異なる場合もあります。
- 対処法
- 地デジアンテナの向きを、映らないチャンネルの受信レベルが最大になる(チャンネル全体の受信レベルが平均的になる)ように微調整します。(高所の場合や作業が難しい場合は専門業者へと依頼)
- 地方チャンネルの場合は、電波の方向や強度が大きく異なるため、受信するために主な地デジアンテナとは別に、地方チャンネル用アンテナを設置するケースもあります。さらにアッテネーター(減衰器)で強すぎるチャンネルの電波を弱めて、全体の地デジ電波レベルを平均化することもあります。
- 他にも、各チャンネルの地デジ電波を全体的に増幅、調整するブースターを設置するか、より受信性能の高い高性能アンテナに交換することなどで、問題が改善されるケースもあります。
自力での解決はここまで。専門業者への依頼を検討すべきサイン
ここまでの解説で、ご自身でもできる限りの対処をしても改善しない場合、または作業に危険が伴う場合は、無理をせずアンテナ工事の専門業者に、テレビアンテナ修理などの対処を依頼してください。
特に、屋根の上でのアンテナ調整作業では、転落などの重大な事故につながる可能性もあるため、絶対に自分で行ってはいけません。
以下のようなサインが見られたら、プロに相談するタイミングです。
- ここまで紹介したすべての初期対応を試しても、まったく改善しない。
- アンテナレベルが「0」のままで、まったく反応がない。
- 屋根の上にあるアンテナの向き調整や交換が必要だと考えられる。
- アンテナ本体や支柱に、明らかなサビや破損が見られる。
- ケーブルが壁の中を通っているなど、自分で配線を確認できない。
- 原因の特定がどうしてもできず、お手上げ状態。
アンテナ工事の専門業者は、専用の測定器を使ってテレビ電波の受信状況を正確に診断し、豊富な経験に基づいて最適な解決策を提案してくれます。
失敗しないアンテナ工事業者の選び方と費用相場
信頼できるアンテナ工事業者を選ぶことは、アンテナトラブルを確実に解決し、将来的な安心を得るためには非常に重要なポイントです。
以下、テレビアンテナの修理はどこに頼むべきかのチェックリストをご用意しました。こちらを参考に、慎重に優良な業者を選んでください。
※上記は業者を選ぶ際の主なポイントになります。
アンテナ工事の費用は、具体的な作業内容によって大きく異なります。
以下で作業別のおおよその費用目安をご紹介しますが、はあくまで一般的な相場であり、建物の状況や使用する部材によって変動します。
複数の業者から「相見積もり」を取り、見積もり料金と具体的なサービス内容を比較検討することが、納得のいく優良業者を選ぶことに繋がります。
【独自情報】年間6,000件以上の施工!「あさひアンテナ」が選ばれる理由
上記でご紹介した優良なアンテナ業者の条件をすべて満たしており、さらに「期待を超える」サービスを提供している専門会社として、本記事の筆者からおすすめできる業者があります。
本記事の執筆にもご協力いただいた経験豊富なアンテナ職人が所属する「あさひアンテナ」が、まさしくその業者です。
同社では、年間6,000件以上という圧倒的な施工実績を誇り、その豊富なノウハウによる高品質な施工と、低価格の料金をはじめ充実したサービス内容が、多くのお客様から信頼される証です。
以下、あさひアンテナの強みについて、具体的にご紹介します。
あさひアンテナが選ばれる5つの理由
- 完全自社施工による高品質と適正価格
- 経験豊富なベテランスタッフが、すべてのアンテナ工事について責任を持って施工します。下請け業者を使わないため責任の所在が明確で、中間マージンもなく、高品質な工事を低価格でご提供できます。
- 年間10,000件以上の圧倒的な施工実績
- 関東・関西エリアで、あらゆる電波状況や建物に対応してきた豊富な経験があります。高品質なデザインアンテナ設置をはじめ、どんな難易度の高い工事にも対応可能です。
- 業界最長クラスの10年保証
- 施工技術に絶対の自信があるからこそ、工事後10年間の長期保証をお付けしています。万が一のトラブルにも迅速・無料で対応します。
- 24時間365日の迅速対応
- 急なアンテナトラブルで「今すぐ直してほしい」というお客様のご要望に応えるため、最短即日の工事や、24時間体制でのご相談も受け付けています。
- 細やかな顧客志向のサービス
- 子育て世帯向けの割引や、火災保険の申請サポートなど、お客様の状況に寄り添ったサービスを提供しています。
あさひアンテナでは、アンテナ工事に伴う事前の電波調査とお見積もりは、完全無料(出張料やキャンセル料など各種費用含む)で行っています。
アンテナ設置であれば、現場の緻密な電波調査により可能な設置方法をすべて割り出し、お客様のご要望に最適な工事をご提案いたします。
受信トラブルの場合も早急にトラブルの原因を割り出し、的確な修理工事を判断し、どのような工事も業界最安に挑むお見積もり費用でご提案します。
アンテナトラブルに対する修理や、アンテナ新規設置、交換などの工事をどこに頼めばいいかお迷いの際は、ぜひ一度「あさひアンテナ」のフリーダイヤル、メールフォーム、LINEアカウントまでご相談ください。
優秀なスタッフ一同が、お客様ファーストの姿勢を徹底して、皆様のご不安を安心に変えるお手伝いをさせていただきます。
豆知識:アンテナ修理は火災保険が適用されるケースも
あまり知られていないことですが、台風や落雷などの自然災害(地震を除く)や、近隣での爆発など想定外の事故によってお住まいのアンテナが破損した場合、その修理費用に火災保険が適用できるケースがあります。
まずは以下で、適用できるケースとできないケースについてご紹介します。
- 適用される可能性が高いケース
- 台風や竜巻などの「風災」でアンテナが倒れた、向きが変わった。
- 「雹(ひょう)災」でアンテナがへこんだ、破損した。
- 大雪の重みによる「雪災」でアンテナが壊れた。
- 「落雷」でアンテナやブースターが故障した。
- 適用されないことが多いケース
- 経年劣化による故障やサビ。
- 地震による損害(地震保険への加入が別途必要)。
- 人的な原因による破損。
まずは、ご自身で加入されている火災保険の契約内容に「風災・雹災・雪災補償」が含まれているかどうかを確認してみてください。
またアンテナ修理で火災保険の申請を行うには、被害状況の写真や修理業者の見積書などの書類も必要となります。
上記でも少し触れた通り、あさひアンテナでは、アンテナ修理と同時に、火災保険申請に関するサポートも行っております。
ご相談をいただければ、火災保険の申請に必要な写真、報告書などの書類をすべてご用意するほか、お客様ご自身による申請書類の作成や保険会社との交渉も、専門知識を持つスタッフによる万全のサポート体制をご用意しております。
火災保険の適用に関するご相談も、どうかお気軽にあさひアンテナまでお寄せください。
まとめ:「アンテナが受信できない」トラブルは原因の切り分けが重要
突然、テレビ放送が映らなくなる「アンテナ受信不良」のトラブルは、一般のお住まいであれば、どこでも起こりうる普遍的な問題です。
しかしその原因は多岐にわたるため、もし実際にトラブルが発生したときは、決してあわてず、冷静に原因を切り分けていくことが解決への一番の近道です。
万が一の際に確かな手順を取っていただけるよう、最後にあらためてこの記事の重要なポイントをもう一度おさらいします。
- まずは自分で5つのステップを確認:エラーコードの確認、再起動、ケーブル・カードの確認、再スキャン、ブースター電源の確認。
- 原因を推測する:アンテナ本体、周辺機器、外部要因など、何が問題を引き起こしているのかを考える。
- 危険な作業はプロに任せる:屋根の上など高所での危険な作業は絶対に自分で行わず、専門業者に依頼する。
- 信頼できる業者を選ぶ:料金、実績、保証、口コミなどを比較し、納得のいく業者を見つける。
多くの軽微なトラブルは、ご自身での確認作業で解決できます。
それでも直らない場合は、アンテナ設備に専門的な対処が必要なサインです。
そんな時は、年間6,000件以上の実績と10年保証で安心の「あさひアンテナ」まで、いつでもお気軽にご相談ください。
あさひアンテナでは、フリーダイヤルなどへのアンテナやテレビの不具合のご相談に対しては、現場経験も豊富なオペレーターが担当し、まずはお住まいのエリアやアンテナ設備、トラブルの状況などをうかがった上で、考えられる原因とお住まいでも可能な対処法をご案内いたします。
そのご説明だけでトラブルが解消された場合には、料金は発生いたしませんので、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
そしてアンテナや配線部の不具合など、現場での修理が必用なトラブルだと思われる場合には、ご依頼いただければ弊社の経験豊富なアンテナ職人が早急に現場へと駆け付け、原因の特定と必要な工事のご提案を、業界最安に挑むお見積もり価格でご案内いたします。